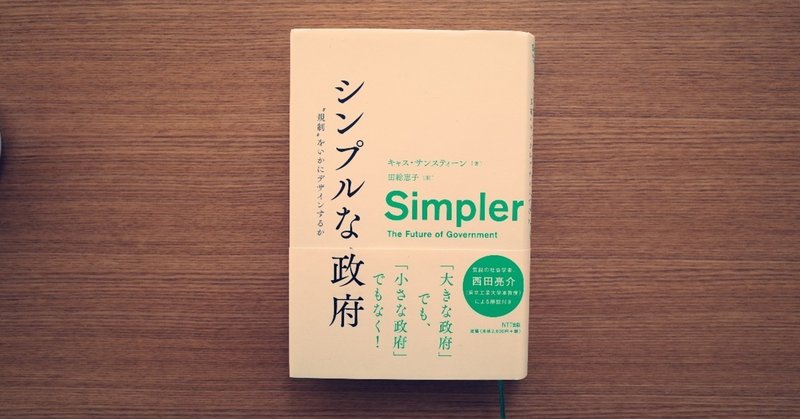
社会人になってから毎月寄付を続ける理由
大学を卒業して社会人になってから、アラサーになる今まで複数のNPOの月額寄付会員(マンスリーサポーター)を続けている。「寄付について考える」というnoteのテーマで、改めて「なぜ自分は寄付を続けているのか」を考えてみた。答えは「投資」だった。「大いなるもの」への投資だと信じてきたからだった。
寄付というのは不思議なお金の動き
寄付は一般的な投資ではないとは思う。自分も投資信託をやっているけれど、投資というのはそうやって、お金をギブすることで運用益などのリターンを得る仕組みだと思う。
寄付には基本的にリターンはない。もちろんNPOは活動報告をちゃんと送ってくれるし、誰かのためになることは嬉しいことで、感情的なプラスを受け取っているのは間違いない。だけど見返りが目当てじゃない。
そもそもNPOの活動が不思議だ。企業の経済活動を考えると、商品やサービスを提供した代わりに貨幣を受け取っている。つまり商品などを受け取る「受益者」が「支払者」とイコールになる。NPOの場合、寄付をする人が「支払者」になって、「受益者」へ支援を展開する。受益者と支払者は同じじゃなくて、個人にしろ、補助金を出す企業や政府にしろ、寄付をする人に支えられる仕組みだ。
かといって施しだとは感じていない
じゃあ「受益者」への施しだと思って寄付をしているかといえば、実感としてそうではない。
自分がいまサポートしているNPOが支援の対象にしているのは「子ども」が多い。ある団体は、アフリカを活動地として、エイズで親を失った子の教育支援をしている。ある団体は首都圏を中心に、児童養護施設など社会的養護が大切になる子どもの進学を支えている。そういった子どもたちを「かわいそう」だと思っているかといえば、そうでもないかもしれない、というのが正直な気持ち。
人間の根本的な「インフラ」を守って育てたい
だとしたらなぜ寄付をするのだろう。それを説明するのに、前に読んだ本が思い浮かんだ。オバマ政権で規制緩和担当をしたキャス・サンスティーンさんという人が書いた「シンプルな政府」という本だ。
この本で、オバマ大統領の演説の一節が出てくる。それは「自分の力で成功したと思っている人は、そもそもこの社会で誰かが作ってきたインフラに手助けされたことを忘れていないか」という警句だった。
(中略)頭が良かったから成功したのだと思っている人には、いつも驚かされる。頭のいい人間なんていっぱいいるじゃないか。あるいは、自分は他の人より一所懸命働いたからだと言う人もいる。一所懸命働いている人は世の中にいくらでもいる。
成功できたとすれば、それはそこまでの道のりで手助けしてくれた人がいるからだ。人生のどこかで、素晴らしい先生がいたはずだ。誰かが、このアメリカの、驚くべきほど素晴らしい制度を作るのに力を尽くしてくれて、そのおかげで私たちは繁栄することができた。誰かが道路や橋に投資してくれたのだ。自分で起業したとしても、一人で作ったわけではない。それを可能にしてくれた人がいる。インターネットは自然に生まれてきたわけではない。政府の研究がインターネットを開発し、そのインターネットを利用して、企業は利益を上げることができたのだ。(p84)
誰かが築き上げた道路や橋が、民主主義や福祉の制度が、インターネットの研究が、いまを支えている。「誰かが投資してくれたのだ」とオバマさんは言う。
この「インフラ」を突き詰めていくと、より根本的なものに行き当たる気がしている。それは恥ずかしがらずに言えば、優しさだったり、助け合う気持ちだったり、困っている人をなんとなく放っておけない感情だったり、そういうもの。「人が人を思う気持ち」だと思う。
人生を振り返れば、たくさんの優しさに支えられてきた。親に限らない。友達も先生もそうだし、ツイッターで目にしたちょっとした言葉に救われたこともある。自分が寄付するNPOの受益者となる子どもたちは、相対的にそういったきっかけが少ない可能性がある。家族がいなかったり、差別を受けていれば、しんどいこともあるだろう。そんなときにNPOを通じて、「人が人を思う気持ち」が伝わる瞬間がきっとあると思う。
だから自分の寄付は、人間の根本的なインフラに対する投資なんだと思う。その子らが成長して、自分を助けてくれるだろう、という話じゃない。きっとNPOの支えを受けた子たちは、別の誰かに優しさを渡せる機会もあるだろう。そうやって、自分が人生(30年に満たないけど)を通じて支えられてきたような人間の「人間性」が、未来に続くいていく気がする。優しさや助け合いがなくならず、細らず、育っていくんだと信じている。
万が一いただけたサポートは、本や本屋さんの収益に回るように活用したいと思います。
