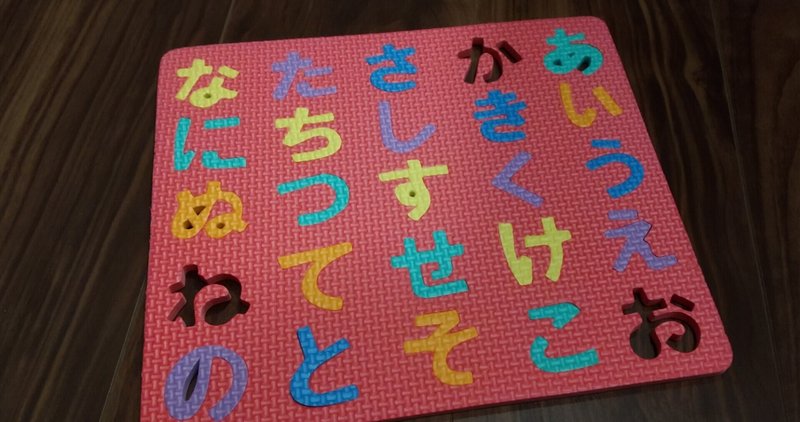
通貨発行と日銀バランスシート論
通貨発行を考慮した日本の運営方針について、世の中で有名な論を私は見つける事がてきていません。だから、考え続けています。
日銀をバランスシートでみると言う論があり、高橋洋一さんがバランスシートで日本が破綻しないと海外に証明したと言っていたのを思い出しました。
バランスシートの右側は調達?
調べると、世に出ている日銀当座預金と発行紙幣を借り方に書いているものは誤解の元との論がありました。
右側は調達という捉え方がある(銀行から借りるとか)けど、日銀当座預金はどこから調達したのか?(通貨発行できるのだから、あえて言えば「神から」になるとの話)
日銀券という不換紙幣を発行しても何かを渡す義務は生じません
私の理解は、金本位制で紙幣が金と交換するものだった時代とは、お金の概念が変わったのだと。
通貨は意図的に増えつづけるモノです
不換紙幣となり、以来世界は毎年5%ずつ通貨を増やしています。五穀豊穣を願い米を神からの恵みと見るかのように、毎年前年比5%で意図的に通貨発行しています(インフレするとお金の価値が長期的に減るので使う方に圧力がかかり、社会で価値の交換が促進される雰囲気がつくられます)。
世界に存在する金という金属がほぼ一定であり、誰かの負債は誰かの資産だと考えるとスッキリした時代と違い、インフレをねらう現代の増える通貨量をバランスするものと捉えることが間違いに感じます。
不換紙幣は金と交換できない
政府と日銀を一つと考えた場合、通貨発行は借用書を預けてお金をもらうようなものではありません。
そしてお金が増える時、債務証書と引き換えに渡されているのではなくて、単に渡されているのです。
金本位制の時は、発行紙幣が右側で左側に保有する金を書く考え方もあるかもしれませんが、通貨発行も信用創造の概念も表現しにくいと感じます。
バランスシートは「誰かの資産は、誰かの負債」として等しくなるという考え方です。負債というと「返さなくてはならない」感じがしてしまいますが、通貨発行に関していえば「神から単に毎年前年比5%で渡されるもの」と捉えた方が自然です。
銀行の信用創造とバランスシート
銀行自身の説明では、信用創造すると「資産に貸し出し金」「負債に創造したお金の預金」をいれる(バランスして両側に増える)とありました。しかし私の考えは違います。

信用創造すると、上図での固定資産に貸し出し金になる(1年以内に現金化しないが、10年などかけて固定資産→流動資産の現金に変わる)。預金は預かっているだけなので、次の扱いが考えられます。
1.書かない。
2.預かっているサービス料を貰うので「サービス料という資産」。
3.預かって金利を払うので「金利分の0.001%の負債」
金利はほぼ今は0なので、振り込み料などサービスとのバランスで考えると、預金が負債とみる時代は終わったかと思います。となると「書かない」が今は自然なのではないでしょうか?
信用創造で銀行に生まれた資産とバランスするのは、日本銀行の紙幣発行の負債(世の中にお金が増えたという意味において)なのかなとも感じます。
まだ、自分の中でもまとまっていないので、もう少し考えていきたいと思います。皆様はいかがお感じなりましたか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
