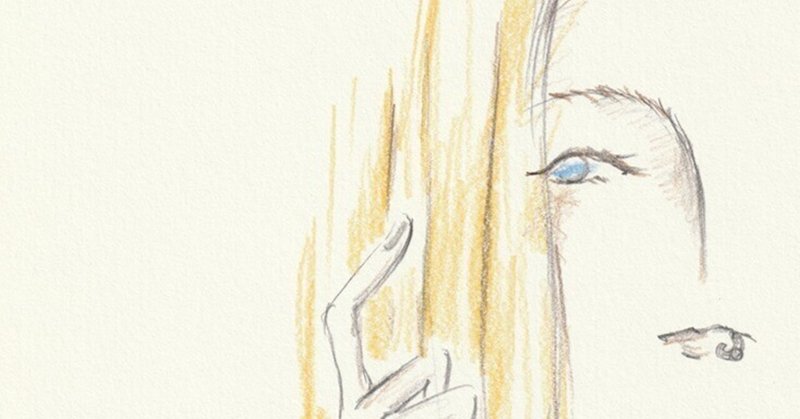
その名はカフカ Disonance 3
2014年9月プラハ
レンカが仕事においても単独行動を許されたのは、六月にスロヴェニアから戻ってきた直後のことだった。アダムはレンカに「どのような状況で誰と行動すべきかの判断は自分でできるだろう」とだけ言った。実際、レンカが常にアダムかエミルのどちらかを伴わなければならない環境よりも、ある程度レンカが一人で動けたほうが、あとの二人が並行して別の仕事ができるという意味でも効率がいい。レンカ自身も「一人になるな」と制限されているよりも、勝手な行動は取らなくなるような気がした。そして、誰かがついているべき状況で、一人にならざるを得ない時には、もう無理をして自分だけで解決しようという気は起こさないのではないか、と考えられるようにもなってきていた。
この日は数年来の顧客との面会があり、レンカはプラハ城の近くで協力者の一人が経営するレストランに来ていた。レンカは自分の事務所に招く人間は最小限に抑えたいと常々考えていたが、ドイツからやって来るその客も、景観の良いこのレストランが気に入っているようだった。プラハ城はプラハ観光の中心地ではあるが、城へ向かう上り坂の中腹でその坂と枝分かれした細い車道に面して佇むそのレストランの周りは観光客も滅多に通ることはなく、常に静かだった。
面会の相手も警戒すべき人物ではなく、オーナーが協力者である店を指定したことから、レンカは一人で面会に臨むことにした。エミルには他の仕事に集中してもらうため、通信機器で繋いでおくこともせず、後で録音したものを渡すことにしていた。
昼食時には混み合っていた店内も、午後二時を過ぎるとレンカの他には二、三の二人連れがレンカからは距離を置いて座っているだけだった。まだ面会相手が来るまでには十分ほど時間がある。先方は具体的に何を依頼するつもりか事前に言っていなかったな、と交渉内容の予想に考えを巡らせ始めたところで、レンカは何者かが自分を目指して近づいてくるのを感じた。まだ店からは離れたところにいるが、その人物の荒々しい気の塊が自分に向かって突進してきている、そんな確信があった。今日約束している客ではない。彼は気配らしいものは綺麗に消し去ってやって来るのが常だった。では、誰なのだろう?今日は何の危険もないはずではなかったか、とレンカは焦って意識の深い部分を探ったが、そもそも「直観の警告」は探して見つかるような代物ではない。そんなことをしているうちに、レストランのドアが開き、突風のようなスピードで一人の若い女が店の片隅に座っているレンカのほうに近づいてきて、レンカの半メートルほど手前で立ち止まった。
まだ高校生かと思われる女はレンカに
「お姉さん、あたしが誰か、分かるよね?」
とだけ言った。レンカは黙って頷いた。その初対面の女の顔は、レンカにとっては名刺のようなものだった。女はレンカの向かいの椅子に勢いよく腰を下ろすと、レンカのほうに椅子を引き寄せた。
レンカはカウンターの側に立って心配そうに指示を待っているオーナーに目で「大丈夫だ」と伝え、女に視線を戻した。女はブロンドの髪を長く伸ばし、下唇の左の隅にピアスをしていて、眼鏡はかけていなかったが、それでも顔はエミルと瓜二つであることは一目瞭然だった。エミルと妹のジョフィエは八歳も歳の差があるというのに、ここまで似るものだろうか、とレンカは心の中で感嘆した。何を思っても外部の人間の前では感情を表さないよう訓練されているレンカは、当然のことながら驚きを顔には出さず、無表情でジョフィエの顔を見つめた。ジョフィエは目もエミルと同じ深い青色をしていたが、その色の持つ表情は、少なくともレンカにとっては、エミルとは全く違ったものだった。エミルは常に何かを観察しているが、ジョフィエの目は、まるで「私は見たいものしか見ない」と宣言しているかのような印象を与えた。
ジョフィエは右手の人差し指で自身の右耳を軽くはじいて
「繋いでないよね?」
と聞いた。レンカは首を横に振った。
「録音は?」
「まだ、始めてないわ」
ジョフィエはこれまでレンカの仕事のために様々な機器を作ってきたが、一度もその注文主である「エミルの上司」に関心を示したことはなかった。エミルはジョフィエの制作費を断っていたが、本人は納得していなかったのかもしれない。他に何かジョフィエがレンカに話したいことなどあるだろうか?レンカはジョフィエの意図が全く読めず、とりあえず
「いつも、お世話になってるわね」
と言ってみた。ジョフィエの目はレンカの目を真っすぐ見つめていたが、レンカが普段エミルの視線に感じる「心の中まで見透かされているかもしれない」という感覚は全くなかった。エミルはよく「見たくないものまで見えてしまうことがある」と言うが、ジョフィエにそのような悩みは皆無のようだった。外見はこんなに似ているのに、人間性は全然違うんだな、とレンカはジョフィエの瞳を観察しながら思った。
ジョフィエはレンカの言葉には答えず
「お姉さんさ、いつもエミルにあたしのこと、頭がおかしいって聞かされてるよね?」
と言いながら肩にかかった髪を後ろに振り払い、テーブルに頬杖を突いた。
ジョフィエの言ったことは、ほぼ事実だった。精神が不安定な天才少女である妹は時々暴走して犯罪を犯しかねない、だから未だにエミルは妹を抑制するため祖母のところで実家暮らしをしている、と言うのが、レンカが把握しているエミルの現状だった。レンカ自身は自分の姉に長年冷たい態度を取り、距離を置いている。エミルとジョフィエの絆の強さは当初、レンカには理解しがたいものだったが、二人の両親がまだジョフィエが幼かった頃に失踪してる事実を考えると、レンカは自分がとやかく言えることは何もない気がしていた。
ジョフィエはレンカの何を言っても動かない表情を追いながら、言葉を続けた。
「あれ、演技なんだよね、分かる?エミルが怒ると楽しいから。だいたいあたしが犯人だってバレるようなハッキング仕掛けるわけないじゃん。エミルの目の前でやると、心配してくれるからやってるの。でもねえ、エミルが言ってるような、自分で制御できないような暴走とは違うんだよ?」
「……どうしてそんな話を、私に聞かせるのかしら。あなた、どうやって今日私がここにいることを知ったの?」
レンカの反応に、ジョフィエは小馬鹿にしたような顔をした。大人の言うことはことごとく面白くない、とでも言っているかのような顔だ、とレンカは思った。
ジョフィエは同じ表情のまま暫くレンカを見つめていたが、再び新しい悪戯を思いついたかのような顔をして
「お姉さんは、知らないよね?エミル、女がいるんだよ」
と言った。
レンカはジョフィエの「女がいる」という表現に唖然とした。彼女がいる、恋人がいる、付き合っている人がいる、他にいくらでも言いようがあるのにもかかわらず、なぜこの子はこんな表現を選ぶのだろう?これも兄への執着の現れなのだろうか。そんな思いが頭の中では飛び交っていたが、相変わらずレンカの表情は微動だにしなかった。
ジョフィエはレンカの顔を見つめたまま言葉を続けた。
「今回はかなり本気みたい。エミル、家を出るかもしれない。ねえ、お姉さん、あたしを雇ってよ」
レンカはジョフィエの最後の一言に、ようやく心持ち厳しい表情に目つきを変化させた。
「あなたのお兄さんが家を出ることと、私があなたを雇うことに、どんな相関関係があるのかしら?」
「だからさ、エミルはやっぱり心配するでしょ、あたしを残して女のところに転がりこむなんてさ。でも同じ会社に雇われてれば、エミルもあたしが道を外してないか、簡単に確認できるじゃん」
「今までいろいろ工作してもらっておいて言える立場じゃないかもしれないけど、私、子供は雇わないの」
「あたし、成人してるよ?」
レンカは更に厳しい視線をジョフィエに向けた。
「自分が大人だという自覚があるのなら、まずそれなりの作法を身につけなさい。あなたの私に対する態度は、どう見ても初対面の大人に対するものじゃないわ。あなた、この九月から高校の最高学年でしょう?まずは高校卒業試験と大学入試を滞りなく済ませなさい。あなたの要求について検討するのはその後ね」
「あたしにとって、学校のお勉強って言うのがどんなに簡単なのか、お姉さんは分かってないね」
「きちんと試験会場に行って試験を受けなければ、合格の可能性はゼロでしょう。あなたを見ている限り、そう言った常識的なことが実行できるかどうかも怪しいわ。それから、もし本気で私のところで働きたいのなら、今すぐそのふざけたハッカーの真似事はやめなさい。目的意識の欠ける犯罪行為ほど無駄で無意味なものはないわ。そんなことを続けていたら、そのうち自分のしていたことは所詮素人の趣味の領域を出ていなかったんだと思い知らされることになるわよ」
ジョフィエはレンカの言葉を聞きながら、心底面白くなさそうな顔をすると
「お姉さん、妙に説教臭いな。予想外に真面目だね。お姉さんみたいな立場の人だったら、もっと頭のねじが飛んでるもんだと思ってたよ」
と言って立ち上がった。レンカは何も答えなかった。
「お姉さんには気に入ってもらえなかったみたいだけど、雇ってもらいたいっていうのは、けっこう本気だから。考えといてね」
そう言い残すと、ジョフィエは踵を返し、店から颯爽と出て行った。ジョフィエと入れ替わるように、約束の面会相手が側近を一人連れて入り口から入ってきたのに気が付き、レンカは腕時計に目をやった。ちょうど面会の約束をした時間になっていた。ジョフィエはレンカがこの時間に顧客と約束していたことさえも把握していたのだろうか、という疑問が湧き、レンカは少し眉を寄せた。

【補足】
チェコ共和国での成人は十八歳、高校は四年制ですから、順当に進級していった場合、高校最終学年で十九歳になる、と言うことになります。
ジョフィエは1995年生まれ、今学年度で十九歳になります。
【地図】

豆氏のスイーツ探求の旅費に当てます。
