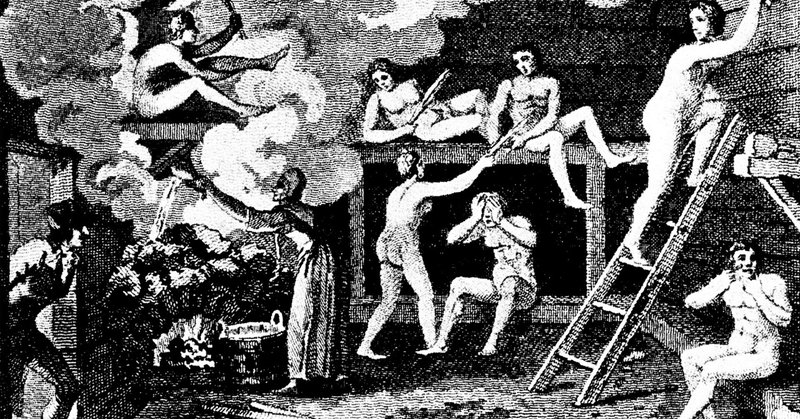
サイバネティックスとしてのサウナ
技術の進化と制御の欲望
人間は技術を利用して様々なものを制御してきました。例えばSpaceXのファルコン9ロケットが打ち上がったあと、ブースター部分が、まるで打ち上げ映像の逆再生のように戻ってくる様子を見てびっくりした人は多いと思います。
これは、ロケット部分が常に自分の姿勢をセンシングしながら、翼とガス噴射を利用して常に理想のポジションに少しづつ補正していくという、「フィードバック制御」という技術を利用しています。高いセンシング技術と、高い制御技術を組み合わせることによって、これまで制御が不可能と思われたものが制御可能になったのです。
2013年にスイスのチューリッヒ工科大学が開発した立方体型ロボットも、内臓された慣性センサの数値を元にモーターによってホイールの回転数を制御することによって、常に自分のバランスを崩すことなく自立し、跳ねたり転がったりすることができます。
こうした数々の不可能を可能にしてきた「制御」の欲望は、やがて機械的なシステムにとどまらず、我々人間自身を制御することへ向かうことになります。
人間を制御する手段としてのデジタルヘルスケア
近年スマートフォンやスマートウォッチをはじめとするモバイル/ウェアラブルデバイスによって、ユーザの運動量や睡眠時間といった健康関連情報をセンシングして記録していくことが簡単にできるようになってきました。一日の歩数や消費カロリーが可視化されると、自然とつける前よりも運動量が増えるという方も多いようです。
こうしたシステムは、多くの場合、データを可視化するだけではなく、座りっぱなしの状態が続くと軽い運動をオススメされたり、よりユーザを健康な状態に導くような「フィードバック」をしてくれるようになりました。これはウェアラブルデバイスを利用して習慣的行動変容を促すことによって、人間をより健康になるように制御する技術といえます。
2010年には、血糖値を記録することで、適切なタイミングで疾患指導や生活習慣・モチベーション維持に関するアドバイスをもらえる糖尿病治療用のスマートフォン向けアプリ「Bluestar」が、大規模な臨床試験において、糖尿病新薬などの医薬品と同等以上の効果があったという結果が示され、日本の厚生労働省にあたる、米国のFDAの認可を取得し、「デジタル薬」として、医師から処方されるようになりました。(近年このような「デジタル薬」は「デジタルセラピューティクス(DTx)」と呼ばれています)
人間の身体や心の健康を制御するには様々なアプローチがあります。薬や食べ物を直接身体の中に取り込む方法から、デジタルセラピューティクスのような行動に介入するアプローチ、微弱な電気や磁気によって体内の神経活動を操作するニューロモジュレーションと呼ばれるアプローチや、催眠などもその有効性が認められています。
「ととのい」のメカニズム
近年人気のサウナも、温冷刺激という外的制御によって人間の気分を変容させる制御技術ととらえることができそうです。
暑いサウナ室に入ると、身体は熱を放散するために血管を拡張させ、皮膚の表面に熱を放出します。このとき、心臓は体温を下げるために、血液を皮膚の表面に送り出し、体温調節を行います。この過程で、心臓は血液を押し出すために、心拍数を上げるといわれています。
そして、サウナ室から出て、水風呂に入ると血管が収縮して血圧が上昇するため、交感神経が刺激されて一時的に心拍数が上昇します。しかし、一定時間が経過すると、身体が水温に適応し始め、副交感神経が優位になって心拍数が下がります。
この、一度上がった心拍数と体温が急激に低下していく中で副交感神経が優位になっていくという一連の流れが、いわゆる「ととのい」の気分をつくるメカニズムの一つと言われています。
自律神経は人間が意識的に操作することができません。また、心拍数も同じように意識的に操作することはできません。しかし、自律神経と心拍変動の関係や、心拍と温冷刺激の関係、心拍と呼吸との関係といった、人間というシステムのメカニズムが明らかになるにつれて、実は、昔から存在したサウナのような温冷刺激のメカニズムに説明がつくようになる、というのは非常に興味深いですよね。
サウナと人の関係は、ある種「サイバネティックス」ととらえることができるのではないか、という気がします。
サイバネティックス
「サイバネティックス」とは、1940年代に数学者ノーバート・ウィーナーによって提案された横断的な学問領域で、通信・制御・統計力学を駆使することによって、(まさに上で触れたフィードバック制御のように)本来制御できないものを、別の制御可能な要素を操作することによって制御することができ、そしてそのメカニズムは機械だけでなく、生物や社会にも適応し得るのであるという、1940年代とは思えない先進的な仮説をベースにしています。(生物を機械と同様の制御可能なシステムとして捉えるというサイバネティックスの思想は、後に「サイバースペース(Cybernetic Space) 」「サイボーグ (Cybernetic Organism)」といった言葉を生み出すことになります。)
われわれの状況に関する二つの変量があるものとして、その一方はわれわれには制御できないもの、他の一方はわれわれに調節できるものであるとしよう。そのとき制御できない変量の過去から現在に至るまでの値にもとづいて、調節できる変量の値を適当に定め、われわれにもっとも都合のよい状況をもたらせたいという望みがもたれる。それを達成する方法がサイバネティックスにほかならない。
サイバネティック・サウナの可能性
この考え方をさらに推し進め、サウナと身体を一つのシステムとして捉え、より高い「ととのい」を目指すシステム、いわば「サイバネティック・サウナ」のようなものを考えることはできないでしょうか。
サウナ愛好家御用達の情報サイト「サウナイキタイ」に投稿されている様々なサウナのレビューをのぞいてみると、サウナ愛好家の方々は「サウナ室→水風呂→休憩」の組みわせを1セットとし、それぞれの時間を記録して最も自分が整いやすい「サウナ・ルーティン」を作っているようです。といっても、常に決まった時間入っているわけではなく、サウナ室の温度、湿度、水風呂の温度などによって微妙な調整を行なっているようです。ただし同じ条件でも個人によって「ととのいの可否」についてはバラつきがあり、個人の経験の蓄積による暗黙知がベースになっているようです。
仮に「ととのい」=副交感神経優位の状態だと定義すると、何かしらの方法で副交感神経の活動量(制御できないもの)を測定することができれば、この値を最大化するように「サウナ室」「水風呂」「休憩」それぞれの時間(調節可能な変量)を指示するようなシステムが考えられます。
例えば温度計/湿度計/マイク/脈拍系が搭載されたウェアラブルデバイスを装着した状態で、一連のサウナセッションを行い、副交感神経の変化量を計測することによって、「ととのい具合」をシステム側で評価するとともに、ユーザ自身が「ととのい具合」を評価し、学習のループを回すことによって、徐々にユーザにフィットした「ととのい」をもたらすためのサウナ・ルーティンを提案してくれる…といったイメージです。
自律神経の活動量を非侵襲的手法で比較的定量的に計測する方法としては、心拍の拍と拍の間の時間の変化量=心拍変動を測定し、一定時間の心拍変動のスペクトル解析することによって交感神経、副交感神経の指標を算出するアプローチが知られていますので、これを活用するのは一つの手でしょう。しかし正確な心拍変動を記録するためには高いセンシング精度が求められますし、また100度近くまであがるサウナ室の中で高い精度が見込めるデバイス類の選定やハウジングのデザインなど、実現にあたっては様々な課題があります。
「ととのう」とは自らを制御すること
このように、人間という関数の特性(どのような刺激をあたえるとどのような変化が起きるのか)が明らかになるにつれ、今後、人間は自分達自身を制御するための様々なテクノロジーを開発していくでしょう。
これまでのように、有効成分を直接摂取するタイプのアプローチではなく、思いもよらなかったような方法…それは例えば風邪をひいた時にはこの映画を見るといいとか、ひたすら雑務をこなしたい時はBPM170以上のドラムンベースを聴くと良いといったようなもの…が発見されるかもしれません。
自らを一つのシステムと捉え、能動的に刺激を与えることによって自らを自発的に調律していくこと。その行為こそが「ととのい」という言葉の指し示すものなのかもしれません。
※そして、これはまさに「身体情報学」の領域といえるでしょう。THE TECHNOLOGY REPORTでは、この分野の第一人者である稲見昌彦先生にインタビューさせていただいた記事がありますのでこちらもぜひ。
この記事は、Dentsu Lab TokyoとBASSDRUMの共同プロジェクト「THE TECHNOLOGY REPORT」の活動の一環として書かれました。この記事の執筆者はTHE TECHNOLOGY REPORT編集チームの一員でもある、Dentsu Lab Tokyoの土屋泰洋です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
