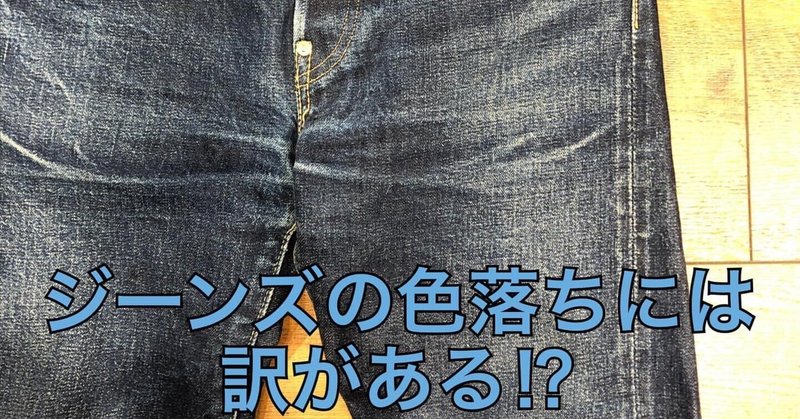
501XXジーンズのあのかっこいい色落ちにはワケがある!?
デニム生地ってなんであんな美しい色の落ち方を
するのだろう。
そのポイントはいくつかあって。
まず糸。
綿花として摘まれた綿は撚りを加えることで細く
強い糸になります。
この撚りの技術は今よりもずっと拙く、均一の太さに
撚ることか難しかった。また綿花の不純物を現代ほど
丁寧に取り除くことができなかった。
結果として凹凸感のある糸になり、
その糸が使われていたということ。
染料
インディゴ染料はそもそも浸透力が弱く糸に
定着しにくい性質を持っています。
その染まりにくいが故に糸の芯まで染まらず、
中白というドーナツのような染まり方をします。
これがジーンズの色落ちに一役買っています。

染め方
デニム生地の登場までは糸をインディゴ染料で
染める時はかせ染めと言われる製法が一般的でした。
これは束ねた糸を染料のカメに漬けては絞り、空気に
さらして酸化させ、深い藍色にしていく訳ですが、
これには時間と手間がかかります。
そこで大量の糸を一気染めるための技術として
ロープ染色が開発されます。

これはジーンズを作るために開発された技術といっても
過言ではないでしょう。
このロープ染色。ロープ状に束ねた糸をインディゴ
染料の水槽に潜らせては酸化させる作業を一気に
繰り返し、染め上げます。
安価で大量に染められるのですが、かせ染めと違い
糸の中心までは染まらないんです。
結果として中白の糸が生まれました。
推測ですが
元々インディゴは蛇避けであったこと。
作業着であったことを考慮に入れると、
全く色落ちのしない生地を
作る必要はなかったのでしょう。
安価で大量ということの方が当時は重要だったことが
伺いしれます。
織り方
そして織り方。これは前にも独り言で話しましたが
シャトル織機は過度なテンションがかからず、時間を
かけて織られるため、程よく柔らかく、
よく言えば風合いのある、悪く言えば凸凹した生地が
出来上がるわけです。

こうして均一ではない糸が風合いのある凸凹した
生地になる。
そこにインディゴならではの色落ちしやすい染料で
染められていれば、
おのずと色落ちは一本ごとに表情が違うほど
千差万別の色落ちをもたらすことになったんです。
現在はその生地を再現するため
コンピューターによって意図的にムラ糸を作り
古いシャトル織機で生地を織り、ジーンズを作る。
そうして現代のセルビッジジーンズは生まれています。
やはり当時の糸そのものや染料そのものを再現するのは
かなり困難になってきています。
綿花の育て方自体も進歩し、綿自体が不純物が少なく
均一に細く撚りやすい綿が多くなっていているから
です。
染料も今はより進歩して糸に定着しやすくなっています。
やはり本物には叶わないということかもしれません。
でも現代のジーンズにはまた違った魅力が多く詰まって
います。
自分の好みに合った風合いで当時のような色落ちに
近いジーンズを見つけることができるはずです^_^
その中でもやはり日本製のジーンズは世界一だと
思っています。
日本製のジーンズを履き比べてもらえたらな
と思います。
ジーンズってなんで破けやすいのかなって
考えていて、生地の特徴なんだろうなあ
と考えてるうちにデニム生地について書いてました😅
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
