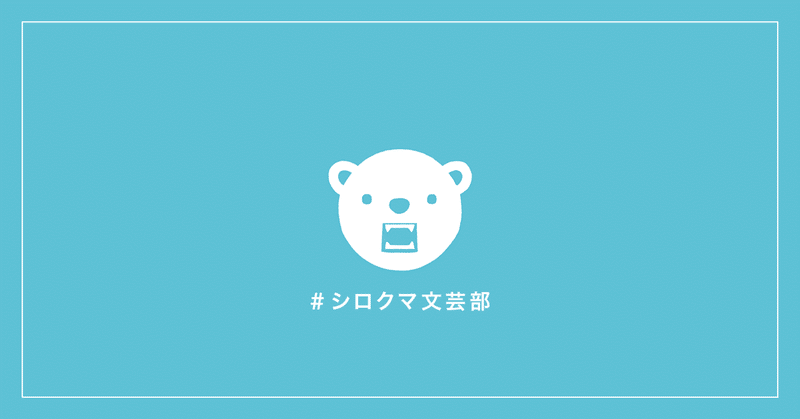
秋が好き(#シロクマ文芸部)
「秋が好き」
きみは蜻蛉の羽のごとく透けそうな声でつぶやく。
それはたちまち、窓辺でカーテンを揺らす風にまぎれて消えた。
秋の日は釣瓶落としというが、つい先ほどまで、部屋の隅にも届きそうなくらい光の裾を伸ばしていた西陽は、静かにドレスの長いトレーンを引きずって去っていく。
(頼むから、きみまで連れていかないでくれ)
ぼくの手の中で、きみの手は透けていき、しだいに温度を失っていく。
口もとは「き」のまま、横にかすかに開いていて、うっすらと微笑んでいるようにみえた。
もしも、生涯の会話の文量というものがあらかじめ決まっていて、それが尽きたら、おしまいなのだとしたら。きみは、もう、十分に語りつくしたというのだろうか。そんな最後のひと滴のようなつぶやきだった。
‥‥‥‥
「秋が好き」
きみは鳶色の大きな瞳を見開き、まるで宣言するように胸を張り、くすっと笑って挑戦的な目でぼくを覗いた。そのときぼくがどんなに戸惑って、そしてどんな表情をしていたのかは、もう覚えてはいない。
けれども、この言葉がぼくたちのはじまりだったことだけは確かだ。
世の中はバブル景気の最後の残照にきらめいていた。
ふたりで暮らしはじめるのに、いくらも時間はかからなかった。
おそらくぼくたちは、町のはずれにある古い図書館の書架に並ぶ書物と同じ文量ぐらいは語り合ってきた。お互いをもっと知りたくて、読んだ本や好きな映画や漫画、駅前のパン屋の新メニューについてやその日見た雲のことなど、そんなどうでもいいことから、ときには宇宙物理や哲学の話なんかもした。気づくと2DKのアパートの掃き出し窓から、うっすらと白い朝の陽がにじむこともあった。
きみはキッチンに立ちながらよく「秋の日の/ヰ゛オロンの/ためいきの」と、上田敏が訳したヴェルレーヌの詩を口ずさんでいた。
ねえ、バイオリンじゃなくて、「ヴィオロン」というところがすてきでしょ、といいながら。
ほんのちょっぴり文学少女で青臭かったぼくたち。ディスコに繰り出す代わりにプラネタリウムで肩を並べ、水族館で手をつないだ。
けれども、歳月が落ち葉のごとく積み重なるにつれ、しだいにぼくは、きみの話にあいづちをうつだけになった。新築マンションの購入と引き換えに仕事に追われ、一日の大半が仕事だけで埋め尽くされるようになると、ぼくは語る言葉を失ってしまった。本のページをめくる時間などなく、美術館に出かけることも、家でDVDを鑑賞することすらなくなった。
流産のあと仕事を続けられなくなったきみは、たまにパートで働く程度だったから。ときどき映画を観にでかけたり、誰それとランチに行ったなんて楽しそうに話す。疲れて帰ってきたぼくは「気楽でいいよな」と毒づく。それでも性懲りもなくきみは、遅い夕飯を胃に流し込むだけのぼくの前に座って、ひばりのようにさえずり続けた。
「秋が好き」きみは、話のあいまに時おりつぶやく。
ぼくはそれに気づかないふりをして無視する。
どんどん干からび、くたびれていくぼくの世界を、きみは必死でこじ開けようとしてくれていたんだと、今ならわかる。
傲慢だったぼく。
秋久という名のぼくを、きみは「秋」と呼んでいた。だから。
「秋が好き」ときみがつぶやくたびに、今さらそんな恥ずかしいことを言わないでくれと苦々しく思っていたけれど。もしも、面と向かってそう返したら、きみはきっと笑いながら
「もう、自意識過剰なんだから。わたしは、大好きなモンブランがおいしくなる秋が好きなの」とでも言い返していたかもしれないね。いたずら好きな瞳をくるくるさせながら。
ああ、それでもぼくは、「秋が好き」ときみがつぶやくたびに、
「春が好き」と言えばよかったよ、春香。
<了>
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
今週は、なんとかまにあいました。
あいかわらずの駄作ですが。
サポートをいただけたら、勇気と元気がわいて、 これほどウレシイことはありません♡
