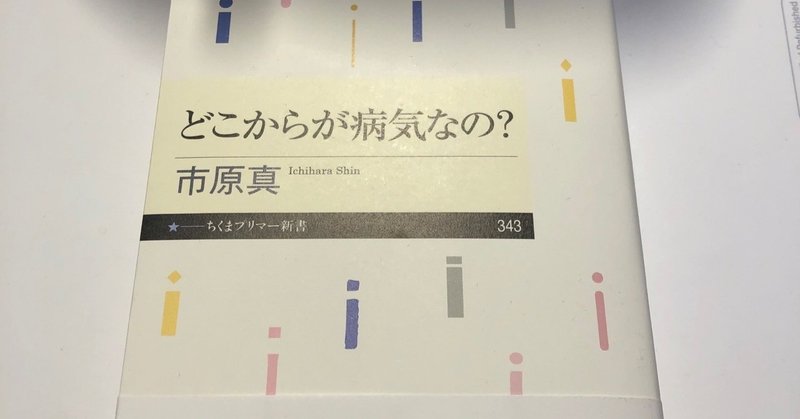
市原真『どこからが病気なの?』(ちくまプリマー新書、2020)
このブログは、あくまで未来の自分に知識を送るために書いたものです。思いっきり主観的です。私以外にはおそらく参考にならないため、みなさまは是非本を買って読んでください。
未来の自分へ
2020年現在の私が、ツイッターでフォローしている病理医ヤンデル先生こと市原真先生の本を読んだよ。まだ彼をフォローしていますか?ヤンデル先生は相変わらずウサミミをつけて、高度すぎる親父ギャグを連発していますか?ヤンデル先生とよう先輩がやっているポッドキャスト「いんよう」はとっても面白いから、まだ続いているといいなぁ。
この本を手にとった理由は、ヤンデル先生(市原真先生)が書いたから面白いだろう、と思ったから。
本の内容は以下の感じ。
プロローグ「病気と平気の線引きはどこ?」
なんと市原先生はお題を編集者のTさんにお題を送ってもらって本を書いているらしい。それをこんな冒頭から話す人いる?
プロローグでは、この質問「病気と平気の線引きはどこ?」について取っ掛かりを探している。医者が提示する「正しい回答」と、みんなが「求めている回答」がマッチしない。というか、医者が提示する正しい回答は、地味でもんやりしていて分かりにくいとすら思った。それに比べて「この水を飲めばがんが治る」的なニセ医療は方法そのものズバァッと明確に提示してくるので惹かれてしまうところがあるのだろう。いや、ダメだけどさ。
医療従事者でもなんでもない当時の私はこの質問に対し、「病気は病院へ行かないとマジムリと思うとき、平気は病院へ行かなくてもOKOKと思えるとき」と超絶気安く考えたが、そんな簡単な線引きじゃなかったことも言っておく。
第1章 病気ってどうやって決めるの?
「医療シアター」という捉え方、分かりやすいし面白い。群像劇であり複雑系。
・病気だと決める人は誰?
大きく分けて3つ。本人、医者、社会。私たちは幼少時から様々な痛みやなんやらを経験し、周囲の助けを借りて乗り越えていくことによって、ほぼ直感的に未来予測する力を獲得していく。自分では予測不能な事態にぶち当たった時、更に多くの経験知識技術を持つ医者のところへ行って自分の代わりに予測してもらう。社会とは患者と医者以外、例えば家族とかが病気という枠に当てはめることもある。
お腹が痛い時、「痛い無理しぬうわあああああああん(大人なんとかしろー)」→「最近便秘過ぎたわ、トイレにこもってウンコすれば治るな、多分(自分で診断、未来予測)」→「あれ?あれれ?くっそ腹痛いだけかと思ったら気持ち悪いし目眩もするし、冷や汗まで出てきたゾ⭐︎(ピーポーピーポー)」のような雑すぎる例を添えておく。
・すぐ分かる病気=医者がすぐ行動する病気
名医と呼ばれる人たちは、出会った瞬間に患者や救急隊の報告するエピソードから受ける全体的な雰囲気(これをゲシュタルトと呼ぶ人がいる)を、そのままふんわりと受け止め、いちいち言葉にして解析せずに即座に行動に移し、行動することでさらにそこから深く考えるためのヒントを次々と探り出していく。(p.53)
医療に限らず、沢山の経験値が溜まった人って、論路的思考による行動が直感的に見えることあるよね。 ある程度予測がついていて、それを確定させるために他の選択肢を潰していく感じ。
考えるより先に行動することはありふれてるよ、という例として、
耳元でブーン→ウッギャと叫んで首をすくめて飛び退く→音が聞こえないところまで逃げながらそちらを見る→虫らしきものが見えたらさらにまたフギャアと叫びながら、時間をかけて物体を目視→「なんだハエかよ」とようやく理解。(p.55)
な、なんだこの秀逸な例えは・・・。ウッギャとかフギャアとかあんた・・・確かにそうだけど・・・笑い転げたw
・救急車を呼ぶか迷ったら、Q助
この書で市原先生がオススメしている「Q助」というアプリを初めて知った。これは元気なうちにスマホに入れておこう。一生使わなければそれでいいし。文字がくっきりはっきりして見やすいし、直感的にパッと選べていい感じ。「消防庁やるやん・・・!」などど上から目線で感動してしまう。
あのね、でもね、早速AppleStoreで「Q助」って検索したら、該当のアプリがズバリ出てこなくて、どこやどこや探したけど無くて。結局、検索上位に出たストーリーの中に入ってたからダウンロードできたけど、勿体無くない?これって私だけかい?
・なかなか分からない病気
医者の言う「様子を見ましょう」という言葉に、私は大いなる誤解を抱いていた。「様子を見る」というのは、投薬などに対する反応を見ること、時間経過観察ということであり、「この病院では分からないからお手上げ〜」というような意味ではないのね。一発解決!する治療があればそれを施しているだろうし、こちらの都合で「何回も通院するの面倒だから一発で治してよ」というのはおこがましかったな・・・。うう・・・反省。以下、そんな私にぐっさりと突き刺さった言葉。
まず、一度医者が出した薬が効かなかったときに、その医者をヤブ医者と認定して次の医者に行くというのはあまりいい選択ではない、ということを知っておいてほしい。医者は、この薬が効かなかったらこっちだなと、ニの矢三の矢を放つ準備をしている。最初の薬が効かなかったという強力な情報を医者が手に入れることで、次の行動はより明確になる。それをしないで、医者を替えてしまうというのはいかにももったいない。
高校生の頃、肺炎になった時、元気になったからと再度受診もせず、薬も途中でやめたし・・・プロじゃないのに、アホだったなぁ・・・。
・病気には原因がある?
世にある多くの病気のほとんどは、原因は一つじゃない。複雑系。人間も複雑系。人生の選択の連続をくじに例えるの面白い。自分の選ぶ行動によって未来のくじの中身が変化する。
・結局病気ってなんなの?
市原先生が今度新しく出版する本では、
病気とは「こないだまでの自分がうまく保てなくなること」、健康とは「こないだまでの自分をうまく保ち続けていること」(ホメオスタシス)。
のように定義したらしい。
第2章 それって結局どんな病気なの?
まず、体性痛と内臓痛、あと血管痛(と関連痛)の話あり。読んでいてなんか聞いたことあるな?と思ったら、同じく市原先生の『症状を知り、病気を探る 病理医ヤンデル先生が「わかりやすく」語る(照林社)』で読んだっぽい。あれすっごく分かりやすかったぞ。あれを読むまで、痛みに種類があるなんて知らなかったし。
以下のちょっと具体的な病気の内容については、漫画『はたらく細胞』を読んでいたので、文章から映像にイメージしやすかった。はたらく細胞は最高、はっきりわかんだね。
・腹痛
・かぜ、肺炎
「人体の防御システムはすごい」という小見出しで語られているところで、私が妙に感激(?)したところ。
そもそも皮膚という皮が強烈な防御力を発揮している。お風呂に入っても水が侵入しない時点でとんでもなく高性能なバリアであることがわかるだろう。自然界に存在する、金属以外の多くは基本的に水が浸みるのだから、皮膚がいかにすごいかという話だ。
冬寒い時にさ、乾燥して痒くて、適当にボリボリかきむしって、「なんでこんな痒いねん、だから私の皮膚弱くて嫌だわ〜」とか逆ギレしてさ。皮膚さんたちが内部に外敵を入れないように年柄年中頑張っていてくれるのに、大変申し訳なく思ったわ・・・ちゃんと保湿して良い状態を保つようにするね。
・喘息、アレルギー、アトピー
・高血圧
「人体という都市のライフライン、血管」って小見出しになっているんですけど、かっこよくない?なんでこんな語呂いいの?細胞もカスミを食って生きてるわけじゃないから、細胞がお仕事するための栄養が必要。それを送るための大事なライフラインが血管。長く使い続ければガタがくるし、血圧が高ければさらにガタが来やすくなる。高血圧って痛みがないだけに見過ごしやすいし、健康診断で発見されても今現在は直接的な痛みを感じないから・・・将来のリスクを抑えるために現在の快楽を抑制できる人はどれくらいいるんだろう。自分はそう選択できるのかな・・・
・腰痛
・がん 内なる脅威。バグった細胞。
第3章 病気と気持ちの関係は?
・病は気から問題、気合い問題
病は気からに根拠ない。もちろん気持ちは大事だけど。気持ちと気合いは違うで。気合いで病は治らねぇかんな。そんな単純なもんじゃねぇかんな。気合い入れなくていいからお布団で休ませて。この令和の時代にもまだこんなこと言ってる人多いよ。インフルエンザは気合いじゃ治らないし、私という最高に大事な存在にインフル移すくらいなら仕事に来るな。
・病気と平気の線引きはどこ?
第1章の最後でも述べられたように、病気とは「こないだまでの自分がうまく保てなくなること」、健康とは「こないだまでの自分をうまく保ち続けていること」(ホメオスタシス)。
あとがき ならぬ 推薦図書
・中山祐次郎『医者の本音』『がん外科医の本音』(SB新書)
・大塚篤司『心にしみる皮膚の話』(朝日新聞出版)
・國頭英夫『死にゆく患者と、どう話すか』(医学書院)
・東畑開人『居るのは辛いよ』(医学書院)
→シリーズ「ケアをひらく」でも評判らしい・・・読みたい!!!
・『町医者ジャンボ!!』
・あと市原先生の自著『Dr.ヤンデルの病院えらび ヤムリエの作法』『病理医ヤンデルのおおまじめなひとりごと』『症状を知り、病気を探る』
推薦図書に『はたらく細胞』無しかぁ・・・取っ掛かりとして良さそうだよなと思ったり・・・。漫画はダメなのかな?それにしてもまーた読みたい本が増えてしまった・・・。1冊読むたびに4、5冊読みたくなって読んで・・・一体いつになったら私の読書に終焉は来るのか?
以上で本の中身については終わります。
普段からヤンデル先生のツイートに慣れ親しんでいる我が身からすると、市原先生の語り口がとても面白いし、文章も読みやすい。ちょこちょこ入るセルフツッコミにクスッとする。こういう小休憩ポイントが自分的には読みやすいのかな。
最後に。未来の自分、高血圧になってたらやだよ。適度に運動して、いろんな食事をほどほどにして、未来の自分に体を託すから、未来でもめげずに頑張ってね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
