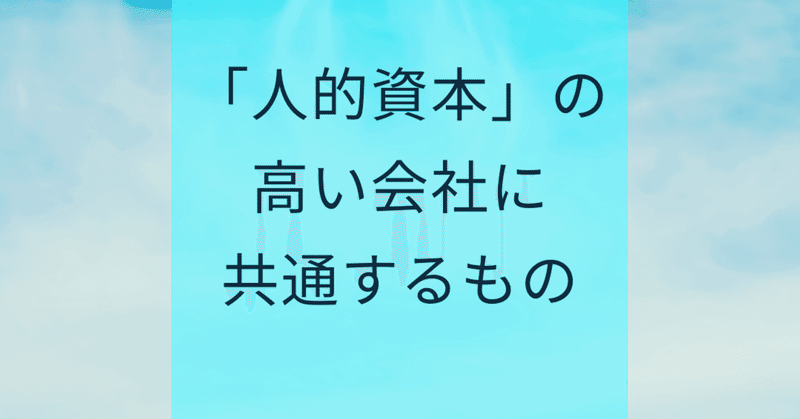
「人的資本」の高い会社に共通するもの ー 私はこんなふうに考えた(2022/5/16)
本投稿は日経新聞に記載された記事を読んで、私が感じたこと、考えたことについて記載しています。
記事の長さはおよそ1,000〜1,800文字ですので、2〜3分程度で読めます。
みなさんの考えるヒントになれば嬉しいです。
よろしければ、お付き合いください。
「マガジン」にも保存しています。
「学びをよろこびに、人生にリーダシップを」
ディアログ 小川
「人的資本」情報開示へ
スキルや女性登用 人材に投資
政府方針
記事のポイント
政府は今夏にも企業に対し、従業員の育成状況や多様性の確保といった人材への投資に関わる19項目の経営情報を開示するよう求める。
従業員を投資の対象である人的資本と位置づける考え方は企業経営で広がっている。製造ラインでの作業などが多かった時代は、人件費をコストと捉える傾向があった。
今は経済のデジタル化が進み、従業員が生むアイディアが企業に利益をもたらす。企業が人材にどう投資しているかは、財務諸表の数値だけでは読み取れず開示気分が高まっている。
内閣官房が6月中にまとめる骨子案では、投資家に伝えるべき情報を19項目に分けて整理する。主な項目は従業員のスキル向上などの人材育成や多様な背景を持つ人材の採用状況など。
企業には自社の戦略に沿う項目を選び、具体的な数値目標や事例を公表するよう求める。従業員の男女比や人種などは、企業ごとの差を測れるように具体的な算出基準の開示を促す。企業によって異なる従業員の研修方法などは、できるだけ具体的な事例を記載してもらう。
金融庁は23年度にも人的資本に関する一部の情報を有価証券報告書に記載することを義務付ける方針。内閣官房は金融庁の方針とは別に、人的資本に関わる幅広い情報公表することを企業に求める。
人的資本への投資の遅れは、日本企業が競争力を失う一因となっている。20年の主要企業の時価総額から有形資産の評価額を引いた額を無形資産の価値と考えると、米国はこの比率が90%を占め、日本は32%に過ぎなかった。人的資本の情報開示が進んでいる米企業は、人材への投資で無形資産を積み上げ、株価を上げている。
岸田首相は「非財務情報開示を推進する」と述べた。形式的な開示内容にとどまれば市場の評価が高まらず、投資家にわかりやすく伝える努力が求められる。
***********
みなさんは、投資でいちばん大切なことはなんだと思いますか?
私はリターン(効果)が大切だと考えています。
せっかく投資するなら、少しでも効果が高いほうがいいですよね。
記事の中で開示を促す19項目と、具体的な開示例が紹介されていました。
この項目を見ると、どこに・どんな投資しているかと、その結果「働きやすい」かどうかはわかりますが、効果、つまり人的資本が高いと市場で評価される企業になっているかは測れない気がします。
みなさんは、「人的資本の高い会社」と聞くと、どんな会社を思い浮かべますか?
いま現在業績の良い会社もあるでしょうね。
私はそれに加えて、「辞めた人が活躍している会社」を思い浮かべます。
元マッキンゼー、元グーグル、元リクルート、元P&G、元GEなど、その会社を離れた多くの方が多方面で活躍されている会社は「人的資本が高い」と感じます。
書籍などの情報によると、これらの会社の共通点として、心理的安全性の高さがあるように思います。
(心理的安全性:誰もが安心して発言や行動ができる職場環境)
ほんとうの人材投資の効果を測りたいのであれば、「心理的安全性の高さ」や「辞めた人の活躍率」などが開示項目に必要だと思いませんか。
参考:19項目と開示例
人材育成(リーダーシップ/育成/スキル/エンゲージメント/採用/人材維持/後継者計画)
・自発的、非自発的離職率
・研究者の確保、定着への議論状況
・後継者の育成プロセス
多様性(多様性/非差別/育児休業)
・性別、人種、民族の割合
・期間中の差別事例の総件数
健康安全(安全/身体的健康/精神的健康)
・労働災害発生割合
・従業員の欠勤率
労働慣行(労働慣行/児童・強制労働/賃金の公正性/福利厚生/組合との関係/コンプラ)
・団体交渉協定対象の割合
・基本給と報酬総額の男女比
・福利厚生の種類や対象
美味しいものを食べて、次回の投稿に向けて英気を養います(笑)。
