
日本書紀の話
昨年が「日本書紀」が完成して1300年が過ぎた、或る意味では記念すべき年でした。
おそらくは日本で最初の正史です。
古事記は正史ではないのですよね・・・・・・最古の歴史書となるようです。
両書には内容に差異があってそれはそれで面白いのですが、古事記の第二十四代・仁賢天皇から第三十三代・推古天皇までが系譜の羅列になっていて、素人には役に立たないのです・・・・・
欠史十代という言葉があるのは今し方知りましたが、聖徳太子の話なんかはまったく古事記だと載っていません。
なので「日本書紀」を中心に見ていくことになりますが、これがまた不親切な歴史書で、言葉足らずな部分が多いのです。

異論は多々あると思いますが、どうやら継体天皇までは集団的指導体制というか族長会議みたいな中から大王が選ばれていたのではないか?もっとも有力で優れた指導者を族長集団の中から選んでいたのではないか、というのが近年の見方らしいです。
イメージ的にはモンゴルのクリルタイに近いのでしょうか。
もちろん、農耕民族と騎馬民族では随分と文化が違うでしょうから、遊牧民が戦の強さでハンを決めたのとは基準が違うでしょう。
ただ、族長会議で大王を選出していくと、有力血族というのが当然のように出来てくる訳で、それが雄略天皇の系統だったのでは?
ところが雄略天皇が跡取り争いになり得る血族をみんな粛正してしまったため、起こったのが断絶の危機。
血縁を五代さかのぼって越(北陸)まで探さなくてはならなくなった・・・・・
今も近代も変わらないのですが、離れた血縁を近くに戻すために近縁の系統の娘を嫁に取ります。
そうなると、元々の跡取りと、新たな嫁の息子の跡取りで、跡目争いになるわけで・・・・・
それが欽明朝での争いなのかも??
欽明天皇の系統が、それまでの曖昧な血族意識から抜け出して、有力な大王家に変わっていった理由というのは、それが蘇我氏との結びつき=蘇我氏との婚姻関係だったのではないか・・・・・・・ここは私の個人的な意見です
継体天皇が出現するまでは、血族意識が希薄で曖昧なままの選出。
ですから三王朝交代説とかは古い言説のようです。
天皇の諡の文字に意味を読み取ろうとする書が多くありますが、それは奈良時代の淡海三船の学識によるところなので、彼なりの人物評は表されているでしょうが、歴史の暗号解きの根拠にするのは勘弁して欲しいです。
淡海三船自身は非常に博学で、漢風諡号にこめた意味は深いものがあると思います。
奈良朝に使える身ですが弘文天皇(大友皇子)の ひ孫 ですから、思うところがあってもおかしくはありません。
現政権批判をいろいろなところで隠しこめていることだって、なくはないでしょう。
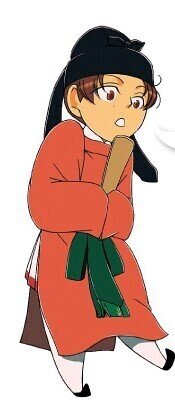
多分、三王朝交代説の根拠にされていると知っても一笑に付されて終わりかなぁ・・・・・
日本書紀が分かりにくいのは、新しい「万世一系」という概念を、それが始まる以前の記録に当てはめ直したせいなのかも知れません?
あ、ここで書いた意見に反論してきても、私には答える材料がないので、ある蒙昧な素人の戯言として読み飛ばして下さいネ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
