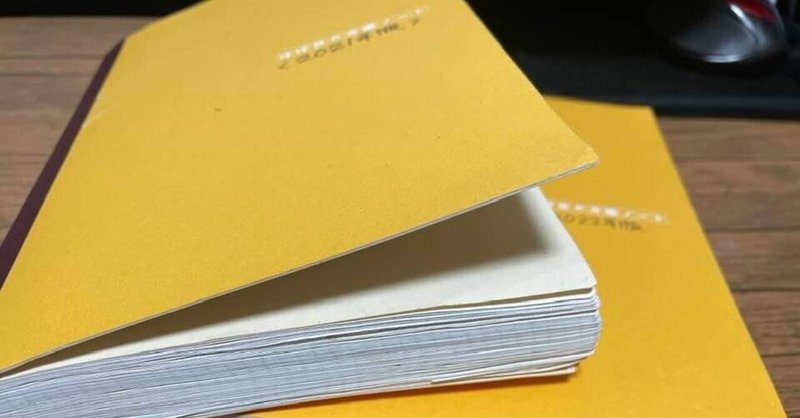
ノートと私(4)
導入研修が終わり、営業所に配属されてからも、教えていただいたことはノートに記録しながら少しずつ覚えていきました。
考えるより行動することが好きなので、1日中デスクに張り付いて同じことを繰り返すことなんて、私に続くだろうか?と不安でした。
注意力散漫で、要領が悪いので、同期入社の高卒の子の方が、手際よく仕事をしており、入社して3カ月くらいは、落ち込んでばかりいました。
仕事に慣れるために、始業時間より早く出勤して自分の業務(帳票と伝票の照合や入力作業)を終えておき、始業とともに入るスポット的な業務にも対応出来るようにしました。
営業所には、どんなに早く出勤しても、私より早く出勤している先輩がいました。その方から、仕事についての考え方ややり方をたくさん教えていただきました。早い段階で、先輩から「仕事は、やり方だけを理解しても応用が効かない。何の目的でどのような流れで行うのかを理解すると、自分なりに工夫出来るようになる」ということを教えていただいたことで、仕事の進め方も変わり始めました。
先輩は、いつでも担当する業務が誰かに引き継げるように、業務マニュアルを作成していました。私も先輩を真似て、人に見せても理解してもらえるような内容にしたいと思うようになりました。
マニュアルづくりのために、通信教育で「フローチャートの書き方」「ビジネス文書」「ペン習字」も学びました。(当時はワープロが普及していなかったので、マニュアルや引き継ぎ書は全て手書きだったのです)その頃作成したマニュアルが↓です。

業務全体の流れを把握することで、期限を意識しながら仕事ができるようになりました。
扱っている伝票の役割や管理の仕方を知ることで、うっかりミスを防ぐこと、ミスをした時の対処の仕方が身につきました。
そして、その後の人生において、何か新しいことに取り組む際に、何をどう理解し、身につけたらよいかを考えながら取り組めるようになりました。
PTA会長を務めたときに作った「PTA会長マニュアル」自治会長を務めたときに作った「自治会運営の手引書」も、この経験によるものです。
マニュアルを作成することにやりがいを感じ、苦手だった業務も面白くなった頃、営業所での実績が買われて、女子社員の教育インストラクターに選ばれました。それまで、教育インストラクターは本社の人事部に所属する女子社員が務めていました。しかし、女子社員のほとんどが、営業所勤務であり営業所の実務を熟知した者もインストラクターを務めるべきなのでは?という考えに変わり、私がその第一号に選ばれたのです。
私はその頃結婚し、「今までのように残業も出来ないし、私がここで仕事を続ける意味があるのかな?」と悩んでいましたので、インストラクターの仕事をやってみることにしました。
営業所で担当している仕事はそのまま継続しながら、本社で実施される新入社員の導入研修、フォロー研修を担当し、営業所に配属された後輩女子社員のOJTを行い、近隣の営業所に伺って、勉強会を開催するなど、教育に関する経験をたくさん積ませていただくことができました。
人前で話すのが苦手で、出来ればそういう仕事は避けて通りたいと思っていた私に「人前で話すテクニックより、伝える内容の準備をしっかり行うことが大切」と教えていただきました。また、以前は〝人に任せるより、自分でやった方が早い”と思ってましたが、教えた人が成長するプロセスに立ち合えることは、自分が何かを出来るようにすることより、達成感があると気づき、「もしかしたら、これは私の天職なのかもしれない」と思うようになりました。
できれば、インストラクターの仕事の専任になって、もっともっと、この会社の女子社員の活性化を図りたい!
しかし、そう思っていた矢先に妊娠し、無理がたたって切迫流産になりかかっていました。
1カ月、自宅で療養しているときに、上司や人事に「インストラクターとして専任で仕事がしたい」ということを相談しました。しかし、上司や人事のからは、「インストラクターはあくまでも補足的な仕事としてやってもらいたい。あなたには、管理職としての道を歩んでもらいたい」と言われました。
一般職で入社したにも関わらず、これまでの仕事が評価され、管理職候補に選んでいただけたのは、とても嬉しいことでした。しかし、私が本当にやってみたいのは、管理職ではなくインストラクターでした。私は、療養から復帰してすぐ会社に退職を申し出ました。
しかし、退職を決めたものの、教育インストラクターの今後に不安を感じていました。私の後に、営業所勤務のインストラクターは増えていったのですが、会社はインストラクターを増やすことばかりで、何も仕組みづくりを考えていないように見えたからです。任命された後輩インストラクターたちも然りで、身に付けたそのノウハウを活かして仕事をしている人は皆無でした。
退職するまでに、インストラクター業務について現状と課題をまとめて会社に提出しよう!と決意し、最後のマニュアル作りがはじまりました。
なかなか作成作業が進まず、退職しても作業を続けました。パソコンなど個人では高くて買えなかった時代だったので、全て手書きです。夢中で作業したため、腱鞘炎になったほどですが、自分なりにまとめることができ、人事部に提出しました。


会社や後輩インストラクターの方たちが、このマニュアルを活用してくださったかどうかはわかりません。
たとえ活用されなかったとしても、後悔はありませんでした。私は、会社や後輩のためにこのマニュアルを作成したかったと同時に、これからフリーのインストラクターとして活動していくための土台を作りたかったのです。
会社で自分の目標を達成出来ない悔しさを、これからは本当にやりたいことに夢中で取り組めるんだ!という嬉しさに換えながら、インストラクターとして活動した4年間を検証し、重要性や役割、担当し続ける上での課題と改善のヒントについてまとめました。
その後、私は住み慣れた大阪から地元である広島にUターンしました。地元では皆無に等しかったネットワークを作って拡げるために、ある企画会社が募集していた人材登録を行いました。
その企画会社の社長が、「将来、研修インストラクターの仕事がしたい」という内容を見て、「これまでの実績がわかるものがあれば送ってください」と声をかけて下さったので、作成したマニュアルをコピーして郵送しました。すると社長からすぐ連絡が入り、「すぐに仕事が出来ますか?」と
尋ねられたのです。マニュアル作成は、実績を伝えるのに役に立ちました。そして、間もなく、社長の紹介で研修会社に所属し、その企画会社がプロデュースしていたビルメンテナンス会社のインストラクター養成研修を担当させていただきました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
