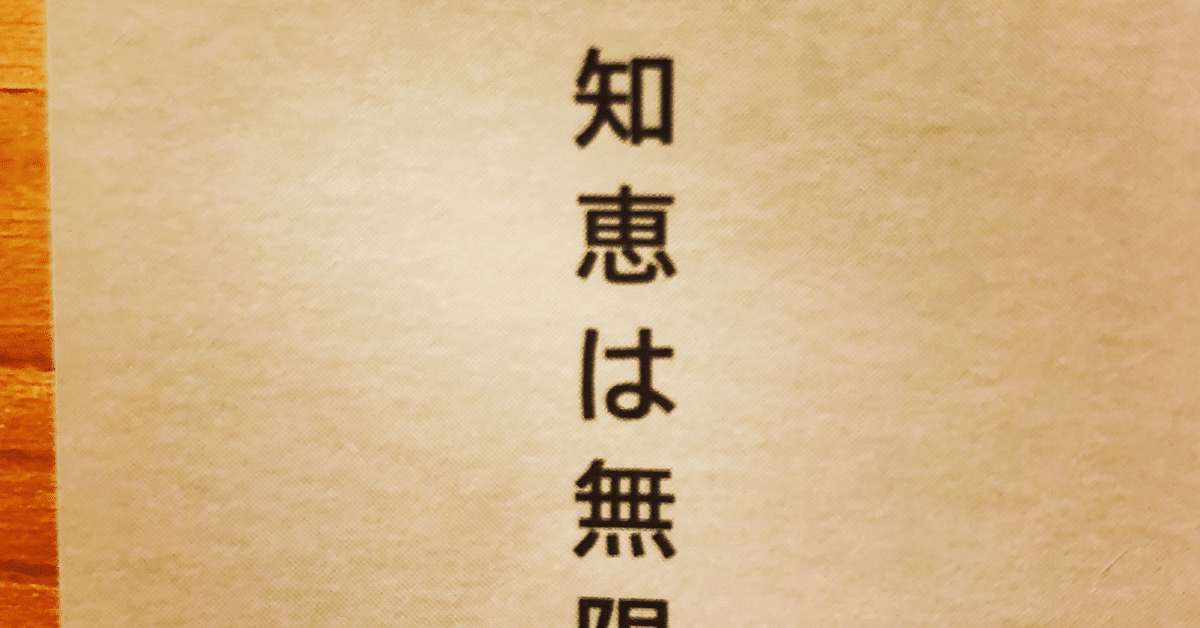
本とは資産。
初稿です。
初稿は絶対この内容にしようと決めていました。
本とは資産である。
これは、ごくごく一般的に言われてる事ですよね。
でもじゃあなぜ資産・財産なんだろうって、
一旦冷静に分析して考えたんです。
①単純に、一般教養知識としての、頭の中に内在されている見えない資産
これ、意外と言語化すると面白くて、単純に教養がある大人と、教養が無い大人を一般的に比較した時に、教養があった方が明らかにそれだけで“多くのアドバンテージ”がありますよね。
・博識で様々な分野に精通する事を知っていて、知性に溢れている大人
(分かりやすく言うと林修先生。テレビで引っ張りだこですよね)
・博識で知性に溢れ、ましてや徳や品格まで備わっている大人
(皆さんの周りに思い付く方々が居るのではないでしょうか。会社の尊敬している上司、または尊敬している部下、ご近所付き合いのある紳士淑女な大人、間接的に知っている一流芸能人や過去の偉人たち、そして尊敬する両親)
こういった方々は、一般教養が有り、
そして一般教養が秀でているから、
それ自体がお仕事になっていたり、
会社で言うと昇格・昇給・プロジェクトリーダーになる判断要素になったり、
家庭や仕事での成長度合の変化に寄与していたり、健全で逞しい家庭を育めていたりしていますよね。
②実際に本はモノとして(古本等)売れるから、
モノとして保有する場合の資産
(資産価値は取得時より、一般的に下がってしまう場合が多いので、考え方は人それぞれ)
私は、本はハードの状態で保有するものである、という前提があるので、この考え方はあまりオススメはしていません。
③本を読む事で新たな知識を吸収し、咀嚼して、自身の知恵にし、効果的に実践できる
これが今回の本丸です。
仕入れを行った知識を、
「今」「近い未来」「数年後から数十年後の未来」の3つに分け、具体的且つ、自分一人一人に合う形で効果的に実践する事で、
本を買った際の価格より、“圧倒的”に大きな流動資産(現金)や無形資産(信頼/人望)を得る事が出来る。
また、“その連続性のサイクル”を生む事が出来る。
「そうは言っても、誰しもそんな都合良く、本を買って読むだけは、その好循環のサイクルに入れる事は出来ないですよ」「そんな事いってもやり方の HOW TO が分からない」って声が聞こえてきそうですね。。。
しかし、その問題を解決する方法が既に有るとなったらどうでしょうか?
その答えは、
“圧倒的”努力である。
結局はここです。とどのつまり、何をするにしても、「努力が積み重ねられない人に、約束された明るい未来は来ない」という事です。
努力ってなんだか耳の痛くなるような、壮大な響きになりますよね?人間は本質的に言うと怠惰な生き物で、*「動物の血」と「理性の血」で構成されています。(*人間の本性 丹羽宇一郎著)
本来人間は、科学的に類人猿から進化した生き物ですから、当然の事だと思います。
しかし、*人間の本性 でも書かれていますが、努力が出来るのは人間である証 だと私も考えています。
人類の起源は宗教によって捉え方が変わってきますが、私は九州学院高校(ミッションスクール)を卒業したので、そこで学んだ事から言うと、人間は知恵の実を食べて、神から人間になったと言われています。
動物や他の生物と明らかに違うのは、人間は知恵を与えられて(または進化の過程で知恵や学習能力を与えられて)、いまここに人間の遺伝子として存在している、という事実です。
④知的好奇心をとめるな。
努力の話に戻りますが、努力って、何だか壮大な響きに聞こえますよね。
そうなんです。努力し続けるって滅茶苦茶に大変だし、疲れるんです。
それを単発や短期的な努力であれば、人間は集中力を発揮して、終わりが見えているゴールに突き進むことはできますが、ゴールを人生の終焉に設定すると、
「それは無理でしょ」ってなります。
= いつもの怠惰な、実に動物の血に委ねた毎日の連鎖に繋がります。(サバンナのライオンの生活を想像すれば分かり易いかと)
しかし、知性/知恵/「動物の本能」以外に発揮できる学習能力や知的好奇心は、人間に与えられた専売特許です。
その生物界で唯一与えられたであろう知的好奇心を捨て去って生きるのは、余りに勿体無い人生であるし、空虚な人生であると言えます。
“圧倒的”努力の積み重ね = 壮大な理想
このロジックを日々忙しいなかで実践していくのは、“特に動物の血の濃い方”ではかなり難易度が高いと言えます。
ただ、ここで一言あるとすれば、
“圧倒的読書”は容易だ,という事です。
何故かというと、知的好奇心は全ての人間の遺伝子に、産まれる前から平等に備わっているからです。
あとは、その遺伝子に素直になってあげれば良いのです。
ただし、圧倒的努力・圧倒的読書の定義は、死ぬ直前まで継続できる連続性のあるものでなくてはなりません。
⑤本はハードとして買うべき。
人それぞれですが、私は本はハードとして手にとってめくりながら読んだ方が良いと考えています。
理由はいくつかありますが、単純に「あれ?あれどんな内容だったっけ?」となった時に折り曲げていたページに瞬時にアクセスできるからです。
読書を様々なジャンルで、継続して続けていると、、
この部分はあの本でもあったな。
この部分とあの部分を組み合わせてあげるとこんな面白い発想になるな。
この発想から仕事や新しいビジネス、家庭に活かせるな。
といった瞬間が頻繁に訪れます。
その時に、「あれどんな内容だったっけ?」も頻繁に訪れますが、その瞬間、まさにすぐさま読んだ本を引っ張りだして知識の整理をしないと、「めんどくさいからもういいや」と動物の血が顔をだして、知的好奇心が薄まってしまいます。
あとは本を手にとって指を動かし、五感で感じながら読書をするだけで、自分の脳が活性化される感覚になります。
ハード本を読んで脳が活性化される → 仕事や家庭において良いパフォーマンスが出来る → 結果が伴う → 更なるやる気に繋がる → また本を読みたくなる
これだけ切り取っても、考えただけで良い循環です。
⑥なぜハードの本を買い、保有しつづけ無ければならないのか。
ハードの本を数多く保有しているという状態は、モノが多くなり片付かないし、狭い家では本は邪魔だと思うかもしれません。ホコリを取ってまわるだけで家事が増えそうです。
しかし、そこで考えないといけないのは、その大きい本棚に格納された圧倒的数の本が映し出す、“役割”です。
分かり易い例でいくと、メンタリストDaigoさんです。
Daigoさんの動画を覗いて頂くと分かりますが、彼が動画を録画している空間は、まさに圧倒的数の本で壁が埋めつくされています。
その空間で、読んだ本を交えて様々なテーマで、時には心理学、時には経済学、時には文学、時には人類学など幅広い考察が繰り広げられています。
ただそこに必要不可欠な要素は、話している彼の後ろに圧倒的佇まいで鎮座している、本が映し出す説得力です。
これが例えば、1つのiPad等にスッキリ収まった、Kindle のアプリの中の数万冊だとしたら、それを必死に動画で説明して、「これだけの数の本を読んでいるから俺の言葉は本質に近いものがある」と説明したとしたら、視聴者は何故か、同じ話をしていても、信憑性を疑うし、その光景は滑稽になってしまいます。
恐らくDaigoさんがここまで本を書いたり、ここまで講演会に呼ばれたり、ここまでの社会的影響力を持つ事も無かったでしょう。
本はそこにあるだけで、それだけで資産・財産であるのです。
⑦知恵は、恐らく「この世で唯一である」と言うぐらい無限。
先ほど、④好奇心を止めるな。でも有りましたが、その前提で話を進めると、「知恵」や「理性の血」を許されているのは人間という存在、オンリーになります。
まさしく、そこだけを切り取れば、生物界で唯一の存在です。
その強みを強化し続けない選択肢は、実に空虚で怠惰であると言えます。
それだけでも圧倒的読書を持続する意味や意義はありますが、さらに、知恵は無限という本質的な部分もあります。
諸説ありますが、人間は一生のうち、脳の可能性の数パーセントしか使用せず、終焉の時を迎えると言われています。
ではこの世で無限の可能性があるものが、いくつあるでしょうか。
時間、お金、身体の自由、友人の数、アクセスできる情報の数(これはインターネットが無限にしたという考え方も出来ますが、インターネットはネット環境があるというのが前提にある為、ある意味有限のツールとして捉えます)
どれを取ってみても、際限のあるものであると言えます。
まさに、唯一無限であるのは、知恵であり愛であるのです。
また、現状人間が使用している脳の稼働を考えても、90%以上の伸びしろがあると言う事もできます。
「動物の血」ではなく、「理性の血」を優先して努力を積み重ねれば、その先に広がる可能性と連続性は計り知れないものがあります。
終わりに
本当は資産であり、投資である。
本は資産である。という事を冷静に分析して分かった事は、資産になるとすれば積極的な投資目的になると言う事です。
ましてや、自分の裁量と努力量に比例して、間違いなく大きなリターンになる投資です。
しかも、文庫本であれば往々にして1000円以下で容易に手に入る投資です。
こんな不確実性を最大限まで排除した、自分自身に決裁権のある、自由度の伴う健全性の高い投資商品は他にあるでしょうか?
是非、手元の通帳の残高数字ばかりを気にしていないで、Amazonでも町の小さな本屋さんでも結構ですので、これを機に足を運んでみて、自身の精神世界にマッチする本から手に取って、読書を始めてみて下さいね。
ただ、あくまでも、投資という概念を忘れずに、消費や浪費で終わらせないように、本から得た知識を知恵に出来るように、咀嚼して意識しながら読書を楽しんで欲しいと切に願っています。
それだけで、20年後30年後の日本は変わると思いますよ。
本気で、心からそう思って、いま筆を走らせています。
#未来読書研究所
柴田大輔
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
