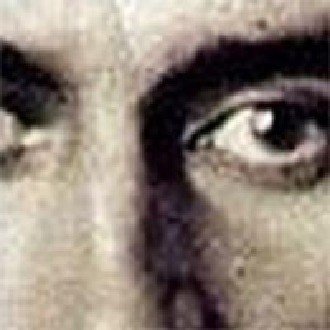「オイルドボーイ」2024年2月23日の日記
・動画が出てます。わざわざ前乗りまでしてサービスエリアへ歩いていく動画。なんもなさすぎて、左折するかどうかで盛り上がりを作ろうとしてる。
・道中で「富士山の火口には宝物がいっぱいある」みたいな話をしているが、これは去年富士樹海ツアーをやったとき、待合席においてある冊子に書かれていた知識だ。本当かどうかは知らない。修験者がお賽銭を火口に投げる文化が室町時代からあったみたいに書いてあったはずだから、お宝はたぶんあると思うんだけど。正誤がハッキリしない情報を動画メディアみたいに訂正のできないところで放言するのって不安で気持ちいい。
・道、誰もいなかったな。
・かまどさんとみくのしんさんの記事が出てて、記事の中にチラッと出てます。

・私は謎解きが好きだけど、謎解き嫌いのみくのしんさんが言ってることはかなり芯を食ってるし、この疑問に「そんなことないよ!」って胸を張って言える謎解き関係者っているのかな? と思う。少なくとも「誰でも」ではない。「義務教育で習う範囲の知識で解ける」ってよく見聞きするけど、それ言ってる人だいたい大卒だし高学歴だ。そういう階層って義務教育で習った=覚えていると自然に思っていがちだし。
・私も偏差値でいえば50よりは上だったわけで、無意識に「できる側」の論理を振りかざしている場面は多々あると思う。謎解き界隈がそのへんの感覚に無自覚になりやすいのは事実としてあるんじゃないだろうか。
・私も日々謎解きイベントに参加して楽しみつつ「高学歴の集団が楽しそうになんかやってらぁな……」というひがみ根性が心で顔を覗かせることがないでもない(だいたいクリア失敗したとき)。特に私はワーキングメモリが小さく、短時間に大量の情報を処理するのが苦手で、手際の良さと短期記憶能力が必要な謎解きはだいたい失敗する。高校のとき優等生に数学問題を教えてもらったとき「イコールの右側から左側に数字を移動するとき、何を移動してたのか忘れて書き間違えるから解けなくなる」と言ったら絶句されたことは今でもよく覚えている。でもそういう人は私以外にもたくさんいるわけで。「義務教育レベルの知識」と「必要十分なワーキングメモリ」と「適度な積極性」がクリアのために必要なイベントを「誰でも遊べるゲーム」と呼ぶのは少し無理がある。
・実際、私も謎解きイベントでは基本的にほとんど役に立ってない。周りにめちゃくちゃ有能な人がいるので、だいたい指をくわえて見てるだけ。それでも楽しめているのは、イベントの場や界隈に対する心理的安全性を築けているからだと思う。むちゃくちゃ頭の良い人にたくさん会ってきたけど、そういう人も試行錯誤の段階ではトンチンカンな勘違いをたくさんするし、ケアレスミスだってよくするのを知っている。あと制作側もプレイヤーをあざ笑うためにゲームを作っているんじゃなく、不安でいっぱいになりながらおずおずと謎を差し出しているのを知っている。
・ただ、そういう事実を知るには場数を踏む必要があるから、みくのしんさんみたいな苦手意識を抱くのも当然だと思うし、参入障壁の下げ方にはまだまだいろんな方法があるなと感じる。「間違えたら軽蔑されたり笑われたりするんじゃないか」という意識が強いととつらいし。私はもう「どれ、ちょっくら頭のいい人の頭のいいところを見せてもらおうかね……」という見物人の気持ちで足を運んでいる。
・あと、間違えても「まあいいか……」と開き直っている。「とにかくカスみたいなアイデアでも言わないより言ったほうが絶対いい」というのを身を持って体験したからだ。その意味では学力より「試行錯誤力」のほうが重要だ。しょうみ英単語とかはわかんなくても調べりゃいいし、最悪聞けばスタッフが教えてくれる(単語を覚えてるかどうかは本質と関係ないから)が、間違うこと自体に苦手意識があると足踏みしてしまう。仮説を立ててから試してみて駄目だったらすぐ別の仮説をやってみる、という流れに抵抗がなくなるとだいぶ体験が変わると思う。
・みくのしんさんは謎解きに苦手意識があると言ってるけど、発想そのものはかなり豊かだし料理ができる時点でワーキングメモリも広いと思うから、チームにいたらかなり貢献できるタイプだと思う。なにより一緒に遊ぶと面白いし。『HUNTER×HUNTER』が楽しんで読める時点で素養はある。心理的安全性大事。

・小田原城見てきた。
ここから先は
スキを押すとランダムな褒め言葉や絵が表示されます。