
筋力トレーニングで動作を変えるコツ2選【ポイントは特異性の原則】
脳性麻痺を持つ方々に対する筋力トレーニングをより効果的にするために重要な考え方である筋力トレーニングの原則について分かりやすく解説します。
1. 脳性麻痺と筋力トレーニングの有用性
脳性麻痺とは、出生前や、出生時、出生後間もない時期の脳の損傷によって引き起こされる永続的な姿勢と運動の障害を示す症候群です。この障害は、筋力や、関節可動域、運動の協調性に影響を及ぼし、日常生活における様々な活動に支障をきたすことがあります。
筋力トレーニングは、筋力を向上させ、関節の柔軟性を保ち、運動機能を改善することで、脳性麻痺者の活動制限の影響を抑えるのに貢献します。そのため、適切に計画された筋力トレーニングプログラムは、脳性麻痺者の自立度と生活の質を高めるための有用なツールと捉えることができます。

2. 筋力トレーニングに重要な2つの基本原則
筋力トレーニングを効果的に行うためには、筋力トレーニングの基本原則に則った計画を立てることが重要です。筋力トレーニングの原則の中で特に重要なのは漸進性過負荷の原則と、特異性の原則の二つです。
漸進性過負荷の原則とは、筋に徐々に大きな負荷をかけていくことで筋力トレーニングの効果が表れるという原則です。つまり、トレーニングの初期段階では、軽い負荷から始め、徐々に負荷を高めていく必要があります。
例えば、トレーニング開始時にはスクワットを自重で10回3セット行い、トレーニングの進行に合わせて重りを入れたリュックを背負って負荷を高めたり、11回12回と回数を増やしたり、4セット5セットとセット数を増やすことで筋力トレーニングを効果的にすることができます。
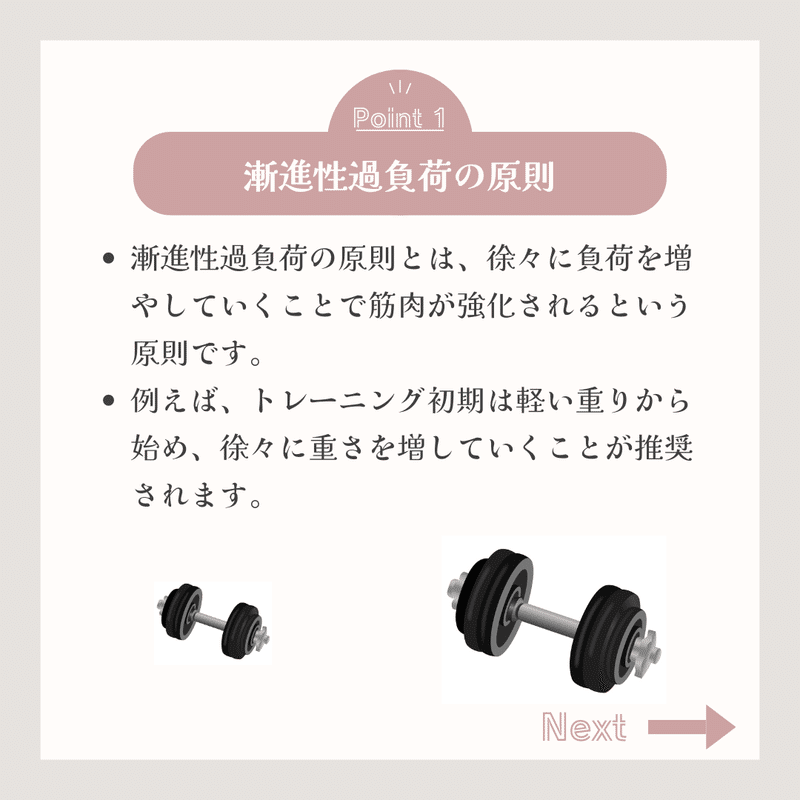
特異性の原則とは、トレーニングの効果はそのトレーニングで対象となった筋や能力に特化して現れるという原則です。つまり、ある特定の筋群を強化したい場合や、特定の運動能力を向上させたい場合は、その筋群や能力に直接関連する種類の運動やトレーニングを行う必要があります。
例えば、階段を降りる動作を改善したい場合、階段を降りる動作に近い要素を含むトレーニングが効果的です。

3. 特異性の原則の詳細:4つのポイント
特異性の原則を考えたときに、目的とする運動と行おうとしている筋力トレーニングの関連性が高いかどうかはどのように判断すればよいのでしょうか。
特異性の原則を筋力トレーニングの計画に生かすには4つのポイントを押さえることが重要です。その4つとは「筋の種類」と「筋の収縮様式」、「筋間の協調性」、「バランスの要求の度合い」です。これらのポイントが目的とする活動を構成する動作と近い筋力トレーニングであるほど効果は高いといえます。
特異性の原則のポイント①:筋の種類
目的とする活動に使用される筋の種類が近いほど、筋力トレーニングの効果は高いと言えます。
階段を降りる動作を例に考えてみましょう。階段を降りる動作で使用される代表的な筋は大腿四頭筋と下腿三頭筋です。
階段を降りる動作を改善したい場合には、大腿四頭筋と下腿三頭筋を鍛える筋力トレーニングが有効ということです。一方で、ハムストリングスや広背筋を鍛えるような筋力トレーニングの効果は限定的でしょう。
特異性の原則のポイント②:筋の収縮様式
目的とする活動に使用される筋の収縮様式に近いほど、筋力トレーニングの効果は高いと言えます。
階段を降りる動作を例に考えてみましょう。階段を降りる動作では重心をスムーズに下降させるために主に大腿四頭筋と下腿三頭筋が遠心性収縮します。
階段を降りる動作を改善したい場合には、遠心性収縮を中心とした筋力トレーニングが有効ということです。一方で、等尺性収縮や求心性収縮のみの筋力トレーニングの効果は限定的でしょう。
特異性の原則のポイント③:筋間の協調性
目的とする活動に使用される筋間の協調性が近いほど、筋力トレーニングの効果は高いと言えます。
階段を降りる動作を例に考えてみましょう。階段を降りる動作では主に大腿四頭筋と下腿三頭筋が同時に活動します。
階段を降りる動作を改善したい場合には、大腿四頭筋と下腿三頭筋が同時に活動するような複合運動が有効ということです。一方で、端座位での膝伸展運動やカーフレイズなどの単関節運動のみの筋力トレーニングの効果は限定的でしょう。
特異性の原則のポイント④:バランスの要求の度合い
目的とする活動におけるバランスの要求の度合いが近いほど、筋力トレーニングの効果は高いと言えます。
階段を降りる動作を例に考えてみましょう。階段を降りる動作には片脚でバランスを維持する局面が不可欠です。
階段を降りる動作を改善したい場合には、片足で立位バランスを維持するような要素を含む筋力トレーニングが有効ということです。一方で、シートや背もたれ、手すりなどで安定した状況での片脚レッグプレスの筋力トレーニングの効果は限定的でしょう。

階段を降りる動作を改善させるために重要なポイントをまとめます。
階段を降りる動作では、下肢を下の段に踏み出す際には片脚で姿勢を保持しつつ、主に大腿四頭筋と下腿三頭筋が協調的に遠心性収縮することで重心のスムーズな下降が達成されます。
このような複数の機能が求められる階段を降りるという動作に対して、立位からの着座動作や段差を降りる動作はバランスを保持しつつ行う遠心性の複合関節運動であり、多くの点で階段を降りる動作と近く、特異性の原則の観点からみるとより練習効果の高い課題と言えます。
一方で、端座位での膝関節伸展運動や長座位での足関節底屈運動は大腿四頭筋と下腿三頭筋を使用するものの、ほとんどバランスを保持する必要のない求心性の単関節運動であり、課題としての特徴は大きく異なります。
このような課題は筋力や筋の収縮速度などの単一の機能が著しく低い場合や、荷重制限のある場面で安全に筋の機能を改善させたい場合には有効となるでしょう。しかし、このような課題の反復だけでは動作を改善させることは難しいと思われます。
動作の改善を目指す場合には、目的とする動作と関連性の高い課題の練習を取り入れることでより高い練習効果が見込めるのです。
まとめ
脳性麻痺は、出生前や出生時、または出生後間もなく脳が損傷を受けることで発生する障害で、筋力の低下、関節の可動域制限、運動の協調性の低下といった特徴があります。これにより、日常生活において多くの制約が生じます。こうした制約に対して筋力トレーニングは非常に有効で、筋力を向上させることで運動機能の改善を図り、より自立した生活を支援する手段となり得ます。
筋力トレーニングを行う際は、「漸進性過負荷の原則」と「特異性の原則」を理解し適用することが重要です。
漸進性過負荷の原則とは、徐々に負荷を増やしていくことで筋肉が強化されるという原則です。例えば、トレーニング初期は軽い重りから始め、徐々に重さを増していくことが推奨されます。
特異性の原則は、トレーニングの効果が目的の運動や筋肉に特化して現れるという原則です。つまり、階段を降りる際に多く使われる大腿四頭筋と下腿三頭筋をターゲットにしたトレーニングが、階段を降りる動作の改善に直結します。
特異性の原則を最大限活用するためには、以下の4つのポイントを理解し適用する必要があります:
①筋の種類: 関連性の高い筋肉を鍛えること。例:階段を降りる動作では、大腿四頭筋と下腿三頭筋が主に使われるため、これらの筋肉を強化するトレーニングが適切です。
②筋の収縮様式: 目的とする活動で主に使われる収縮タイプを反映したトレーニングを行うこと。階段を降りる際の遠心性収縮を模倣するトレーニングが効果的です。
③筋間の協調性: 関連する筋肉が協調して動作するトレーニングを行うこと。例えば、大腿四頭筋と下腿三頭筋が同時に活動する複合運動が効果的です。
④バランスの要求の度合い: 目的とする活動におけるバランスの要求をトレーニングに取り入れること。階段を降りる動作においては、片足でのバランスを保つ能力が重要ですから、同様の要素を含むトレーニングが推奨されます。
このようなトレーニングは、ただ筋力を向上させるだけでなく、運動の質と効率を改善することで全体的な生活の質を高めることが期待されます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
