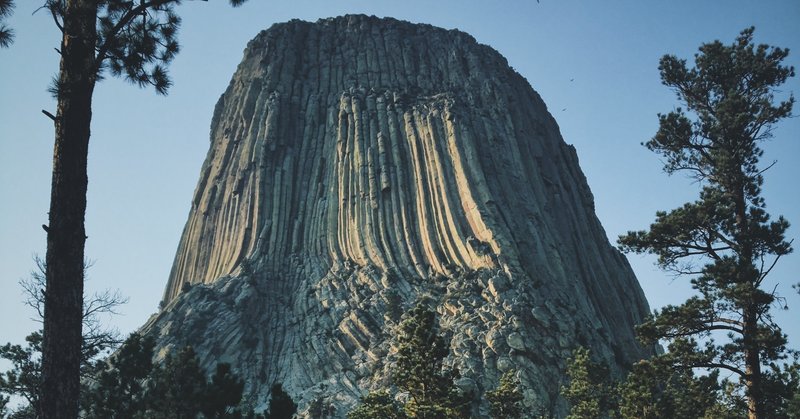
新鮮な驚きを。
先日、子供とドラえもんの映画、『ドラえもん のび太の大魔境』を見た。
ストーリの初めのほうで、のび太が地球上のどこかにまだ隠されている秘境を探す。ドラえもんに道具を借りて探し始めるが、そこでのび太は、地球は探検しつくされていて、どこにも秘境やロマンはない、ということをいう。
この言葉を聞いて、ハッとなった。
自分もある程度そのように考えてしまっていたからだ。
どこを見ても分かっているものばかり、新鮮な驚きはないという勘違い。
そのことについて考えてみた。
いくら行っても、分かったつもり
「分かる」ということについて、以下の二つを考えてみた。
①自分が理解していると思っているものは、どこまで理解しているのか?
②人間により理解しえないものがある
①について、
こどもは「なんで?」をいくらでも繰り返す。私は最後まで説明しきれたことはない。
「なんで空は青いの?」「なんでパパは勉強するの?」「なんでお仕事するの?」
なんで?という疑問には2回ほどは答えられるが、途中からは「~らしいよ」「パパにはわからないな~、一緒に調べてみようか」となってしまう。
そして調べたところで、自分の理解を超えた説明に行き着いたりする。
そして、Whyを究極に重ねたところにはその先のWhyがあり、わかりきることはない。
②について、
①と重複することがあるが、原則として私たちの感覚と理解には能力の限界がある。
私たちが認識している世界は、犬やモンシロチョウのそれとは違う。私たちは視覚の可視光と呼ぶ波長帯の情報に大きく依存する一方モンシロチョウは紫外光、犬は嗅覚に重きを置いた感覚のデザインとなっている。
理解の及ぶ範囲については、感覚と同様でいくら拡張しようとも、私たちのシステムでしか理解をすることができない。いくらAIなどの科学が発展したとしてもである。
絶対的な事実を真理や、西洋では神と呼ぶが、その視点には到達しえない。
つまりは、私たちは実用的な範囲でわかることはできても、根本的・究極的な理由については分かりえないということである。
分かったつもりに至る構造とそれから逃れる方法
私たちは、わからないものに出会ったとき、多くは以下の経路をたどる。
「すごーい」→「なぜ?」→「納得」
なぜ?と問う力は、人類を大きく発展させてきた。
それが究極のなぜ?を解明できないことは前述の通りだが、私たちは簡単に中途半端なレベルで納得してしまう性質も持ち合わせている。
そして、特に情報の流速の早い今日では、次々に「すごーい」情報が送られてくるもので、本当はもっと噛みしめるべきものが、もう理解したものとして倉庫に眠ることになる。
この、簡単に納得して「すごーい」という感動を失ってしまうことをもったいないと思う。
もちろんすべてのことを精査しようというつもりはない。
重要なのは、なぜ?を問いある一定の考察や調査(ググったり)した後に、改めて、そのWhyを含めて物事をもう一度味わってみること。
私たちには、わかりえないことがたくさんある、という謙虚さをもって見つめること。
以上、科学全能主義であった過去の自分の反省も含め。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
