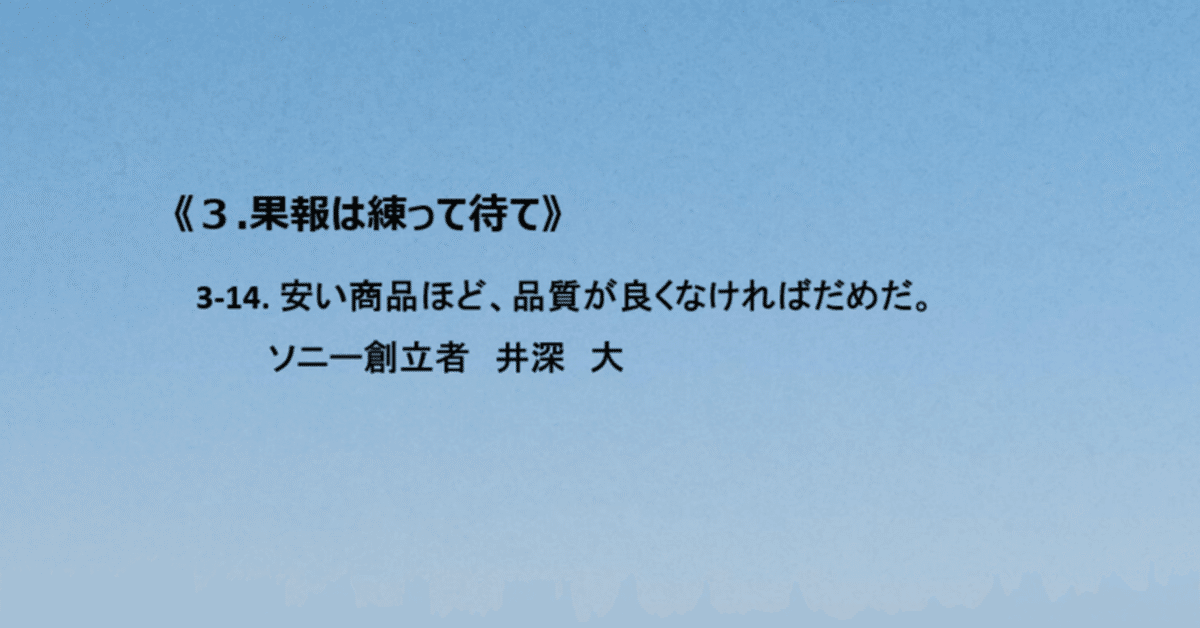
3-14. 安い商品ほど、品質が良くなければだめだ。
ソニー創立者 井深 大
高額の商品ほど品質が良くなければならない、というのが常識である。消費者は、価格の安い商品は安価な分だけ品質に寛容になるはずだからである。
同じように、民生品と軍用品という点で見ると、軍用品はちょっとした不具合でも人命にかかわるケースが多いだけに品質が厳しく求められるが、民生品はそれに比べると緩い品質水準で済む……というのがこれまでの考えであった。
しかし井深は、これは逆だと言う。
「値段が安い民生品で故障、特に設計ミスなどを起こしたら、その商品は破滅ですからね。安いものほど故障を起こしてはいけないのです」
と言うのである。
アメリカ軍用規格のMIL-STDは厳しいことで有名だが、そのMIL規格品といえども故障を起こすことを前提にしている。
しかし、民生品はそうではない。故障を起こしてはいけないのである。価格が安いだけに、メンテナンスにもコストをかけることはできない。だから、民生品を作るほうが、より高品質・低価格を要求される本当のインダストリーだと言う。
日本の電子工業は民生品を作ってきたから故障を起こさない技術を開発してきたが、アメリカのエレクトロニクス業界は国の宇宙開発と軍を得意先とし、故障は直せばいいと考えてきたから品質的にはスポイルされている……というのが井深の主張だ。
戦後、日本に駐留していた米軍は、通信機器を遠い母国から運ぶより、日本国内で調達した方が安価に済むと考えた。しかし、第二次大戦直後の日本産業界に、米軍規格に合わせて生産する技術力はなかった。そこで1950年(昭和25年)統計学の大家であったデミング博士を日本に招聘し、日本の産業界に向けて品質管理の教育を行った。これがデミング賞の発端である。
それまで日本の製造現場では、検査によって不良品を見つけ出し、外にはじき出して良品だけを使うことで高品質を補償すればよいと考えていた。そんな日本の産業界に、現場で管理するのではなく、統計学を使ったスマートな品質管理手法があることを教えたのである。
不良を選別するのではなく、不良の原因を統計的に探り出し、改善して不良品が作られない工程を実現する、「工程で品質を保証する」という発想の始まりで、これが日本産業の品質管理の原点になった。
安い商品ほど高品質でなければならない……ソニーの発展の根幹がうかがえるような言葉である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
