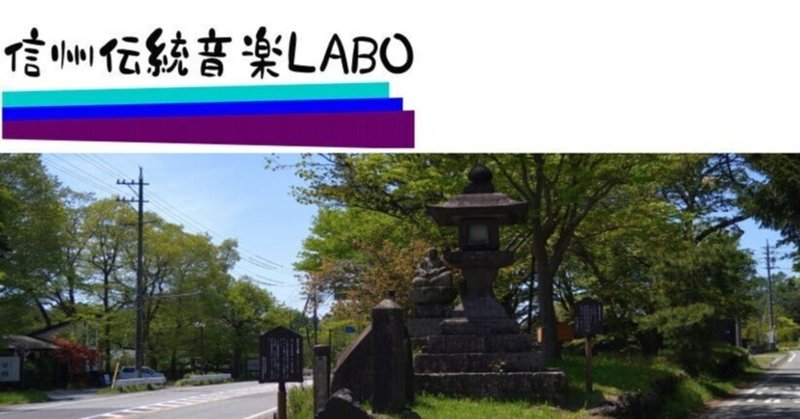
《安曇節》~安曇平から全国へ広がった豊科調(長野県安曇野市)
北アルプス山麓に広がる自然豊かな景観の安曇野。清冽な湧水、素朴ながらもほほ笑ましい道祖神など、この地を訪ねる人々は絶えません。南安曇郡穂高町、豊科町、堀金村、三郷村と東筑摩郡明科町が合併し、平成17年(2005)に安曇野市が誕生しましたが、豊科がその中心地です。

この地で歌われる民謡に《安曇節》がありますが、実は北安曇郡松川村で生まれた《安曇節》が広まったのは、実は豊科が中心でした。
唄の背景
安曇節の誕生
この唄は、北安曇郡松川村板取の医師、榛葉太生(しんは ふとお)(1883~1962)による新しい民謡です。
安曇野を愛した榛葉は、当地域に残る古民謡が歌われなくなっていくことを嘆き、これらをもとに節をまとめました。唄の特徴としては、下の句の第3句目を2回繰り返し、最後に「チョコサイ」というハヤシ詞をもつ「チョコサイ節」がベースと考えられています。これを大正12年(1923)の夏に《安曇節》として発表されました。すると、安曇野各地で歌い踊られるようになります。その後、松川安曇踊会が組織され、さらに《安曇節》を覚えた人々が、南安曇郡穂高町踊会、同郡豊科踊会、北安大町北安曇踊会など、各地で「踊会」が結成されました。最終的には地元松川村の安曇踊会、北安曇踊会、南安曇踊会を中心に支部まで結成されました。やがて「安曇節大会」が開催され、歌詞を一般公募するようになり、各地でオリジナルの歌詞が生み出されるようになりました。
豊科調安曇節の確立
大正12年(1923)に発表されたものの、まだ満足のいかない榛葉は、各唄の冒頭に「サァー」を加えるなどの工夫を加え、《正調安曇節》としました。また、昭和7年(1932)にはコロムビアレコードから吹き込まれましたが、この時は松川調の《正調安曇節》は大町花柳界の立花家壽三代、裏面には《安曇節》として、豊科花柳界の日吉家金時により吹き込みが行われました。
その後、戦時の歌舞音曲の抑制下で《安曇節》も下火になっていきましたが、戦後《安曇節》の復興は、松川村ではなく実は豊科町でした。昭和20年代以降、各地で民謡大会が盛んになり、長野県観光課からの依頼もあり長野県代表の1つとして《安曇節》が選ばれ、時の豊科町長が中心となって、豊科花柳界の歌と踊りが全国大会のステージで発表されました。この取り組みの中心になったのが、豊科花柳界の都小春でした。
美声の芸妓として知られていた都小春の尽力で、豊科調の《安曇節》が全国に広まります。昭和30年代には都小春の吹込みも行われ、皮肉にも松川村の《正調》よりも、いわば行政が中心となって普及が図られた《豊科調》の方がよく知られるようになったのでした。

豊科調の広がり
《豊科調》と《正調》とのちがいは、松川村では各唄の冒頭に「サァー」を入れるようになっていますが、《豊科調》では直接第1句目から歌い出します。リズムについては《豊科調》は複雑なリズムが少なく、拍節の明確な音楽です。一方《正調》はリズムに特徴があり、付点と短い音が続き、弾みが特徴の[長短リズム]ではなく、短い音を先に出す[短長リズム]が多用されています。また、《正調》はテンポがやや遅く、コブシが多めですが、《豊科調》はやや速めで淡々と歌われます。各唄の最終句の後のリフレイン「チョコサイコラコイ」の最後の「コラコイ」については、《正調》は音程を高く入りますが、《豊科調》は「チョコサイ」と「コラコイ」を同じ音程を繰り返します。
また、三味線の手付けについては、《豊科調》は、ほぼ四分音符が多く、高い勘所も少なく、平易なものとなっていますが、《正調》はリズムにも変化に富み、前奏なども独特なものに仕上げられています。
松川村の人々は、豊科の節回しは松川調とは異なることから、松川調の《正調》に対して、豊科の節回しを《豊科調》と呼んでいます。
こうして《豊科調》が全国的に広まったことから、プロの民謡歌手によって舞台調に仕立てられて更に普及していきます。現在、全国的に知られている《安曇節》は、都小春のものとも若干変化しており、前奏もやや異なる手が付けられています。
また、地元安曇野でも、各地で「踊会」が盛んに活動してきた名残もあって、変化が見られます。特に、最終句の後の「チョコサイコラコイ」を「チョコサイコラホイ」として歌う場合もあります。
音楽的特徴
拍子
2拍子
音組織/音域
民謡音階/1オクターブと5度

歌詞の構造
7775調を基本とします。下の句の第3句目の7文字を2回繰り返して、最終の第4句につなげます。その後、付けによって第4句目を更に2回繰り返して、「チョコサイコラコイ」で締めます。前述のとおり、穂高あたりでは「チョコサイコラホイ」と歌う方もあります。
〽︎寄れや寄ってこい 安曇の踊り
田から町から 田から町から
野山から
[付け]
野山から 野山から チョコサイコラコイ
演奏形態
歌
唄バヤシ
三味線
鳴り物
※笛や尺八を入れて演奏される場合もあります。
下記には《安曇節》の楽譜を掲載しました。なお《豊科調》と、比較のために《普及調》《穂高調》を載せてあります。
ここから先は
¥ 200
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
