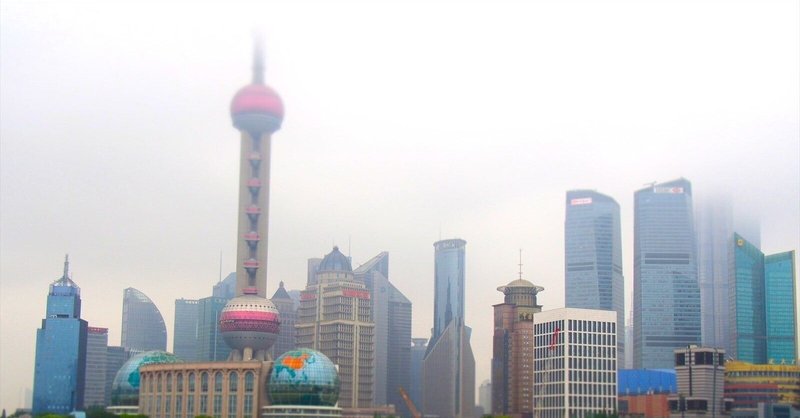
新型コロナウイルスワクチンの特許権放棄、WHOによるシノファーム製ワクチンの緊急使用承認について(5月10日こびナビTwitterspacesまとめ)

☝Twitterspaces参加方法はこちらのツイートを参考にしてください。
2021年5月10日(月)
こびナビの医師が解説する最新医療ニュース
本日のモデレーター:木下喬弘
【ニュース1】新型コロナワクチンの特許権放棄
木下喬弘
さて、本日の話題に行きたいと思います。
ずっと論文とかやっていたんですけど、今日はニュースでいきたいと思います。
3日前ぐらいまで英語メディアで結構話題になってたのが、バイデン大統領が新型コロナワクチンの特許権放棄に賛成するという話です。
今回選んだニュースの一歩手前の背景になったこととして、アメリカの通商代表部(Office of the United States Trade Representative; USTR)という組織のタイ代表(注:国の「タイ」の代表ではなく、タイさんという人名)が特許権の一部停止を支持すると表明しました。
これが、 世界貿易機関(World Trade Organization; WTO)の中で、米国は自分たちで作ったメッセンジャーRNAワクチンを含むワクチンの特許権を放棄するという方向でコメントをしてるんですね。
これは普通に考えて、他の国にとって全く悪いことはなさそうじゃないですか。
このあたりを深掘りして行こうと思います。
先に言ってしまうと、私はアメリカにとって何の得があるのかはよく分かりませんでした。
ただ、実はヨーロッパがこれに反対してるんですよね。なぜ反対してるのかっていうところをニュースで見てきたいと思います。
バイデン大統領がワクチンの特許を放棄すると言っても、それがワクチン供給の問題を魔法のように一気に全て解決するようなものではないというタイトルがついています。
本文を見てみると、EUサミットがポルトガルで行われていて、EU のリーダー達はワクチンの特許放棄は短期的なワクチンの供給に対して有効ではなく、輸出制限を解除することのほうが重要だと言っているようです。
特に欧州理事会のチャールス・マイケル代表が「短期的な魔法の弾丸ではない」と言ったようです。さらにフランスのマクロン大統領は、最初は特許権の放棄に対して賛成していたのですが、EUサミットの時点では「特許権の放棄に関することをディスカッションすること自体、今するべきことではない」と発言しています。
ドイツのメルケル首相も同様に「特許権の放棄は機会を増やすのではなくリスクを増やす」というようなことを言っています。
つまり、特許放棄よりも直接アメリカで作ったものをくれと言っているわけですね。
そもそもアメリカは厳しい輸出制限をしているのですが、それが不公平だということです。
メルケル首相は、ヨーロッパは結構多くの数のワクチンを輸出しているという点を割と強めに主張しています。
現時点でヨーロッパでは、トータルで EU の27ブロックに住む4億4600万人分と同じ量のワクチンを輸出することを認めていて、実際に2億本分を EU 内で使い、それと同じ量を90か国に出しているそうです。
マクロン大統領は、アングロサクソン、要するにアメリカとイギリスはワクチンの輸出に対して後ろ向きで、それを開放すべきだと主張しています。
メッセンジャーRNAワクチンは、特許権を放棄されても作ること自体が難しく、諸外国に製造方法を公開したところで供給量が上がらないので、それでは意味がない。
だから直接アメリカで作って渡せと言っているわけですね。
他のいくつかの記事も併せて見ると、ワクチンの原材料は200個ぐらいあって、発展途上国でそれを組み合わせて安定的に作るのは相当難しいみたいです。
というか、今までそういった製造経験のない企業で作るということは多分欧州の企業でも難しいことなんだと思います。
そういった点から、最初特許権の放棄に前向きだったマクロン大統領も踵を返して、特許権放棄では問題解決しないからアメリカで作っておくれと言っているのだと、そのようにこのニュースを理解しました。
製造工程に関してはこの前岡田先生が話してくださいましたね。それがどれだけ難しいかとか、他の国でもできそうなのか。例えば原材料の確保がそもそも難しいのかとか、いろんな知見をお持ちの先生がいらっしゃると思いますので、ちょっとコメントいただければと思います。
……シーン、ですね(笑)
安川康介
アペタイザー行きます。
これはすごく大事な話で、木下先生がおっしゃったように、特許を放棄したとしてもじゃあ他の人がすぐ作れるかって言うと、作れないということがありますよね。
アメリカ国内でも原材料が足りなくて、バイデン政権が国防生産法というのを発動させて、メッセンジャーRNAワクチンを作る原料を優先的にワクチン製造に回すということをやっています。
ですので、他の国で実際に作って下さいって言っても、すぐには作れないというのはもちろんあると思います。
後は技術面で、それだけの科学者がいるか、そういうスキルを持った人たちがいるか、設備があるかなど色々なことがあって、特許を放棄した時点で他の国が自動的に簡単に作り始められる状況にはならないのは、明らかだと思います。
あとやはりもう一つは、これはバランスかもしれないんですけれども、このように開発をした製薬会社があって、もし他の国が簡単に製造できるような感じで特許放棄して、その会社が儲からなくなると、開発に関するインセンティブがなくなってしまいます。
それが果たして将来的に本当にいいのかっていう議論もあると思います。
木下喬弘
最後のポイントについて、僕はあえてカバーしてなかったんですけど、おっしゃる通りですよね。
そもそも普通に考えたら米国は米国企業の利益を守るべきだという話になるわけで、実際にファイザーの CEO は、特許放棄に対してふざけんな的なことをマイルドにツイートしてるんですよね。
そういったことも合わせると、なんでアメリカが特許放棄に対して前向きなのかがちょっとイマイチ理解できないんですけども、特許放棄するって言っても実際は作れないだろうから、一応世界にワクチンを届けようとする姿勢を示しているのかも知れません。アメリカが独り占めしているという非難の矛先をかわすために、あえて無理だとわかっていて放棄すると言っているということです。あるいは、他の意図があるのか…
なお、民主党の急進派がバイデン大統領に特許放棄するようにプレッシャーをかけて、バイデン大統領はそれを支持するようなことを言ったということのようです。
繰り返しますが、特許をちゃんと守ってあげないと、企業としてはこれだけ大変なワクチンを製造しておいて知的財産権が守られなければ、やる気削がれてしまいます。
もっと大きな問題として、メッセンジャーRNAワクチンの技術そのものが、元々新型コロナワクチンのために開発されたものではないという点があります。
元々の製造のモチベーションであったがん治療のためのワクチンのメッセンジャーRNAワクチンの技術を、新型コロナに流用してうまくいったせいで、その特許権を放棄して他の国でがんのワクチンを先に作られたりしたらたまらんっていう話もあるわけですね。
峰先生、何かコメントありますか?
峰宗太郎
大事なことで、これはいろんな会社だとかいろんな研究者が長年研究してきて、実は特許も分散していて、一つではなくたくさんあるんですよ。
それが全部放棄されてしまうと、今おっしゃったように他のことに流用されて、特許の正当性を台無しにしかねないということがありますので、本当に必要なことは何かを考えないといけないですね。
つまり、EU が求めている域外への輸出ということだけではなく、実はファイザーはそんなに利益を乗せずにワクチンを提供していて、富裕国・中等国・低所得国に対して値段の付け方を変えています。
下の方は完全にボランティアに近いというか、利益も何も乗せないで提供する、もう「差し上げますよ」ということを表明しているんですね。
そういうことを考えると、本当に特許を放棄しなければならないのか、それとも製造技術を移転しつつライセンス契約を結ぶだとか、いろいろ考えられると思うので、特許マターだけでお話するというのは確かにおっしゃるような危険性があるような気がします。
木下喬弘
実は Twitter 上でファイザーの CEO の手紙を訳されている方がいます。
「Dr. Tad」先生というアカウント名の方で、直接存じ上げないのですが、勉強になるツイートをされているので僕もよく見てるんですけど、このファイザーの CEO の手紙でいくつかポイントになりそうなところをピックアップしてご紹介します。
今、中・低所得国には確かにワクチンが提供されてないのですが、その理由について説明しています。
2020年6月時点でワクチンの製造の見込みができたときに、他の様々な経済レベルの国に対してどれぐらいワクチンが必要かを聞いたところ、注文のほとんどが高所得国で、高い値段で設定しているにもかかわらず注文が入ったそうです。
では中・低所得国は大丈夫かということを各国の首脳に手紙とか電話、メールで連絡したけれども、その時点ではメッセンジャーRNA の技術が未検証だとか、現地での製造方法を提案されたとか、他のワクチンメーカーに発注したということで、ファイザーを選ばなかったと言っています。
CEO の手紙だけで本当かどうかはわからないですし、2020年6月時点でメッセンジャーRNAワクチンに賭けろっていうのはちょっと無理な話で、「そうは言ってもいいものできたからちょっと送ったるよ」って気持ちも若干ありますが、とにかく最初は提供しようとしたけど向こうが欲しがらなかったと説明しているようです。
さらに原材料についても先ほどと同じようなことを言っていて、280個の原材料と部品があって、19か国のサプライヤーによって生産されていて、これを作ること自体がそんなには簡単ではなく、特許を放棄して作る技術が十分でないところで製造させると出来の悪いものができてしまうとのことです。
ですので、ファイザーの CEO としては当然特許を守る方向にいきたいとコメントしている感じですね。
ということで、この問題は結構複雑なんですけれども、まとめます。
そもそもファイザーの作ったメッセンジャーRNAワクチンは新型コロナワクチンのためだけに作ったものではないということもあって、重要な技術の特許を全て放棄しちゃうと、企業としての開発のインセンティブがなくなってしまいます。
かつ、特許を放棄しても他の国で簡単に作れるものではないので、EU としては本当はその製造技術が欲しいんだと思いますが、それ以上に今はワクチンを直接欲しいとアメリカにプレッシャーをかけているのが現状かなと思います。
この話題について僕の予定していた内容はここまでなんですけど、何か追加でコメントとかある方いらっしゃいますか?
安川康介
すごく重要な話だと思います。
メッセンジャーRNAワクチンの場合は特殊で、すぐに作れないとか原材料の問題とか複雑なんですけども、過去に例えば HIV の薬の特許で問題になったのがテノホビルというお薬です。
テノホビルはギリアド・サイエンシズ社が特許を持っていたために、他の低所得国で作れなかったときに、インドのある会社がテノホビルを作り始めて訴訟になり、どうしたらいいのかとなったことがありました。
その時に確かニューイングランド・ジャーナルで患者 vs 特許 のどちらを取るかみたいな話題にもなっていたりして、他の国で作れるようになった場合に、もし特許があることによってその薬やワクチンが行き渡らない状況があったら、真剣に議論しなければいけないですね。
薬に関しては過去にこういったことがあったので、今回のワクチンのことだけではなく医学の中では問題になるところかなと思います。
例えば作る会社が限られている薬で、昔は安価だったのに今はすごく高額で売られていて買えないなど、薬のロジスティクス(運送面の問題)とか特許に関しては結構難しい側面があるなと思います。
<参考資料>
Patents versus Patients? Antiretroviral Therapy in India
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp058106
木下喬弘
広い意味で言うと、医療を無料にするかどうかみたいなところとも関連があると思うんですけど、ヘルスケア関連のイノベーションって人の生活に与えるインパクトが大きすぎて、お金のある人だけが高いお金を払って手に入れたらいいよねっていうものではやっぱりないですよね。
一方で、インセンティブをつけないとなかなか新薬の開発が進まないという問題もあって、結構ジレンマですよね。
この話題はこのような感じで、特許の問題で揉めていることと、各国のスタンスをご理解いただけたらいいかなと思います。
【ニュース2】WHO による中国シノファーム製ワクチンの緊急使用承認
もう一つ木下的注目ニュースがありますので、これを最後に5分ぐらいで紹介して締めたい思います。
ニューヨーク・タイムズでこれも結構話題になってたのですが、WHO(世界保健機関) が中国のシノファームのワクチンを緊急使用で承認したとのことがニュースになっています。
このシノファームのワクチンがどんなワクチンか、皆さんご存知ですか?
安川康介
アルミでアジュバントつけた不活化ワクチンですよね。
※アジュバント・・・薬物による効果を高めたり補助したりする目的で併用される物質・成分の総称。
引用:Answers
https://answers.ten-navi.com/dictionary/cat04/644/
木下喬弘
その通りです。結構伝統的な作り方をしている、アジュバントの入った不活化ワクチンです。
インフルエンザのワクチンとかと同じような作り方をしてるということでいいでしょうか、安川先生?
安川康介
そうですね、過去にもアルミがついたアジュバントのワクチンはいくつかありますね。
木下喬弘
なるほど、アジュバントっていうのはアルミを使っているものだと思ってたんですけど、他のものを使ってることもあるんでしょうか。
安川康介
ノババックスは Matrix-M を使っていたり、色々あります。
木下喬弘
ああ、なるほど。
いずれにせよシノファームのワクチンは伝統的な作り方をしているワクチンで、WHO 曰く有効性が78.1%だったということで、FDA(アメリカ食品医薬品局)における緊急使用許可みたいなものですが、緊急使用の承認をしたということがニュースになっています。
背景にあるのは先ほどと同じで、先進国はワクチン接種がかなり進んでいるわけじゃないですか。
特にアメリカとイギリスは、初回接種者が5割前後くらいまで来ていて目処が立ってきたところですが、中・低所得国でまだ1個もワクチンが入ってきてない国もあります。
そこに対してワクチン供給を増やすために、中国製のワクチンを出していこうという話になっています。
私たちはこれをあまり取り上げていないのですが、その理由は大きく分けて二つあって、一つ目は日本に入ってくる予定がないこと、もう一つは第3相試験に当たる部分の論文化がまだされていないので、78.1%をどう評価していいかわからないことです。
WHO も承認したくらいですから、きっとそれなりの臨床試験をやってるんだとは思いますが、自分たちで解釈するデータが無いのであまり触れていません。
ツイートでもう一つぶらさげたのですが、ニューヨーク・タイムズは全てのワクチンの作り方を一つ一つページにしてくれていて、そこを見ると結構面白いんですけれども、どうやって不活化するかについて書かれています。
β-プロピオラクトンというのを使って、ウイルスの遺伝子の活性を殺して、細胞内で勝手に増殖できないようにしているようです。一方スパイクタンパク質の方は無傷の状態で入っているので、これを投与するとスパイクタンパクに対する抗体がちゃんとできるということだそうです。
このあたりもご確認いただくと、従来の技術でも新型コロナワクチンを作っている国があるということと、それなりの有効性が示されていることをキャッチアップしていただけるかなと思います。
何かこの点について追加コメントとかある方いらっしゃいますか?
黑川友哉
これは WHO で承認されたからといって、他の国々でも同時に使えるようになるっていうこととは意味合いが違うので、そこはちょっと注意しなきゃいけないかなという印象を持っています。
木下喬弘
実はこれ、独自の薬事規制を持っていない国は WHO の基準で準備をするみたいでなので、今回の緊急使用許可がそれなりに意味を持つ国もあるみたいですね。
黑川友哉
そうですね、アメリカなら FDA、欧州なら EMA(欧州医薬品庁)、日本では PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)、中国だと NMPA(国家薬品監督管理局)など、規制がしっかりされていて、ICH(医薬品規制調和国際会議)という規制のグループの枠組みにもしっかり入っているような国々では、今回の WHO の承認に影響を受けることはありません。
一方でおっしゃる通り、COVAX(ワクチンの共同購入・分配)の枠組みを使ってのワクチン供給に依存せざるを得ないような国にとっては、かなり大きなことなのかなと思います。
でも、これ…WHO ってどうやって審査してるんですかね?
各国の規制当局は、臨床試験の妥当性や信頼性のチェックに結構人と時間とお金をかけてやってるんですけど、その基盤がその WHO にもあるのかどうかっていうのがちょっとよくわからないです。
ですので、その辺が私もなんかコメントしづらいなと思いつつコメントしているんですけれども、また何かわかればアップデートできればと思います。
木下喬弘
日本の皆さんには直接的にはあまり関係ないですが、間接的には全世界にワクチンが行き渡るまでこのパンデミックは終わらないという問題と、先ほど最初のニュースでもご説明したように、アメリカは中・低所得国に対してワクチン自体を輸出しろとプレッシャーをかけられているので、発展途上国でのワクチン需要が満たされることは、高所得国に対してもワクチンが行き届きやすいというのがあると思います。
またファイザー、モデルナのワクチンは明らかに有効性が高く、それを先進国だけで消費していいのかという問題もあり、全ての国に関係があるといえば関係がある話題になるかなと思います。
それでは、今日はこの辺りで締めさせていただこうかと思います。
本日もお聞きいただきありがとうございました。
それでは日本の皆さん、良い1日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
