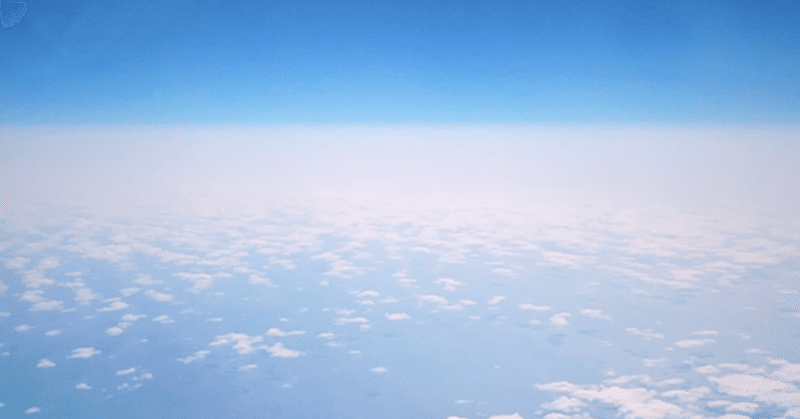
アストラゼネカ社が米国での治験の結果を報告(3月23日こびナビClubhouseまとめ)
木下喬弘
先日も触れましたが、ボストンはケネディ元大統領の出身地でもありますが、アイルランドやイタリアの移民が多い街です。
場所によってはイタリア人街のようなところもありますし、イタリアンマーケットも色々あるわけです。
今、料理にハマっていて、スーパーでペコリーノ・ロマーノやパルミジャーノ・レッジャーノ、パンチェッタを買えるので今日はカルボナーラを人生で初めて一人で作っていました。
こちらはペペロンチーノと違ってブレンダーで油を体中に撒き散らすこともなく作れましたが、作る量が2人用なので、昼からカルボナーラを二人前食べて胃がムカムカしています。
そんな感じで、日本の皆様おはようございます。
朝のこびナビの医師が解説する世界の最新医療ニュースをやっていきたいと思います。
昨日、峰先生に変異の話を教えていただきましたが、変異にもバリアント(Variant)や、リニエージ(Lineage)、ストレイン(Strain)など色々あるということでした。
このチャンネルも10日前くらいまでは真面目に医療の話ばかりしていたのですが、いつの間にか僕がブレンダーを回して乳化させるみたいな話をして若干料理チャンネルに変異していっている感じがします。
今日のこびナビも料理の話から始まっているので、単体でいいますとやっぱりバリアントであろうと思います。
また、ここ数回料理の話から始めるのが定着しつつあるので、これはリニエージで、更に僕が料理の話しかしなくなったら、ストレインと呼べるでしょう。
そしてClubhouseじゃなくて地方のラジオやYouTubeなどに移行したら種が変わったと思っていいのではないかと思います。
峰宗太郎
いいですね!そういうアナロジー大好きなんですよ👶
木下喬弘
ハマったようで何よりです(笑)
最近こうして人が集まるまでの間、本題にどんどんいくとまずいかなと思って、しょうもない話をしてから始めるようにしています。文字起こしの方にも最初はいくらか聞き逃しても大丈夫なようにしようと思ったら、この最初を文字起こししないといけないみたいな熱意が出てきていて、いたちごっこみたいになっています(笑)
ここから皆さんが一番気になっているであろう医療の話をさせていただきたいと思います。
毎日聞いていただいている皆さんとは信頼関係にあると思っていますので、単発の情報でもこちらの意図をくみ取っていただけると思って、あえてこのニュースを持ってきました。
The AstraZeneca vaccine protects fully against Covid-19’s worst outcomes, new study shows.
https://www.nytimes.com/live/2021/03/21/world/covid-19-coronavirus/the-astrazeneca-vaccine-protects-fully-against-covid-19s-worst-outcomes-new-study-shows
アストラゼネカのワクチンの、新型コロナウイルス感染症に対する予防効果が、アメリカの研究で示されたということで、FDA(Food and Drug Administration、アメリカ食品医薬品局)の承認がおそらくとれると思います。
この研究について少しだけ見ていきたいと思います。
そもそも、アストラゼネカのワクチンは主にイギリスでランダム化比較試験をやっています。
その中間解析の結果が去年の12月に報告されているのですが、治験のデザインがかなり複雑で、2回投与する内の1回目を間違って半分量投与してしまった人たちが一定数いました。
投与量を間違った症例は除いて解析するかと思いきや、間違って「1回目に半分量、2回目に全量」投与した(Low-dose/Standard-doseと呼んでいます)人の有効性は90%だと報告されました。
「いやいや、間違って投与しちゃった人の有効性をそんなに推されましても」という感じがしますよね?
一応理屈としてはウイルスベクターワクチンはベクター(運び屋)自体に対する抗体ができてしまう可能性があり、初回の投与量は少なめにしておいた方がベクターに対する抗体が体の中にできにくく、2回目に投与したときにベクターを撃退する可能性が下がるということもあり得るとは思います。
それによって細胞までスパイクタンパク質のDNAを届けることができて、2回目のブースト効果で抗体もちゃんと上がって感染予防効果が上がるのですということです。
ただ、アストラゼネカが「間違ってやった」くせにあと付けで「初回は半分量の方が効果が高い」と言い出したという経緯があって、モヤモヤする部分がありました。
今回はそれとは別で、アメリカとチリとペルーで行った研究の結果が報告されたというニュースです。
アストラゼネカの研究に対して僕も若干身構えているところがあります。
ファイザーやビオンテック、モデルナのもののように、わかりやすいランダム化比較試験なら良いのですが、今回の臨床試験でもどのようなデザインになっているのかまだよくわからないので、これは論文になった時点で再度評価して、有効性がありそうだったらこびナビのサイトにもきっちり記載していこうと思っています。
現時点でデザインは不明ですが、速報段階では79%の有効性が示されたと発表されています。
(※注 後日NIHの専門家委員会からこの数値が間違っているという指摘があり、76%に訂正されました)
どのワクチンもそうですが、重症化予防や入院予防の効果は確実だと考えられています。
例えばジョンソン&ジョンソンのような比較的低めの数値が出ているワクチンについても、重症化予防効果は保たれていると報道されていますね。
ワクチンを打つと少なくとも死んでしまう可能性はすごく下がるという趣旨ですが、これは個人にとってワクチンを接種することの根源的なメリットで、その結果自体は喜ばしいことだと思います。
さて、このアストラゼネカワクチンの臨床試験についてです。試験の詳細はあまりしっかりと書かれていませんでしたが、32449人集めて、141人の発症が出るまで試験を行ったみたいです。
今回の試験は、2対1でのランダム化で、これはワクチンを打つ人が2人に対してプラセボを打つ人が1人ということです。
3万人参加したということであれば2万人がワクチンを打っていて、1万人がプラセボを打っている臨床研究ということですが、これはランダム化としてはあまり効率がよくないです。
いずれにせよ、その結果有効性が79%でした。
高齢者に対する有効性が十分証明されてないために、ドイツやフランスなどのいくつかヨーロッパの国々では、アストラゼネカのワクチンを高齢者の方々には使わないといっていますが、高齢者に対しても80%の有効性がデータとして上がっているということです。
ファイザー、ビオンテック、モデルナのものもそうですけれど、喜ばしいことにこちらに関しても、高齢者に対しても発症予防効果があると考えられる臨床研究の結果になります。
実はアメリカではファイザー、ビオンテック、モデルナ、そしてジョンソン&ジョンソンのワクチンで全人口分くらいはカバーできるらしいのですが、それに加えて少しアストラゼネカのワクチンも入ってくるということで、少し余裕のある運用ができるのではないかと考えられています。
またノババックスのワクチンもおそらく5月には承認がとれて打ち始めることが出来るだろうということで、バイデン政権は少なくとも5月までには全国民に打ち始められるようにしようという話をしています。
このニュースについてなにかコメントのある先生方いらっしゃいますでしょうか。
安川康介
いいですか?
木下喬弘
はい、安川先生お願いします。
安川康介
アメリカのワシントンDCで内科医をしている安川です。
前回の12月に発表されたランセット(Lancet)の論文で批判があったのは、まず高齢者がすごく少なかったということです。
特に効果が高く90%くらいあったというLow-doseとStandard-doseを併せたものでは、56歳以上がいませんでした。
そのほかの群でも高齢者は10%とか12%とかかなり少なかったので、かなり批判がありました。
今回のUSの研究では65歳以上が20%含まれていて、発症予防効果が80%あったということなので、これはすごくいいデータだと思います。
さらに60%が何らかのハイリスクになる基礎疾患を持っていたという方なので、これらの方に対しても効果があったというのもいい結果だと思います。
ただ、現在血栓のことが色々言われています。
血栓のリスクの上昇はなかったということですが、具体的な数字をきちんと書いて、透明性を保つようなことがあってもよかったのではと感じました。
木下喬弘
以前もちょっとこのルームでお話ししたと思うのですが、疫学的に患者さんの背景、例えば性別であるとか、人種であるとか、基礎疾患を持っているかどうかによって治療の効果が変わることをeffect measure modification、日本語では効果修飾といいます。
ドクターの方々は交互作用(interaction)という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、この交互作用という言葉は疫学的では明確に区別して使います。
ともかく、臨床研究をやる上で、効果修飾は関心の一つではあるのですよね。
例えば、アメリカで行った研究が日本でも同じような結果の解釈が出来るのかどうかを知りたいので、白人での結果が例えばアジア人とはちがうとか、そのようなことがないのかということを調べるのはすごく重要なわけです。
モデルナやファイザーのものは臨床研究のデザイン自体が非常に良いという話を何度かしました。
何がいいかというと、当然限界はあるのですが、男女比も均等ですし、白人が多いものの、アフリカ系アメリカ人やアジア系のアメリカ人もたくさん入っていて、人種間で治療効果が違うかも調べられる、すなわち効果修飾がないかというところも調べられるデザインになっているところで、これがすごく大事です。
そういう点が今回の研究では非常によくて、具体的にこの人種における効果は、といったところまではまだ発表されていないのですが、臨床研究のデザインとしては少し改善していると思います。
安全性に関しては安川先生がおっしゃって頂いた通りで、血栓症のリスクというか、懸念は認められなかったとプレスリリース段階では発表されていますが、詳細に何例あったかという点はまだわかっていません。
池田早希
いいですか?
木下喬弘
はい、池田先生お願いします。
池田早希
木下先生もワクチンの効果や安全性がワクチンを受ける人の属性(人種、年齢など)によって効果や副反応が違うかどうかを調べるのはとても大事だとおっしゃっていましたが、まさにその通りで、今後アメリカではワクチンの供給が進んで色んな種類が出てきて、選択できるようになる可能性もあります。そうなった時にどのワクチンをどの人たちに優先して接種するかを考える上で使える検討項目になります。
もちろんまだまだ研究が足りませんので、研究を続ける必要があります。また、供給が安定しないうちは、その時に接種できるワクチンを接種し、罹る前にコロナウイルスから自分を守ることが大切です。
木下喬弘
池田先生ありがとうございます、この辺は疫学の永遠の課題みたいなところでして、やっぱりどうしてもマイノリティの人に対する効果は非常に検証が難しいです。
たとえば妊娠している方やに対する効果や安全性を調べるのが難しいのと同様に、マジョリティではない人種に対する効果なども調べるのが難しいです。
しかもこれはかけ算になって来るんですよね。
たとえばアフリカ系アメリカ人の妊娠している方となると、妊娠している方の全体から更に少なくなる、といったように、いくつか項目を足していくと、”Curse of dimensionality”、日本語で次元の呪いというのですが、分類カテゴリの方が参加者よりも多くなってしまう。
そうすると結局自分に効くかどうかは自分にやってみないとわからない、といった状態になります。
どこかで線引きをして、人種や妊娠しているかどうかでの効果の差などをひとつずつ調べていって解決していく方向性で、疫学研究が組まれています。
次の話題にいきたいと思いますがその前に宣伝をさせて頂きます。
いよいよ我々のクラウドファンディングも残りの期間が短くなってきました。
毎朝聴いて頂いて、すでにご支援頂いている方もたくさんいらっしゃると思いますが、もしまだご支援頂いていない方で、我々のこのClubhouseないしHPの情報提供が役に立っているとおっしゃって頂ける方は、もしよろしければそちらでも支援していただければありがたいなと思っています。
#こびナビ :コロナワクチンの正確な情報で元の世界を取り戻したい(一般社団法人 保健医療リテラシー推進社中 2021/03/04 公開) - クラウドファンディング READYFOR (レディーフォー)
現在3000万円のゴールを目指しておりまして、現在1267万6000円のご支援を頂いております。
ご支援頂いた皆様改めましてありがとうございます。
我々情報の質には自信を持っておりますが、オンラインでの情報提供というのは届く人の範囲に限界があります。
特に高齢者の接種が始まる前に、高齢者の方々にも正確な情報を見て頂けるような、新聞折り込みチラシや電車広告などで多くの人にわかりやすく情報を見て頂いて、自分はコロナワクチンを打った方が良いのかということを判断する助けになればと思っています。
木下喬弘
次の話題にいきたいと思います。
ここからはニュースではなく、昨日の子どもにおけるコロナの重症化の話に対してご質問頂いたことについてです。、
小児科の先生がたくさんいらっしゃいますので、少し補足をしながら解説をしていきたいと思います。
原則論として、今回のコロナの感染症について子どもはすごく重症化しにくいということは皆さんご存じかと思います。
高齢者の中では、例えば80歳以上であれば死亡率10%以上とか言われていますが、子どもはほとんど重症化しないと言われています。
一方で、1歳未満の子どもに関してはほかの年齢の子どもよりも少し重症化しやすいという話があります。
またそれとは別に、この中では池田先生がコロナ禍で一番子どものコロナ感染をたくさん診ておられるのですが、生まれた直後の子どもで、コロナ陽性というのがわかることもあります。
けれども、コロナ自体はそんなに重症じゃない患者さんが多くて、むしろ他の合併症や他の感染症で入院してくる患者さんが多い、というようなお話があったと思います。
結局、生まれたばっかりの子どもは重症化しやすいのかどうかがわかりにくかったというご指摘を頂いたので、そこを少し補足して頂ければと思います。
いかがでしょうか。
池田早希
そうですね、いま木下先生がおっしゃったように、生後28日までを新生児と言いますが、新生児の場合は罹っても無症状か、軽症のことが多くて、重症化するのはとてもまれです。
ですので、昨日のお話ではWHOからはお母さんが出産時にコロナに罹っていたとしても、母子分離でカンガルーケアができないことのデメリットが大きいので、マスクなどの感染対策をした上で、出産直後には母子分離をしないことが推奨されています。
後程、クラブハウスを聴いてくれた方から、お母さんがコロナに罹患している場合、母乳から赤ちゃんにうつる可能性はありますかとご質問を頂きました。
母乳からうつる可能性はないと考えられています。
感染しているお母さんはマスクや手指衛生を徹底して、出産直後から授乳しても良いですし、怖かったら搾乳して他の方にあげてもらうことも出来ます。
もう一つの追加質問ですが、妊娠中にお母さんがコロナに感染した場合、胎盤を経由して赤ちゃんが感染するのか、という質問に関して。こちらは非常にまれです。
新生児が感染した場合は出産直後の場合が多いです。
とは言っても、まだ100%確定的なエビデンスではないのですが、1歳未満のお子さんは重症化しやすいので、周りの家族の方がワクチンを接種して、家に持ってこないということはすごく大切ですね。
お母さんが妊娠中にワクチンを接種した場合は、免疫グロブリンGという種類の抗体が胎盤経由で赤ちゃんにプレゼントされます。
また、母乳には免疫グロブリンAという抗体が含まれます。それはほとんど血液には吸収されなくて、赤ちゃんの粘膜を保護して、コロナウイルスが体に侵入するのを妨げます。
ですので、可能であれば母乳がベストということです。
でも1歳未満のお子さんがいるお母さんに対して「完全母乳育児をしなければならない」というようなプレッシャーを与えるつもりはないです。
(ちなみに私はあまり母乳が出なかったので母乳とミルクの混合育児でしたし、仕事が大変だったので7ヶ月くらいで断乳しました)
木下喬弘
非常にクリアにお答え頂いてありがとうございます。
そもそも1歳未満は重症化しやすいというのはとても正確なデータとして出てきているわけではなくて、少し重症化のリスクが高いのではないかという風なレベルのことでしょうか。
池田早希
CDCや中国からの、入院リスクが上がるという報告でした。
木下喬弘
最初の28日間は重症化リスクが低いというのはデータとしてあるのでしょうか。
池田早希
お母さんが感染していて、産後赤ちゃんを調べたという研究は結構あって、陽性の場合はほとんどが無症状や軽症でした。
ヒューストンは爆発的に感染者が増えていたので、実際に私もたくさんのコロナ陽性のお子さんを診ましたけれど、わたしが診た新生児の患者さんは全て別の原因で入院していて、陽性でもコロナウイルスに関しては無症状の患者さんが多かったです。
木下喬弘
最初の28日間はそんなに重症化しないということと、初乳からうつる可能性は考えなくて良いということです。
胎盤を通して感染したというのは数日前に日本でもニュースになっていたと思うのですが、コロナが流行り始めてからもう1年3ヶ月くらい時間が経っている中で、1例そういった症例があったということが報道されるくらいまれだとお考えください。
池田早希
報告はされてはいるのですが、その中の一部は、本当に胎盤経由で感染したのか、本当は出産直後に感染して陽性になったかもしれないけど厳密にはわからない、という例も含まれていますので、起こる可能性はありますが、頻度としては非常にまれということです。
木下喬弘
ありがとうございます。
まれと言っても段階がありますけれども相当まれなので、現状、皆さんがご心配される必要はほとんどないと思います。
もし感染してしまうと、出産直後に子どもと一緒にいられないといったリスクもあるわけなので...
これについては分離しなくても良いのではないかという議論もありますが、そもそもワクチンを打って免疫をつけて感染を防いでおけば母子分離のリスクを心配する必要もなくなります。
そういったこともワクチンを打つ判断材料の一つに入れて頂ければ良いのではないかと思います。
そのほか内田先生コメントありますでしょうか。
内田舞
そうですね、混乱が起きてしまった原因としては、重症化リスクが高い低いといったときに、比較対象が何なのかがはっきりしていなかったからなのかなと思いました。
生まれたばかりの子どもは重症化リスクが結局高いの?低いの?といった質問について、比較対象を考えてみるとわかりやすいかと思います。重症化リスクに関して、子どもは大人と比べると全体的に低いということが言えて、これは各国のデータでわかっていることです。その「大人と比べると重症化リスクの低い子ども」全体の中では12ヶ月未満の子どもは重症化しやすい、入院頻度が高いといったデータも出ています。
でも絶対数としては重症化する新生児や子どもは大人と比べると少ないと言えます。
ただし絶対数が少なく、大人と比べると重症化リスクは低いとは言っても、重症化してしまう子どもというのはその中に必ずいます。
これは池田先生がクラウドファンディングに対する思いとして、池田先生自身が実際に診て来られた患者さんのお話を書いてくださっているのですが、その中で、血栓症が出てきて両足を切断しなければいけないお子さんや、かなり侵襲性の高い治療が必要になってしまったお子さんもいらっしゃいます。
それを見てみると、大人と比べるとどんなに重症化リスクが低いと言っても、重症化してしまった場合には本当に悲しいケースになってしまうというのがすごく胸に響いてわかることかと思います。
なので、そういったことも考えるとどんなに絶対数が低いと言っても子どもの感染リスクは無視できないものと感じております。
そういう意味で、赤ちゃんの時期から抗体を持って赤ちゃんをコロナから守ってくれるというのは素晴らしいことです。
妊娠中に妊婦さんがワクチンを接種した時に、お母さん側が作った抗体が胎盤を通して赤ちゃんに移行したり、母乳を通してそれを飲んだ赤ちゃんに移行して赤ちゃんを守ってくれるっていうのはすごく喜ばしいニュースだと思います。
更にその母子分離をすべきかどうかという話に関しても、とにかく議論自体を避ける方法として、お母さんも赤ちゃんも感染を防ぐことが一番重要なので、その点で、お母さんや子どもと接する方々がワクチンを打つことによって感染を防ぐということが一番重要です。
木下喬弘
内田先生ありがとうございます。
子どもに関して若ければ若いほど感染しにくいという傾向には確かにあるんだけれども、最初の12ヶ月だけちょっとイレギュラーかもしれないと考えて頂ければ理解しやすいかなと思います。
両先生にもご指摘頂いて、私も今までこのルームで何度もご説明させて頂いているんですけれども、妊娠中にワクチンを接種することとしないことに関しては、しないことを選んだらすべてが解決というわけではなくて、こんな怖いことがあるとということを僕たちは言っていたと思います。
ですがあんまりネガティブな情報提供ばかりだと、やっぱり聴いている側の皆さんもちょっと疲れてしまうかと思います。
あんまりどうすればいいというような一概に解決策はないのですけれども、妊娠中にコロナに感染しないということが一番大事です。
ワクチンという方法をとるのか、感染対策という方法をとるのか、最終的には皆さんで考えて頂ければと思います。
ワクチンというのはすごく怖くて、ネガティブなもので、自分の体を変えてしまったり、赤ちゃんになにかそのダメージを負わせてしまう、といったようなものではありません。
すごくもろい物質なんですよということを皆さんには分かっていただいて、それなら受けてみようかなと思って頂ける方はワクチンを打って頂ければ良いと思いますし、そうは言ってもやはり不安が残るという方は、特に感染対策には気をつけて妊娠中の大事な期間を過ごして頂く、くらいに思っていただければいいかなと思います。
本日はここで締めさせていただこうと思います。
最後にもう一つ、面白い記事がありました。
そもそもRNAってなんなの?というものです。
コロナワクチンの材料「RNA」とはそもそも何か 「タンパク質」「DNA」「RNA」に至る遺伝子研究の歴史(1/4) | JBpress(Japan Business Press)
https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/64579
おそらく皆さんの中にも気になっている方がいらっしゃると思いますので、明日基礎研究チームにmRNAのRNAとはなにかについて超絶わかりやすく解説してもらう、という回をしようと思います。
明日の登壇者の先生方はその準備をして頂いて、皆さんとディスカッションしながらやっていきたいのでお願いします。
僕も正直そんなに詳しいわけではないので皆さんの説明を聞きながら賢くなりたいと思っています。
最後まで聞いてくださった皆さんありがとうございました。
我々こびナビ、毎朝のClubhouseだけではなくて、HPの定期的な更新などで情報提供しておりますので、各種SNSアカウントも是非フォローしていただければと思います。
登壇して頂いた皆様、今日はありがとうございました。
日本の皆さん、よい一日をお過ごしください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
