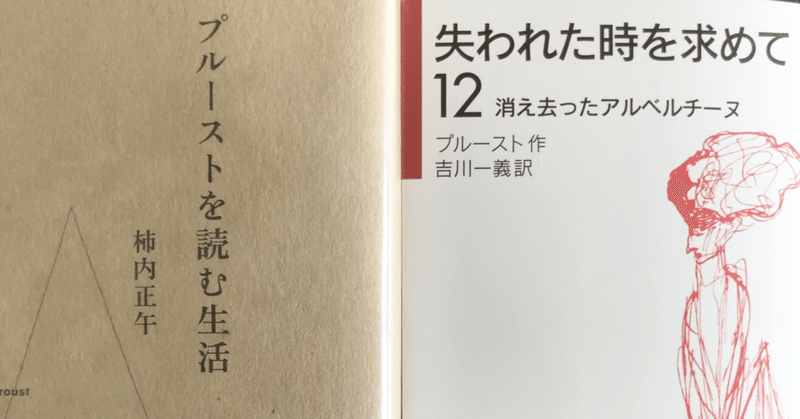
「失われた時を求めて」と「プルーストを読む生活」を読む 113
失われた時を求めて
12巻、407ページまで。デポルシュヴィル嬢という新しい女性がちらっと登場する。主人公の心から、徐々にアルベルチーヌの存在が離れていく。
主人公の書いた文章が新聞に載る。フィガロ紙という大手で、かなり前に投稿したのがやっと載ったようだ。7巻にその話が出ており、長らく放置されていた。父の友人であるノルポワ氏からは酷評されていた文章が、時を経て日の目を見た。これでやっと主人公は名実ともに作家となった。今の日本で言うところの、文学賞を獲って作家デビューしたようなものだろう。
主人公は浮かれに浮かれ、読者のふりをして何部もフィガロ紙を購入しては読む。褒めてもらいたくて、既に読んでいるであろうゲルマント夫妻の家に行く。残念ながらゲルマント夫妻は主人公の文章がフィガロ紙に掲載されたことは知らず、驚きはするもののその場であっさりと流される。
ゲルマント邸では、ジルベルトと出会う。3巻に登場した主人公の初恋の相手、亡きスワンの娘ジルベルトだ。再登場といった感じで、これまでの経緯が語られる。主人公との関係は子供時代を知る者同士といった程度だが、今後も登場するのだろうか。
主人公は次第に、アルベルチーヌとの別離を悲しまない日々を過ごすようになる。それについて、新たな自我と入れ替わったというふうに表現している。
他者にたいするわれわれの愛情が衰えるのは、その他者が死んだからではなく、われわれ自身が死ぬからである。
この感覚は非常によくわかる。僕は一度別れた人ともう一度付き合うことができない。いわゆる元サヤみたいなのがありえなくて、その理由がもう人格が入れ替わっているから。かつての自分と今の自分に連続性を感じない。かつて相手のことが好きだった自分は、もういないと思ってしまう。ここで語られている話もそれに近いんじゃないか。
このあとまたアンドレからアルベルチーヌについての暴露話があり、主人公はもうあまり動揺したり傷ついたりしなくなっている。重要性が下がっている。
「失われた時を求めて」というタイトルの中の「失われた時」とは、このかつての自分ではないだろうか。入れ替わった自我とともに、失ってしまった愛情であったり、感覚であったり、思い出。そういうのを求める旅がこの小説全体ではないか。
小説に書かれていることは、その場その場ではすごく新鮮に読める。アルベルチーヌと出会った頃、楽しく過ごしてた頃、飽きた頃、浮気を疑っていた頃、読めばそのときが今であるかのように、強い感情が活き活きしている。文章に書くという行為そのものが、「失われた時」を永遠にする行為かのように思える。プルーストの小説を書く行為は、移り変わり失われていく諸行無常への抵抗、永遠への挑戦行為ではないだろうか。
プルーストを読む生活
601ページまで。著者は職場に水筒で飲み物を持ち込んでいるようだ。今はコーヒーだとか。水筒なー、少し前小学校で研修があり、今の小学生はみんな家から水筒にお茶を入れて持ってきていることを知った。僕らの頃にはなかった。僕は水筒なんて邪魔で重いから持ち歩きたくない。だいたい水筒なんかに入る量は一瞬で飲み干してしまって足りない。僕の頃はみんな水道水を飲んでいたように思う。小学校には冷水機もなかった。
「自分の気持ち至上主義」がどうとか。あまり興味ないなー。他人がどんな主義であろうと興味ない。「気持ち」も「信念」も大して変わらないと思うけどなー。
サポートいただけると店舗がその分だけ充実します。明日への投資!
