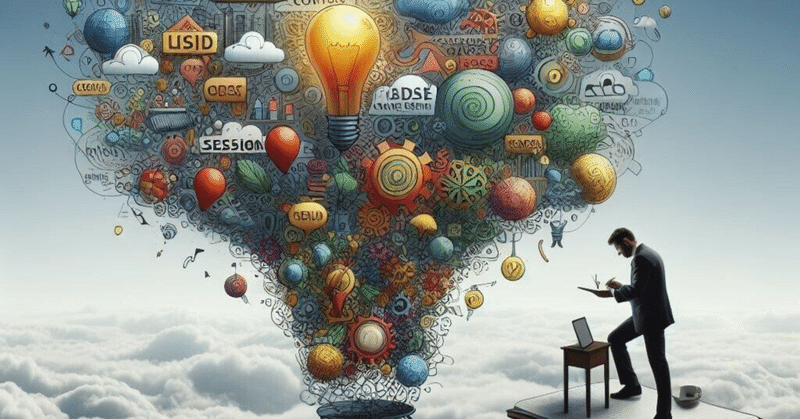
強みは何の役に立つのか? ~「強みが持つ17の機能」を明らかにした論文~
こんにちは。紀藤です。本記事にお越しくださり、ありがとうございます!
さて、本日は強みに関する論文で「強みが持つ”機能”とは何か」を調査をしたものとなります。
”機能”とは、なかなか日本語では馴染みが少ないかもしれませんが、機能とは「Function(機能、用途、目的、役割、任務)」と訳される言葉です。「強みがもたらす”機能”」とは、「どんな強みが、どんな役に立つのか?」と言い換えられるかもしれません。
ということで、どういう内容かなのか、早速見ていきたいと思います!
<今日ご紹介の論文>
『性格特性的強みは何に役立つか?:強みの発揮に関する日々の日記の研究』
Gander, Fabian, Lisa Wagner, Lukas Amann, and Willibald Ruch.(2022).
”What Are Character Strengths Good for? A Daily Diary Study on Character Strengths Enactment.”
The Journal of Positive Psychology 17 (5): 718–28.
30秒でわかる論文のポイント
性格的強みは、ウェルビーイング(幸福度)や抑うつなどに影響があることがわかっている。
一方、性格的強みは特定の目的を果たすことがあることも想定される。たとえば「好奇心の強み」は知識の獲得と活用をサポートする、などである。
本研究では、性格的強みが持つ潜在的な機能について検討する調査を行った。結果、性格的強みは「17の機能」を持つことがわかった。
また、参加者に14日間の日記調査を実施し、「日々の性格的強みの発揮」と「17の機能」の経験を報告させ、調査した。その結果、性格的強みの発揮は、いくつかの機能と正の相関があることが示唆された。
とのこと。なるほど、「性格的強み」が「どんな機能」を持っているのか、気になるところです。
性格的強みがもたらす「長期的な成果」と「短期的な成果」
性格的強みは、様々な成果をもたらすことがわかっています。たとえば、これまでの研究でいえば、人生全体に亘る生活満足度、学業成績、タスクパフォーマンス(仕事の成果)、人間関係、健康関連行動、抑うつetc・・・。
学生であれ、社会人であれ、性格的強みは異なる生活領域における様々な「長期的な成果」と結びついていることがわかります。
一方、成果はより近しい目標(短期的な成果)に役立つ可能性もあるわけです。たとえば、
・肯定的な人間関係を築くことができるのは「ユーモア」の強みが役立つ
・喜びを経験しやすくなるのは「美や超越性」の強みが役立つ
・学習の知識の獲得や活用は「向学心」の強みが役立つ
というように、「学業成績」「仕事の成果」などの長期的な成果よりも少し手前にある「短期的な成果」にもつながる可能性が考えられます。
研究のポイント
上記の仮説を元に、以下のようなプロセスで研究を進めていきました。
以下ポイントについてまとめてみたいと思います。
調査(1)「強みがもたらす機能」を特定する
まず、「強みがもたらす機能」を調査するために、以下のようなステップで調査を進めていきました。
{STEP1}参加者への質問調査
・参加者63名にVIAの24の強みを説明し、自分自身の中で顕著だと思う5つの強みについて以下3つの質問に答えてもらった。
<強みの機能を特定する質問>
Q、その性格特性的強みを何に使いますか?
Q、この性格の強さによって可能になること、あるいは容易になることは何ですか?
Q、あなたの生活の中で、この性格特性的強みを、具体的にどのように活かしているか、具体的な例や状況を挙げてください。
{STEP2}定性データから強みがもたらす機能を分析する
参加者の回答から集まった定性データについて、研究者3名で分析し「強みがもたらす機能」を概念的に類似したものを集約し、統合する反復アプローチを行っていった。結果、以下「強みがもたらす17の機能」が明らかになった。
{STEP3}「強みがもたらす17の機能」の特定する
これらの分析によって以下17項目が、「強みがもたらす機能」として識別されたものとなりました。VIAの言葉とも重複するところがありますが、内容を整理いたします。
<強みがもたらす17の機能>
・知恵(Wisdom):私は既存の知識を適用したり、新しい知識を得た。
・勇気(Courage):私は内部や外部の抵抗を意志の力で乗り越え、目標を達成した。
・人間性(Humanity):私は他者との交流を通じて共感や慈しみを示した。
・正義(Justice):私はコミュニティの福祉に貢献した。
・節度(Temperance):私は過度な行動を抑制した。
・超越(Transcendence):私は何か大きなものや意味深いものにつながったと感じた。
・意味(Meaning):私はより高い目的のために自分の潜在能力を使った。
・エンゲージメント(Engagement):私は活動に夢中になり、完全に没頭した。
・喜び(Pleasure):私は楽しみ、幸福、または喜びを感じた。
・健康(Health):私は元気で健康だと感じた。
・楽観(Optimism):私はこれからのことに楽観的でポジティブだと感じた。
・達成(Accomplishment):私は個人的に何かを進歩させることができた。
・習得(Mastery):私は日常の課題に対処するための手段を見つけた。
・ポジティブ思考(Positive Thinking):私は自分自身、他者、または世界に対するポジティブな視点を影響させた。
・独立(Independence):私は自由で独立していると感じた。
・理解(Understanding):私は自分自身、他者、そして世界を理解することができた。
・自己効力感(Self-Efficacy):今日、私は自分の行動で違いをもたらすことができたと感じた。
調査(2) 性格的強みと強みがもたらす機能の相関を調べる
次に、これらの結果を元に、196名の参加者を対象に「14日間連続の日記調査」を実施したのでした。
内容は、参加者に対して毎日アンケートを送ります。アンケート内容は「性格特性的強み」と「強みがもたらす機能の経験」についてランダムに設問が出されます。参加者は、それらに答えていきます。
そしてアンケートの結果から、個人内で「強みの発揮」と「強みのもたらす機能の経験」の相関がどれくらいあるか?を調査することとしました。
それらの結果、「性格的強み」の各項目と「強みがもたらす機能」には、いくつかの相関が見られることがわかりました。以下が、特に相関が高かった項目となります。
<「性格特性的強み」と「強みがもたらす機能」の相関が高かったもの>
●知恵と知識の美徳
・創造性(Creativity):熱中、喜び、達成、習得
・好奇心(Curiosity):知恵、熱中、楽観
・知的柔軟性(Judgement):知恵、理解、自己効力感
・向学心(Love of Learning):知恵、達成、熱中、理解、自己効力感、人間性
・大局観(Perspective):勇気、ポジティブ思考、達成、自己効力感
●勇気の美徳
・勇敢さ(Bravery):勇気、ポジティブ思考
・忍耐力(Perseverance):達成、勇気、知恵、熱中
・誠実さ(Honesty):人間性、理解、自己効力感
・熱意(Zest):健康、熱中、喜び、楽観
●人間性の美徳
・愛情(Love):人間性、喜び、楽観
・親切心(Kindness):人間性、喜び、理解
・社会的知性(Social Intelligence):人間性、喜び、理解
●正義の美徳
・チームワーク(Teamwork):正義、人間性、理解
・公平さ(Fairness):正義、人間性、理解
・リーダーシップ(Leadership):正義、自己効力感、意味
●節度の美徳
・寛容さ(Forgiveness):正義、理解、自己効力感
・慎み深さ(Humility):正義、人間性、ポジティブ思考、自己効力感
・思慮深さ(Prudence):節度、ポジティブ思考
・自律心(Self-Regulation):勇気、達成、知恵
●超越性の美徳
・審美眼(Appreciation of Beauty & Excellence):喜び、独立、楽観
・感謝(Gratitude):喜び、人間性、楽観
・希望(Hope):楽観、喜び、習得
・ユーモア(Humor):喜び、独立、楽観
・スピリチュアリティ(Spirituality):超越、熱中、自己効力感

まとめと個人的感想
確かに言われてみれば、「性格的強みによる成果」は、ウェルビーイング・仕事の成果、抑うつなどの「比較的長期的な成果」であるものを目にしていました。
しかし、今回の視点「強みがもたらす機能」を見てみるのは、より性格的強みの活用を発展させるものだと感じました。性格的強みを活用することで、「新しいことに”関心”を持つようになった」とか、「”楽観的”に考えられるようになった」とか、「学びの”習得”に役立った」などは、明確な成果とは言えないかもしれませんが、たしかに成果に繋がる重要な「機能」です。
そして「自己効力感」「ポジティブ思考」「達成」などそれぞれ質の違う成果を得るために、特にどの性格的強みを発現させると効果的なのか?、それらを相関分析等の調査を含めて検証するという研究デザインに「ほほーこんなのもあるんだ」と感銘を受けました。
いやはや、2022年の比較的新しい研究ですが、より面白い研究が増えていて読み応えがありました。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
