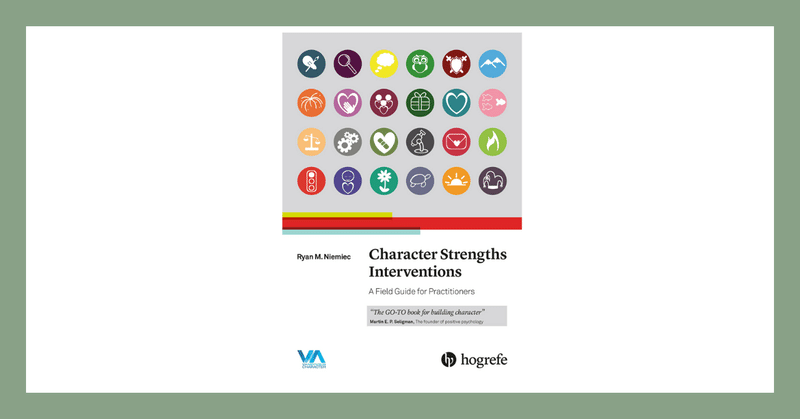
書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く #6(第3章_前半)
こんにちは。紀藤です。さて、少しお休みをしておりましたが、本日は強みシリーズ「書籍『Character Strengths Interventions』を読み解く」をお届けいたします。
今回は、第三章の「強みの実践 ー強みに基づく実践の6つの統合戦略ー」というタイトルの章になります。
ここでは「性格的強み」を実践につなげるために抑えておくべきポイントが「6つの強みの統合戦略」として語られています。
<強みに基づく実践の6つの統合戦略>
1,強みを認識し、ラベルを貼り、肯定する
2,強みは社会的なものである
3,強みを活動につなげる
4,強みに基づく実践モデルを使う
5,強みをプロフェッショナルなアプローチに組み込む
6,自分の強みをセッションとミーティングに使う
本日は、この中の前半1~3について読み解いていきたいと思います。
それでは、早速参りましょう!(前回のお話はこちら↓)
1,強みを認識し、ラベルを貼り、肯定する
さて、まず強みを活かすためのまず最初のステップは「ストレングス・スポッティング」すなわち、強みに注目することです。
私達は、どちらかというとネガティブなことに目を向けてしまいがち。しかし、その中にある強みに目を向ける事がはじまりなのです。その上で、具体的にどのような方法が強みの実践の入口となりえるのか、見ていきましょう。
「強みのアセスメント」を受ける
では、どのように強みに目を向けるかというと、一般的でわかりやすい出発点が「強みのアセスメント(VIAサーベイなど)」を受けることです。
その上位の結果から、自分自身を最もよく表す5~7個の強みを書き出します。
自分自身の「強みを観察」する
その他にも強みを見つける方法は、「自分自身を観察する」ことです。
朝など一定のルールを決めて振り返り、自分を観察することで、自分の性格的強みがどのように使われているかに意識を向ける方法です。
(例:夜、歯を磨きながら、明日のことにワクワクしていると感じていることを自覚する(「希望」の強みが出ている)、何気ない親切に心からありがとうと思える(「感謝」の強みが出ている)など)
<自分の強みを理解するための問い>
・自分の性格的強み、特徴的な強みについて自分は何を信じているだろうか?
・私は自分の最高の強みについて、どれほど本当に理解しているだろうか?
・私が自分の最高の強みについて学ぶために、何が必要だろうか?
・なぜ、私の特徴的な強みは価値があるのだろうか?
・私の他の強みは、どのような価値があるだろうか?
自分を理解している人に「強みを聞く」
自分の強みを発見するもう一つの方法が、友人、部下、配偶者、上司など、自分を理解している人を考えます。そして、彼/彼女らが、「わたしの強みについて何を理解しているのか?」を聞くという方法です。他人の目を通じて自分の強みを見つけることができるようになるシンプルな方法です。
自分の「強みを肯定する」
自分の強みを認識し、ラベル化し、理解を深めた後は「強みを肯定する」することが重要なステップとなります。自分の強みを肯定することが、強みに価値を見出すことに繋がります。
自己肯定感理論(Steele, 1999)によると、自分の価値観を肯定することで、自分に対する見方が広がり、重要なことが見通しやすくなり、ストレス要因から身を守ることができるとのこと。
その他の研究によれば、自分の価値観(性格的な強み、その他の価値観)について書くことで、ポジティブな効果(行動の変化、健康状態の改善、人間関係の改善)などがあることが示されています。
2,強みは社会的なものである
「性格的な強み」とは、もちろん自分ひとりのときでも表現できるものですが、その重要な特徴として「社会的な性質を持つ」ことが挙げられます。
我々は、家庭でも職場でも様々な状況で強みを発揮しますが、それらを考えると、「我々の強みは他者に貢献すべき共同体の共有財と見なすことができる(Fowers,2005)」とのこと。
他者の強みをみつける3ステップ
さて、強みを社会的なものと考えた時に「自分の強みと、他者の強みをつなげる」ことは重要な行動になります。
では、社会的なものとして具体的になにをするのか?ですが、「他者の強みを見つけること」が強みの実践者としては重要なアクションである、と述べています。そして、他者の強みを見つけるための行動が、以下の3ステップであると述べました。
<他者の強みを発見するための3ステップ>
ステップ1:ラベリング(気付いた強みに名前をつける)
ステップ2:説明する(強みの説明と根拠を述べる)
ステップ3:感謝する(その強みの価値を伝える)
そして、1つ補足をすると「強みに注目する実践者」は、”性格的強みの「言語」に精通していなければならない”と強調します。強みの分類やその概念、次元を学ぶことで、強みを見つけるための視点を広げることができるのです。
「強みの行動」を探す訓練をする
性格的強みは、「思考・感情・行動」に現れます。
思考はその人の主観的なものですが、行動は話し方や言動など観察可能なものです。たとえば、VIAの24の強みを考えると、いくつかの強みを表している行動があると示しています。本書では行動例が示されていました。

3,強みを日常生活につなげる
性格的強みは、私達の中にある「自然のエネルギー資源」のようなもの。
であるならば、それらをぜひ私達の日常の仕事やプライベートに持ち込みたいものです。
米国の労働者を対象とした調査(VIA institute, 2015)では、労働者64%が仕事での成功は自分の強みを活かすことにかかっていると考えていることに対して、弱みを改善することで成功が向上すると考えているのが36%にすぎないそうです。
しかしながら「自分の強みを毎日発揮できている」と答える労働者は約半数にとどまり、上司から自分の強みを全く認めてもらえないと回答された労働者は2%であるとのこと。
職場におけるワークチームの7つの役割
では、具体的に私達は性格的強みを、どのように職場に持ち込むことができるのでしょうか?
そこで、1つMayerson(2015)が、職場の役割においてワークスチームに共通する共通の役割として、以下の7つを述べました。そしてこれらは、性格的強みとの関連性があることが明らかになっているそうです。
<ワークチームに共通する7つの役割>
1,アイデアを生み出す
2,情報収集をする
3,意思決定のための情報分析をする
4,アイデアやプログラムを実行する
5,社内、社外の他者に仕事へのメリットについて影響を与える
6,同僚との人間関係をマネジメントする
7,仕事とチームに活力を与え、困難を乗り切る
まとめと感想
とのことで、本日はここまでといたします。
時間はかかりますが、一つずつ読み解くことで、自分の中で散らかっていた知識が、再度整理をされていく感覚を覚えます。
本日のお話は、強みの実践者としては共通で、VIAだけではなく、ストレングス・ファインダーにも重要なことだと感じました。個人的には「強みの実践者は、強みの言語に精通しなければならない」が一番のヒットです。
そのためにも、VIAという視点から、強みのレパートリーを増やしたいと改めて感じた章でした。
最後までお読み頂き、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
