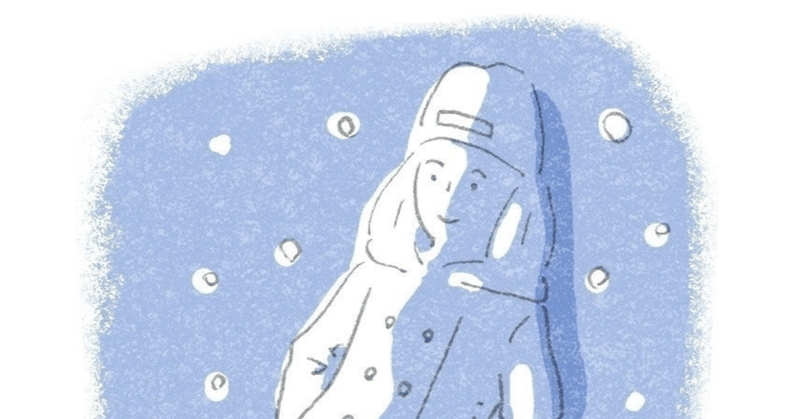
最後のレーション
今夜はメシが食える。敵兵を一人、殺した。
拠点のテントに戻った。拠点を守る味方が構えている兵士のカラシニコフにはマガジンが装填されていない。極東の平和ボケした国みたいだと思った。もう、拠点防衛に使う弾丸など残っていない。しかし、そんなことを口に出そうものなら督戦隊の女子高生士官に背中から弾を撃ち込まれる。俺は、そんなロバを二人は見た。いや、もっと、見ていたかもしれない。この戦争がはじまって、何年かを俺は忘れていた。その間に中止になった五輪は夏季、冬季が数度あった。
督戦隊のメス犬が、俺に声をかけてきた。戦争が長くなり、俺の故郷(くに)から誘拐されてきて洗脳されて兵士に仕立て上げられた少女だった。うれしいことに洗脳されて督戦隊にふさわしい女性に成長したのだ。
「お前は何日ぶりの夕食になる?」
「三日ぶりであります」
「役に立たないやつだ。まぁ、いい。三日、続けて畜生どもを処分したらもっといいことがあるのはわかっているんだろ。あんたの最後はいつだったかな?」
そうして、彼女がレーションを地面に投げつけた。俺はそれを拾った。俺は彼女を見た。俺を見る、彼女はオーガズムに達したように見えた。
レーションは「牛肉入りお粥」、「牛挽肉のミートボール」、「牛肉とにんじんとえんどう豆の煮込み」だ。俺は自分のベッドのあるテントに向かった。レーションは軍用の保存食だ。
俺はバーナーでお湯を沸かし、レーションを温めた。敵側のレーションを略奪したことがある。奴らのレーションは加熱式パックになっておりお湯で温める必要がない。その上、うまい。俺らのレーションは半世紀以上前の本来は廃棄されるはずだったレーションだ。当然、まずい。そして、こちら側はそれですら、補給が追いついてはいない。それで、戦果をあげた時にしか支給されない。俺はこの部隊では戦果をもっともあげている。それでも一週間でメシを食えるのは3日もない。そんな腹ペコで戦争に勝てるか?勝てるわけがない。それでも俺たちの国は戦争を続けている。ある意味ではSDGs的な持続可能な戦争だ。俺たちの軍が不利になると、なぜか補給が増えて反攻が可能になる、そして戦力の均衡がはかられる。戦争は続く。その時は毎日、メシも食える。そのために少女・少年たちは戦い続ける。
腹ペコになった兵士はどうなるか?死ぬだけだ。俺の隊だけでもこの1年で俺以外の顔ぶれは全員、変わっている。この拠点で言えば、俺と日本のやくざの片手の指ほどの兵士が一年間、生き残った兵士だろうか。あとは督戦隊のメス犬だけだ。
お粥をスプーンですくい、口に運ぶ。寒い時は暖かいものはまずくても体が温まる。小雪が舞っている。同時におふくろのボルシチが懐かしくなる。思いだす、暖炉が部屋を暖め、家族3人で食べた、ボルシチ。あの頃、俺は5歳だったろうか。俺もメス犬と同じく、誘拐されて兵士になった。
彼女が気の毒なのは美人すぎたことだ。ゆえに大人たちの玩具にされ、狂ってしまった。彼女を玩具にした大人たちはストレートだけではない。LGBTQ+、そんなものはきれいごとだと彼女は絶望している。俺も狂っているが、彼女はもっと世界に絶望している。
わかっている今夜は来るだろう。いやだった、愛のない交わり。それも彼女が達するまで何度も何度も続く。ひどい時は朝まで休みなしだ。その上、彼女は交わりでドラッグを使う。
兵士が生き残るためにはドラッグが必要とも言われる。俺は違うと思う。ドラッグをやると敵を感じる繊細さが失われる。撃たれる恐怖も感じなくなり、殺されていく。俺はドラッグをやらなかった。だからこそ、生き残れた。
少年・少女をあやつるためには食そして性しかない。戦場では貨幣など価値をもっていなかった。少年・少女の戦場でのストレスのただのはけ口がメス犬だった。
彼女がなぜそんなことをやるか?そこまでしないと士気が保てないからだ。彼女自身の士気も。彼女の意思などはそこにはない。絶望して狂った彼女が求めるものなど、そこしかなくなる。
今夜の彼女は様子が違った。しおらしい。レーションを持って、俺のベッドにやってきた。今日はないのだろうかと思った。
「ねぇ、今日はなんの日だか覚えている?」
「開戦記念日はまだだろ?敗戦記念日か?」
言ってはいけない、冗談を言ってしまった。しかし、彼女は逆上しなかった。
「それもいいわね。もう、味方を後ろから撃つのはいやよ。あんたと出会った日よ」
俺は、メス犬がなぜこんなことを言うかと思った。
「覚えちゃいないよ。そりゃ、あんたが子どもだった時から知っているけどね。同じ施設から出てきたからな」
「あんたは覚えていないだろうけど、戦争がはじまる前にあんたに出会った日よ」
俺は、メス犬がとうとう狂ったかと思った。が、彼女はまじめだ。記憶の奥までダイブした。思い出せ、俺。
思い出した。雪の日の公園で出会ったブランコをゆらしている黄色いダッフルコートの少女のことを。
「あんた、あの時の子か?」
「思い出したくれたのね。あの日、わたしは誕生日だったけど、おとうさん、おかあさんは工場に行っていて一人っきりだったの」
「あの時、あんたは。たしか、泣いていた」
「そう、その時にハンカチを差し出してくれたのがあんた」
そう言い、彼女はポケットからハンカチを出してきた。ぼろぼろになった白いハンカチに、俺のイニシャルがキリル文字で縫い込まれている。
「わたしの初恋。あんたと出会えて幸せだった。立場を利用したことは謝る。だけど、それしか生き残る方法もなかったの」
時代だった。わからなくもない。俺も似たようなものだ。俺がトリガーを引くたびに壊れた家庭はいくらでもある。俺も世界を破壊している。俺とメス犬と同じような子どもを生産していた。そうしないと俺も生き残れなかった。
「ケーキよ。二人で祝いましょう」
彼女はケーキのレーションを二つ、出してきた。俺たちはそれを包みから開け、口にした。クッキーにチョコレートがまぶしてあって、ナッツとドライフルーツがトッピングされていた。甘いものなど何年ぶりだ。
そして、彼女は泣きながら言った。
「これがこの部隊の最後の食料。後方の補給拠点は昨日、爆撃されて、もう補給は来ないの。一緒に死んで」
彼女になにかやさしい言葉をかけなければ。
「あんたの作ったボルシチを食べたかったよ」
彼女は泣き止んだ。俺にキスをしてきた。唇は震えていた。でも、人間の暖かさがあった。
<了>
[作者の声]
これは匿名掲示板のあるスレに投稿したものに、そこからのアドバイスで手を入れました。
作品(かもしれない)の舞台は説明しません。そこの国のスラングを使っています。わかりにくいですが、そこの説明は野暮なのでしません。ただ、ちょっと匿名掲示板への投稿時はスラングの使い方を間違えていたので修正はしています。フルメタはちょっと意識しています。ボルシチのくだりはフルメタのあるエピソードから着想を得ました。
戦場のリアルが伝わるならいいのですが。
戦場での誘拐をテーマにしたのは、NHK クローズアップ現代を見たからです。そこからの着想です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
