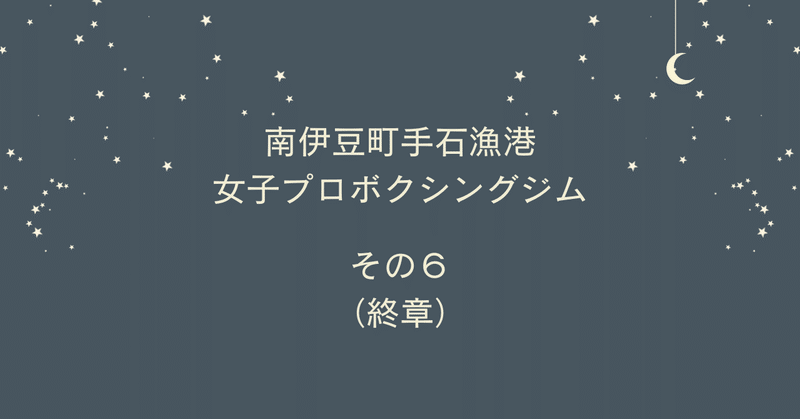
小説:南伊豆町手石漁港女子プロボクシングジム その6(終章)
TKO
コーチ、リングに急いで入ってルミを抱える。
「だいじょぶか?だいじょぶか?どっか痛いか?」
ルミ、少し笑いながら答える。
「だいじょぶだよ。ラッキーパンチだから」
マリが出したイスにルミが座る。マリは水を飲ませる。コーチはアドバイスをする。
「ダメだ。ルミ、ラッシュの時、左のガードが下がっちゃってる」
ルミが苦笑する。
「そっかー。もうすぐ勝てる、あいつに恩返しができると思ったら、なんか、、、」
コーチは身振りを交えて説明する。
「女子に多いんだよ。強いパンチ打つ時にさ、反動つけようとするのか、力込めるためなのか、逆側の腕で反動つけるようにしてガードが下がっちゃうんだ。こう、、、」
左腕を横に振って右のパンチを打つような仕草をする。たしかに、左のガードが下がって、ガードとして機能していない。
「だから、倒そうと思ったダメなんだ。シャドーやってるような気で、リラックスして打ってかないと」
ルミが力強くうなづいた。
「はい。すいません」
ゴングが鳴った。両者が立ち上がった。
前回の攻勢に気を良くしたキヨシが勢いよく向かってきて、左ジャブ、右ストレートを出してくる。ルミは驚いて後退した。コーナーを背にした。キヨシのセコンドが盛り上がる。
「いいぞ、いいぞー、追い込め、追い込め」
キヨシが、さらに攻勢をかけようと進んでくるところに、ルミは「かみのひだり」の右ストレートを出した。ちょうどカウンターのような形になって、キヨシの鼻のあたりを真芯で捉えた。キヨシはその場に、前のめりにダウンした。
「おぉぉぉぉーっ!」
会場に歓声があがる。
レフリーがカウントを始めたが、動かないキヨシを見て、両手を振った。レフリーストップによるTKO(テクニカル・ノックアウト)だ。ルミが勝った。
「おぉぉぉぉーっ!」
さらに会場に歓声があがる。
コーチとマリ、リングに入ってルミの肩にタオルをかける。マリが話しかける。
「うまかったなー。ルミちゃん、強いわー」
ルミが照れる。
「テヘ」
コーチは倒れているキヨシを見ている。キヨシが上半身を起こしたのを確認して、ルミの方に振り返る。
「ナイス右。ナイスKOだったよ」
ルミが照れる。
「テヘ」
サダオが友人の肩を借りてリングを降りる。会場からパラパラと拍手が起きる。
入れ替わりに、漁協の若い事務員がマイクを持ってリングに入ってきて、話始める。
「え、す、素晴らしい戦いでござ、ござりました。え、このような素晴らしい選手がいるのは、手石漁港女子ボクシングジムでござります。練習生を募集しておりますので、「強くなりたい」「自分を鍛えたい」とお考えの女性のみなさん、どうぞ無料体験に来てください。年齢制限はありません。それから、スポンサーも募集しておりますので、このような女性たちを後援したいという篤志家の皆様も、ぜひ無料体験におこしください」
サダオが友人の肩を借りて控え室に向かっている姿をみていたルミ、急にマイクを奪って呼びかける。
「キヨシ、おい、キヨシ」
歓声がやむ。キヨシが立ち止まってリングを振り返る。ルミが力一杯叫ぶ。
「お前、女なめんなー!」
観客から大歓声。ルミはマイクを投げ捨てて両手をあげて観客にアピール。観客が総立ちになる。
大歓声の中、ルミがリングを降りると、ミッコとばーちゃん3人が立っている。ばーちゃん3人はルミを取り囲んで、3人それぞれの両手で、ルミの腕をつかんだ。
「ルミ、痛くねーか?痛くねーか?」
「ルミ、よーがんばった。すーっとしたぞ」
「ルミ、ようやった。ようやった」
ルミ、ばーちゃん達一人一人にハグする。ミッコがばーちゃん達を引き離す。
ルミは誇らしげに両手をあげて、控え室に戻っていく。
控え室で、ルミがイスに座っている。その前にコーチがひざまづいて、バンデージをほどいている。マリはその後ろで、ほといたバンテージをまとめている。ルミが急に話し始めた。
「あたし、子どもの頃から一人だったから、、、」
コーチとマリがルミに顔を向ける。ルミが続ける。
「また一人になるのが怖いんだ。だから、ヘンな男でも、寄ってくるやつと一緒にいるようになっちゃうの。へへへ」
ルミは自虐的に笑った。コーチとルミは何を言っていいのかわからなかったので、作り笑いで応答して、バンデージをほどく作業を再開した。少し間を置いて、ルミがいった。
「コーチはさ、裕ちゃんだって思ってたんだ。信頼できる人だって。初めて会った時から、、、」
コーチ、不思議そうに尋ねる。
「なんで?」
ルミが自分のコブシを見ながら言う。
「だって、初めて会った時、質問した時、そこの花壇のとこで、立ち上がって答えてくれたじゃない?」
コーチ、バンデージをほどきながら言う。
「そうだっけ?」
ルミが、それを見ながら言う。
「そうだよ。渡哲也さんが、新人の時、日活の撮影所で挨拶に回ってたんだって。そん時、裕ちゃんだけが、立ち上がって挨拶返してくれたんだって。渡さんはど新人で、裕ちゃんはもう大スターだったのに、、、コーチも偉い賞とってるのに、あたしなんかに立ち上がって答えてくれたんだ。「あぁ、この人は裕ちゃんだ」って感激しちゃった」
コーチ、照れる。
「へへへ」
ルミがコーチを見て言う。
「でも、なんか、ユー子ちゃんの谷間ばっかり見てるからだいじょぶなのかなーって思った時もあったけど(笑)、やっぱり裕ちゃんだった。。。コーチ、ありがとね、、、」
コーチ、不意をつかれたので照れる。
「や、やめろよ」
ルミ、バンデージを見る。
「あたしさ、ダウンした時さ、呼びかけてくれたじゃない?おっきい声でリング叩きながら、、、」
コーチ、照れる。
「あ、あぁ、ちょっと興奮しちゃったよ」
ルミが続ける。
「あたし、あれで気がついて。コーナー見たらコーチとマリが一生懸命呼びかけてくれてて、、、」
コーチ、照れる。ルミも照れながら、つとめて明るく言う。
「そ、そりゃ、あたり前っしょ」
ルミが何となく引きつった笑顔でコーチとマリを交互に見た。そして、下を向いた。
「あぁ、アタシにも仲間がいる。あそこのコーナーに、あたしの事を、ほんとうに心配してくれてる仲間がいる、、って思って、、、うれしくて、うれしくて、、、」
ルミがポロポロと涙を流した。それを見て、明るく振る舞っていたマリもポロポロと涙を流した。
「やめてよ。もー、ルミちゃん、勝ったのにぃー」
コーチ、真上を向いたまま立ち上がった。真上を向いたまま、少し震えた、少し高い声で言う。
「ト、トイレ行ってくる、、、」
明らかに不自然に上を向いて、コーチが控え室から外に出て行く。
控え室の外には、ミッコとばーちゃん3人が心配そうに控えている。そこで上を向いたコーチが出てきたので、質問を始める。
「ルミ、どうだ?」
「ルミ、ケガしてないか?」
「意識、ちゃんとあるか?」
その質問にすべて答えず、コーチは上を向いたまま「クカッ、クカッ」と妙な声をあげて、トイレに向かって歩いていった。トイレに行くコーチを見ながら、ばーちゃん達がやりとりする。
「泣いてんのか?」
「泣いてるみてーだな」
「中でルミ死んだのか?」
ミッコがばーちゃん達に教える。
「コーチは繊細なんだよー。だーから直木賞取れたのよー」
ばーちゃん達は感心する。
「はー。なるほどなー」
コーチがトイレで顔を洗って控え室にもどってくると、ミッコとばーちゃん達がいる。ばーちゃん達が口々に言う。
「よかったよ。コーチ」
「ほんとだ。よかった。スッキリした」
「あたしんとこのヤドロクもロクなもんじゃなくてねー、酒飲んじゃ暴れてたよ」
「ほんとだよねー。昔は多かったよねー。あたしんとこもだよ」
「ほんとだ。ぶんなぐってやりたかったけど、あの頃コーチがいればねー」
「ほーんと、スッキリした。ルミはよくやったな」
「ほんとだねー」
少し間があったので、ばーちゃん達の話は終わったんだと思い、コーチは相づちを打った。
「ほんとだねー。ルミちゃん、強かったねー」
ハツばーちゃんが尋ねる。
「ルミはプロになれっかい?」
コーチが自信を持って言う。
「なれるよ。問題ないね」
ミツばーちゃんが言う。
「よし。わかった。アタシたちで1200万円寄付する。一人400万円ずつだ」
コーチは、少し頭がボンヤリした。
「へ?」
ミッコもヘンな声で言った。
「へ?」
おでんを頼んだのにチクワブが入ってなかった時みたいな、クリームあんみつを頼んだのにアイスクリームがのってなかった時みたいな、そんなボンヤリした時間が少し流れた。それを見て笑いながらタツばーちゃんが言う。
「なんだよ。ルミがプロになるのに、どっかに加盟すんのに1千万円必要なんだろ?」
コーチがぼんやり答える。
「そ、そうだけど、、、」
ミッコが我に返る。逆にばーちゃん達に尋ねる。
「みんな。いいの?そんなことに使って。息子や娘は反対すんじゃない?」
「いいんだ、いいんだ。あいつらにはもう必要なものはやったから。いー大人なんだし」
ミツばーちゃんも同意する。
「そーだ、そーだ。もう先も短いんだ。たまには自分の好きなことに使うんだ」
タツばーちゃんも同意する。
「アタシたちはな、ルミがプロになるとこ見たいんだ。ルミが手石でプロになって、がんばって練習して、歯を食いしばって試合してるとこ見たいんだ。だから3人で1200万円寄付する。でも、試合の時は、アタシたちを必ず連れてってくれよ」
コーチ、試合の疲れで頭が回らない。ボーッとしながら答える。
「そ、それは、もう、毎回連れてくけど、か、必ず連れてくけど、いいの?ミッコさん、いいの?」
と、ミッコの方が見る。ミッコは笑顔で言う。
「いーよ、いーよ。いー話じゃない?ばーちゃん達の夢を載せてさ、このばーちゃん達カネ持ってっから。昔はこのあたりにも魚がいーっぱい来たからさ。でも使い道なかったからさ、よかったじゃん。ね?あっちに行ったら、じーちゃん達にみやげ話ができるよ」
3人のばーちゃんがビッグスマイルで答える。
控え室の中では、マリが嗚咽しながらルミのバンデージを巻いている。ルミは、座って床を見て、静かにポロポロと涙をこぼしている。
町役場
3月になった。温暖な南伊豆は、やっぱり東京より暖かい。
町役場の駐車場に大きなBMWが止まって、漁協長が降りてきた。紋付き袴だ。なんかキメてる。
ミニバンが入ってきて、プップッとクラクションを鳴らした。漁協長が見ると、ルミが運転している。助手席にミッコが座っている。漁協長が近づいていく。
「おーす。なに?おばちゃん、車新しくしたの?」
ミッコが降りてくる。
「うん。後ろ自動ドアなの。これでばーちゃん達試合に連れてくんだ」
後ろの自動ドアが開いた。ルミが手伝いながら、ミツばーちゃん、ハツばーちゃん、タツばーちゃんが次々に降りてきた。みんな洒落た着物を着ている。
「なんだ。イチロー。似合わねーな」
漁協長が苦笑する。
「オレの嫁はステキだって言ってたよ。ばーちゃん達はお似合いじゃねーか?」
ばーちゃん達、照れ笑い。
「ルミの晴れ舞台だからな」
ミニバンの自動ドアの前に立っているルミがうれしそうに苦笑している。漁協長は、笑いながらルミにサムズアップした。ふと見ると、ミニバンの自動ドアにシンボルマークが描かれている。漁協長はマークを指さしながら、ミッコに話しかける。
「お。ミッコおばちゃん、さっそく使ってんだ。やっぱ洒落てんな」
ミッコ、うれしそうに答える。
「でしょ?でしょ?ばーちゃん達3人がモチーフだから、なんか洒落てて奥深いよねー」
ばーちゃん達が笑う。ミツがばーちゃん達を見て言う。
「ばーちゃん達の善行にあやかれるようにさ」
ばーちゃん達、照れる。ハツばーちゃんが照れくさそうに言う。
「これで、いつ死んでもいいよ。いつ死んでも、このマークとジムが残るからな」
ミツばーちゃんが真顔で漁協長を見る。
「イチロー、あんたも思い出せよ。ジムとさ、このマーク見たら、アタシ達のこと思い出せよ」
漁協長が苦笑する。
「なんだよ。シンミリしちゃうこと言うなよ。まだまだがんばれよ。ルミが引退するまで見届けろよ」
タツばーちゃんが真剣に言う。
「見てぇなー。引退までなぁ」
町長室で町長が満面の笑顔で立っている。向かいに、漁協長とルミとマリが立っていて、漁協長が話している。
「というわけで、南伊豆町の皆さんのお力添えのおかげで、町初の女子プロボクシング選手が2人生まれました。ありがとうございました」
漁協長が頭を下げた。町長が引き取る。
「おめでとうございます。我々も鼻が高いですよ。あれかな?」
と、傍らの職員に尋ねる。
「プロボクシング選手自体、町としては初めてかな?」
職員が答える。
「調べてみたんですが、そーゆーデータにはたどりつけませんでしたので、おそらく初めてではないか、と」
町長が笑いながら言う。
「じゃ、いいよ。町初のプロボクシング選手ってことでいこうよ。すごいな。初のプロボクシング選手が女性二人だ」
ルミとマリ、微笑。町長がマリを見ながら怖い顔で言う。
「しかも、そのうちの一人は、昔っからオレのイカを横取りばっかりしてるやつだ」
マリが不満げに言う。
「取ってないっすよー。マルオさんがくれたみたいに渡すからー」
町長が「ははは」と笑った。「あぁ、冗談だったのか」とみんな理解して一緒に笑った。ミッコが口を挟む。
「じゃ、静岡新聞さん、町の広報さん、いい?ルミとマリは認定証出して。はいはい。はい、町長は真ん中で」
町長、ちょっと困る。
「オレはいいよー。オレは脇役だから、ハジでいいよー」
ミッコがちょっとイラつく。
「んなわけにいかねーよー。マルオはじっこにしたら、あたしたちが悪く言われるべよー。はいはい。マルオ真ん中に入って、ルミとマリが左右に立って、、、」
漁協長は注意する。
「おばちゃん、ここで名前呼んじゃダメだ」
ミッコ、ちょっとビックリ。
「あっ、ほら、ほら、町長、町長、両手に花だよ。うれしいでしょ?静岡新聞さん、町の広報さん、これで一発撮って」
静岡新聞と町の広報のカメラが連写した。ミッコがばーちゃん達3人に言う。
「はい、次、ばーちゃん達も入って。町長、このばーちゃん達、ジムのスポンサーなの。このばーちゃん達がお金出してくれたから、ルミとマリはプロになれたの」
町長とルミとマリとミッコが笑顔で手招きした。ちょっと恥ずかしそうに、ばーちゃん達が並ぶ。漁協長も一緒に並んで、みんなで一緒に何十枚も写真を撮ってもらった。
静岡新聞
ルミとマリが町長を表敬訪問した写真が静岡新聞に載った。3面だ。ジムのイスに座ってそれを見ながら、ハツばーちゃんが文句を言う。
「なんで3面なんだよー」
横に座ってるミツばーちゃんが諭す。
「だってよー、「プロになった」ってだけじゃ弱いべー?「日本タイトル挑戦」とかじゃねーと」
その横に座ってるタツばーちゃんがヒザを打った。
「それだ!そーだ、そーだ、それいいな。日本タイトル行こう」
サンドバッグを打っているルミに大声で尋ねる。
「ルミー、日本タイトルって挑戦できんのかー?」
ルミ、「あ?」という顔を向けて、「ムリムリ」と手を振って、またサンドバッグを打ち始めた。
ばーちゃんたちの目の前を、折りたたみの長机を抱えた漁協長が通る。ハツばーちゃんが尋ねる。
「イチロー、日本タイトルってのはどうやって挑戦すんだ?」
忙しそうな漁協長、困る。
「えぇ?ちょっと忙しいから、コーチに聞いて」
ミツばーちゃんが言う。
「そいえば、今日コーチいねぇな」
漁協長が折りたたみの長机をかかえて外に出て行く。ジムの入口に折りたたみの長机が2つ並んでいる。持ってきた一つを足して3つになった。
「これでだいじょぶかな?」
事務員の女の子が答える。
「どうですかねー。あんなに並んでますからねー」
港の方を見ると、50人くらいの10代から70代くらいの女性が並んでいる。そこへ、トレーニングウェア姿のユー子が歩いてきた。谷間は出していない。
「なに?あれ?なんであんなに女ばっかり並んでんの?」
漁協長が困りながら、だけどうれしそうに答える。
「静岡新聞にさ、ルミとマリがプロになったの載せてもらったんだけど、一緒に無料体験募集したのよ。そしたら、集まった。集まった。50人以上いるべ?」
ユー子が目を見開いた。
「エー!!!50人以上???そんなに来てだいじょぶなのー?つか、南伊豆にそんなにたくさんボクシングやりたい女がいたの?」
漁協長がうれしそうに言う。
「オレもさっきビックリしたんだー。伊豆中から来てんだよー。ま、南伊豆以外の女はちょっとだけ月謝とるけど、いやー、ずいぶん来たなー」
そこへ、ジムの中からルミが出てくる。
「漁協長、コーチどこ?ばーちゃんたちが「日本タイトルにはどうやって挑戦すんだ」ってうるさいんだけど、、、」
漁協長が言う。
「そいえば、見ないな」
ユー子が言う。
「コーチ、休みだよ。東京で新刊の取材だって。インタビューなんだって」
終章
東京のとある大きな出版社の会議室。コーチがイスに座っている。向かいにインタビューアーの女性が座っている。インタビューアーは谷間を出している。コーチは谷間を一直線に、真摯に見ている。
「直木賞受賞後、満を持しての第一作は面白い題材ですね」
インタビューアーが本を手に取って見る。
「『手石漁港女子プロボクシングジムの物語』ですか。今回はどのようなテーマで?」
コーチ、谷間からインタビューアーの顔に目を移す。
「今回は「幸せ」について書きました」
「え?「幸せ」ですか?」
「はい。「幸せ」です」
答えてから、また谷間に目を移して、一直線に、真摯に見た。
手石漁港女子ボクシングジムの前では、数多くの老若の女性が用紙に書き込んでいる。漁協長と漁協の事務員とユー子がそれを受け取ってさばいている。
ふと見ると、ジムの入口の上に新しい看板がかかっている。ばーちゃん3人をモチーフにした洒落たシンボルマークが描かれていて、その下にこう大書してある。
「手石漁港女子プロボクシングジム」
3月なのに、手石漁港は暖かい。春が近づいた陽気な太陽の光が、看板を照らしていた。
