
都市のイメージを読む 1
本との出会い
僕がケヴィン・リンチの「都市のイメージ」を初めて読んだのは、駒場での前期教養課程が終わって大学生活最初の夏休みが始まった頃です。(高専から東大に編入すると2年生の前期教養からスタートします。)この頃始めたインターン先のCEO(建築学科OB)の方に薦めて頂き、豊島区立図書館で借りて読みました。
その後御茶ノ水の古本屋で古い版の「都市のイメージ」を見つけて購入し、本棚で眠らせていたものを都市工学科の授業がスタートしてしばらくした後に読み直しました。
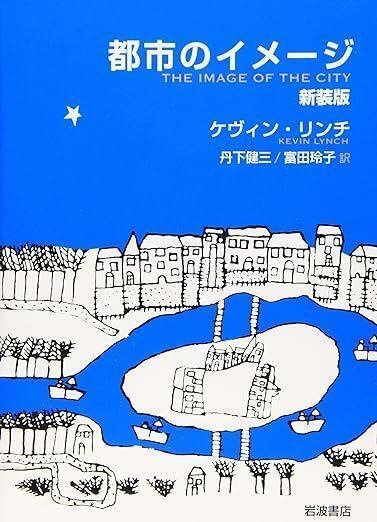
都市のイメージという本について
まず簡単に、著書と訳者のプロフィールをご紹介します。
著者 ケヴィン・リンチの簡単なプロフィール (Wiki)
「都市のイメージ」が刊行されたのは1960年で、ケヴィン・リンチがMITの教壇に立った1948年はノーバート・ウィーナーのサイバネティックスが出版された年でもあります。
訳者 丹下健三の簡単なプロフィール(Wiki)
丹下 健三(たんげ けんぞう、1913年(大正2年)9月4日 - 2005年(平成17年)3月22日)は、日本の建築家、都市計画家。一級建築士(登録番号第15182号)。位階勲等は従三位勲一等瑞宝章、文化勲章受章。フランス政府よりレジオンドヌール勲章受章。カトリック信徒。
日本では「世界のタンゲ」と言われたように、日本人建築家として最も早く日本国外でも活躍し、認知された一人。第二次世界大戦復興後から高度経済成長期にかけて、多くの国家プロジェクトを手がける。磯崎新、黒川紀章、槇文彦、谷口吉生などの世界的建築家を育成した。また、日本人並びにアジア人として初めてプリツカー賞を受賞した人物である。
この本を日本に紹介した訳者の丹下健三は、東大都市工学科の設立初期のメンバーで、東京都内を散歩していると丹下健三のかっこいい建築をよく見かけます。

国立代々木競技場

東京カテドラル聖マリア大聖堂
第一章の紹介
📔 第1章 環境のイメージ
わかりやすさ Legibility
イメージづくり Building the Image
ストラクチャーとアイデンティティ Structure and Identity
イメージアビリティ Imageability
それでは早速内容についてご紹介します。この本では、都市に住んでいる人たちが心の中に抱いている「イメージ」のパターンや構成要素について考えています。
まずはじめに、第1章ではアメリカの都市が美しく快適な環境になっていないこと、「環境」というものに対しての理解がほとんどされていないことに対する課題意識からはじまります。そこで、住んでいる人が「自分の暮らしている都市のイメージ」をイメージすることができるか、ということを課題として挙げ、具体的に都市環境の「わかりやすさ Legibility」というものについて考えていきます。また、「都市のイメージアビリティ」や都市のイメージを構成する5つの要素「道路(path)、目印(landmark)、縁(edge)、接合点、集中点(node)、地域(district)」、「ストラクチャーとアイデンティティ」といった重要な概念が紹介されます。2章以降では、1章で挙げられた考えに基づき、具体的にボストン、ジャージー・シティ、ロサンゼルスなどを例に考えていきます。
わかりやすさ Legibility と イメージづくり Building the Image
さて、「東京」と耳にしたらどのようなイメージを抱きますか? また、出身の市町村に対してはどのようなイメージをもっていますか?駅周辺のにぎわっている様子や、特産品をイメージする人が多いかもしれません。
ここで、個人によって描くイメージは異なることが想定されますが、都市を計画する際には住民間の協力が必須です。その前提として「多くの人が共通認識」できる都市のカタチを表現することが重要になります。
この本では、都市で生活している人へのアンケートをもとに、「みんなの頭の中にある都市のイメージ」を構造化し、「多くの人が共通認識できるその都市の形」を紹介しています。例えばノードは駅とし、公共交通によりつなぐことで都市の構造が見えてくると思います。みなさんの自宅周辺のイメージを描けそうでしょうか?

5つの要素

ボストンのイメージマップ
このように可視化された「都市のイメージ」に含まれるものと、市民たちに忘れ去られてしまうものの違いとはなんでしょうか、また、「イメージを構成しやすい都市」と「イメージを構成しにくい都市」の違いとはなんでしょうか。
ストラクチャーとアイデンティティ Structure and Identity
著者は、「都市のイメージ」を構成するのは
アイデンティティ【Identitiy】(個性、単一性、そのものであること)
ストラクチャー【Structure】(構造、つくり)
ミーニング【meaning】(意味づけ、例:あのビルは成功の象徴だと思う)
の3つであるとしています。また、この本では「その都市に住んでいる多くの人が共有できるイメージ」について考えているため、個人的な心象が反映されるミーニングに関しては置いておいて、アイデンティティとストラクチャーについて考えています。
イメージアビリティ Imageability
イメージアビリティとは、その都市の「イメージのされやすさ」のことです。
「イメージを構成しやすい都市」と「イメージを構成しにくい都市」の違いとは何か、という問いは、イメージのしやすさ、イメージアビリティとは何か、という問いになります。
ここで注意したいのは、「イメージしやすいように方眼用紙みたいな都市にすれば良い」という議論をしている訳では決して無い、ということです。
都市の(当然複雑な)環境によって、「みんなが共通して持てるアイデンティティがあること」、「みんなが共通して持てるストラクチャーが構成されること」が必要な訳です。
そのため、歩いていて思いがけない変化があったり、予想できない新しい発見があるにも関わらず、「共通したイメージに繋がる物理的な各要素(アイデンティティ)と構造(ストラクチャー)を見出すにはどうすれば良いのか」というのが論点になります。
このようにざっと第1章の内容を紹介してきましたが、次回は第1章についてもう少し踏み込んで考えるために、高専生らしく図を使って考えてみます。
興味を持った方が「都市のイメージ」を手にとって頂けると幸いです。
補足 ミーニングについて
都市に関する個人的な意味づけであるミーニングに関する説明が分かりにくかったので、印象的な都市に関するミーニングを引用します。
引用したのはグレート・ギャツビーでニックが都市の景色に心象を反映させているシーンですが、違う心象の人が同じ景色を見ていれば全く異なる意味付けをするはずです。
"The city seen from the Queensboro Bridge is always the city seen for the first time, in its first wild promise of all the mystery and the beauty in the world.”
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
