
ETSとカーボン・クレジット市場は違います
このところ「カーボン・クレジット」という名称の知名度が上がり、「なんとなく知っている」という方が多くなってきたように感じています。
また、JPXがカーボン・クレジット市場を開設したために、株式と同じようにマーケットを通じて売買できるということを知った方もいるでしょう。
ですが、市場を通じて(もちろん、相対でもできますが)売買できる「カーボン・クレジット」全てが、EU-ETSを始めとする、ETS(Emission Trading Scheme)でも使用できると思っている人もまた、多いと思います。
ですが、ETSで使用する(取引する)のは、一義的には、システムオーナーが、参加者に対して割り当てた「Cap」相当の「排出許可証(Allowance)」になります。日本語では「排出枠」と呼ばれることが多いのですが「権利」です。
この「Allowance」は、無償で割り当てられることもあれば、有償(オークション)の場合もあります。
ここで「Cap」の説明をしておきたいと思います。
ETSを少しでも学んだことがあれば、「Cap & Trade」という言葉を聞いたことがあるでしょう。参加者は排出できる排出量が決められており「Cap」、オーバーしそうな場合は取引で達成したことにできる「Trade」というスキームです。
この「Cap」は、先ほど説明したように、システムオーナー(一般的には、政府や州など各法域の規制当局)が決定する量で、極めて政策的です。
EU-ETSを例に説明します。
EUは、「Fit for 55」という政策に整合させるために、EU-ETSの削減目標を2030年までに2005年比62%減と定め、それを全体の「Cap」とし、参加企業に対して割り当てています。
この割り当てが「排出許可証」であり「EUA(EU allowance)」です。現在、無償及び有償で割り当てられています。最終的には全量オークション(有償)を視野に入れていることでしょう。
ですので、「Cap」が決まっているので、EUAを取引したとしても、総量(Cap)は変わらないのです。そして、EUは「政策的」に「Cap」を減少させていきます。つまり、確実にGHG排出量の削減につながるのです。
これが、ETSの本質です。
だからこそ、ETSが「Mandatory(義務的)」であるべきなのです。
しかし、「Cap」があまりに硬直的だと、ビジネスを阻害する可能性もあります。その場合の緩和措置、救済として、特定の「カーボン・クレジット」や異なるETSの「Allowance」の使用を認める場合もあります。
EU-ETSで使用できるユニットについては、こちらのサイトを参照ください。
それでは、「カーボン・クレジット」とは何でしょうか?
ETSの基礎が「Cap & Trade」であるのと同じ文脈で、カーボン・クレジットは「Baseline & Credit」を基礎としています。
既存技術(Business as usual:BAU)の排出量から、新規プロジェクトを実施した場合の排出量を差し引いた差分が「カーボン・クレジット」です。
「カーボン・クレジット」取引では総排出量が減少することはありません。
プロジェクト現場では減少しますが、購入した現場では増加するからです。

先ほど、ETSにおいて特定の「カーボン・クレジット」や異なるETSの「Allowance」の使用を認める場合が多いと説明しました。
すると、どうなるでしょうか。「Cap」を超過してしまいますよね。
政策により確実に削減できるというETSの利点をスポイルするのです。
このように、ETSという政策は非常に複雑な方程式を解くようなもの。
だからこそ、EU-ETSは2005年の開始し以来、様々な難局に遭遇しました。
それを乗り越えて、信頼されるスキームに成長した今、炭素国境調整措置(CBAM)へと、次のフェーズへと歩みを進めたのだと思います。
で、「カーボン・クレジット市場」です。
これは、文字通り「市場」「マーケット」です。
売買される商品が、株であれば株式市場、商品先物であれば商品先物市場。
リアルもあればウェブベースもある。それでも、本質は変わりません。
ここで、「EUA」が取引できる市場も存在し、価格形成に寄与しています。
ですが、その市場自体が「ETS」ではありません。
「ETS」はスキーム、仕組みです。
日経が、当初「排出枠取引」と表現し、次第に「排出量取引」という名称へ変わっていったと記憶しています。「カーボン・クレジット」であれば「排出量」、「Allowance」であれば「排出権」という表現が良いカモですね。
ちなみに、以前のnoteで、インドネシアETSに苦言を呈しました。
今回の記事がお分かり頂けたのであれば、「ナルホド〜」と思ってもらえるはず。ポイントを外した制度設計を志向しているように感じました。
ということで、些細だけど重要なことを突っ込んで説明するシリーズ。
いかがだったでしょうか。
気になってるけどよく分からない、分かっているようで分かってない。
そんな疑問質問、お待ちしています。
ズバッと回答、出来るように頑張ります。
ご期待下さい。
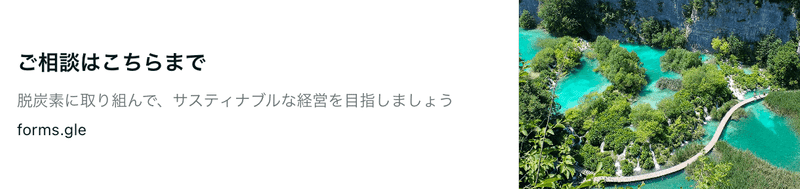
もしよろしければ、是非ともサポートをお願いします! 頂いたサポートは、継続的に皆さんに情報をお届けする活動費に使わせて頂きます。
