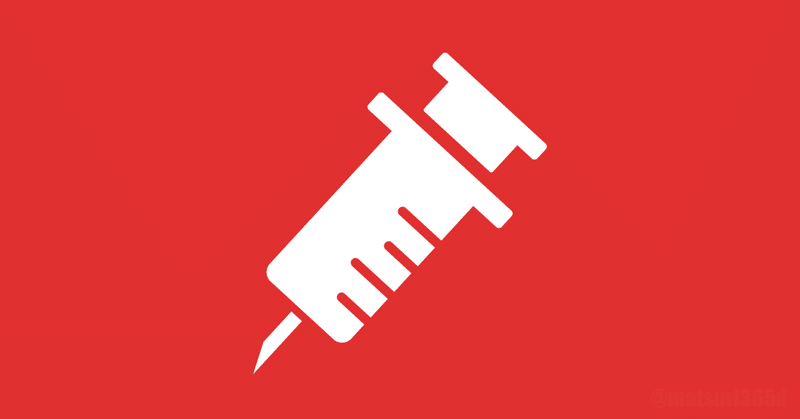
はじめての献血(24歳・男性)
はじめに
はじめまして。コドンと申します。
Twitterでは譫言じみたツイートばかり垂れ流していますが、少しは真面目な文章を残していきたいと思い立ち、noteを始めることにしました。
特に定期更新などは予定していないので、この記事だけで終わるかもしれませんし、続くとしても内容が様々なジャンルに渡ると思います。よろしくお願いします。
献血とは
先日、人生で初めて献血に行ったので、それについて書きたいと思う。
以下、常体で書かせていただく。この章は前置きなので、読み飛ばしてもらって構わない。
"献血"という単語を聞いたことはあるだろうか?
多くの人は「ある」と答えると思う。
献血とは「医療に使用する血液を一般市民から募ること」である。
中学校の理科などで習ったかもしれないが、血液は均一な水溶液ではない。
赤血球、白血球、血小板といった細胞が血漿中を漂っている。
そしてそれゆえに、完全な血液を人工的・工業的に生産する方法は現時点で存在しない。iPS細胞などの最新技術を応用して世界中の研究者が奮闘しているが、実用化には程遠いのが現状だ。
そして医療において血液は大量に必要とされる。
2022年7月8日の安倍晋三元首相銃撃事件でも輸血が話題になったことは記憶に新しい。ひとたび動脈を損傷するような大怪我を負えば、当然大量出血する。
体重の約7.7%が全血液の重量とされている。また、全血液の40%が短時間で失われると失血死の可能性がある。
体内を流れる血液量は、体重1kgあたり約80mL(体重あたり7.7%)です。体重50kgの人の血液量は約4Lになります。
さまざまな原因で血管が破れ、血管内を流れている血液が血管外に漏れ出て出血します。全血液量の約30%(体重50kgの人で1200mL)以上が短時間で失われると血圧低下となり、さらに40%(1600mL)以上の出血で意識がなくなり生命の危険があるといわれます。
原因が何であれ、全体重のたった3%分の血液を失うだけで人間は生命の危機に陥ってしまう。この時にまさに命綱となるのが輸血であり、その元をたどれば献血である。
それだけではない。献血で集められた血液のうち、輸血に使われるのは半分程度だ。では残りの半分はというと、"血漿分画製剤"という医薬品として、特定の感染症の予防などに用いられる(念のため、mRNAワクチンとは無関係であることを記述しておく)。
血漿に含まれるアルブミン、免疫グロブリン、血液凝固因子等のタンパク質を分離し取り出したものが血漿分画製剤である。アルブミン製剤はやけどやショック等の際に、免疫グロブリンは重症感染症や、ある種の感染症の予防治療のためや免疫機能が低下した場合等に、凝固因子は血友病患者の治療等のために用いられる。
)
このように、医療において血液は欠かせない存在である。にもかかわらず、前述したとおり、血液は人工的に生産できない。さらに、血液は長期保存もできない。
血液には生きている細胞が入っているので長期保存ができません。「赤血球」は採血後21日間、「血小板」は採血後4日間、「血漿」は凍らせて採血後1年間です。そのため、絶えず多くの方の献血協力が欠かせないのです。
したがって、常に新鮮な血液を供給できる体制を築いて医療を下支えするのが献血であり、だからこそより多くの市民が日常的に献血に協力することが重要であると言えよう。
思想・信条の自由はあれど、献血のボイコットや妨害などを働きかけたり実行したりするのは、輸血や血漿分画製剤を必要としている誰かの基本的人権(生存権)を蹂躙しているに等しいと個人的に感じる。
近年、喜ばしいことに献血量は増えている。特に血漿成分献血が目覚ましく、平成29年から令和3年のたった4年のうちに2倍以上の伸びを示している(日本赤十字社, https://www.jrc.or.jp/donation/blood/graph/ )。他は横ばいだが、日本赤十字社も血漿成分献血を推奨しているらしく(献血時に「400 mL献血か血漿成分献血がありがたい」と言われた)、まだまだ増えて良いのかもしれない。
一方で、40代以下の献血者数が横ばい~減少傾向にあるというのはあまり好ましくない。献血者は多いに越したことはないし、若年層なら尚更だ。少子高齢化が続く今だからこそ、長期的に献血に協力する若者は増えたほうがいい。
とはいえ献血に行ったことのない人も多いだろう。私は24年の人生の中で今回が初めてだった。
事前に赤十字社のホームページを読み漁ったのだが、たしかに記述はかなり丁寧ではあるものの、それでも献血の経験がない人が献血ルームに足を運ぶには些か足りない部分もあるように思われた。
この記事はそれを補足するような形になればいいと考えている。
実際に行ってみた(初回献血の手順)
それでは本題に入ろう。初回の献血の手順を、当時の時系列に沿って記述していこうと思う。ただの一例であり、献血ルームやタイミングによって相違点もある、また献血バスでの献血とも異なるという点にはご留意いただきたい。
私は先日、最寄りの献血ルームで献血をした。理由は「何となく」である。
⓪ 予約は不要
私は予約を入れずに突然献血ルームを訪れた。
実は、献血は事前に予約しなくてもよい。
日本赤十字社は予約を推奨しているが、別に予約なしでも混雑していない限り(そして時間外でない限り)、門前払いされることはないだろう。
献血をされる方が一時期に集中することを避けるため、是非、最寄りの血液センターまたは献血ルームまで、献血のご予約をお願いいたします。
)
どうしてこのような(一見すると日本赤十字社にとって不都合な)ことを述べるかというと、一部の若年者にとっては初回献血の予約を入れるハードルが高いからである。
ここで、献血の予約方法を確認しよう。
① WEB予約
② 電話予約
以上、2つの方法がある。
このうち、①はラブラッド(献血Web会員サービス, https://www.kenketsu.jp/Login )への登録が必要となる。そして献血カードに書かれた献血者コードがなければ登録できない。その献血者コードと献血カードは初回献血が完了した時に初めて発行される。
つまり、①のWEB予約は「一見さんお断り」であり、初回の献血では利用できない。
それでは②はどうかというと、若年層にとって、不慣れな電話を敢行しなければならない。しかも相手は献血というよく分からないフィールドの主だ。何を聞いてくるのか、何を答えればいいのか事前に分かるはずもない。相手の表情も読めない。電波状況によっては、聞きなれない単語を何度も聞き返したり聞き返されたりするかもしれない。文字に書き起こしてもらうこともできない。人生経験に乏しく、また電話という行為をほとんどしてこなかった私程度の人間ならこう考えるだろう。
「電話は、やめておこう」
もちろん、臆せず電話で予約ができるならそれが良い。だが、電話予約に怖気づいてそのまま献血にも行かない、というのが最悪なパターンだ。そんな状態になるくらいなら、予約せずに献血ルームに押しかけたほうがよっぽどいい。現在、献血は常に不足している(日本赤十字社関東甲信越ブロック血液センター, https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/bbc/index.html )。
以上が、初回は予約なしで献血ルームに立ち寄るのが良いと考える理由である。2回目以降は是非ともラブラッド( https://www.kenketsu.jp/Login )に登録し、そこからWEB予約しよう。
もちろん、予約なしで行くと混雑時には断られることもあるだろう。土日は献血に訪れる人も多くなる。比較的空いているであろう、お昼時を狙うのがよいかもしれない。
(あくまで個人の見解です。大勢で行く場合や電話予約できるコミュニケーション能力を持っている方はぜひ予約をお願いします。)
① 事前準備(持ち物・服装)
順番は前後するが、ここで献血ルームを訪れる前の準備について確認しておきたい。
初めての場合、事前に以下の11項目を準備・確認しておくとよい。
身分証明書(氏名・生年月日・顔写真の付いているもの)
身長と体重
服用中の医薬品の処方箋
過去に輸血を受けたか否か
最大直近1年のワクチン接種歴
直近半年の性的接触歴
感染症の感染・濃厚接触歴
海外への渡航・滞在歴(母と祖母も含む)
最後に食事を摂った時刻(献血日は朝食と昼食と水分をしっかり摂取)
昨夜の睡眠時間(献血前夜は充分な睡眠を)
入浴(3日前から毎日風呂に入れ)
身分証明書は絶対に必要だ。これがなければ献血ができないこともある。
健康保険証には顔写真がついていないので、運転免許証やマイナンバーカードがあると良い。2.以下は受付後の質問で訊かれるので、確認しておこう。
以上は必須だが、さらに追加で時間を潰せるものがあるとよい。
少なくとも合計で1時間程度の暇な時間ができてしまう。
献血ルーム内に漫画が設置されているが、新型コロナウイルスのこともあって抵抗を感じる人も多いだろう。
そんな時に役立つのが持参した暇潰しアイテムである。
具体的には本やタブレット端末、必要なら尻に敷くクッションなど。一部の座席にはコンセントも設置されている。
なお、以下のものは避けたほうが良いと思われる。
ノイズキャンセリングイヤホン(遮音性の高いイヤホンを含む)
すぐに手を離せない暇潰し(オンライン対戦ゲームなど)
腕に大きな負荷がかかるもの(筋トレ道具など)
その他、周囲に迷惑がかかるもの
周囲の物音を聞き取れなくなる1.は、スタッフの呼び出しに気づけなくなる恐れがある。
呼ばれたらすぐに移動しなければならないので、2.も良くない。
献血後2時間は、腕に負荷がかかると内出血に繋がる可能性が高く、3.はもってのほかである。
腕への負荷を考えると、荷物が多すぎても良くない。ロッカーは備え付けられているが、片腕で軽く持てるような分量にとどめよう。
軽く、かつA4クリアファイルが入るカバンがベスト。
服装については、腕を露出させやすい薄手の服と爪先と踵が尖っていない歩きやすい靴が良いだろう。寒い時期には重ね着を活用したい。
② 受付
献血ルームの入口で手指消毒を済ませ、「受付」と書かれた窓口へ向かう。
受付の人に献血カードの提示を求められるはずだ。「献血初めてです」と言うと献血の種類などの簡単に説明してくれる(分かりやすい資料つき)。
説明後に献血の種類を選ぶことになったが、私は勧められるままに400 mL献血を選択した。400 mL献血は成分献血と比べて所要時間が短く、身体への負担も小さく済むので初心者向けということらしい。
なお、その半量の200 mL献血は使用時の都合がそんなに良くないらしく、「できるかぎり400 mLの献血を」と言われた。
その後、血圧測定を挟んだのち、初めての献血者向けの説明と問診・同意取得を改めて丁寧に行った。担当者の方と待合スペースまで移動し、1:1で書類を挟んで説明を聞いたり書類に記入したりする。
同意書などは非常に簡潔にまとめられているが、真面目に話を聞いて自分の判断で記入していこう。
書類を書き終わったら数分間待たされる。私は飲み物(全て無料)を飲みながら呼び出されるのを待った。
③ 登録/質問への回答
呼び出されると今度は先ほど書いた同意書の最終確認と本人確認をする。ここで身分証明書が必要になるので、持参したものを提出しよう。
これにより献血者としてデータが登録され、全国の献血センターに同期される。
そして同時に献血者であることを示す首から提げるタイプのカードを渡され、数字が書かれた紙の帯を腕に巻いてくれる。今回の献血が終了するまで、氏名とこの番号で管理されることになる。どちらも絶対に取らないように。
さらに続けて献血前の質問に答える。ここで先述の服用中の医薬品などの情報が必要になる。タブレット端末で答えていくのだが、問題文をよく読もう。適当に「はい」だけ、「いいえ」だけを選んでいては真逆の回答をしてしまう。
私は3問ほど進んでやっと違和感を覚え、最初からやり直した。
この手順が終わるとクリアファイルに挟んだ様々な書類を渡され、すぐに医師が待つ部屋まで案内された。
④ 医師の問診
書類をそのまま医師に渡し、問診を受けた。問診自体はそんなに多くない。
問診の後は血液検査になった。
⑤ 血液検査
献血用のベッドが並ぶ献血スペースの一角にある、カウンターのようなところまで案内された。ここでは献血用の針を刺す腕を決め、そしてその逆側の手の指先から少量の血液を採り、献血可能か(赤血球が充分か)を検査された。
献血の腕は、肘裏の血管が見えやすいほうが選ばれる。利き手は一切関係なく、私は右腕を選ばれた。もちろん私の利き手は右である(つまり、数時間は利き手に労働をさせられない状態になった)。
血液検査はすぐに終わる。採血に1分、赤血球(またはヘモグロビン)濃度の測定に30秒、血液型簡易検査に1分程度。研究系の仕事に就いていることもあって、検査は見ていて面白かった。
⑥ 献血……の前に
検査も問題なく、いざ献血……の前に、こう言われた。
「一旦、待合室に戻って最低でも飲み物を2杯飲んでからあの椅子(献血スタンバイ用のベンチ)に座ってください」
事前の水分摂取は非常に大事なようだ。温かい飲み物のほうが血液が出やすくなる、と自販機の近くに掲示されていたので、温かいアクエリアスと温かい綾鷹をいただいた。この世界には温かいアクエリアスを紙コップで提供する自動販売機(全種無料)が存在するのである。
⑦ 献血
ベンチに座るとすぐに献血用のベッドまで案内された。ベッドの足元には小さなカゴがあり、手荷物はそこに置ける。万が一の災害などに対応するために、ベッドには靴を履いたまま横たわるようになっていた。ベッドには大きなテーブルが備え付けられているので、靴の爪先が尖っていると少々邪魔になる。
いざベッドに横になったらいざ献血なのだが、針を刺すときの消毒液には基本的にヨードを使用するらしい。私は問題なかったが、そこそこの割合でかぶれる人もいるとのこと。肌に異常を感じたらすぐに申し出よう。
針をさして血を抜いている間は暇である。読んでおいてください、と渡されたA4で裏表5枚程度の資料に4回ほど目を通した後は、そこに書かれていた血液の巡りをよくする足の運動をしながら、目の前に小型モニターに流れている野球中継を無心で見ていた。スピーカーは耳元、ベッドの頭部に埋め込まれている。もしかしたらチャンネルを変えられたのかもしれないが、私は電話すらできないコミュ障である。具合が悪くなった、等の緊急事態でもないのにやり方など聞けるはずもない。
献血中は意識が遠のいたり腕に痺れを感じたりなどの危険な異変はなかったが、飲み物を飲んだばかりで喉も潤っているのに、その一方で喉の渇きを感じるという不思議な感覚に襲われた。飲み物をあと1杯くらい飲んでおけばよかったのかもしれない(献血中にトイレに行きたくならないか心配で躊躇した)。
血を抜き終わると針を抜いて止血とテーピングをしてくれた。そしてふらつき等がないか確かめつつ、細かく指導されながらゆっくりとベッドから降りて待合室へ。好きな飲み物を1杯持ってきてくれた。至れり尽くせりである。
⑧ 事後手続きと待機
そのまま待合室の席に座って待っているように言われ、しばらく待っているとクリアファイルに挟んだ資料と献血カードを渡された。資料には、気分が悪くなったときの対処法や、感染症に罹患していたことが後になって分かった場合の対応などが掲載されていた。
また、私が献血を行った時は大人気アニメ『ガールズアンドパンツァー』とのコラボキャンペーンが開催されていたので、そのキャンペーン品として献血カードケースを貰った。


個人情報が透けていたので一部加工。
キャンペーン品は他にステッカーやケースの柄違いが用意されており、なんと選ぶことができる。ブラインドガチャ商法ではないことにささやかながら感激すら覚えてしまった。現代の悲しいオタクである。
あとは30分ほど休んでから帰るように言われていたので、置き菓子をつまんだり飲み物を飲んだりしながらのんびりと過ごした。帰り際に首から提げていたカード(献血カードではない)を返却し、気を付けて家路に着いた。
私はハイヒールやパンプスを履いたことがないが、もし献血後に立ち眩みに襲われたときは踵が高い靴だと転倒に繋がるリスクが高いように思われる。
⑨ その後
帰宅してすぐに作り置きしていたほうじ茶をがぶがぶと飲んだ。ちょっと歩いただけなのに、身体が多くの水分を求めていた。
渇きも落ち着いたところで、ラブラッドに登録し、次回の献血を予約した。
やはりWEB予約こそ正義であると実感した。
余談ながら、ラブラッドでは献血ポイントというものがカウントされる。献血の累計回数で貰える昔ながらの記念品とは別に、このポイントで様々なグッズが貰えるらしい。
数日後、血液検査の結果がラブラッドに反映されたが、血液型だけ1, 2日遅れた。検査項目は、最高血圧、最低血圧、脈拍、ALT、γ-GTP、総蛋白、アルブミン、アルブミン対グロブリン比、コレステロール、グリコアルブミン、赤血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値、平均赤血球容積、平均赤血球ヘモグロビン量、平均赤血球ヘモグロビン濃度、白血球数、血小板数、血液型の19項目。他にも、一部の感染症が検出された場合は通知されるらしい(エイズは通知されない)。

以上が初めての献血の顛末である。終わってみれば大したことはなかったが、献血後の強い渇きには少々面食らってしまった。
まとめ
長く書いてきたが、最後に初回献血の注意点を箇条書きの形でまとめたい。
初回の献血は、予約なしでもだいたい問題ない。
前日と当日は睡眠と食事と給水と入浴をしっかりと。
服用中の医薬品・予防接種歴・性的接触歴・海外渡航滞在歴の確認を。
荷物は軽め(A4サイズ)、靴は歩きやすく、服は腕を出しやすく。
顔写真付きの身分証明書が必要。
受付で「初めてです」と言う。
質問や問診の答えは正直かつ正確に。
異変があったらすぐに伝える。
スタッフの指示に従う。
かかる時間はだいたい2時間(うち1時間が暇)。
終わったらラブラッドに登録推奨
私が書き連ねてきた内容の多くは、日本赤十字社のHPに掲載されている。こちらを参照したほうが分かりやすい部分も多いだろう。
また、過去に輸血を受けていたり特定の医薬品を服用していたりして献血ができない人や、単に針を刺すのが苦手な人は寄付という選択肢もある。
最後、ここまで駄文を読んでくださった皆様に感謝の意を表したい。
何らかの形で献血に寄与する人が増えることを願っている。この記事が、1回目の献血の心理的なハードルを少しでも低くできたら何よりだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
