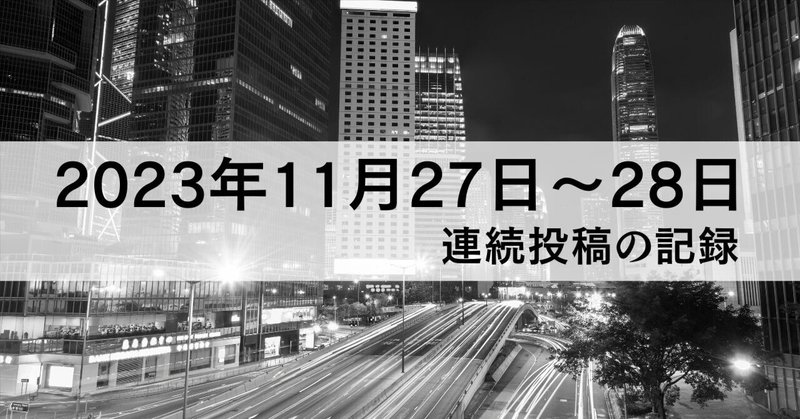
記憶と話す
ものすごく記憶力がよくて、ぼくは損ばかりしている。
実は、もう文字でしか確認出来ない「現場」にありありといあわせた記憶が、ぼくにははっきりある。
ところが、おそらく当人たちにはまったくその記憶がない。
ぼくの記憶を裏付けてくれる人がまったく、いない。
あなた、人より記憶力がいい、とか。
他のひとと比べられる程度のレベルの話をしていない。
すいません。
ぼく、たぶん、はっきりいいますけど、ある意味ではものすごい恵まれた能力があります。
これは反則だよね。
ていうくらい…。
人から
「君よく覚えてるね」
って言われるけど、違うんです。すいません。
よく「西巻さんって歌をすぐ暗誦できるんだね」
って言われるんですけど、
「ふつうの人と比べてこれができる」
というレベルの話をしてない。
「ぼく「ふつう」じゃない」人なんだけど…。
活字はさすがに、誤記があって、一字一句そのとおりは覚えてないんだけど、人から聞いたこととか、耳にしたこととか、自分でその短歌を読んで湧き上がってきたイメージを、「忘れない人」っているじゃん。
たまにいるんですよ。些細なことをしっかり覚えてる人。
「ギフテッド」みたいな言い方するのかな。
マンガキャラみたいな反則レベルの能力で、「そんなことをよくおぼえてるね」ってみんな言うけど、「覚えてる」ってことを言ったら、震え上がるとおもう。
ぼくが「あ、それおぼえてるわ」っていうのを、どこまで言っていいのかわからない。なぜなら、当人が覚えてないから。
ぼくがそのことを話すと、反則になると思うから、でも、あなた、ぼくが覚えてたことって、活字にはなってないかもしれない歌葉新人賞以降の「短歌の生の記憶」ですよ。
言い方変えます。アーカイブなんです。
そんなエピソードにはこと欠かなくて、今ベテランになったあの人たちと「思い出話」をしたくても、たぶん覚えてないか、語ろうとしない。あと、俺が記憶にどうしても残したいひとでも、自らの意志で歌の活動をしてなくて、「覚えてる?」って直接話して確認できないひとが二人。
一人は彗星集ではないけど、歌集がでました。今現代短歌クラシックスにいます。五島さん。
もう一人は、歌集がないので、だれも、名前で呼べない…。
絶対確認できないひとがひとり。それは今なにか、「賞」の名前になってるんだけど、それ、ぼくが唯一といっていいくらい話のわかった友人なんです。でも彼はいなくなってしまって、彼とぼくとのエピソードに関してはだれも確認できない。
実は電話でよく話してたし、福岡の批評会にも行った。
笹井宏之さんという人です。
実はこのことって、言っていいか悪いか、「自分にも記憶がないふり」をしてるんだけど…。
すべては、アーカイブのなかに。
言えることがあったら、順次、話していきます。
短歌にまつわることで、事実が確認できそうなことだけを話す。題して「記憶と話す」シリーズ。
本人の名誉と、文学的価値、どっちが大事なのかという話は読み手に判断してもらう。
・「彗星集」という場にいた
今もある。彗星集という欄あります。未来短歌会に。
ところがもう全く違うのよ。ぼくは「あのころの彗星集」にはいたけど、 今の彗星集にはいません。
当たり前っすよね。
「意味がわからない」
という人いると思う。あなた今Operaでしょ。みたいな。そういう話じゃないな…。
2006年入会から、うつになったりして、だんだん社会からドロップアウトしながらも、歌というか、文学は続けてて…。現場で、ぼくは休まず、歌を出してました。
それは記録にあると思います。ほぼ欠詠してなかった。いまは欠詠期間のほうが長くて、歌が出せないけど、もういまから今残ってる同名の欄とかに歌を出す気力がない。
もう違う場なので。
いまは、はっきりいって残滓ですね。
選者に問題があるとか以前の話で、顔ぶれがクズなので、堂々とあの人たちと一緒に「加藤治郎に師事」。
なんてとてもと言えない。
はっきりいいます。いま残ってて堂々と加藤治郎に師事。ってTwitterで名乗ってる馬鹿はほんとすぐ撤回してほしい…。いま加藤治郎の弟子を名乗れる能力と資格がある人って、唯一、ぼく「だけ」なんです、もう。「文学的」に。
資格はみんなあるよ。加藤さんのところにいれば。
しかし、能力が絶望的に不足してます。
それをさ、「加藤治郎に師事する」ってどういうことなのかを、意味も分からずアクセサリーみたいにプロフィールに書いてるやつ、全員やめて。
もうだめ。
おとむらいをしよう。
たましいのやどらなかったことばにもきちんとおとむらいをだしてやる/笹井宏之
・「あの頃」の彗星集
中島さん、朽木さん、そして治郎さん。あとは知らんけど、セクハラ問題とかで喧嘩してる場合じゃないよ、っていうことを、あなたたち。
ちょっと、一瞬、ここに、読みに来てください。
みんなに俺が、これから未来短歌会「彗星集」代表として追悼文を書くので、ちょっと誰かリツイートするなりして宣伝して、見つけたやつ、みんなここによみにこさせて。
さすがに、元同門だったら俺の言ってる意味はわかる。
中島さんはよくわかる。
加藤さんはこの問題で誰が傷ついてるかをそもそも理解してないよね。
じゃあ、はじめますよ。
ぼくの選択
ぼくの選択はもうどっちかしかないっす。
1.欄を去る。
2.最後までいる。
たぶん俺はいきなりだけど、セクハラ問題とかめっちゃ「実社会的な倫理」の話はまったくしないっす。
いろいろ中島さんともやりとりはしてる。でも、俺はそのことは公開の場では書かない。
それは、いくら中島さんが追求しても加藤さんは謝罪も訂正も認知もしないと思う。
それを言う意味はまったくない。
俺が話すのは思い出話だけ。
ぼく、たぶんいろんなものの死を、見送る立場で歌う歌人です。
そして、そのいろんなものの死のただなかに、いままさに居合わせています。
「選歌欄の死」を見送るのははじめてだけど。
いまからもうここに入るひともいないし、そもそも論なんですけど「文学的価値」を生み出せなくなった結社の選歌欄(「場」とか、「グループ」です。ひらたくいうと)なんてもう戻りたくないというぼくの立場もわかると思う。
当時の未来短歌会の加藤治郎選歌欄「彗星集」が、どんな場だったかというのを、当時他結社で覚えてくれてて、面とむかって言ってくれた人って、唯一じぶんで直接確認したのは、だやさんだけです。
ごめんだやさん。何も言い返せない。
でも一つだけ言わせて下さい。そのグループが「変わり果てた姿」で存続していることを、一番恥じてるのって、「失望してます」って言うだやさんじゃなくて、言われた「俺」。
当事者だって。
だやさんにすごく失望されてるな、という「恥」とともに、いま、自分の記憶のなかにあった「彗星集」を語ります。
さすがにこれは「文学」の問題なので、個人的に心のなかにこらえて死を見送るたぐいのものではないね。
黙って見送るわけにいかない。
俺はいま会費を払わず、歌も出してないという事実はあるけど、語る資格はあるよね。「いた」んだからその場に。「文学的に死んだ」という意味を頭から教えてあげる。
場の死、とか、グループの死って想像がつかない?
バンドにたとえればいいとおもうけど、「グループの消滅」の場合、多くが自然消滅なんだけど、ただ、まさかあの「彗星集」がこんな状態、っていうのは誰も当時は想像しなかったと思います。
文学的価値って、ほんと、なんにも誰も持ってないものです。もともとは。
それは、「自分の内部」で持ってて、活動を続ける原動力なんだよ。
「本人の自覚」だけがそれを支えてます。「自分のやってることが価値がある」といえる自覚だけが、それを支える。
それを支えるのって、メンタリティも必要だけど、それにあった「プライオリティ」【付加価値】を、最低限選者が与え続けること、というか、後進の「名誉とかプライド」を守る役割が選者にはあるでしょと思うけど、それがないから、みんな去っていくんです。
加藤さんは、育成者としてだめ。
ということを、言えるやつが、いない。
だから、みんなめちゃくちゃ、加藤さんが作り上げた「場」に裏切られたひとたちが、なんかすごい加藤さんに過剰に怨念をだくんだよ。
で、それを別の文脈でいうから、加藤さんは、「文学的な問題」じゃない。とか言うの。
師弟制度の意味をまったくわからない奴らと、無能なやつが渦巻いて今の批評のダメさを作ってて。彗星集は終わるわけ。
おれはもうそのあまりのダメさに絶望してて、もうコレを語るしか、ない。
プライドっていうの。文学的価値を見出す努力って、
そういう問題じゃなくて、
「誇り」と「恥」の概念に似てる。
大辻さんにだけ話したの、覚えてるかな。
西巻家って、実は昔南朝にいた武士の家系らしくて。
なんかDNAの中に「武士道」がある。
命がけで文学の問題をやるということは、もう三島の自殺に近いくらいの意識があって、その意識をもって、文学の問題を語る人間ってもういないな。
俺が、すごい力をなくしたように見えてて、なんかかぼそい、よわい、障害をもった人間だ、とみんな思ってるから、同世代の人間は黙って投げ銭のマネ、みたいなことをしたのかもしれない。
俺の記憶のなかでは、大辻さんと加藤さんとか、斉藤斎藤さんとか、あのへんのメンバーが、みんなどんな発言をしたかを覚えちゃってて。俺はその自分の価値をわかって、仕事をしてたから、誰も俺を恐れてないけど。
狂犬と言われた俺のことを説明できる。
もう俺言う。
決めた。
俺は誇りにかけて、加藤治郎の弟子だから。
そして恥の意識とか、記憶とともに。
とても恥ずかしくて。彗星集にいられません。
代表で追悼文を読み上げます。
※
まず、当時の彗星集のシステムとメンバーをお話しますね。
論より証拠。これ。
その、歴史っていうか…。アーカイブの話。ちょっと懐かしい記事だすよ。
https://www.banraisha.co.jp/humi/eda/eda124.html
江田さんの文章です。中島さんと俺は書いてあるからいいけど、他に書いてない人間として、野口あや子さんもいたよね。そして名前を出せない人もいる。「うたびとの日々」にならってTさんとしておきます。
ごめん山崎聡子さん、あなたはこのときはいなかったので、名前があげられません。
あのころ。この文章を、まず読んでくれ。
長谷川眞理子さんという人がいたんです。彗星集に。
もうぶっとんでて。。。
江田さんが発掘してるんだけど、この一首を見ただけで、彗星集の「価値」がわからないやつ、みんなきっぱり断交する。2007年4月号だって。
鳥の正面衝突(音楽のやうに帽子を変へる)、鳥の側面衝突(もつともあたらしい記憶)/長谷川眞理子
〈80801742479451287588645990496171
>>0757005754368000000000〉いかな頰摺りせしや蝶
これ確か長谷川さんが初登場で、「うわ。やべ…。」というのを、初めて感じた歌群だったよ。
このやばさを江田さんはこんな書き方してて、「反応したひとがいない」みたいな書き方してるけど、「みんなやばいこれ」っていうのを、言わないだけなの。多分中島さんは覚えてる。
「未来」に掲載された長谷川の歌に注目した歌人がいったい何人いたのか詳しいことは分からない。しかし、選者の加藤治郎以外に長谷川を特に注視していた痕跡はない
引用の手順踏むのめんどくさいから、江田さんごめんね。
俺中島さんと話があった記憶って、元かばんの編集長だった「鈴木二文字」さんという方の話題。
実際にお目にかかったのは、かばんと彗星集で合同歌会っていうのがあって、鈴木二文字さんの批評を直にきいて、いや、「この人がちでやばい」
と思った記憶があります。でも、それはもう誰も「経験」出来ないからいいんだよ。で、その話を中島さんと共有しようとしたら、覚えてるかな…。
その「鈴木二文字」さんの作品「たんかっち」に似てるけど、長谷川さんの作品はそれよりも全然「視覚的」かつ「音楽的」で、めちゃくちゃぶっとんでて、これには脱帽だよね。
。俺はその当時まだmixiですらないブログやってて、そんとき、まだ細見晴一さんの「シロナガスクジラの夢」っていうブログがあって、細見さんと、お互いにその「やばさ」を語り合ってた記憶があります。
細見さんはいまほとんど見かけないけど、その当時の「前衛」の紹介者として俺にはすごいキーパーソンでした。
俺がyoutubeで、
rammsteinというバンドのアメリカという曲のすごさ、批評性の高さをメチャクチャ紹介したら、一瞬で細見さん意味がわかって、そのかわりに安川奈緒さんを紹介してくれました。
「前衛」の意味わかる?
このくらいには文化的な素養がみんなある人だった、というのが前提で、かつ。
加藤さんという歌人の名のもとに、スゴいメンバーが集まってて、毎号毎号身を削るようなしのぎの世界だったわけです。
だれかがカジュアルに「欄頭ファイブ」ていう言葉をはやらせたらしい。上位5人のなかに入ってなければあとはその他。
その他の人は、都道府県別に並べられた。あとの人は、もう全員だめ。「ここにいる意味がない」みたいな場でした。
彗星集って、実態はすごい激しい競争社会。
お互いさ、「同門」の意味ってわかってて…。
めちゃくちゃサバイバルなのよ。こいつを蹴落とさなければ、俺の名前上位5人にのらない。
みたいな。だから、この場のなかで、「いかにしてめだつか」
を考えたよね。
なんだろう。その雰囲気で、お互いに情報共有してて、意見交換もしてたから、中島さんと俺は歌がぜんぜん違うんだけど、その良さは、お互いわかってた。
で、俺は読者じゃないの。この長谷川眞理子さんの凄さをわかって、説明ができるけど、でも、同じ欄だから、この人と競わないといけないみたいな。
その競うやつらが、どんどん人数が増えてくんだよ。ライバルなの。
俺は「総合誌の賞には出さない」けど、加藤さんには読んでほしい。
このメンバーのなかで、だれが5人優れてるかを決めてくれ、っていうモチベーションだったと思う。
中島さんはその「競う」っていう認識がなくて、1首の人だよ。
加藤さんにそもそも「選」されたくないんだよ。
それが中島さんの批評性というか個性なの。
中島さんが、10首の枠、フルで使って、出して上位5人に入ったのは一個だけ覚えててて。
アスキーアートで「歌の死」
ってかいてあるやつ。コレは覚えてる。それは中島さんも歌集に載せたじゃん。
加藤さんって、ある意味メチャクチャだめな人でした…。
もともと、場のちからに依存するひとと、いうか、指導力不足の欠如は甚だしい。
俺も中島さんも基本的に、「加藤さんからおそわったこと」ってある?
たぶんない。
でも、既に総合誌で賞をとったひと、野口あや子さんとか、柳澤さんとか、まあだいぶ後れてだけど笹井さん。
とかを連れてきて、「このメンバーのなかで歌だしてみない」ってやる。
発掘のひとだよね。
でも、加藤さんは、その集めてきたひとを、なんか適当に競わせて、お互いで上位5人を決めるだけ。
価値判断しかしないの。
このシステム、めちゃくちゃひどいというか。。。。
だれも教わってないよ。
結社って、もっとさ、その岡井さんなら岡井さんでいいけど、その人がどういう人かっていうのを、ちゃんと懇切丁寧におしえてくれるじゃん。
岡井さんの凄さを、加藤さんは「前衛だ」「前衛だ」っていうだけ。
説明はいっさいなし。
いま大辻さんとか黒瀬さんとかが、ひとりひとり、「見てるよ」ってアピールするために、すっごい長い批評書いてるじゃん。
でも、この上位5人を選ぶっていうシステムを導入したのって、もともと加藤さんなんだよ。で、あとで道浦さんとかがその「競うこと」の意味、とか凄さに気づいて、慌てて導入してて。。。
いままでにない「場」を作ろうとして、才能の塊みたいなひとをコレクターのように自分の欄に集めて、競わせて、価値判断して終わりみたいな。
それが毎月なの。
その当時は、岡井さんたちが、総合誌の選考委員やってて、で、そこで賞を取ったひとを加藤さんが、連れてくるだけ。
発掘という意味では、笹井さんだけかな。60人くらいいたか、毎月。
で、育成されたことはない。みんな加藤治郎という読者に「存在をアピール」するの。
でも、俺は、まったく無名で、「でも、このメンバーに毎月勝たなきゃ」みたいな意識だけがあって、自力で勉強っていうか、短歌の歴史を知らないと勝てない。というのは気づいてて、完全に中島さんとはポジショニングの話しかしないんだけど、でも、その意識の高さだけで短歌史を自分で勉強するとか。
もう自己研鑽しかないわけ。
変なパロディとかしても、うまくいってないと、「落とされる」んだよ。
その野口とか、柳澤、笹井は意識の高いスゴイ仲間だけど、絶対コイツらとは違うことをやる。みたいな意識しかないの。ライバルだから。
同じようなことを、たぶん斉藤斎藤さんが考えてた。
短歌っていう歴史のなかで、このひとはこういうことをやってる、こういうことをやってる、じゃあ、俺はこういうことをやろうかな、
みたいな、ことを考えて歌を出す。
みたいな。
それは、オリジナリティあるけど、真似できないよね。
っていう話。
で、その意味を間近でみてて、「あ、ガチでこのシステムすごい」
というのを、導入したのが、あとから選歌欄をもった黒瀬さんとか大辻さんとかなんだよ。
でも、加藤治郎の発掘能力というか、そのひとのすごさを、みきわめて、惚れ込んで、連れてくる。みたいな、もうそういう意味合いでは、黒瀬さんも大辻さんも勝てない。もとからある多様性をそのまま維持できない。
そこが図抜けてんの。加藤さんの審美眼。
でも、説明はなにひとつできない。
お。いいじゃん。てのを、見つけるだけ。
新聞歌壇は、それであってる。
でも結社はだめだよそれじゃ。
いるメンバーが固定化してるから。
そのメンバーが抜けたり、無選歌になると何もモチベーションがわかない。
競わなくなる。
歌会に出ないと加藤さんの存在が感じられないない。
だから、Operaなんて、タイトルがかっこいいだけで、みんな競わないから、モチベーションが下がるだけ。
そもそも実は加藤治郎とかどうでもいいの。
「自分が輝ける場所」に、「他のひと」とか、「自分」を比較できるとか、そういう場に毎号自分の歌を置きたいという、欲求だけなんだよ。
比べることと評することができない。批評がないから、場が死んでいくんです。
今のメンバーで、このなか、笹井、野口、柳澤、俺、中島、あとTさんとか、競ってないけど山崎さんとか盛田志保子さんとかがいるなかで、目立てるの?
そういうことを意識して、歌を作ったことってある?
あのころの彗星集と
いまの彗星集は
もう歌のレベルがぜんぜん違う。
誰かもうやめたやつが、いきなり「入ってすぐ特選になりました」っていって喜んでたけど、
笹井さんや野口さんと比べて特選なら、価値あるな。
でもクズ同士が競って特選を競っても、もう中身ないよ。
みたいな…。
批評って、毎号毎号自分はどうするか、っていう「ポジショニング」なんだよ。
そこで醸成される空気のなかで、俺は加藤さんは教えてくれないから、大辻さんに教わりに行くわけです。
そういう場の意味を説明できるやつは、もう残ってない。
あとはぐずぐずだよ。
加藤治郎の指導力欠如
俺の自己研鑽は相当徹底してて、たぶん、未来はそれぞれ選歌欄ごとに歌会あったんですよ。
大辻さんの欄、黒瀬さんの欄、笹さんの欄、中川佐和子さんの欄。首都の会。
「お願いします! 勉強させてください」
って、大辻さんにいうんじゃないんだ。
まず、自分の師匠に言うの。
何も言わないで出たら、怒られるんだよ。めちゃくちゃ。
こんな習慣いまないんだけど、毎月加藤さんに報告するんだ。
今月は大辻さんの歌会があるので、いきますとか。
で、西巻は、行くっていう報告が毎月「うるさい」ので、他結社とか、きみ、自由にでていいよ、みたいな話になるの。
俺に報告しなくていいみたいな。
で、みんな自分の弟子っていう意識が、まだあった選者に。
俺はずっと場の話をしてるけど。
いまはなき、大辻さんのメーリングリストができあがるとき、加藤さんのMLがあって、大辻さんのMLができるっていうとき、俺、加藤さんの弟子として大辻さんのML入っていいの、ってすごい長い文章書いたら。
その場で、返事で、「きみ活動は自由だよ」って言われた。
で、あと、外部の会もいった。
さまよえる歌人の会とか、石川さんともうひとり未来のやめちゃった岡井さんのお弟子さんたちが立ち上げた会で、結構、そんな「あっち」じゃなかったんだよ。命名の瞬間に俺いたし。けっこう隣みたいな感じでいってたわけ。
あとはもう地理的に近いから、という理由でガルマンもいったけど。
うわー。歌読めないこの人たち。って絶望して、斉藤斎藤さんと知り合ったりとか。
斉藤さんとの初対面はガルマンでした。その翌日未来の批評会があって、斉藤さんゲストなんです。
で、同じ歌を出してる。その歌もおぼえてる。
雲がほら楽なほうへと流れゆくわけをきかせておこらないから
ていう歌。で、前日、俺がガルマンで解釈して
だれひとり、この斉藤さんの歌がダブルミーニングだっていうことにぱっと気づかないわけ。一つの意味しか言わない。
雲が、楽なほうへ流れゆく。
という解釈しかなくて、俺は別の読み方を提示するの。
雲があって、もうひとり、あなたがいて。
雲がほら楽なほうへと流れゆく/わけをきかせておこらないから
と切れる。みたいなことを、瞬間で判断するんだよ。
で、俺と斉藤さんがもしかしたら覚えてるかもっていうのがあって、
その翌日岡井さんが同じことをいうみたいな流れがあったの。
この岡井さんがそう読んだ、っていう事実は、斉藤さんが岡井さんの追悼文で書いてるから、間違いなくて。でも斉藤さんが俺と初対面かどうかを覚えてるかは知らない。その前日あなたガルマン来ましたね。っていうことを覚えてるか、俺は知らないけど。俺はおぼえてて、めちゃくちゃ渋谷の今ない喫茶店の入口側の席に斉藤さんが座ってて、めちゃくちゃ愛想よく挨拶してくれて…。
斉藤さんめちゃくちゃすごいひと。
っていう意識しかないから。
緊張したけど。
その斉藤さんの歌は覚えてて、岡井さんと同じように読んだ、という事実は、オレは記憶してる。
そうなの。歌会。とか、批評。
この体験。評っていうのは、「活動」なんだよ。
その場を維持するための「活動」。批評っていうのは、アクティヴィティなんだよ。場に応じて、変わるんだよ。
何をいうべきかを変えるんんだよ。
ガルマンの連中は、堂園さんとか永井さんは違うけど、斉藤さんの歌がまったく読めなくて。。。
「歌が読めない」っていう評価が、当時めちゃくちゃ駄目だったんだよ。
引用しない。
全部記憶で書くよ。
大辻さんが
「つくづくと歌の読めない女かなびらびらと赤き付箋を貼りて」
っていう歌を歌集に載せてる。
その真の意味がわかるの一部のひとなんだけど、
「歌が読めない」
って、歌人の中では致命的に駄目なことなの。
もう自分のやってることの意味がわからない、ポジショニングできない、ってことだから。
ていうか、たぶん、大辻さんと加藤さんってめちゃバトりまくってるんだけど、岡井さんが「うちの弟子は、みんな仲がわるくて…」って嘆いてたという話を覚えてる。みんな富士郎さんとか、紀野恵さんとか、めちゃくちゃなメンツのなかで競うと、ほんとに仲が悪くなる。
と言う事実の意味を知らない。
俺は知ってる。
このひと歌読める、とか、
読めないとか。
その意味がわかるもん。
それはフェミニズムじゃないんだよ。
「歌が読めない」のが駄目で、女がだめなんじゃない。
表現者としてだめなの。
中島さんはあんま外の会に出てなくて、俺は出てて、斉藤さんや花山さんとガルマンであったり、今井さんとも内山さんとも永井さんとも五島さんともあった。
Tさんと俺で企画して、このメンバーを横浜に連れてこよう
みたいな話になって、それは、彗星集の歌会として、刺激になるから連れてこよう、みたいな話になる。それが横浜開港歌会。
加藤さんは、場をつくるのはできたけど、柔軟に場を変えるのは無理なひとというか、すごく歌を見る目があるけど、人を見る目がまったくないからね。
俺は、加藤さんと意見交換したのって、そのときがはじめてなんだ。ずっと歌の読みとか、価値判断を勉強してて。
俺とTさんは場をつくりたいという意識が一緒で、俺らは歌会やりたい。って言ったの。最初。
でも、加藤さんは歌会はいいけど、交換条件で、雑誌を作れ。
っていうの。
そもそも、めちゃくちゃ「場」の意味が違う。
雑誌と歌会じゃ。
岡井さんというひとはものすごく「臨機応変」なひとで、
あのねアーサーの歌とか。「場」のなかで柔軟に変えていける自由さがあって、すごい場の重要性を理解してるひとだった。俺は岡井さんというひとを、加藤さんと、大辻さんを通じて知りました。でも、生岡井も経験あるから。
短歌の批評がアクティヴィティだ、っていうことに、ほぼ、岡井さん以外、誰も気づいてないんだよ。
その価値を、大辻さんが気づいて俺を褒めるんだよ。
「歌が読める」って。
その意味が、わからないやつがいるけど。
俺は、その評価の理由を知ってたから。
それで十分。
そして加藤さんはなぜか「場」の意味が分からない。
あなた場作ってきたじゃん。
だから、ふつうに働いてる俺らに無茶苦茶なフリ方して、雑誌作れっていうわけ。
それが「新彗星」です。
これ、俺の妄想っすか。
俺の歌はだれも同世代が評価しなくて、真っ先に評価した人はやめちゃった五島さんと、亡くなった笹井さんだよ。
そして、みんな記憶をとざして、だまってさっていくみたいな。
俺はもうそれに耐えられない。
だから、かなり長い追悼文を俺の記憶で参照して書くよ。
崩壊の予兆
全員過去のひとなんだけど、新彗星に載ってるひと、だれも覚えてないでしょ。
長谷川さんはあったことないけど、長谷川さんともうひとり黒田さんという短歌研究新人賞の受賞者がいて、その二人は絶対載せろ、こら。みたいな。話をした。長谷川さんはたしか載ったけど、黒田さんは辞めるところで、もう短歌全集売り払うみたいな話をしてて。
長谷川さんの前衛の意味はわかりやすいけど、
黒田さんがいた意味。
その人とか西村旦さんがいるだけで、説明してくれんの。長谷川さんみたいなことを自由にやれる下地は、この地味な文語旧かながあるから、目立つんだよ。
っていうことを。
いまでいうと、杉森さんとか、岩尾さんみたいなポジションのひとがいる意味を誰も気づけてない。
俺必死でバランス取ろうとしたけど、もう墜落寸前の彗星の軌道は上がりませんでした。
実質的に、俺は育ったけど、
Tさんは潰れたね。
加藤さんがTさんを潰した事実は、俺はっきり覚えてる。
3人だけのミクシィまだあるから。
Tさんは加藤さんの無理な人員配置というか、人を見る能力がない感じをみてやる気なくして辞めた。
俺は編集長の座を俺に譲れ、って言ったの。
そのとき、コピーライターやってから実績作りたいみたいな、すごい理由でねじこんだんだけど、
本当の意味を理解してるひとがいなくて、
2号までの実質的な紙面づくりは俺とTさんでやったんだけど、編集長もやめちゃったハッピーアイランドの鈴木さんで、福島にいたんだよ。
その二人が、俺が実質的な仕切りをやらないと潰れるということに俺なんか気づいたんだよ。
でも加藤さんは、意味がわかってなくて、
なんで鈴木さんから俺に、編集長を変えるのか、
みたいなことがわからない。
鈴木さんはめちゃくちゃデザイナーだから、ヴァーサスみたいなレイアウトは全部鈴木さんが考えたんだけど、
中身は全部俺が作ってて。鈴木さんも中身がわかんなかった。
雑誌はひとがつくるっていう意味が、全然わからないのが加藤さん。
ISSNっていうんだけど、ISBNの前の国際規格みたいなのを入れるように進言したのも俺で、それはだやが気づいてたね。
で、ブログで売ったのも俺で、一緒に謹呈リストを作ったのも俺。雑誌としての体裁を整えることで必死だったけど、中身はすかすかなんだよ。創刊号は。
笹井さんと、野口さんと、柳澤さんの対談。それはおれが企画して、文字起こしできないし、遠隔だから、対談の原稿は文字ベースでやりとりしてもらってまとめただけ。
あと歌の数だけ加藤さんが調整して評論たしか細見さんか中島さんに書いてもらって終了みたいな。
なんだけど。
これ、誰の雑誌なのっていう感じ。
立場が変わらず、責任だけ押し付けられたTさんがが潰れるという現象を見送った俺は、崩壊の予兆をもう、感じてたけど。
そのあと、俺は2号で編集長を譲らないならTさんと一緒に辞めるって言った。
それを「いいよ」っていったじてんで、鈴木さんが潰れる。
中身を鈴木さんがわからない。
で、誰の雑誌なん。っていうのがわからない。
そういう能力が取替が聞くもんだと思ってる時点で、加藤さんはだめなの。
だから「新彗星」はぽしゃった。
俺と加藤さんはたぶんその時が一番印象最悪で。お互いもう、表面上は仲良くしてたけど、加藤さんはもう俺に仕事をふる気がなくて。
俺はめちゃくちゃ、加藤さんの前で当てつけに大辻さんの歌集読んでたりして。
「大辻か!」
って言ってたよ。
中島さんとかを歌会の実質的な総合司会とか、そういう能力があるから、
そのあとは俺の社会から脱落したから、中島さんが継いだ。
でも「誰でもできる」わけじゃない。
全然中島さんや朽木さんが感じてる加藤さんの倫理観のなさと、あの仕事のできなさは、もうみんな感じてる。
あの人は、違う、謝ればいいって問題じゃない。
能力がないんだよ。場を運営して維持する能力が。
それが、人づくりとか、なんかそういう能力がまったくないから、みんな辞めてくんだよ。社会的な倫理観じゃなくて、文学的な倫理観がないから、いま、もう、中島さんが辞めて朽木さんが辞めて、大変なことになったあと、また代わりとして、場を維持するために、zoom歌会を俺がやって。
それを補おうとするんだけど、やっぱり加藤さんが潰すね。
それで、人が育たないの。
みんな自分のやってる意味を、歴史とか、同時代性と比べられる能力が育たないの。
俺は、加藤さんからその能力を習って、メンバーの歌を全員覚えて、で、雑誌の実質的な編集もやったわけです。
その新彗星はだやさんが気づいてて
今の彗星集を「見る影もない」
みたいな話を俺にしてくれたけど。。。
短歌が場である
っていう話は、たぶん、演劇人のだやさんはわかると思う。その場に参加するということの重要性「価値」を、誰も気づいてない。
加藤さんが教えてくれないので、しょうがない、教えてくれたり、一緒に考えるひとのなかに出向くしかない。
みたいなイメージで、毎月、よその選歌欄の歌会や、未来の他の選歌欄で、勉強をしたの。生の場で、歌のよみを。
その量がぜんぜん違うから、今の残ってるメンバーを、全員クズって言える。
みたいな話。
価値はあなたが判断してください。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
