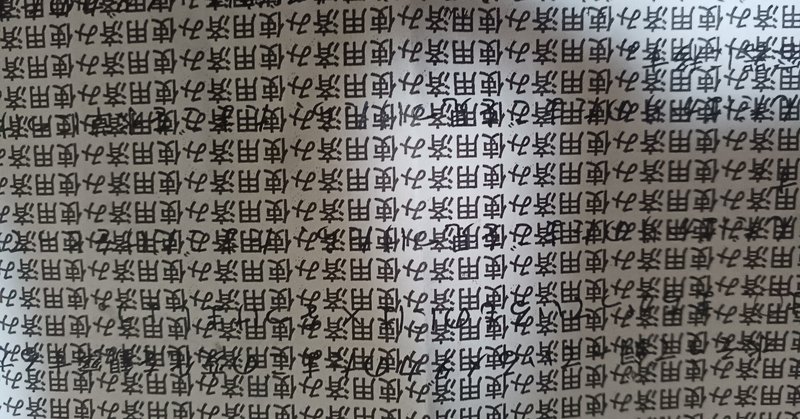
人間モノカルチャア(小説)
私の友達に、今日において珍しいタイプの子がいた。SNSを一切やっていない人なのだ。津々浦々、ネット上の、対面としてのコミュニケーションも等しく人間関係を維持する1つのツールに収まり、ネッ友リア友という言葉も使われなくなって等しいこの時世にだ。理由を尋ねると、「依存したくないから」という単純なものだけれども。それでも、小柄で華奢な見た目に沿う朗らかな性格のおかげか、ある程度交友関係も広いようだったので別段不便そうな様子でもなかった。
確か私が某人気投稿型snsアプリで知名度を上げ始めたのが、大学に入った頃だったと思う。私と彼女は、同じR大学に進学していた。
「そっか、、、オフ会なら沢山人来るし仕方無いよね。」彼女は蚊の鳴くように何時になく寂しそうな声を出した。
「そう、ホントはフォロワーさんに断ってでも一緒に行きたいんだけど、、そこのお店に行くのはまた今度にしない?」
電話だと気持ちが声に表れてしまうので難しい。「おっけー、じゃ、ファイト!」
突然おどけた声を出して、彼女は電波の向こうに消えた。初めてにして一大イベントだ。夜行性の私は、明日に備えて、もう寝なければいけない。欠伸をひとつして、布団を被った。
まずは目覚ましを1回、スヌーズしたのを2回止めたのが間違いだった。
「ヤバい!!遅れる!!!」
やっと獲得したネームバリューを死守する為にも、絶対に遅刻はしてはならない。集合時刻は9時半、時計の針はしっかり左にcos45°を指している。もっと近い場所にしておくんだったと思いつつ、市の中心部にあるビルへ車を飛ばす。飛ばす筈だったのが、生憎の渋滞であった。スピードメーターは0付近をぐらついている。もう日が高く登ってしまって何時か分からない。私は自分を殴りたい衝動に駆られながらビルの階段を昇った。この時間になって誰もいないということは皆帰ってしまったのだろうか。貸部屋の灯りがついていた。あれ?どちらにしろ本人確認は必要だった筈だが…
「遅れてすみません!!」意を決して入っていった時、大勢の中で一番初めに目が合った人がいた。瞬間、閃光が走ったような気がした。
「あっ」
と短く声を発して勢いよく席を立つ。拍子に手元のグラスがガシャンと派手な音を立てて倒れた。「えっどこ行くの、浦添さん。」浦添?浦添は私ですが??私はただ呆然として、駆け出していく彼女の背中とテーブルから滴り落ちる液体を見ていた。
私は一切のSNS上での活動を辞めた。同じ大学の彼女が泣きながら私のところに謝りに来たのは、それからまもなくのことだった。
もともとスマホだって持っていたこと。SNS上に友達がいないと言えばある程度皆優しく接してくれたこと。私の熱烈なフォロワーだということ。オフ会には眼鏡をかけて髪型を変えていけばバレないと思ったこと。私がいつまでも来ないのでつい魔が差したこと。
私は腸の煮えくり返る思いで、なおも彼女を許さなかった。会を開いたのも、遅刻したのも確かに私だった。しかし、自分の人生設計をめちゃめちゃにしたのは、これほどの奈落に私を追いやったのは彼女の独りよがりが全ての元凶だろうと、八つ当たりとも思える程に彼女を罵倒していた。彼女はしゃくりあげながらも謝罪を辞めなかった。
申し訳ないこと。魔が差したこと。貴方しか友達と思える人がいないこと。本当に申し訳なく思っていること。だから、
「これからも仲良くして欲しい、理由なんて、何にも、ないけど。」
妙にその言葉が脳裏にしがみついて離れなかった。私は昔家に遊びに行った時の彼女の口癖がいつも「何にも無いけど、」だったのを思い出していた。
古いアカウントのことは忘れたいがために、全く使っていないが消してはいない。頑なにフォローを外さないフォロワーが1人だけいるのだ。消したらこちらの負けな気がするのだ。そのアイコンには「それでも私がいるでしょ、」と言わんばかりの誇らしげなかたえくぼの笑顔が写っている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
