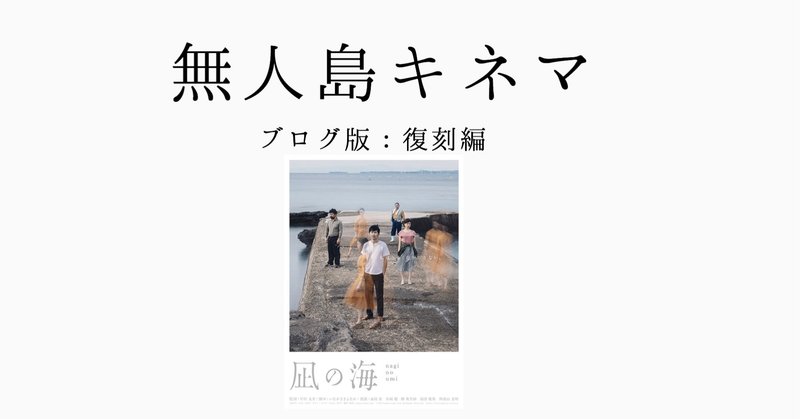
【私的な思いや記憶に刺さった『凪の海』の話】
(2019年7月7日 無人島キネマ・ブログ版 初掲)
何を手に入れたら満足できるのか、
何を手放したら諦められるのか、
どんな居場所に迎えてもらえれば寂しくなくなるか、
どんな人から距離を置けば劣等感に苦しまなくて済むようになるのか。
そういうことに悶々とする時期は意外に長くて、
ようやくこのくらいがちょうど良い感じなのかなと思えるようになったのは、40代も半ばを過ぎたごく最近のことで、
でもそれも一過性の通過点に過ぎないかもしれないよねと思うこともある。
そういうことを話す相手もいなかったので、自分ばかりがこんな歳までくすぶっていたのかと思っていたけれど、話してみれば、そんなふうに「自分ばかりが、」って思ってたっていう人もいた。
人の心に波が立つのは、案外自分がバシャバシャやってるからというだけのことで、もがくのをやめると案外海は凪いでいる。
でも動かない限りは沈んでしまうので、溺れない程度にうまく泳いでいければいいなとも思う。
辛いことがたくさん描かれていて、それに打ち勝つような話ではない映画にこそ、救われることがたびたびある。今回観たのも、僕にとってはそういう映画。
とても私的な思いや記憶に刺さる映画だった。だからこれは、僕のためだけの映画なのかもしれないし、普遍的に誰しも刺さるところのある映画なのかもしれない。
“不在の中心”である兄
僕は22歳の頃に27歳の兄を亡くしたことがあるので、「兄弟」が描かれる映画に対しては敏感なところがある。僕がこれまで観た多くの映画に描かれる兄弟像は、「小利口で社交的で、でも実は小心者な弟に対して、兄は不器用で奔放で厄介者。でも家族や周りの人たちに慕われ愛されているのは兄で、実は兄は大らかで良い人だった。」という話が多いような気がする。実際僕自身がそういうパターンだったから、被害妄想的にそう思うのかもしれないけど、そういう映画を観るとモヤモヤしてしまうことが度々ある。
『凪の海』ではそういう兄は冒頭から亡くなっていて、その存在を“不在の中心”として、周りの人の心が波立つ様子が語られていく。この“不在の中心”の物語という構造は、『桐島、部活やめるってよ』が思い起こされるけど、ちょっとした群像劇的に、複数の立ち位置にいる人たちのそれぞれの思いを描き分けるのに優れたタイプの構造だと思う。「その人はなぜ、いなくなってしまったのか」というミステリーで観客の関心を牽引する利点もある。
周りの人たちに慕われ愛されているはずの人物が亡くなり、それによって立つ波は、どうやら単なる悲しみとか寂しさとか喪失感ではない。だから『凪の海』は、そういう悲しみとか寂しさとか喪失感を、残された人たちが感動的に乗り越えていく話ではないようだ。
僕は序盤からグッと引き込まれた。
故郷に戻って疎外感を味わう、「東京の人」になった人
別に東京でなくてもいいんだけど、地方出身者にとって東京は「ここではないどこか」の象徴だったりする。
夢や仕事の目的地として東京を目指した人ではなく、「ここではないどこか」に生きたくて故郷を離れて「東京の人」になった人には、「裏切り者的な疎外感という呪い」が貼り付きがち。たいがいその「呪い」は故郷の人たちが貼り付けるのではなく、自分の罪悪感や挫折感や自意識によるものだということに、なかなか人は気づけない。僕はジェイソン・ライトマン監督の『ヤング≒アダルト』という映画を思い出した。
『凪の海』には、そんな「東京の人」になった人が2人、故郷に帰る。ひとりは永岡佑演じる主人公の圭介で、もうひとりは柳英里紗が演じる元兄嫁の沙織だ。
圭介はバスの中から故郷の海を見ただけで嘔吐してしまうほど強烈に呪われている人なんだけど、基本、場当たり的にしか物事を考えられない男なので、清々しいほどに最後まで色んな人に怒られたり呆れられたりしている。地元の人にミニライブを頼まれて、穴の空いたギターをチューニングするんだけど弦を切ってしまう。「代わりの弦を街まで買いに出ようか?」と言う父親に「これでこのままやる。」と答える場面があるんだけど、東京のミュージシャンとしてダメだった10年間を、観客は一瞬で納得させられる。ついには「お前は誰だ?」とまで根本的なことを問われるんだけど、「俺は、俺だ。」と。「だからその“俺”が何者になりたいんだ?」というのが命題であることに最後まで考え至ることができない圭介のダメさが、映画の苦さとして良かった。その最後で圭介は成長することができるのか?
もうひとりの「東京の人」になった人の沙織は、さすがに主人公よりはもう少し大人で、ちゃんと自分のための答えを見つけて東京に戻っていく。彼女の見つけた「答え」は、決してポジティブなものではなかったけど、僕はそれにとても救われた思いがした。「朝陽が眩しすぎて、自分は逃げてしまった。それがなくなって、正直ホッとしてしまった自分がいた。」という答え。それを言ってくれてありがとう、と僕は思った。現実社会において、なかなか言えないタイプの弱音だと思う。「善きこと、良い人に、自分の弱さを意識させられてしんどい。」良い人は文字通りに良い人で悪人ではないから、そのしんどさを責める相手が巡り巡って自分になってしまう。「しんどい」と口にして、それはお前の弱さやヒガミだろと言われるのがわかってるから、なかなか言えることじゃない。なかなか言えることじゃないことを言ってくれる映画は、弱い僕のような人間の救いになるんだ。
変わりたくない男と、変わりたかった女
本作のもうひとりの主人公、小園優が演じる凪。湯澤俊典演じる洋とは「妹と兄」だけれど、肉親でありながら「男と女」の関係を想起させる。幸い僕にはそのへんについて私的に思い当たる痛みや記憶はないので、そのいやらしさとか煮詰まり感はキム・ギドク監督の『弓』が好きな僕には、エンタテイメントとして楽しめた。
お互いのお互いに対する認識によって、兄妹はその街に縛り付けられてる。兄は、足の不自由な妹を守る責任と執着を理由に、変わることを頑なに拒み、妹は不自由な足と束縛の強い兄を理由に変わることを諦めてる。それらは結局それぞれ自分で自分に貼り付けた相互依存という「呪い」なんだけど、本作では最後に、この兄妹が幸せになれたかどうかは別として、共に「呪い」からは救済されている。この兄もまた、沙織と同じように「ホッとした」んじゃないだろうか。
今回映画での演技は初めてという、洋を演じた湯澤俊典の演技の強度が、抑制と爆発のバランスが効いていてとても良かった。圭介が凪に対する好意を公言した時の、哀願するような表情がとても突き刺さった。
足の不自由な少女、凪を演じる小園優も「壊れた人形」をイメージさせて素晴らしい。特に圭介がミニライブを放棄した後、客席に座ったまま表情を失った目は、まさにその瞬間決定的に人形が壊れてしまったのだと感じさせられた。その後にも彼女にとって大きな出来事は起こるんだけど、僕にはあの場面によって本作の結末を受け入れることができた。今後注目したい女優だと思う。
また観たい映画
僕はこの映画の予告編を、2018年7月の『第2回柳英里紗映画祭』で観た。そしてこの本編を観たのが2019年7月の『第3回柳英里紗映画祭』だった。ずいぶん待って、正直忘れかけてもいたのだけど、一般公開に先駆けたワールドプレミアとして鑑賞できたことは嬉しいことだし、それが自分にとってすごく良かった映画だったことも嬉しいことだった。柳英里紗映画祭のいちコンテンツとしてではなく、僕のような弱い人たちにたくさん観てもらえたらいい映画だと思う。
そしてまた僕自身のために、また観たい映画だ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
