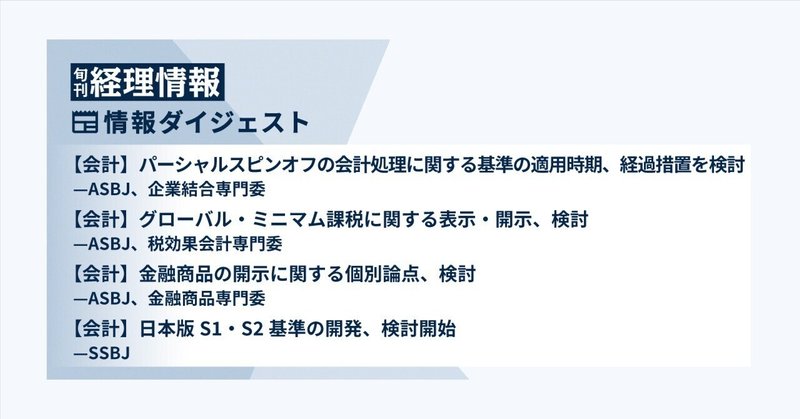
【会計】旬刊『経理情報』2023年9月10日号(通巻No.1687)情報ダイジェスト
【会計】パーシャルスピンオフの会計処理に関する基準の適用時期、経過措置を検討─ASBJ、企業結合専門委
去る8月10日、企業会計基準委員会は第108回企業結合専門委員会を開催した。
第107回(2023年8月20日・9月1日合併号(No.1686)情報ダイジェスト参照)に引き続き、「パーシャルスピンオフの会計処理」について審議された。また、8月24日開催の第508回親委員会でも審議が行われた。
■適用時期
事務局は、適用時期について、パーシャルスピンオフ税制が時限的措置であること、早期に基準開発を完了させて適用を開始できる状態にするニーズがあることなどの理由から、「公表日以後、ただちに適用する」とする事務局案を示した。
■経過措置
事務局は、公表日後に実施される取引から適用し、2023年4月1日から公表日までの間に実行された取引について早期適用を可能とする経過措置を設ける案を示した。
*
専門委員および親委員会委員から異論は聞かれなかった。
■改正の文案検討
前回に引き続き、企業会計基準適用指針2号「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」および会計制度委員会報告7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」について、意見が分かれている点につき、それぞれ次のようにパターン分けした改正文案の検討が行われた。
【自己株式】
現物配当を行う会社が、配当財産の適正な帳簿価額をその他資本剰余金等から減額する場合として規定する、保有する完全子会社株式の一部を株式数に応じて比例的に配当し、次に該当しなくなった場合
案A:子会社株式および関連会社株式のいずれにも
案B:子会社株式
【連結】
完全子会社株式を配当した場合の処理
案A:支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合
案B:支配を喪失して関連会社になった場合を含む
自己株式については、案Bを支持する専門委員が多くみられた。
親委員会では、自己株式、連結ともに案Bを支持する意見が多く聞かれた。
また、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」の改正文案の検討も行われた。
【会計】グローバル・ミニマム課税に関する表示・開示、検討─ASBJ、税効果会計専門委
去る8月23日、企業会計基準委員会は第86回税効果会計専門委員会を開催した。
前回(2023年8月20日・9月1日合併号(No.1686)情報ダイジェスト参照)に引き続き、グローバル・ミニマム課税(以下、「GM課税」という)に関する改正法人税への対応について、審議が行われた。また、8月24日開催の第508回親委員会でも審議が行われた。
■当期税金・繰延税金
前回、次のような事務局案が示された。
GM課税の表示
連結では法人税等として表示し、個別では税引前当期純利益の内訳項目とはせずに、法人税等に含めて表示する。GM課税制度に基づく上乗せ税額の法人税等の計上時期
年度の連結・個別において経過措置を認めず、また、適用初年度より計上する。適用初年度は、四半期財務諸表において、計上しないことができる旨を定める。見積りの取扱い
企業における見積りが不合理である場合を除き、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づいて最善の見積りを行った結果として見積られた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じても、「誤謬」には当たらない旨を結論の背景に記載する。繰延税金の取扱い
実務対応報告44号の適用を継続する。
親委員会では、事務局案への賛成意見が多く聞かれた。
■表示・開示
⑴ BSにおける未払法人税等の流動・固定分類
事務局より、当期のGM課税に関する未払法人税等については、一般的な流動・固定の区分の基準であるワンイヤールールに従って、貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するか否かに基づき、流動負債に表示するか、固定負債に表示するか区分するとの案が示された。
専門委員、親委員会委員から異論は聞かれなかった。
⑵ PLにおける法人税等の区分表示・開示
事務局より、個別については、GM課税に関する法人税等を、重要性がある場合には区分して表示または開示することを求めるとの案が示された。
また、連結については、GM課税に関する修正IAS12号「法人所得税」では区分表示が要求されているが、日本基準の開発にあたって、その情報の有用性について関係者の意見を確認する方向性が示された。
専門委員からは、個別に関しては賛成意見が聞かれた。また、連結については、「税率差異の注記で把握できるので、区分は不要」、「利用者としては、連結でも区分したほうが分析しやすい」などのさまざまな意見が聞かれた。
親委員会では、個別に関して異論は聞かれず、連結に関しては「国際的整合性の面からも区分しては」との意見が聞かれた。
【会計】金融商品の開示に関する個別論点、検討─ASBJ、金融商品専門委
去る8月9日、企業会計基準委員会は第204回金融商品専門委員会を開催した。
金融資産の減損に関する会計基準の開発に関して、ステップ2を採用する金融機関における開示の以下の論点について審議が行われた。また、8月24日開催の第508回親委員会でも審議が行われた。
■金融商品の区分別等の信用リスク・エクスポージャーの開示
IFRS7号「金融商品:開示」35M項に規定される区分別等の信用リスク・エクスポージャーの開示要求を取り入れるかが検討された。
事務局から、貸付金、債券等の有価証券、ローン・コミットメント、金融保証契約などのコストと、国際的な比較可能性の観点などの便益を比較し、IFRS7号の定めを取り入れるとの事務局案が示された。
また、CECLモデルを採用している場合の開示については、規範性のない教育文書において複数の開示方法があることを示すとの案が示された。
専門委員からは、方向性について賛成意見が聞かれた。また、「教育文書等で各社の管理状況にあわせた開示を認めては」との意見が聞かれた。
親委員会でも、事務局案に異論は聞かれなかった。
■財務諸表以外の開示への参照
IFRS7号35C項の財務諸表以外の開示への参照に関する規定を取り入れるか検討が行われた。
事務局から、わが国では、財務諸表利用者が財務諸表と同じ条件で同時に利用可能なものという要件を満たす開示が実質的に存在しない可能性があるとの分析がされた。
そのうえで、IFRS7号の定めを取り入れるか否かについて、将来的な実務の進展があり得ることを踏まえ、取り入れるとする事務局案が示された。
専門委員から、賛同の意見が多く聞かれた。また、「開示制度全体の枠組みに影響するので、包括的に別プロジェクトで検討したほうがいいのでは」との意見も聞かれた。
親委員会でも賛同の意見が多く上がった。
【会計】日本版S1・S2基準の開発、検討開始─SSBJ
SSBJは、去る8月3日に第18回、8月22日に第19回サステナビリティ基準委員会をそれぞれ開催した。
今回よりIFRS S1号およびIFRS S2号に相当する日本基準の開発の審議が開始された。
■基本的な方針
事務局は、日本版S1基準および日本版S2基準の開発にあたって、基本的な方針を次のように示した。
⑴ サステナビリティ開示基準は、原則として国際的な基準の定めを取り入れる。ただし、これは国際的な基準の定めを無条件に取り入れることではない。
⑵ 国際的な基準の定めをそのままの形で取り入れないことについてコンセンサスが得られる項目については、サステナビリティ開示基準に定めを取り入れない。この場合、その理由を明示する。また、国際的な基準の定めとは異なる開示を求めることがある。
⑶ 国際的な基準の定めを取り入れつつ、これとは異なる開示をもって代えることを容認する定めを置くことについてコンセンサスが得られる項目については、そのような形でサステナビリティ開示基準を取り入れる。この場合、その理由を明示する。
⑷ サステナビリティ開示基準に国際的な基準の定めをそのままの形で取り入れない理由として次のようなものが考えられる。
① 国際的な基準の定めによって提供される開示が有用ではないと判断されるため。
② その開示に一定の有用性が認められるものの、作成者に過度の負担となることが明らかであると判断されるため。
③ 周辺諸制度との関係を考慮した結果、国際的な定めをそのままの形で取り入れないことが適切であると判断されるため。
⑸ 国際的な基準の定めをそのままの形で取り入れるかどうかについてコンセンサスが得られない項目については、取り入れたうえで、当面、適用を任意とすることを検討する。
⑹ 周辺諸制度との関係を考慮した結果として、国際的な基準と異なる定めを置くことにならないものの、わが国の諸制度を当てはめた場合の取扱いを明らかにすることが有用である場合、当該取扱いをサステナビリティ開示基準に含めるのか、規範性のない補足文書に含めるかどうかは個別に判断する。
■具体的な検討事項
次のような事務局案が示された。
⑴ 報告企業
「報告企業」について、IFRS S1号における定義を取り入れる。また、「連結財務諸表を作成している場合は連結財務諸表に含まれる企業集団、連結すべき子会社が存在しないため連結財務諸表を作成していない場合は個別財務諸表を作成する企業」であるという点について日本版S1基準の規範性のあるものとして定める。
⑵ 商業上の機密情報
IFRS S1号と同様の定めを取り入れる。
⑶ 合理的で裏づけ可能な情報
項目を限定せずに幅広く認めることとする。この案に対し、委員からは、「比較可能性がなくなる懸念があるため、慎重な検討を」との意見が聞かれた。
⑷ 報告のタイミング
日本版S1基準では、サステナビリティ関連財務情報開示について、法令により要求または容認されている場合および任意で提供する場合を除き、関連する財務諸表と同時に報告しなければならない旨を定める。
⑸ 情報の記載場所
法令により要求または容認されている場合および任意でサステナビリティ関連財務開示を提供する場合を除外する。
⑹ 相互参照
法令において相互参照することが禁止されていない場合とする日本基準特有の定めを取り入れる。
⑺ 公表承認日・後発事象
公表承認日よりも前に、報告期間の末日現在で存在していた状況について情報を入手した場合は、関連情報を開示する。公表承認日は社内の承認プロセスにより決定する旨および承認する権限者の例を、規範性のないガイダンスにおいて示す。
〈旬刊『経理情報』電子版のご案内〉
本記事は、旬刊誌『経理情報』に掲載している「情報ダイジェスト」より抜粋しています。
『経理情報』は、会社実務に役立つ、経理・税務・金融・証券・法務のニュースと解説を10日ごとにお届けする専門情報誌です。タイムリーに新制度・実務問題をズバリわかりやすく解説しています。定期購読はこちらから。
電子版(PDF)の閲覧・検索サービスもご用意!詳細はこちらから。

