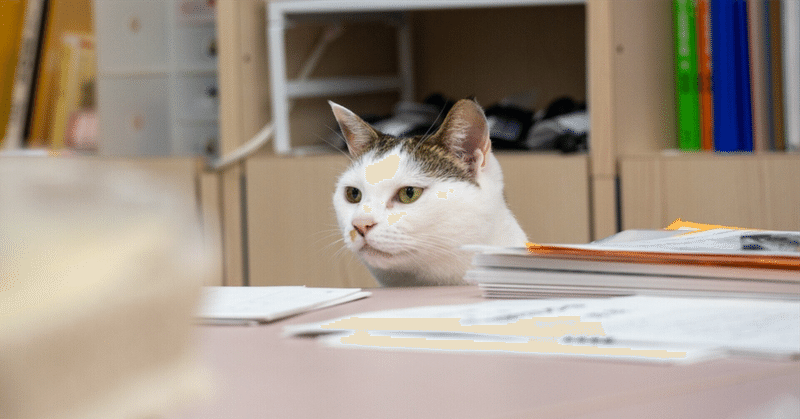
「4/7日能研全国テスト(6年生)」感想
概要
2024年4月7日に行われた日能研全国テスト(6年生)の感想。
国語
一番正答率が低かったのが4-5の13%。
この問題は「ウォーリーを探せ」になっている点が悪問。
「文章中から12文字で抜き出す」という指定によって確かに答えは一意に定まっている。
しかし別の文字数なら他にも該当するところがある。
20文字以内で答えよという文章問題ならもっと正答率が高かっただろう。
内容を理解して意味的には答えがわかっているが、該当の12文字が見つからない。
同じような意味の部分があるので文字数を数えて「あ、これ15文字だ、違う」となる営みは無駄。
算数
前回から始めた「正答率予想」。
今回もやってみた。
予想と実際の正答率の差を見ながら感想を書いていく。
大問1
予想
(1)90% (2)85% (3)80% (4)75% (5)70% (6)65%
実際
(1)99% (2)80% (3)73% (4)66% (5)64% (6)48%
予想と実際の差が10%以内に収まらなかったのは(6)。
haとaの単位変換。50%切るのか。
大問2
%省略。(5)は文章問題なので飛ばした。
予想
(1)80 (2)80 (3)70 (4)60 (5)ー (6)40 (7)25 (8)5
実際
(1)85 (2)91 (3)76 (4)19 (5)ー (6)46 (7)13 (8)1
(2)は和差算の基本。こういうのは90%超えるのか。
(7)は差集め算(以下)。

200本全部ボールペン買ったら36000円差。
現実の4610円差より31390円差大きい。
1本シャーペンにする毎に430円、差が縮まる。
31390 ÷ 430 = 73本
これ系は片方に寄せて全体の差を1つの差で割るだけで全部解ける。
(8)は小学生には難しすぎ。
前々回だったか、図形で同様に難しすぎ問題出してた。
日能研の図形問題の作問方針どうなってるんだろ。
大問3
予想
(1)75 (2)35
実際
(1)87 (2)41
(1)みたいな導入小問は落とさない人が増えてるのか。
さすが小学6年生。
大問4
予想
(1)60 (2)40 (3)25
実際
(1)54 (2)49 (3)41
(3)の41%は意外。
(2)が49%だから(2)を解いた84%が(3)も解けたのか、まじか。
大問5
予想
(1)75 (2)25
実際
(1)48 (2)17
今回最も正答率を外したのが5-(1)。

なにが難しいんだ。
とりあえず9999×9999するだけなのに。
どういう誤答が多かったのか知りたい。
大問6
予想
(1)25 (2)①15 (2)②10
実際
(1)15 (2)19 (3)9
ぎり10%以内。
(1)は6本同時に入れると考えれば簡単だけど、1本ずつ考えて解けない子が多いと思って下げたが、もっと下げて良かったのか。
大問7
予想
(1)25 (2)5
実際
(1)18 (2)1
これも10%以内。
(2)は難しいけど最後の問題だし許せる。
社会
前回に引き続き歴史なしの地理オンリー。
そんな出し方で良いのか。
内容も、6年生になってもっと読み取る系の問題が増えるかと思いきや、そうでもない。
意外と知識ごり押し。
天然ガス輸入の2位がマレーシアとか知る必要あるんかな。
3位アメリカ,4位カタールと僅差で大人になる頃には変わってそうだし。
理科
悪くない大問構成。
大問4で夜の長さでつぼみが出来る仕組みの実験問題が出た。
こういう実験問題の小問の1つに、長日植物を選ばせる問題とかを1つ入れて欲しい。
こういう実験と普段勉強で覚えている長日植物短日植物の具体名。
子供は意外とリンクして考えれていない。
そのリンクのきっかけになるかもしれないので。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
