
大奥(PTA) 第三十話 【第六章 提灯】
【第六章 提灯】
<火の用心>
その時、かちん、かちんと拍子木の硬い音がして、自身番屋の番太の火の用心の声が、辺りに響き渡りました。
「御用心候え〜、お火元、御用心候え〜」
「これからの季節は空気が乾燥するからねえ。火元には十分気を付けないとね。ウチの兄貴なんざ、昨今毎晩の様に二丁目の自身番屋の火の見櫓に張り付きでさあ、中々家にも寄り付きゃしないよ」
おりんさんのその言葉に頷きながら、常磐井様がこう仰いました。
「そうでしたね。おりんさんのお兄様は、確かこの街を取り仕切る火消しのと組の若頭で、歌舞伎役者みたいに大層鯔背な良い男だって評判でしたよね」
「いやあ、兄だけじゃあなく、と組の若い衆は皆んなキップの良い色男揃いでさ。ってまア兎に角、夜は提灯も行灯も手燭も、ウッカリしてたら火元になっちまうから、くれぐれもご注意を」
おりんさんがそう注意を促すと、
「ええ、分かりましたとも。と組の頭のお嬢様!」
常磐井様はそう仰って、安子様とお顔を見合わせて笑い合いました。
その笑い声がお聞こえになったのか、ぎぎぎぎ、と言う大きな音がして、漆喰の壁に丈夫に埋め込まれた分厚い土戸が開き、中から行灯の光が漏れ出ると、じゃらりという筥迫の銀の房の音と共に、御吟味方(選出委員)取締御後見(副会長)の大典侍様のお顔が拝見出来ました。
「お約束の暮六ツ半(午後7時)をとうに過ぎておりますよ。皆様もうお揃いで御座います」
<歯磨>
安子様と御吟味方の面々が、窺書(アンケート)の御開票作業に勤しんでいらっしゃったのと同じ時分、五ツ半(午後九時)過ぎの事に御座います。
安子様のお屋敷の寝室では、安子様が御出立された時にはすでにお休みになって居られた花子様の右横の御布団に、晩酌が終わった御夫君が、大きな鼾をお掻きになりながら、ぐっすりと眠りについておられました。
太郎君は、居間の円卓の上に、安子様が並べて置かれた三本の房楊枝(歯ブラシ)が、三本とも使われずにそのままになって居るのをご覧になりました。
「ああ、お父様も花子も、歯を磨かないで眠ってしまわれた。お母様があれほど念押ししてお出掛けになったのに」
そうひとりごちると、三本のうち一本の房楊枝をお取りになり、行灯の灯りを頼りにお勝手の流しの所へ行って、「丁字屋歯磨」と書かれた袋から房楊枝に歯磨き粉をつけ、その房楊枝を御自分のお口に含まれると、大人用の歯磨き粉の辛さに時折眉を顰めながらも、七つのお子の小さなお手で、いつも安子様が仰っている通りのやり方で、一生懸命歯を磨かれたので御座います。
太郎君が寝室に戻られ、御自分の御布団にお入りになろうとした、その時の事でした。
真ん中の御布団の小さな膨らみが、がさがさと動いて、中から顔を涙でぐしゃぐしゃにした数え三つ(2歳)の花子様がお顔を出されたのです。
「おかあたま、居ない。お兄たまも居ない」
太郎君のお顔を確認なさると、花子様は堪り兼ねたのか、大声でわああんと、火が着いた様に泣き始められました。
そのご様子をご覧になったお優しい太郎君は、
「分かった、分かったからお泣きなさるな。どれ? お腹が空いた? それともお襁褓かな? 替えて上げようか?」
こう仰って、御自身も七つでまだお小さく、泣きたいお気持ちになるのもぐっと堪えて、妹を懸命に宥めようとなさいました。
「ちがう、ちがうの。お襁褓じゃないの! 花ちゃんはひとりで厠で出来るもん!」
こうむずかる花子様でしたが、流石に数え三つ(2歳)の花子様を、御一人で暗い中、お庭を抜けて土間の先にある厠まで行かせる事は無理であろう、そうお考えになった太郎君は、先ず横の御布団の中で鼾を掻いて寝ておられる御父君にお声を掛けられました。
「お父様、お父様! 花子が厠に行きたがって居ます。どうしたら良いでしょう?」
太郎君がお父君に一生懸命お声掛けをなさっても、お父君は一向にお起きになる気配が御座いません。仕方が無いので、太郎君はお父君の御布団の上から、七つの小さなお体から出せる限りの力を出してお父君を揺さぶりましたが、
「ん? あ?」
と寝ぼけて二言ほど呟いただけで、また寝返りをして大鼾で寝込んでしまわれました。
そうこうして居る間にも花子様の泣き声は鳴り止まず、太郎君はほとほと困り果ててしまわれました。
ああ、これはもう私が花子を厠に連れ出すしかないか、そう観念した太郎君は、
「花子、分かった、分かったから。私が今厠に連れて行くから、どうか泣かないで」
太郎君は、こういう時にお母様が居てくれたらどんなに、と思う一方、普段お母様は寝ていらっしゃる時ですら、意識のどこかを常に我々子供達に向けて居て下さるからこそ、こうした状況になっても、直ぐに起き出して対処する事がお出来になるのだな、と感謝の気持ちを覚えたのでした。
「ほうら、花子。今灯りを用意するから、あと少しだけ待って居られるね」
太郎君は、普段安子様がされて居るやり方を見様見真似で、行灯の方に行ってそれを静かに開けると、下の引き出しに入って居る手燭を取り出して手に取り、灯芯に火の灯って居る行灯の灯明皿から、消えない様にそっと手燭の蝋燭の方に火を移されたので御座います。
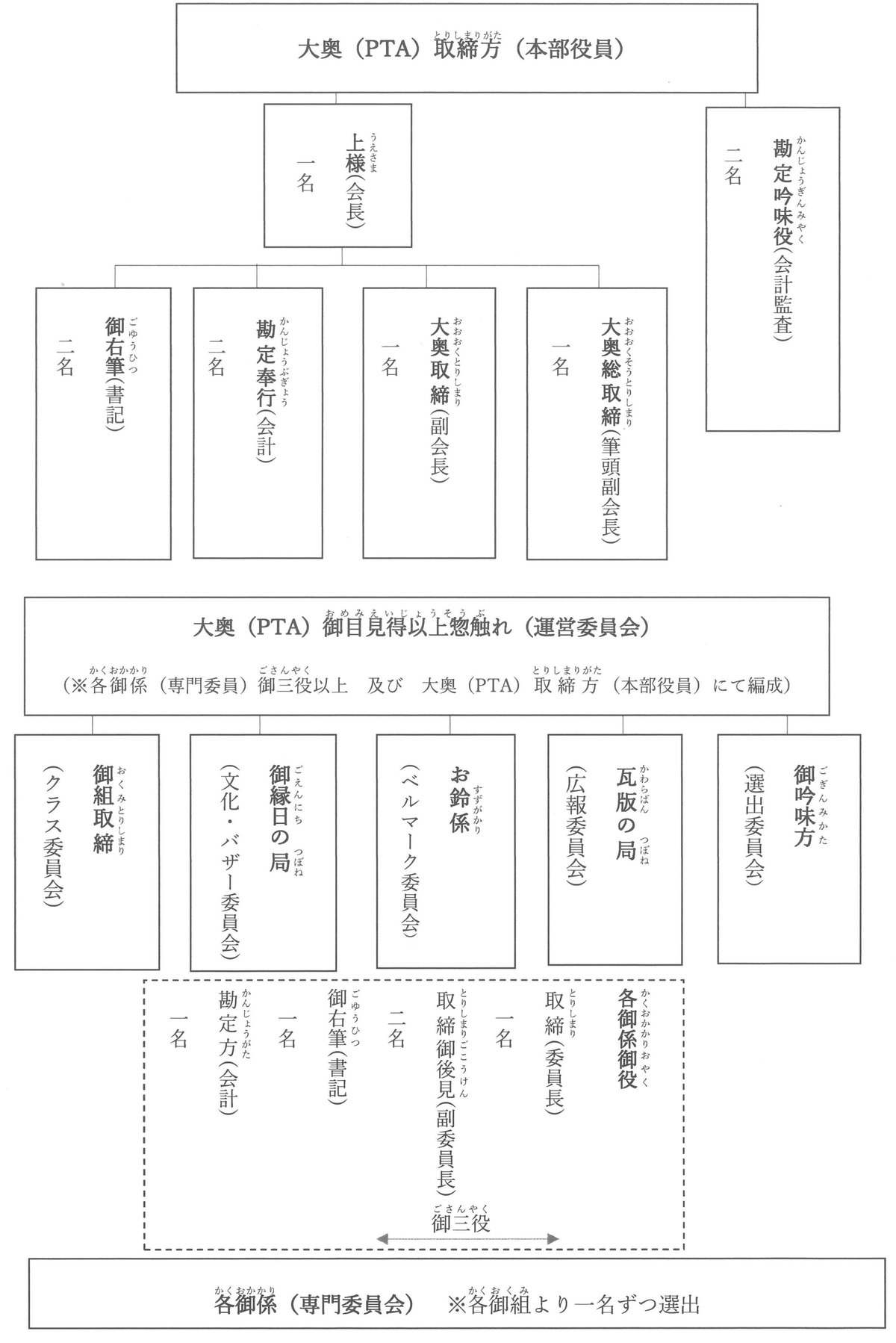
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

