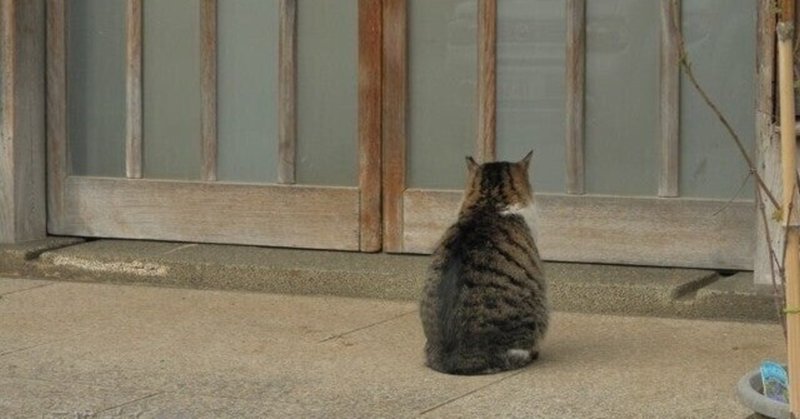
大学院進学(文系)について〜修士編〜
大学院進学の相談を受けることがときどきあります。
今回は、私の大学院進学の経験についてお話したいと思います。
進学の経緯
私の専門分野は「日本語学」です。
学部を5年(1年休学してタイで日本語TA)で卒業し、そのまますぐに大学院に進学しました。
日本語教師でやっていくなら、大学院を出ておいた方が仕事がみつかるよ!
そんな話を聞いていたのが、大学院進学の理由でした。特にこの時点では研究者を志望していたわけではありませんでした。
大学院選び
当時所属していた学部の上の院に進学する、いわゆる内部進学でした。(内部進学でももちろん院試はあります。)
日本語学の研究をしながら日本語教育も学べる大学院はそう多くはありませんし、学部時代から教育環境にはとても満足していたので、特に他の大学院への進学も考えなかったのですが、今思うと、もうちょっと他も見てみてもよかったんじゃない?とも思います。笑
内部進学した私が言うのもなんなんですが、大学院を選ぶときに気をつけた方がいいポイントとして以下の3点をあげます。専攻分野、指導教員など当たり前の項目については触れません。
1. 博士後期課程を有しているかどうか
修士号を取得できる課程は、修士課程と名がつくものと、博士前期課程と名がつくものがありますが、一般的に後者は博士後期課程を有した、博士号まで取得できる大学院です。
博士号まで取得を考えているならば、博士前期課程に進学した方がいい、というわけです。ちなみにお金の話になりますが、博士前期課程から博士後期課程にそのまま進学すると、入学金がいらないケースが多いと思います。
2. 所属学生の研究テーマ
指導教員の研究テーマはもちろんなんですが、所属学生の研究テーマを見ることで、その大学院でどんな教育を受け、どんな研究ができるのかが見えてくると思います。大学のシラバスを見るのも参考になります。ただし、シラバスどおりの授業が行われているとは限らない点は考慮すべきだと考えます。
また、所属学生の研究テーマを見ることで、教員の研究テーマに関連のある分野で研究している人が多いのか、そうではない人もたくさんいるのかがわかります。もちろん、入学前に指導教員と研究テーマについて相談した上で入学を決めた方がいいのですが、指導教員がどのようなテーマで面倒を見てくれるのか、を探ることができます。
3. 修了生の進路
修了生がどのような場で活躍しているのかを見ることはとても大事です。大学院に行った後、自分がやりたいと思っている分野で現在活躍している人の経歴を見ることで確認することもできますし、実際に事前の研究室訪問などで尋ねることもできると思います。
仕事を紹介してもらえたり、学会などの場で他の研究者を紹介してもらえたりと、OB・OGの持つネットワークに入れることは、その後の活動においてとても大事になってくると思います。
お金の心配はしなくてもいい
大学の学費は親が払うべきだと考える人も多いのか、
JASSOなどの奨学金を借りることは、みっともない、恥であると考える人もいるようです。
しかし、そんなことは全くなく学生自身が支払うか、親が支払うか、という違いだけ。
そう考えると、親に支払ってもらう方がみっともない、とも思えてきますよね。
大学院の学費になると、なおさらだと思います。
奨学金を借りて、卒業後ゆっくり返していけばいいのです。無利子であれば、早期返済も不要です。
私は、修士の院生の頃、JASSOの第一種貸与奨学金と民間の給付奨学金の2つを受けていました。ちなみに、大学院の学費は1ヶ月あたりで考えると約5万円でした。
<1ヶ月の収入>(参考)
アルバイトの給与 約70,000円
JASSO第一種貸与奨学金 88,000円
民間給付奨学金 70,000円
計 約230,000円
結果的にJASSOも返還全学免除になったので、これがそのまま収入だったことになります。
これ、実は修士号取得後最初に働いた、海外の大学の月給よりも高いです。笑
お金が心配な人ががんばった方がいいこと↓
1. 奨学金をとる
返還不要の給付奨学金がベスト!必ず応募しましょう。
そして、JASSOの第一種を狙いましょう。ひとり暮らしで家計も独立しているならば、大事なのは成績です。
奨学金ではありませんが、学振をとれたらそれに超したことはありませんね。
2. 業績と社会活動
JASSOの第一種の返還免除を狙うのに必要なのは、第一に学内の成績、そして研究業績や、研究に関連した社会活動です。どのような項目で加点されるかは、各大学の学生課に問い合わせれば教えてくれると思います。
3. 学内のプログラムをしっかり調べる
各大学独自の奨学プログラムがあります。受給資格のあるプログラムには積極的に応募しましょう。
そして、この1、2、3の枠は大学によって持っている数が違います。いわゆる有名大学に入るのには、このような権利を得やすいというメリットはあるかもしれませんね。
進学の目的をはっきりさせる
ただ何かを学びたいだけであれば、科目等履修生などの制度を使って十分に学ぶチャンスがあると思います。
正規学生になって、何を学んでどんな研究がしたいのか、その目的はしっかりと考えた方がいいでしょう。
身の回りに相談できる人がいるのであれば、どんどん相談して対話を通してその目的を明確化していくのがいいと思います。
入学後に目的が変化してもいいのではないでしょうか。
大事なのは、常に目的を意識することだと思います。
就活の空気に飲まれない
学部からストレートで院進学を考えている人には、もう本当にこれだけは声を大にして言いたいことです。
まわりがいわゆる新卒の就活を開始すると、それまでは院進学を考えていた気持ちが揺らぎ始める人は多いように思います。
私も就活サイトに登録したことはありますし、説明会を受けようとしたことはありました。(結局受けていません。)
「新卒ブランド」を失いたくないと本気で思うのならば、就活に転向すればいいと思いますが、修士を出るタイミングでももう一度「新卒ブランド」を手に入れることはできると思いますよ。
1つ前の「目的」ともつながりますが、何のために院に行きたいのかを明確に持つことができていれば、就活の空気に流されることもないのではないかと思います。院進学は仕事してからでもできるし、と言っていた人で実際にその後院進学をした人はほとんど見たことがありません。
以上、どちらかというと心得のようなものが多くなってしまいましたが、大学院進学(文系)〜修士編〜について書いてみました。
修士編というからには今後博士編も書きます。(博士編が知りたいと言われたのがこれを書こうと思ったきっかけでもありました)
学部進学以上に、分野によって勝手が異なるのが大学院ですので、ここに書いたことが当てはまらないケースも多いとは思いますが、1つの参考にしていただけると幸いです。
もしよければ、投げ銭いただけると、今後の励みになります。
(有料部分に記事はありません)
ここから先は
¥ 100
よろしければサポート、お願いします。
