
2022年映画ベストテン
1.『クライ・マッチョ』(クリント・イーストウッド )

イーストウッドが監督しててイーストウッドが主演をしているというだけで迷うことなく一位にした。おもしろいとかつまらないとかいう尺度ではないのだ。イーストウッドかそうでないかというのが問題なのだ。食卓の場面は手話で喋る幼い末妹の要望をイーストウッドが誰よりも早く水差しを取って叶えるのだが、この事後的に動いているにもかかわらず誰よりも早く挙動を終えているという完了的な動作はセルジオ・レオーネと共同した西部劇の諸作だけでなく、ドン・シーゲル『ダーティハリー』のクライマックスをも想起させる西部劇的、あまりに西部劇的、つまりは映画史的なアクションであり、イーストウッドがなんでもなくそれを行っているということがファンにとってはあまりに感動的だった。そして『ダーティハリー』といえば、事故の場面の直後に銃を向けられるシーンはハリーとさそりの位置が反転した『ダーティハリー』的クライマックスであり、そのような位置の不利をあっさり無視する闘鶏の羽ばたきはとてつもなく痛快なイーストウッド的事後のアクションだったといえる。イーストウッドの手は、鶏の羽なのだ。
2.『ケイコ 目を澄まして』(三宅唱)

ジムのメンバーが連れ立って帰るとき、岸井ゆきのに「お疲れ様」の手話を続けざまに繰り出し、岸井もそれを返す。岸井のアクションが伝播する様子は後半でリング上で岸井ゆきののミット打ちの際のフットワークを眺めていたジム生がコーチにアドバイスを貰いながら、それを模倣するという具体的なショットとして映されるが、そういったことはすでに起こっていたことがこの手話で分かる。ボクシング・ジムという反復と模倣のための空間に伝播という要素がさりげなく加わった瞬間、というかもともと内包されていたとわかる瞬間の感動。あと、多くの人が言及する岸井ゆきののクロース・アップ(踏切のシーンが特に言及多い)は、三宅唱がPOPEYEにて連載している「三宅唱のPOP-EYE CINEMA」で取り上げられたパブロ・ラライン『スペンサー ダイアナの決意』のクリステン・スチュワートの顎の震えに相当するものがあると思うが、こちらは未見なので後悔してる。
3.『MEMORIA メモリア』(アピチャッポン・ウィーラセタクン)

映画本編そのものよりも劇場体験を重視してこの順位に置いた。覚醒→半覚醒→入眠のプロセスを繰り返しながらの鑑賞。爆音で目が醒めるたびに画面に変化あったりなかったりなので、夢か映画か区別に戸惑い、しばらくするとまた瞼を閉じてしまうものの、そのような画面の非連続性に対し、音響の連続性は半覚醒の状態だと知覚できるままだというのが稀有な体験だった。追跡する犬、横移動撮影、バンドの演奏、ボルヘス「記憶の人、フネス」的世捨て人、宇宙船は確かに目撃した。再建してないので、これ以上感想は書けない。ちなみに国際芸術祭「あいち2022」で公開された『太陽との対話(VR)』は見れなかった。「日本のクリエーターたちとの国際共同制作のもと、初となるAR/VR技術を使った体験型パフォーマンス作品を制作。」とのこと。機会があれば見たい。見ときゃよかったなー。
4.『グリーン・ナイト』(デヴィッド・ロウリー)

斬首の光景ワンカットから始まる転がる首の大盤振る舞いに嬉しくなってしまう。首の転がりっぷりではエリン・ケリーマンのそれがボーリング球のようで最も素晴らしかった。原作にあたるパール詩人による詩はトールキンの翻案バージョンで知っていたのでデヴ・パテル扮するガウェインの緑の礼拝堂での振舞いにはとてつもなく驚いた。それから約10分ほどにわたるサイレント映画的なシークエンスは『A GHOST STORY/ア・ゴースト・ストーリー』ですでに見せていたものの、ロウリーの演出力の高さを堪能しつつ、どのような結末を迎えるのかというサスペンス=宙吊りの演出としても有効に機能していた。デヴ・パテルのあのクロース・アップを見て、感動とともにこの映画のガウェインにほかにふさわしい俳優はいないとあらためて確信した。長めの記事を書いたのでそっちも参照してくれるとうれしい。
5.『ザ・ミソジニー』(高橋洋)

リモートによる舞台登壇でいみじくも中原翔子が言っていたように「整備不良のジェットコースターのような映画」という形容がなによりもふさわしい。森のはずれの洋館で繰り広げれられる演劇的降霊術、あるいは降霊術的演劇が呼び起こす恐怖から一転、霊的国防ならぬ霊的攻防のオカルト活劇化。カーペンターみたいと言っていいかもしれない。円と切断をめぐるアクション編集のキレの良さが素晴らしい! ちなみに今回も『霊的ボリシェヴィキ』を一緒に観たシネフィル2名と一緒に鑑賞したが、隣にいたのが前作はイマイチ派の方だったので、ジェットコースターが下りに差し掛かってからの展開にはスクリーンと横の座席のどちらにハラハラすればいいかのわからず、終始異様な緊張感が持続した鑑賞となった(感想をお聞きしたら面白かったと言っていたので、製作側でもないのにホッとした)。ここからは余談だが、中原翔子扮するナオミが魔除けとしてコレクションした女性たちのポートレートはドイツの美術史家アビ・ヴァールブルクによる晩年の図像的プロジェクト『ムネモシュネ・アトラス』を想起させる。ヴァールブルクはイタリアにおけるファシズムの勃興をその眼で目撃しており、ファシスト党員の行進に「古代の現前」を目の当たりにしたのだと田中純『アビ・ヴァールブルク 記憶の迷宮』に書かれているが、ファシズムの語源は遡るとラテン語「ファスケス」とされ、これは斧の回りにロッド(短杖)を束ねたものを意味する。ファシズム、斧、あるいは古代的な要素は『ザ・ミソジニー』の要所を飾るが、黒いパネルに複数の図像を並べた『ムネモシュネ・アトラス』にめ同様のテーマを扱ったパネルが存在する。田中純『イメージの記憶:危機のしるし』によれば「(…)ヴァールブルクは、ヨーロッパ数千年に及ぶイメージ記憶の歴史を図版で再構成しようとした晩年の『ムネモシュネ・アトラス』をはじめとする図像パネル群のなかで、ペルセウスのイメージを繰り返し取り上げている。(…)「首狩り」のイメージは、聖書のサロメやユディットといった女性による男性の斬首のモチーフとしてヨーロッパで数多く描かれており、ヴァールブルクはそうした系列にのみならず、「頭を手で掴む」モチーフ一般にまで拡げて、この身振り表現の執拗な残存を『ムネモシュネ・アトラス』で追跡している。」。「頭を手で掴む」もまた『ザ・ミソジニー』において欠かすことのできない要素であることは言うまでもない。
6.『春原さんのうた』(杉田協士)

飯岡幸子の撮影による端正なスタンダード・サイズの画面とどこか対立するようなスマートフォンによる撮影行為と登場人物たちの口元を覆うマスクという矩形の存在にどこか落ち着かない気持ちや勿体ないという思いのまま、スクリーンを見つめていると、キノコヤの二階の外壁にマスクの無い荒木千佳の姿が突然に上映されて驚いた。アスペクト比に無理やり対応させるならビスタ・サイズになるであろうその上映はトリミングだと思っていた行為がじつは捨象された世界を一部分ながらも捉え、拡げる行為として反転し、その瞬間に言葉にできない感動に襲われた。建物の壁面への投影という立体的な行為は、劇場におけるスクリーンへの投影という平面的な行為との対比のようにも思え、ここにも「拡げる」という作用がみえる。余談だが、ちくま文庫『春原さんのリコーダー』の栞文や花山周子「解説にかえて 混沌から浮き上がるリアル」が『春原さんのうた』のサブテクストとしても機能している。「東の「来て」はそれを聞いてしまったものの心に直接に触れて来る。」という花山の文章は杉田協士の映画について語っているかのようだ。
7.『みんなのヴァカンス』(ギヨーム・ブラック)

3人の男の物語が的確なショットで簡潔に語られるが、最も魅力を感じたのは風景のようでありながら活き活きとショットのなかに存在する子どもたち。光、風、水、樹木と親しみながらよく笑う「子どもたちの自然」と呼びたくなるようなこの状態がまさしく「ヴァカンス」だろう。この「ヴァカンス」状態は、大人たちにとっては冒頭の夜の川岸でのダンスパーティやラストのカラオケの場面いがいでは終始訪れない。というか、作り出そうとして失敗し続け、不意にイイ感じになるけど(男女がイイ感じになるよりも、男同士に友情が生起するようなイイ感じ)、それを掴み損ねてまた失敗するみたいな展開がギヨーム・ブラックらしくて笑える。たぶん、子どもに「ヴァカンス」を与えるような行為(歌とかコントとか)が閾値を超えると、大人にも「ヴァカンス」が伝播するんだと思った。悲観的なニコラ・ピエトリが赤ちゃんの世話をしてたらなんかハッピーになってたのもそういうことかもしれない。でも、子どもってわざわざ与えられなくても自然に「ヴァカンス」を発見する存在だし、あんまり関係ないかもしれない。
8.『さかなのこ』(沖田修一)

さかなクンという今ではすっかりお茶の間にお馴染みの人物も、よくよく考えてみればかなり奇矯な人物であることには間違いなく、そのことを再認識させるようなのんというキャスティングにまず唸った。全体的にキャスティングが良く、この映画で最もイヤな役を演じた島崎遥香なんかも短い出番で忘れ難い存在感を示す。幼少期を演じた西村瑞季も素晴らしく、捕まえたのか捕まえられたのか、身体に蛸を張り付けたまま海から上がってくる姿には笑ったし、このエピソードの顛末にあたる三宅宏城のアクションにも大爆笑。この場面だけでも稲生平太郎が提唱する蛸映画であることは間違いない(詳しくは『映画の生体解剖 vs 戦慄怪奇ファイル コワすぎ!: 映画には触れてはいけないものがある』を参照)。全編にわたって水槽という魚を見るためのフレームが頻出し、それに囲まれて生きてきたのんが柳楽優弥の誘いによってテレビというフレームの中の住人となる終盤のあざやかな反転と、そのフレームすら逸脱するラストにはさわやかに感動する。柳楽優弥はのんを魚と看做しているからこそテレビというフレームの内に誘ったのだが、むしろそれによってのんは魚になりフレームの外へと泳いでいく。こうして書くと、スチュアート・ゴードン『DAGON -ダゴン-』そのものなラスト。
9.『ブラックボックス:音声分析捜査(ヤン・ゴズラン)
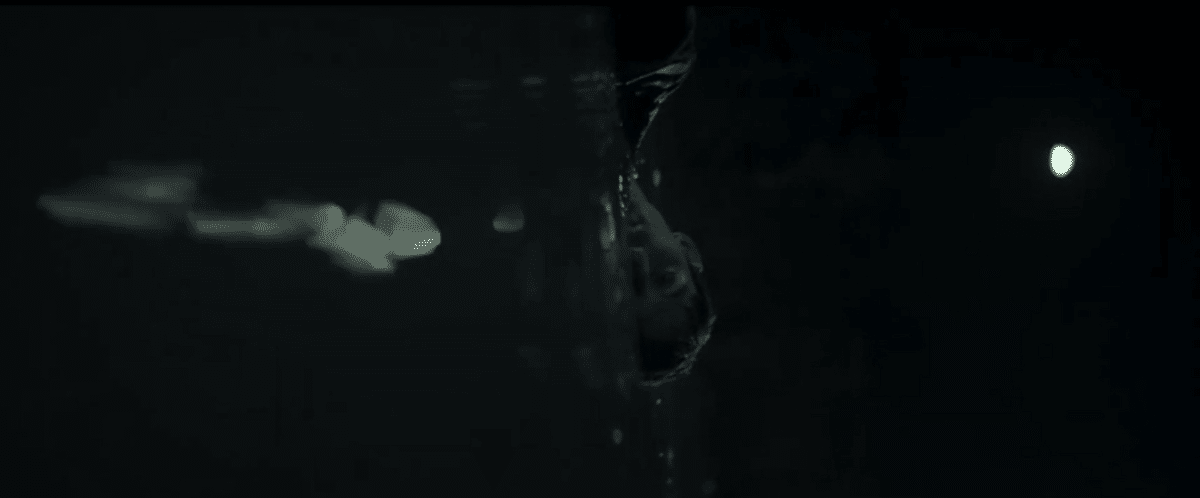
あら、これはマイケル・マン『ブラックハット』へのオマージュではないかしら? とオープニングを見ながら思ったが、墜落事故の真相があきらかになるシーンでマジでオマージュしてたの? というようなショットが出てきてビックリ。そこらへんはまあ冗談で済むとしてポランスキー『ゴーストライター』やフィンチャー『ゾディアック』には私淑してるのはまず間違いなく、結構そのままな演出なのだが、ちゃんとサスペンスとして機能してて良かった。そういえば、最後に流れる映像は主人公への個人的なメッセージ部分は省略されてるので、あの映像も問題となった音声と同じく編集を施されたデータであり、黒幕と主人公側は手段としてはまったく同じ行為をしているのがおもしろい。
10.『ひつじのショーン スペシャル クリスマスがやってきた!』(スティーヴ・コックス)

ビッツァーが事故的スキージャンプに巻き込んだ雪だるまと空中デート的な飛行が始まったかと思いきや即座に電柱に激突し雪だるまが爆散するシーンに爆笑(このとき流れる「ウォーキング・イン・ジ・エアー」を使ったギャグにも笑った。ちなみに予告編で確認できる)。開かれた窓と風に靡くカーテンの演出は細田守『おおかみこどもの雨と雪』と比較しても遜色無しで大満足。クリスマスの映画だということをきちんと意識した展開なのも正しい。カーテン演出に限ればマイケル・チミノ『シシリアン』なんかもちょっと思い出した。あと午前十時の映画祭で『ウォレスとグルミット』(『チーズ・ホリデー』/『ペンギンに気をつけろ!』/『危機一髪!』)を観たときに思ったけど、アードマン製作の作品は30分くらいだと全編がほぼ活劇で占められるのでこれくらいの尺が活劇としてはいちばん良いのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
