小西議員の言う通り、参議院の憲法審査会は毎週開く価値がない2023/4/1Newsweek他日本国憲法関連の記事。
2023年4月20日うちは考え方変えて外国人参政権導入に賛成して二重国籍容認にすることにするよ。
個人的な理由と日本だけが二重国籍認めてないのはおかしいのは事実なのと
戸籍制度が戦争目的に作られた制度なのは事実らしく選択的夫婦別姓推進して戸籍制度廃止したほうが戦争放棄と生得的生物学的女性の生きづらさ解消の観点からみて良いみたいだから。
自公維新国民民主ら緊急事態条項ありのナチスの手口自民党改憲草案改憲勢力が憲法違反行為に利用する憲法審査は行われてますが日本国憲法を活かす憲法審査はされてないから憲法審査会は開く価値なし。


立憲民主党の小西裕之参議院議員が、憲法審査会の毎週開催は「サルがやること」と述べたことで波紋を呼んでいる。言葉の妥当性に関心が向くばかりで、肝心の参議院の憲法審査会の毎週開催についてはほとんど議論がなされていない。そこで筆者は、参議院の憲法審査会に関して、昨年行われた第208回国会~第210国会までの議事録を全て読んでみた。結論としては、参議院の憲法審査会は毎週開催する必要がない、全く内容がない会議だった。【藤崎剛人(ブロガー、ドイツ思想史)】 【画像】「日本の無人島を買った」としている中国人の女 憲法審査会の議論 憲法審査会は、「(1)日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査、(2)憲法改正原案、日本国憲法に係る改正の発議又は国民投票に関する法律案等の審査を行う機関」と位置づけられている。しかし、議事録からみられるのは、殆どの委員は、憲法学の基本的な知見を持っておらず、これまで積み上がってきた憲法をめぐる議論に基づいて法律を論じる能力はないということだ。 たとえば昨年の主な議題のひとつは参議院の選挙制度をめぐる問題だった。参議院は都道府県別に選挙区を設置していたが、一票の格差を解消する目的で、2015年から一部の都道府県を「合区」として選挙を行っている。しかし、参議院議員は地方代表としての性格があり、一都道府県に最低一人の議員を保障すべきであり、これを憲法に書き込むべきだ、とする議論がある。 憲法審査会でもこの議題が論じられるのだが、各々が言いたいことを主張しているだけで、さっぱり議論が進んでいないのだ。たとえば、参議院の選挙制度を一票の格差問題の例外とする改憲に賛成する委員は、日本の地方の惨状を解説し、「合区」は解消しなければならないと述べる。しかしこれは憲法論とは呼べない。 12月7日の会議では、小西洋之委員が、6月8日に行われた会議での参考人の意見を踏まえ、憲法に平等権が原則として書き込まれている以上、一票の格差を無視する制度を憲法に書き込むのは憲法の改正限界の問題があり、「合区」解消は国会改革によって行われるべきではないかという指摘をしているが、そのような憲法上の問題を克服するための具体的な議論は改憲派委員からは全く出てこないし、参考人の意見などなかったかのようにゼロから議論がスタートしてしまう。 それどころか、同じ12月7日の会議で山谷えり子委員は、参議院の選挙制度改革がテーマの会議にも拘らず、ウクライナ戦争に触れながら憲法九条の問題について演説し、主題である選挙制度の話題には全く触れなかった。これには同僚の自民党議員からも苦言を呈されたが、憲法審査会を自分の独演会の場と勘違いしている議員もいるようなのだ。 具体的な憲法論が行われない そのような独演会の場と化しているのが、第208回国会と第210回国会でそれぞれ一回ずつ行われた「憲法に対する考え方について意見の交換」だ。この会議では文字通りそれぞれの委員がそれぞれの「考え方」を述べるばかりで、議論の場にはなっていない。それぞれの委員が語っている内容も、先述の「合区」問題を初め、自衛隊、緊急事態、デジタル化、憲法裁判所、道州制など、自分が思いついたこと、あるいは自分の党の政策をただアピールしているだけ、といった様相となっている。中には憲法に日本の伝統を書き込もうとする西田昌司委員のように、近代憲法の根本を理解していない意見を述べる委員もいる。 また、「日本国憲法は制定以来改正されていないのだから改正されなければならない」「憲法の時代に合わせたアップデートを行わなければならない」など、憲法審査会という専門的な機関で述べるにそぐわない抽象的な意見を述べる委員も多い。これが、憲法審査会が設置された初めての会議で出てくる意見なら、まだ理解することはできる。しかし各国会の会期ごとに、これまでの議論がリセットされたかのような意見交換を繰り返す意味はあるのだろうか。
なぜ議論が進まないのか
これに対して、護憲派あるいは改憲に慎重な立場からは、「憲法を活かす」(吉田忠智委員など)ような審査会にすることが繰り返し要求されている。 たとえば福島みずほ委員は、「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制についての広範かつ総合的な調査」という審査会の役割はいまだ行われたことがないと指摘し、違憲が疑われるような法制について審議することを要求している。確かに、建設的な改憲論を始めたいのであれば、まずはそのような現行法制についての具体的な調査から始めるしかないと思うが、このような要請は棄却され続けているようだ。 憲法審査会の議論が進まない原因は、山添拓委員が繰り返し述べているように、国民の間に憲法を改正する機運が醸成されていないからだろう。だとすれば、小西議員が主張するように、毎週開催するのは無駄ということになるだろう。
日本学術会議は18日、東京都内で2日間にわたって開いた総会で、学術会議法改正案の今国会への提出を思いとどまり、開かれた協議の場を設けるよう、政府に勧告した。 【写真特集】学術会議の勧告を説明する梶田会長 学術会議の勧告は13年ぶり。勧告は同法の規定に基づくもので、政府に対する最も強い意思表明となる。法的拘束力はないが、改正案提出を目指す政府に最後のカードを切った格好だ。 梶田隆章会長は「政府は勧告という形で表明する我々の強い思いを真摯(しんし)に受け止めて検討されることを期待している」と述べた。 総会では、内閣府が改正案の文案を示し、改正案の全容が明らかになった。 それによると、会員選考に第三者が意見を述べる「選考諮問委員会」の委員は学術会議外の5人が務め、会員選考では「諮問委の意見を尊重しなければならない」と定めた。 諮問委員の任命権は学術会議会長にあるものの、任命前に、首相が議長を務める政府の総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)の有識者らと会長が協議するとした。 また「中期業務運営計画」で、他団体との連携強化や国際交流など、今後6年間に学術会議が行う活動について目標や実施時期を定めるとした。学術会議は国の機関として存続することが決まっているが、3年後と6年後に、国の機関以外の組織とすることも含めてあり方を見直すことも明記された。 一連の問題は菅義偉前首相による任命拒否問題に端を発した。学術会議側からは、会員選考に第三者の介入を懸念する声が出ている。内閣府側は「(法改正で)政府の介入は一切ない」と説明したが、会員からは「不透明な形で介入される」「独立性を脅かす」など反対の声が上がった。内閣府側が「制度的な透明性を確保できないとすると、国の機関にとどまり続けることも難しい」とけん制する場面もあった。 学術会議はこの日、政府に対話を求める声明も出した。改正案に盛り込まれた選考諮問委の設置や中期業務運営計画の策定について「学術会議の独立性を毀損(きそん)する」と改めて指摘。「日本の学術の終わりの始まりとしてはならない」と訴えた。【鳥井真平、松本光樹】
2023/4/18(火) 16:04配信毎日新聞
政府が日本学術会議の組織改革の法案を通常国会に提出する方針について、日本のノーベル賞受賞者ら8人が連名で岸田文雄首相に対し「熟慮を求める」と2月に出した声明に対し、世界の自然科学系の61人のノーベル賞受賞者が全面的に支持するとした共同声明を出した。学術会議の総会で17日午後、梶田隆章会長が報告した。 【写真】日本学術会議の総会で、日本政府の法案提出の方針に、世界のノーベル賞受賞者61人からも憂慮が示された=17日、東京都港区 海外のノーベル賞受賞者による共同声明は4月13日付。元米エネルギー省長官のスティーブン・チュー氏(1997年物理学賞)らが名を連ねた。「私たち61人は、8人の日本人科学者が表明した憂慮と希望を共有する。科学は人類の崇高で知的な努力であり、その発展が人類の進歩と幸福の実現に不可欠。日本はアカデミアを通じて人類に貢献する国で、世界に知的存在感を示すだろう」と表明した。 日本のノーベル賞受賞者ら8人は2月19日付で、2020年の菅義偉首相(当時)による会員候補の任命拒否問題をきっかけに、「政府と学術界の信頼関係が大きく損なわれたままになっている」と憂慮。政府による法改正の検討について「学術会議の独立性を毀損(きそん)するおそれがあり、大きな危惧を抱く。単に内閣府と日本学術会議の二者の問題ではなく、学術の独立性といった根源的かつ重要な問題につながる」「政府は性急な法改正を再考し、学術会議との議論の場を重ねることを強く希望する」などと求めていた。
2023/4/17(月) 16:47配信朝日新聞
<フェミニストは戦争に反対します>
こんなメッセージを掲げるロシアの女性たちによる反戦グループのSNS(ネット交流サービス)に4万人以上の賛同者が集っているという。
ロシアでは、ウクライナ侵攻に反対の意思を表明するだけで逮捕される危険がある。女性たちはなぜ活動を続けているのか。【菅野蘭】
◇反戦メッセージ SNSに4万人の賛同 <将来、戦争が終わった後には(2月23日に軍人をたたえる祝日)「祖国防衛の日」が廃止されることを望む。(侵攻が始まった)2月24日は、殺害されたウクライナ人を追悼し、ロシアの戦争犯罪を忘れない日となってほしい> ロシアによるウクライナ侵攻から1年が過ぎた2023年2月25日、こうロシア語でつづった文面がインスタグラムに投稿された。アカウント名は「フェミニスト反戦レジスタンス」。 グループの中心の一人は、ロシア人作家で詩人のダリア・セレンコさんだ。政府批判の言葉や社会問題を書いた紙やボードを持って公共交通機関に乗る「静かなピケ」運動などをしたフェミニストとして知られる。 そのセレンコさんが、図書館や美術館など、ロシア国立の文化施設で働いた経験から書いた小説の邦訳が2月に出版された。「女の子たちと公的機関 ロシアのフェミニストが目覚めるとき」(エトセトラブックス)だ。 作品では「女の子」という表現が用いられている。ロシアの公的機関で働く人たちが、年齢やジェンダーも問わず「女の子」のようにひとくくりに扱われている、という状況を指す。「女の子」たちが、使い捨てられる労働力として働く中で社会への違和感を抱き、フェミニストとして目覚めていく様子を描いた21年の作品だ。 プーチン露大統領の写真を市民が出入りする各部屋に掲示するよう求められたり、「女の子」たちの行動が監視されたりしている様子も登場する。 翻訳したロシア文学研究者の高柳聡子さんは、ウクライナ侵攻が始まったとき、セレンコさんの小説に「戦争に向かう社会の空気が描かれている」と気づいた。 当時、セレンコさんは、反プーチン派指導者アレクセイ・ナワリヌイ氏を支持したフェイスブックの投稿が原因で逮捕されていた。刑務所内からSNSを更新し、侵攻開始とほぼ同時に出所。侵攻翌日の25日には「フェミニスト反戦レジスタンス」を発足させた。 発足当時は主要メンバーは1人を除き匿名だった。しかし、高柳さんは発足宣言の文体からセレンコさんが中心に動いていると確信したという。「女性たちが本気で反戦のために立ち上がったと感じた」と振り返る。 ◇激化する女性への攻撃とフェミニズム運動 逮捕などの危険もある中、なぜ反戦活動を続けられるのか。高柳さんは動機について「いま暴力を振るわれている人がいるのだから、救わなければという思いです。ドメスティックバイオレンス(DV)をなくす活動の姿勢と全く同じ」と説明する。 もう一つ重要なのは通信手段だ。反戦運動に参加するフェミニストたちは、ロシア発の通信アプリ「テレグラム」を利用してきた。秘匿性の高さで知られ、互いに連絡した証拠を残しにくい。ロシア当局の監視の目をくぐり抜け、ウクライナから避難してきた女性たちを支援したり、反戦のメッセージを発信したりしてきた。 高柳さんも活動への支援を考えた。しかし、対露経済制裁の影響で日本からは物資や金銭を送れない。代わりに彼女たちの活動を日本語で発信したり、記事を書いたりしている。「女の子たち」の出版も、出版社のサイトで紹介したところ、邦訳の要望が多数届いて実現した。 高柳さんによると、現在のロシアのフェミニズム運動は、10年代以降に文学と社会活動の両方で育まれたものだという。 1991年のソ連崩壊後に欧米の思想が受容され、フェミニズムの研究者が登場した。女性の文学も広く評価されるようになり、若い世代の作家や詩人が、旧来のロシア文学にとらわれず性の問題について書くようになった。 一方、ロシアでは13年に「非伝統的性的関係(同性愛)」について未成年に「宣伝」することを禁じる法律が成立した。17年にはDVを非犯罪化する法改正もあった。こうした情勢を背景に女性支援団体の活動が活発化し、フェミニズム運動にも火が付いたという。 「女の子たち」の著者のセレンコさんも、LGBTなど性的少数派の活動家たちの休息の場「フェムダーチャ」を運営していたが、脅迫などが相次いでやむなく閉鎖した。セレンコさんも現在はロシアを出国し、外からメッセージを発信している。 ◇「今こそ自分ごととして感じて」 「女の子たち」の日本語版への序文で、セレンコさんは深い後悔を吐露している。ロシアは14年にクリミアを併合し、そのころからウクライナ東部で起きた武力紛争に加担していた。しかし、ロシア国民を含め世界の各国もそれほど関心を払わなかった。当時から今のような厳しい非難があれば、22年からの戦争が起きることはなかった、との思いだ。 そうした罪悪感は、日本に住んでいる私たちにとっても決して人ごとではない、と高柳さんは感じている。政府は防衛費増額の方針を掲げ、23年度当初予算の防衛費も過去最大となった。気づかないうちに日本も戦争へ歩み出しているのではないか、と考えるからだ。 「大きな政治がそばにいたのに、そっぽを向かれていたから私たちは気付かなかった。政治は生活にダイレクトに影響しているのに、なかなか気付けない。彼女たちの後悔に私たちも学ばないといけない」
2023/4/17(月) 16:00配信「女の子」だから、抗議する プーチン政権下のロシアの女性たち毎日新聞
◆歴史に閉ざされた過酷な真実
[評]石井彰(あきら)(放送作家)
「厚生労働省は七日、シベリア地域で亡くなった抑留者のうち、新たに個人が特定された十九人の漢字氏名と出身地の県名を公表した…」(要約)
二月八日、本紙に十行余りの小さな記事が掲載されたのを覚えているだろうか?
戦後七十五年たって死亡した人名が特定されるほど、約五十七万五千人にも及ぶ日本人抑留者の実態は、歴史という凍土に閉ざされている。実は抑留者の中に、千人近い従軍看護婦や電話交換手、民間人らの女性たちがいた事実はほとんど知られていない。
二〇一四年八月、NHK『BS1スペシャル 女たちのシベリア抑留』で、ずっと沈黙してきた女性たちの証言を掘り起こしたのが、番組ディレクターの著者だった。
番組を見た時の衝撃は忘れない。まさか女性たちが零下四〇度を越える寒さと飢餓に苦しみながら、収容されていたのを知らなかったからだ。
およそ六万人が亡くなるほど抑留は過酷を極めた。しかも女性である。従軍看護婦たちは、凶暴な兵士から身を守るため「自決用の青酸カリ」の小瓶を渡され肌身離さず持ち歩いていた。彼女たちは青酸カリの恐ろしさを知っていた。敗戦後に病院が撤退する時に動けない兵士に注射する現場に立ち会った人もいた。
著者は、ほとんど資料のない抑留された女性を捜して訪ね歩く。本人たちがのこした手記や回想録を読み込み、膨大な資料の中から女性たちの存在を確かめ、現地へ出向いて目撃者や墓を捜す。彼女たちはカメラの前で重い口を開き始めた。そこで語られたのは時計もカレンダーもない、いつまで続くかわからない収容所生活の中で励ましあい、生きることをあきらめなかった凜(りん)とした姿だ。
テレビ番組では時間の制約で登場人物たちのディティールは省かれることが多い。カメラで撮れなかったことは使えない。だから本書は五年もかけて書かれた。
語りたくない、でも誰かが語らなければ、なかったことになる戦争の真実が、本書にはくっきりと刻まれている。
(文芸春秋 ・ 1870円)
1976年生まれ。番組制作会社「テムジン」ディレクター。
◆もう1冊
スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ著『戦争は女の顔をしていない』(岩波現代文庫
女たちのシベリア抑留 小柳ちひろ著
2020年3月1日 02時00分
◆20世紀の罪と罰を問う物語
[評]小野民樹(書籍編集者)
齢(よわい)八十を超えた映画監督、吉田喜重の書き下ろし長編小説は、一見無造作に並べられた四つのテキストからなるヒトラーの片腕の「極悪人」ルドルフ・ヘスと「わたし」の呪われた二十世紀の物語である。
テキストその一。北陸福井の十歳の孤独な少年の「わたし」は、生家の納戸の古新聞で、ヘスの名を知った。超高速戦闘機を操縦して単身英国に脱出し捕虜となった不可解なナチス副総統として。以来七十年、その名は「わたし」を呪縛し続ける。
物語の中心は、テキスト二と三。「わたし」が入手した二つの奇妙な文書、アメリカから流出したニュルンベルク裁判の終身刑宣告に至るヘスの自伝的回想手記と、ザルツブルク近郊の修道院の羊皮紙聖書に残されたヘスの恩師ハウスホーファー教授の息子の遺書である。手記には主語が欠落し、遺書には宛先がない。
二つの文書の空白を埋め、翻訳するうちに、一九八七年に自死したヘスのベルリンの監獄での四十年の孤独と、「わたし」の空虚な戦後が共鳴し、ヘスの最後の告白を書くことで、二人の奇妙な関係を終わらせたいと思い始める。テキスト四は「わたし」が代筆したヘスの遺書である。
最後に「わたし」は、ヘスに「罪」を宣告せねばならない。ミュンヘンでヒトラーの演説に心酔し、口述筆記した『わが闘争』がユダヤ人絶滅の根拠を与え、地政学の権威、恩師ハウスホーファー教授の生存圏理論がナチスの侵略を正当化したからか。ユダヤ人排斥を黙認し、妻がユダヤ人であった教授一家を守れなかったためだろうか……。
エジプトの故郷アレクサンドリアを捨て、ドイツ人として生きるべく旅立った十四歳の日、綿屑(くず)の舞う港の埠頭(ふとう)で一条の光に照らされた天使のような幼い兄妹の姿が、愛読した旧約ルツ記に重なり、無垢(むく)の日の象徴のように、獄中のヘスの悔恨を込めて甦(よみがえ)る。「わたし」が、ヘスに課したのは人間の原罪なのだろう。しかし、その罪は自死で償えるのか、評者は、そこに拘(こだわ)りつつ、二十世紀の罪と罰を問う大きな物語を読んだ。
(文芸春秋・3300円)
1933年生まれ。映画監督。映画『エロス+虐殺』、著書『小津安二郎の反映画』。
◆もう1冊
レニ・リーフェンシュタール監督のDVD『意志の勝利』(ハピネットピーエム)
2020年5月23日 02時00分東京新聞
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名 御璽
昭和21年11月3日
内閣総理大臣兼外務大臣吉田 茂国務大臣男爵 幣原 喜重郎司法大臣木村 篤太郎内務大臣大村 清一文部大臣田中 耕太郎農林大臣和田 博雄国務大臣斎藤 隆夫逓信大臣一松 定吉商工大臣星島 二郎厚生大臣河合 良成国務大臣植原 悦二郎運輸大臣平塚 常次郎大蔵大臣石橋 湛山国務大臣金森 徳次郎国務大臣膳 桂之助
日本国憲法
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
このページのトップに戻る
第一章 天皇
〔天皇の地位と主権在民〕
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
〔皇位の世襲〕
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
〔内閣の助言と承認及び責任〕
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
〔天皇の権能と権能行使の委任〕
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
〔摂政〕
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
〔天皇の任命行為〕
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
〔天皇の国事行為〕
第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
〔財産授受の制限〕
第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
このページのトップに戻る
第二章 戦争の放棄
〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
日本国憲法
日本国憲法(条文抜粋)
日本国憲法(昭和二十一年十一月三日) (抄)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
日本国憲法(条文抜粋)





■スイス公共放送とBBCの存在意義 スイスには4つの言語グループがある。ドイツ語、フランス語、ロマンス語、イタリア語。たとえば、ドイツ語グループはドイツの放送やメディアを利用する。人口が多いのでそれだけお金がかかったコンテンツを提供するからだ。他の言語グループも同じことをする。 したがって、スイス人なのに、ドイツ、フランス、イタリアの情報にばかり接して、自国の情報に接することが少ないという現象が起こる。スイスは頻繁に国民投票を行う国である。自分の国のことをよく知らないのでは政治参加できない。 4つの言語グループに対しスイスについての情報を与え、かつスイス人としての意識をもたせる公共放送が必要である。事実、2018年3月に公共放送の改廃を国民投票にかけたが、これまで述べた理由を基に71.6%のスイス国民は存続を選んだ。 実はイギリスも多言語国家で、イングランド、スコットランドは英語を使用するが、北アイルランドではゲール語、ウェールズはウェールズ語を使用する。BBCはこれらの4つの王国に対する放送サービスを充実させている。BBCはそれを公共放送たるゆえんの一つに挙げている。 世界には多言語、多方言国家が多い。これらの国は公共放送を必要としているといえる。 ■公共放送の要件は「民放ではなし得ない役割」 では、日本のNHKはどうか。まったく、このような公共性はないといえる。 法学者の近江幸治は「NHK受信料契約の締結強制と『公共放送」概念」(判例時報 No.2377)のなかで、このようにいっている。 ---------- 「公共放送」を定義することは至難であり、「公共放送」であるために是非とも必要な要件は何かという問いに対しては、おそらく、それが何でないかという消極的な答えしかなしえない。つまり、民放事業には十分果たしえない役割が公共放送には期待されているという答えである」(強調部近江)という。結局において、「民放ではなし得ない役割」を担うということになろうが、しかし、「民放ではなし得ない」ことなどあり得るのだろうか。 ----------
■受信義務規定を削除し、受信料も廃止すべき つまり、民放にはない公共性がNHKになければならないのだが、それは見当たらないという。だから、近江は、放送法第64条の受信契約義務をうたった条項は、あくまでそのようにしたほうがいいという訓示規定であり、しなければならないと強制する規定と考えるべきではないとする。 ところが放送法が改定されて、この4月から受信料不払い者に対して割増金を取ることになった。実質的に訓示規定が罰則規定に変わった。これは不当であるばかりか、時代に逆行している。 世界の趨勢は、放送は、公共放送であっても、広告を入れるなどして無料にし、ネットに移したコンテンツから従量制(見た分だけ払う)で料金を取る方向に向かっている。冒頭で詳しく述べたメディア状況は、日本だけでなく世界的に起こっているからだ。 日本も受信義務規定を削除し、受信料を廃止すべきだ。どうしてもとるというなら、イギリスがそうしているように、公共放送だけでなく、民放にも受信料収入を分配なければならないだろう。「公共の電波」を使う民放も、公共の利益になる放送サービスを提供しているからだ。 ---------- 有馬 哲夫(ありま・てつお) 早稲田大学社会科学部・社会科学総合学術院教授(公文書研究) 1953(昭和28)年生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。東北大学大学院文学研究科博士課程単位取得。2016年オックスフォード大学客員教授。著書に『原発・正力・CIA』『歴史問題の正解』『日本人はなぜ自虐的になったのか』『NHK受信料の研究』(新潮新書)など多数。


権力は潜在的にテレビ放送の力を自らに有利に使いたい野心を持っています。それを阻まないと放送の「自主・自律」は成り立ちません。日本のニュース番組などは政治の影響を受けやすくなっていないでしょうか。そんな問題意識で、『放送の自由』(岩波新書)を出版したばかりの川端和治弁護士に話を聞きました。
桐山 国連特別報告者のデビット・ケイ氏が二〇一七年に国連人権理事会にある報告をしました。日本の放送メディアの独立性を強化するため、独立した監督機関を検討する必要がある、などの提案でした。どういう問題点からでしょうか。
川端 政府が電波法七六条を、放送事業者に放送法四条違反の事案があった場合、総務相は三カ月以内の「停波」、つまり電波停止の処分ができると解釈しているからです。この制度が放送メディアの独立と自由に過剰な制約となっているととらえたわけです。同時に独立した監督機関がないと放送メディアに政府の干渉を受ける可能性が潜んでいると指摘しています。
桐山 そこに日本の放送メディアの弱点があると見抜いているわけですね。
川端 確かに現政権になってから放送局への行政指導の回数が増えています。また一六年には、当時の高市早苗総務相が政治的公平性を欠く放送をした放送局の「電波停止」に言及しています。一つの番組の中で公平性を欠いてもだめだと。
NHKと民放連が自主的につくった「放送倫理・番組向上機構」(BPO)の放送倫理検証委員会の決定第一号にはこんな趣旨の一節があります。「欧米民主主義国には政府から独立した規制機関が設置されているが、日本の場合はロシアや中国、北朝鮮と同様に放送メディアが公権力によってじかに監理監督される状態だ」と。
桐山 驚きの表現ですね。電波の権限が絡むと、行政の影響も受けやすいでしょう。一例がかんぽ生命保険の不正販売問題です。NHKの「クローズアップ現代+(プラス)」では一昨年に、その問題を番組で扱っていました。第二弾の放送が予定されていたのに遅れました。
かんぽの親会社である日本郵政側からの抗議があったのですね。そこの上級副社長(当時)は元総務省の事務次官。電波行政を扱う役所ですね。抗議のためか、NHKの経営委員会がNHK会長を厳重注意するという奇妙な結果になりました。
川端 NHK経営委員会は執行部を監督できますが、会長を厳重注意したなら、その議決があるはずで、その議事録は放送法で公表が義務付けられています。それが一年もたってから議事録ではなく議事経過なるものを公表したのですから…。おかしな出来事でした。
経営委員会の人事は両院の同意が必要で、もともとは野党も賛成する人を選んでいました。しかし、「安倍一強」の政治情勢の中では自分好みで、自分の意思を反映してくれる人を選んでいるようです。この経営委員会が会長を任命するので「政権が右というなら、左というわけにはいかない」という会長もでたわけですから。
桐山 放送と権力との関係は昔からですね。ドイツのナチスがそうですね。ラジオ放送でナチ思想や政策を国民に浸透させました。放送への政治干渉という忌まわしい歴史の教訓です。
川端 日本でも軍事用として電波が使われ、太平洋戦争下ではあらゆる戦争の報道が大本営に統括されます。戦果の捏造(ねつぞう)が行われ、放送は戦意高揚のプロパガンダの手段となりました。
桐山 権力には放送の力が有効だったかが分かります。戦後にできた放送法の理念はどうだったのでしょう。
川端 政府首脳や官僚に戦中の放送に対する反省がありました。占領軍は軍国主義体制や封建思想を除去するため、ラジオ放送を使います。実はこのときも検閲があったのです。一九四七年に新憲法が施行されたとき連合国軍総司令部(GHQ)が当時の逓信省と日本放送協会に放送法案の根本原則を伝えました。放送の自由、不偏不党、政府から独立した機関による監督などの重要な原則です。
川端 五〇年に成立した放送法は、国会で政府案が修正され「公安を害しないこと、政治的に公平であること、報道は事実を曲げないですること、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」-。この四原則をもってNHKも民間放送も規律することになります。この番組編集準則は後に「公安」の部分が「公安及び善良な風俗を害しないこと」に変わっています。
桐山 放送法四条ですね。問題はこの番組編集準則が放送事業者に対する法的義務であるかのように政治家が認識していることです。
川端 放送法の五九年改正当時、田中角栄郵政相は「準則および番組審議機関を設けて、放送事業者の自律によって番組の適正をはかる」と答弁しています。「その順守は公衆の批判に任せる」とも。つまり番組編集準則は自主的・自律的に考慮すべき指標ではありますが、法的義務でないことが明確になりました。放送事業者の自主的責務である倫理規定なのです。
桐山 「政治的に公平」という意味も常に両論併記で、それぞれ平等な時間を配分するということでもありませんね。
川端 与党の政策評価や野党の主張についての議論を公正に伝えることは、たとえその結果が一方に有利に働いたとしても、公平性や中立性を害したことにはなりません。与党と野党の主張を単に並列しただけでは、有権者が問題を理解したうえで選択するための材料を与えたことにもなりません。時間の量的平等を言うのでもありません。
桐山 放送法の他に電波法があり、この運用権限は総務相が握ることになっています。これが現在の「放送の自由」の問題につながっていますね。
川端 放送法四条に違反した場合、電波法の定める「停波処分」の対象になるかという問題ですが、実は立法当時はそういうつもりはなかったのです。立法担当者の回想などにもありません。四条の番組編集準則は倫理規定として立法されたのですから、停波という処分はありえません。しかし「椿発言」問題が起きたとき、政府は解釈を変更して「準則違反があれば電波法による停波処分の対象となる」と明言したのです。
準則にいう「善良な風俗」も「政治的に公平」もあいまいな規定ですから、政府が何を意味するのかをきめて強制できるということになれば、放送の自由が危機に陥ります。特に報道が「事実を曲げた」かどうかを政府が判断できるというのでは、報道の自由はないに等しいでしょう。
桐山 倫理規定と考えないと憲法問題にもなりえます。
川端 番組内容を政府の意向に沿って変更できてはいけません。法的強制力をもっているとするならば「表現の自由」を侵害する違憲の規定でしょう。多くの学説も政府によって準則が強制されるものでないと解しています。
<かわばた・よしはる> 1945年、北海道生まれ。東京大法学部卒。第二東京弁護士会会長、日弁連副会長を歴任。2007年から18年までBPO放送倫理検証委員会委員長。放送倫理を放送界に定着させた功績が認められ「第9回志賀信夫賞」受賞。近著に『放送の自由』(岩波新書)。
<「椿発言」問題> 1993年の総選挙で自民党が過半数割れをし、「55年体制」が崩壊した。このときテレビ朝日の椿貞良報道局長が「非自民党政権が生まれるように報道せよと指示した」と発言したと新聞報道され、政治的公平に反すると問題になった。
「放送の自由」の今は 桐山桂一・論説委員が聞く
2020年3月23日 02時00分東京新聞

「政治的公平」巡る放送法解釈の「変更」 礒崎陽輔氏の問い合わせが契機 総務相認める 文書の真贋は答えず 2023年3月7日 06時00分
松本剛明総務相は6日の参院予算委員会で、安倍政権下で放送法の「政治的公平」を巡る新たな見解を示したきっかけが、礒崎陽輔首相補佐官(当時)からの問い合わせだったことを認めた。立憲民主党の小西洋之参院議員が一連の経過を記した総務省の内部文書だと主張する資料の真贋しんがんについては明言を避けているが、その内容と符合する発言は一部確認されている。一連の経緯と事実関係を点検した。(佐藤裕介)
小西氏が公表した資料には、礒崎氏が2014年11月26日に初めて、放送法の「政治的公平」の解釈や違反事例などの説明を総務省に問い合わせてから、翌15年5月に当時の高市早苗総務相が従来の政府見解を事実上見直すまでのやりとりが時系列でまとめられている。
野党側が「報道の自由への介入だ」と批判しているのに対し、政府は否定。総務省の文書であるかどうかは、内容の不正確さを理由に明らかにしていない。だが、礒崎氏がツイッターに書き込んだ事実はある。
礒崎氏は14年11月23日の投稿で「日曜日恒例の不公平番組」に言及し「仲間内だけで勝手なことを言い、反論を許さない報道番組には、法律上も疑問がある」と指摘。24日には「放送法上許されるはずがない。黙って見過ごすわけにはいかない」と批判のトーンを強めた。具体名の言及はないものの、TBS番組「サンデーモーニング」を指すとみられる。
この時期は衆院解散の直後。それに先立つ20日には、自民党が在京テレビ局に対し、公平中立な選挙報道を要請する文書を出し、言論への不当な介入という批判が出ていた。安倍晋三首相(当時)は、自民党文書について問われ、放送法の規定を根拠に「公平公正は当然」と説明している。
小西氏の資料によると、安倍氏は翌15年3月に総務省から「政治的公平」の法解釈に関する説明を受けた際にも「現在の番組にはおかしいものもあり、現状は正すべきだ」と理解を示した。
最終的に政府は15年5月、それまで放送事業者の番組全体で判断するとしていた「政治的公平」について「不偏不党の立場から明らかに逸脱しているなど、極端な場合」は一つの番組だけでも判断できるという見解を表明した。
6日の参院予算委で立民の石橋通宏氏は「一握りの人間に放送法解釈がゆがめられた懸念がある」と追及した。岸田文雄首相は「総務省で(資料の内容を)精査する必要がある」と述べるにとどめた。
【関連記事】「放送の自由」の今は 桐山桂一・論説委員が聞く
「政治的公平」巡る放送法解釈の「変更」 礒崎陽輔氏の問い合わせが契機 総務相認める 文書の真贋は答えず 2023年3月7日 06時00分

総務省は7日、立憲民主党の小西洋之参院議員が公表した放送法の「政治的公平」の解釈を巡る78ページの文書について、内部文書であることを認め、公表した。文書には、2014~15年に安倍政権の礒崎陽輔首相補佐官(当時)が「政治的公平」の解釈などの説明を総務省に問い合わせてから、高市早苗総務相(当時)が従来の政府見解を事実上見直すような発言をするまでの経緯がまとめられている。礒崎氏はツイッターで「従来の政府解釈では分かりにくいので、補充的説明をしてはどうかと意見した」ことを認め、高市氏は自らに関する4枚の文書は「捏造」と主張している。礒崎氏の発言を中心に文書のポイントをまとめた。(デジタル編集部)※2023年3月9日午後9:00に内容を更新しました。
【関連記事】高市早苗氏は「捏造」強調 総務省幹部は一般論で「考えにくい」 行政文書巡り国会答弁
政治的公平に関する従来の政府解釈 放送法4条で、放送事業者は番組編集にあたり「政治的に公平であること」が求められている。「政治的公平」とは①政治的な問題を取り扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から特定の政治的見解に偏ることなく、放送番組全体としてバランスのとれたものであること②その判断にあたっては、一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断することーとしている。
公開された文書によると、礒崎氏は、番組全体ではなく、一つの番組でも「政治的公平」かどうか判断すべきだと主張していた。(同氏の発言を文書から一部抜粋)
(2014年11月28日)
・これまで国会答弁を含めて長年にわたり積み上げてきた放送法の解釈をおかしいというつもりもない。他方、この解釈が全ての場合を言い尽くしているかというとそうでもないのではないか、というのが自分の問題意識。
・「全体でみる」「総合的に見る」というのが総務省の答弁となっているが、これは逃げるための理屈になっているのではないか。そこは逃げてはいけないのではないか。
・一つの番組でも明らかにおかしい場合があるのではないかということ。今までの運用を頭から否定するつもりはないが、昭和39年の国会答弁にもあるとおり、絶対おかしい番組、極端な事例というのがあるのではないか。これについても考えて欲しい。有権解釈権は総務省にあるのだから、放送法の解釈としてもう少し説明できるようにしないといけないのではないか。
(12月18日)
・番組全体でのバランスの説明責任はどこにあるのか。「番組全体でどうバランスを取っているのか問われれば、放送事業者が責任を持って答えるべきものと考えます」というような答弁はできないものか。
・例えばコメンテーターが「明日は自民党に投票しましょう」と言っても総務省は「番組全体で見て判断する」と言うのか。反対する考え方には一切触れず一党一派にのみ偏る番組といった極端な事例について、もう少し考えてみてほしい。
(12月25日)
・国民の意見が分かれるような課題について、ある番組で一方の主張のみを放送した場合に、他の番組で他の主張について放送していれば政治的公平性が保たれている、くらいのことは言えないのか。
・「国民の意見が二分される問題について、一方の主張をまったく放送せず、もう一方の見解に加担する番組を執拗に繰り広げるような番組」は一つの 番組として政治的公平の観点から番組準則違反にならないのか。それはいくらなんでもおかしいだろう。他の番組とのバランスで判断されることは分かっていると 前から言っている。一つの番組だけでは「どんなに極端な内容であっても政治的公平の観点では違反にならない」と国会で答弁するのか。
礒崎氏は2015年1月13日、従来の「政治的公平」を巡る政府見解の問題点を示すとともに、国会質疑などにおける解釈についての補完的な説明を盛り込んだ私案を総務省に示した。
【問題点】
① これまで、「一つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断する」との答弁に終始し、どのような番組編集にすれば放送事業者の番組全体を見て「政治的に公平である」と判断されるのか、具体的な基準を示してこなかった。
② 同様に、「政治的に公平である」ことの説明責任の所在についても、明確に示してこなかった。
③ 放送事業者の番組全体を見なくても、一つの番組だけを見たときに、どのように考えても「政治的に公平であること」に反する極端な場合が実際にあり得るが、このことについて政府の考え方を示してこなかった。
【 国会質疑などにおける解釈について補充的説明】
① 例えば、ある時間帯で総理の記者会見のみを放送したとしても、後のニュースの時間に野党党首のそれに対する意見を取り上げている場合のように、国論を二分するような政治的課題について、ある番組で一方の政治的見解のみを取り上げて放送した場合であっても、他の番組で他の政治的見解を取り上げて放送しているような場合は、放送事業者の番組全体として政治的公平を確保しているものと認められる。
② 政治的公平の観点から番組編集の考え方について社会的に問われた場合には、放送事業者において、当該事業者の番組全体として政治的公平を確保していることについて、国民に対して説明する必要がある。
③ 一つの番組のみでも、次のような極端な場合においては、「政治的公平」を欠き、放送番組準則に抵触することとなる。
・選挙期間中又はそれに近接する期間において、特定の候補者や候補予定者のみを殊更に取り上げて放送した場合のように、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合
・国論を二分するような政治的課題について、ある番組の中で、一方の政治的見解を取り上げず、他の政治的見解のみを取り上げて執拗に繰り返した場合のように、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合
礒崎氏側と総務省は、礒崎氏の私案についてその後複数回議論し修正を重ね、それをもとに2月13日、総務省幹部が高市早苗総務相に報告。高市氏は同日付の「高市大臣レク結果(政治的公平について)」と題された文書をはじめ、自らに関する計4ページ分は「捏造」と主張している。
◆高市早苗氏が「捏造」と主張する文書中の発言(一部抜粋)
・「放送事業者の番組全体で」みるというのはどういう考え方なのか。
・そもそもテレビ朝日に公平な番組なんてある?どの番組も「極端」な印象。
・苦しくない答弁の形にするか、それとも民放相手に徹底抗戦するか。
・官邸には「総務大臣は準備をしておきます」と伝えてください。補佐官が総理に説明した際の総理の回答についてはきちんと情報を取ってください。総理も思いがあるでしょうから、ゴーサインが出るのではないかと思う。
◆山田真貴子首相秘書官は「言論弾圧」と問題視
2月18日、総務省幹部が当時の山田真貴子首相秘書官(総務省出身)に礒崎氏とのやりとりの経過を説明したところ、山田氏は「放送法の根幹に関わる話」と強い懸念を示したとされる。文書中の山田氏の発言は以下の通り。(抜粋)
・今回の整理は法制局に相談しているのか?今まで「番組全体で」としてきたものに 「個別の番組」の(政治的公平の)整理を行うのであれば、放送法の根幹に関わる話ではないか。本来であれば審議会等をきちんと回した上で行うか、そうでなければ(放送)法改正となる話ではないのか。
・礒崎補佐官は官邸内で影響力はない。総務省としてここまで丁寧にお付き合いする必要があるのか疑問。
・党がやっているうちはいいだろうし、それなりの効果もあったのだろうが、政府がこんなことしてどうするつもりなのか。礒崎補佐官はそれを狙っているんだろうが、どこのメディアも萎縮するだろう。言論弾圧ではないか。
・政府として国会でこういう議論をすること自体が問題。新聞・民放、野党に格好の攻撃材料。自分(山田秘書官)の担当(メディア担当)の立場でいえば、総理はよくテレビに取り上げてもらっており、せっかく上手くいっているものを民主党が岡田代表の出演時間が足りない等と言い出したら困る。民主党だけでなく、どこのメディアも(政治的公平が確保されているか検証する意味で)総理が出演している時間を計り出すのではないか。
・今回の件は民放を攻める形になっているが、結果的に官邸に「ブーメラン」として返ってくる話であり、官邸にとってマイナスな話。
◆安倍首相(当時)は「意外と前向きな反応」
3月5日、礒崎氏らが安倍首相に説明。山田秘書官から総務省幹部への連絡によると、山田氏らが懸念を説明すると「意外と前向きな反応」が返ってきたという。山田氏からの連絡とされる文書中の安倍首相の主な発言は以下の通り。
・ 政治的公平という観点からみて、現在の放送番組にはおかしいものもあり、こうした現状は正すべき。
・ 「放送番組全体で見る」とするこれまでの解釈は了解(一応OKと)するが、 極端な例をダメだと言うのは良いのではないか。
・国会答弁をする場は予算委員会ではなく総務委員会とし、総務大臣から答弁してもらえばいいのではないか。
◆高市氏が国会で「一つの番組でも極端な場合は政治的公平を確保しているとは認められない」と答弁
高市氏は5月12日、参院総務委員会で、自民党の藤川政人氏の質問に対して、次のように答弁した。
・放送法第4条第1項第2号の政治的に公平であることに関する政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げましたら、一つの番組のみでも 選挙期間中またはそれに近接する期間において、殊更に特定の候補者や候補予定者のみを相当の時間に渡り取り上げる特別番組を放送した場合のように選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合といった極端な場合におきましては一般論として、 政治的に公平性であることを確保しているとは認められないと考えられます。
・同じように政府のこれまでの解釈の補充的な説明として申し上げますが、一つの番組のみでも 国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げて、それを指示する内容を相当な時間に渡り繰り返す番組を放送した場合のように当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平性であることを確保していることは認められないものと考えます。
政府は高市氏の答弁に関して、従来の「政治的公平」の解釈に何ら変更はなく、これまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものと説明している。
【関連記事】「政治的公平」巡る放送法解釈の「変更」 礒崎陽輔氏の問い合わせが契機 総務相認める 文書の真贋は答えず

インターネット放送の「番組」が隆盛の今、放送法4条の「政治的公平」を考える 2023年3月8日 17時00分東京新聞
総務省が7日に公表した「政治的公平」に関する行政文書のコピー。「取扱厳重注意」と記されている
放送法4条が定める「政治的公平」原則をめぐる議論。野党側は、安倍晋三政権が、批判的な民放番組を「公平ではない」として圧力をかけようとした疑惑を追及中だ。公平をタテに政権批判を封じるのは許されないが、一方、今や放送法のしばりを受けないインターネット放送の「番組」が隆盛だ。放送法という枠組みではもうとらえられなくなってきた「政治的公平」を考える。(大杉はるか、木原育子)
【関連記事】総務省が放送法の「政治的公平」を巡る文書を公開 何が問題となっているのか
◆礒崎氏「『極端な場合』について総務省に説明しなさいと言った」
「作成者や日時が特定できていないものがある。私に関係する4枚の文書は不正確だと確信している」
参院予算委で答弁する高市経済安保相=6日、国会で
高市早苗経済安全保障担当相は7日、会見でこう強調した。問題となっているのは、高市氏が総務相だった2015年に、安倍晋三政権(当時)が放送法4条に定める政治的公平原則を解釈変更した際の総務省内部文書だ。今月2日、立憲民主党の小西洋之参院議員が、安倍政権時に総務省が作成した文書を公表。松本剛明総務相は7日の会見で、この文書が正式な行政文書であると認めた。
それまで「政治的公平」は、一つの番組だけではなく、放送局の各番組全体を見て判断するとされていた。だが、高市氏は15年5月の参院総務委員会で、一つの番組でも「国論を二分する課題について、他の見解のみを取り上げ、相当な時間繰り返す番組」などは4条違反に当たるとの「補充的説明」を突如行った。
この文書中、総務省に政治的公平の解釈について何度も注文をつけ、高市氏の答弁につなげたのは礒崎陽輔首相補佐官(当時)。
「こちら特報部」の取材に、礒崎氏は「過去の政府答弁で、政治的公平を欠く番組と判断するのは極端な場合を除き困難だという考えが示されており、『極端な場合』について総務省に説明しなさいと言った。曖昧な基準では規範として意味がないので、もう少し分かりやすくということで、解釈変更ではない」と説明。首相の指示があったかは「記憶にない」とした。
◆過去には自民党政権に批判的な放送内容に圧力をかけるケースばかり
政治的公平をめぐる問題はたびたび起きている。古くは1993年、テレビ朝日の椿貞良報道局長が「非自民党政権が生まれるように報道するよう指示した」とされる問題で、椿氏が証人喚問された。01年にNHKが報じた「問われる戦時性暴力」では安倍氏らによる圧力で、元慰安婦らの発言の削除、短縮に追い込まれた。15年には自民党がテレビ朝日とNHKの幹部を党本部に呼び、個別番組について事情聴取する「圧力」を加えた。各番組で、政権に批判的なコメンテーターの降板も相次いだ。
いずれも、自民党政権に批判的な放送内容に対し、「公平性を欠く」と政権側が圧力を掛けるケースばかりだ。ただ、18年に安倍首相が、放送とインターネットの融合を進めるとして、4条撤廃の意向を示したことには、民放連が反対している。
上智大の水島宏明教授(テレビ報道論)は「放送法は放送や編集の自由を重視しており、独善的な放送をひかえる倫理規定として4条があるのだが、第2次安倍政権以降、4条が悪用された」と話す。
市民団体「NHKを監視・激励する視聴者コミュニティ」共同代表を務めた東京大の醍醐聡名誉教授は「4条があるから、公平を追求して報道しづらくなるという批判もされてきたが、なくせば判断のよりどころがなくなる」と説明。「政治的公平を残し、権力寄りの報道の歯止めとすべきだと考える」と強調した。小西文書が示したやりとりは「官邸のどう喝のようで問題」としつつ、なるべく一つの番組でも公平を期すという解釈自体は「違和感はない」と話した。
【関連記事】高市早苗氏は総務省の内部文書を「捏造」と断言 その根拠は? 立証責任は追及側にあるのか?
◆アメリカでは「公平廃止」で社会分断
米国にもかつてテレビ事業者には「フェアネス・ドクトリン」(公平原則)と呼ばれる原則があった。だが、あらゆる規制緩和を目指した共和党のレーガン政権時代の1987年に廃止。言論の自由の権利を定めた米国憲法修正第1条に抵触する、とされたためだ。
現在は地上波の3大ネットワーク(ABC、NBC、CBS)と、公共放送のPBS、そしてCNNやFOXなどがある。テレビ放送上の言論空間はどうなっているのか。
「右と左にどんどん両極化していっていますね」と語るのは、カリフォルニア州在住の映画評論家の町山智浩氏だ。
例えば、FOXは世界的なメディア王、ルパート・マードック氏が共和党寄りの新自由主義を掲げてスタートしたが、「1990年代に時のブッシュ政権から特権的な情報を得て、視聴率では群を抜いていった。だが、今ではニュースマックスという、FOX以上の保守的なテレビも出てきた。逆に、そのカウンターとして、極端にリベラルな対抗局も出てきた」と話す。
その帰結として生まれたのが、「社会の分断だった」(町山氏)。米国での若者のテレビ離れは日本以上というが、そもそも政治的公平原則のない若者が主流のインターネット上ではその傾向はさらに進む。
町山氏は「ネットには、自分の信じたい物の方にどんどん引きずられるアルゴリズムが組み込まれている。過激な分断が米国社会を支配している」と語る。
◆「人権の原則で規制すべきだ」
日本は放送法上の政治的公平原則は維持されているものの、地上波テレビ離れが進むのは米国と同じ。「ABEMA」や「日本文化チャンネル桜」などのネット放送局や、保守系言論人によるユーチューブ「放送局」も次々に現れている。
2018年、保守系ネット番組「虎ノ門ニュース」への出演を告知する安倍晋三首相(当時)のツイッター
ネット上の言論に詳しい評論家の古谷経衡氏は「ネット放送局でも、総合チャンネルの要素が強いABEMAなどと、オピニオン色が強いチャンネル桜などを同列に論じることはできない」とした上で「保守系ネット放送は自分たちが正しい報道をしていると言い張る。反対意見をくむ姿勢が極めて薄い」とする。「そもそも政治的公平は解釈次第でいかようにも押し切れてしまう面がある。万が一、ネット放送局にも放送法が適用されることになっても、公平性から逸脱した意見がなくなることはないだろう」
現在、総務省ではネット時代の公共放送という論点で議論しているが、「既存のテレビ番組のネット配信についての議論で、ネット放送が多数ある時代に対応できてない」と指摘する。
放送の「言論の自由」をめぐり、もろ刃の剣ともなる政治的公平。この原則を維持するにせよ、変えるにせよ、今後主流になっていくであろうネット報道時代に、放送法の枠組みが有効なのかどうかは疑問だ。どうするべきか。
ITジャーナリストの星暁雄さんは、日本より規制が進む欧州連合(EU)の「デジタルサービス法(DSA)」を参考に、人権の原則で規制するべきではないか、と提案する。
DSAでは、特定の属性を攻撃するヘイトスピーチや暴力扇動などの取り締まりを大手ネット事業者に求める。「キーワードは人権だ。人権が損なわれていなければネットの言論は自由であるべきだ」
「政治的公平は、実は誰も定義できない。本人が公平だとすれば公平にできてしまう」とし、「政治的公平を守れと自主規制を命じるのは実効性に乏しい。ヘイトや偽情報などを排除した上で、自由な言論を守るべきだ」と訴えた。
◆デスクメモ
戦前の政府・軍部のような体制から報道の自由を守るという意味での「政治的公平」と、政府の問題への批判報道に対する「政治的公平」要求。立法趣旨の重点がどちらにあるかと言えば明らかに前者だろうが、ネット時代にはこんな議論も通用しない。野放しでいいとは思えないが。(歩)
インターネット放送の「番組」が隆盛の今、放送法4条の「政治的公平」を考える
2023年3月8日 17時00分東京新聞

〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
日本国憲法
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2016/opinion_160414.pdf

京都府警に便乗し、裁判所の令状なしで大阪府警が住宅を捜索したのは違法だ――。銃刀法違反罪に問われた男(55)=同罪で受刑中=がそう訴え、大阪府に110万円の賠償を求めた訴訟の判決が18日、京都地裁であった。植田智彦裁判長は違法と認め、府に3万3千円の支払いを命じた。 問題となった家宅捜索のイメージ 判決によると、京都府警は2019年7月、恐喝未遂の疑い(不起訴)で令状を得て、大阪市内の男のマンションに入った。銃刀法違反(所持)の疑いで同じ男を追い、張り込んでいた大阪府警の捜査員はその場で京都府警と交渉し、令状を得ないまま室内へ。拳銃を確認し、のちに合同捜査にして事件化した。 判決は、大阪府警の捜索は法的根拠に基づかず「警察官としての注意義務に違反し、プライバシーを害した」と指摘。京都府警とは「別個の捜査機関」が令状なしで入ることは許されないとした。賠償額は、滞在時間の短さなどを考慮して算出した。 判決後、原告代理人の石側亮太弁護士(京都弁護士会)は「司法の審査を厳格に守るよう捜査機関に促した、当然だが意義のある判決だ」と話した。大阪府側は「判決内容を精査した上で、今後の対応を決めたい」とコメントした。(阿部峻介)
2023/4/5朝日新聞
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
日本国憲法

中国はやはり香港人を拘束し拷問するのか──英領事館元職員の爆弾証言に怒りが再燃 Is China Detaining Hong Kong Protesters on the Mainland? 2019年11月21日(木)16時05分 ジェームズ・パーマー(フォーリン・ポリシー誌エディター)

中国はやはり香港人を拘束し拷問するのか──英領事館元職員の爆弾証言に怒りが再燃 Is China Detaining Hong Kong Protesters on the Mainland? 2019年11月21日(木)16時05分 ジェームズ・パーマー(フォーリン・ポリシー誌エディター)
今年8月、総領事館前でチェンの似顔絵を掲げ、捜索を訴える女性 Willy Kurniawan-REUTERS
<香港市民のチェンは、中国で拷問され自白を強要された。香港民主派がデモ当初から恐れていた事態だ。秘密警察のやり口や中国共産党のパラノイアも暴露され、香港騒乱には大きな火種が加わった>
香港デモのさなかの8月、15日の間中国当局に拘束された在香港英国総領事館元職員のサイモン・チェンが、11月19日に初めてメディアの取材に応え、拘束中に拷問を受けたと語った。チェンは釈放後も沈黙を守っていたが、取り調べで拷問を受け、身に覚えのない買春行為で自白を強要されたと訴えた。そればかりか、香港のデモは外国が仕掛けたものだという供述も強いられたという。
英政府はチャンの告発は信用に足るものであると確認したと発表している。
チェンは手足を束縛され、目隠しされて、フードを被せられ、「虎の椅子」に座らされたと証言している。これは、中国の秘密警察が取り調べでよく使う、被疑者の動きを封じる金属の椅子だ。警察は釈放前にチェンを脅し、この件については一切口外するなと命じたという。チェンの告発で市民の怒りがさらに高まり、香港の騒乱は激化すると見られる。
チェンは現在、香港以外の安全な場所に身を隠しており、亡命を希望する計画だという。
中国共産党は歴史的に外国の破壊工作に異常に神経を尖らせてきた。こうしたパラノイア(偏執病)が今も根強くあることは、チェンの話から明らかだ。「香港のデモは外国の工作だ」との主張をプロパガンダと片付けるのは簡単だが、共産党の上層部、おそらくは習近平(シー・チンピン)国家主席その人も、本気でそう思い込んでいる可能性がある。そのためチェンのような罪のない市民が標的にされるのだ。チェンはビデオカメラの前で自白を強要された。自白動画の公開は、近年盛んに使われているプロパガンダ手法だ。
英外相は厳重抗議
ほかにも拘束されている香港市民がいるのか。チェンは刑務所で香港のデモ参加者と見られる囚人を複数見掛け、広東語で苦痛を訴える声も聞いたと話している(ただし、中国本土にも広東語を母語とする人は大勢いるので、それだけでは香港市民とは限らない)。今年6月に始まった香港のデモは元々、中国本土への犯罪者の引き渡しを可能にする「逃亡犯条例」改正に抗議するものだった。そのため、チェンの告発で香港市民の怒りが燃え上がるのは必至だ。
ドミニク・ラーブ英外相はロンドンで中国大使を呼び出し、この件について厳重に抗議した。中国は公式の謝罪をせず、国営メディアを通じて英政府を激しく批判している。香港の騒乱をめぐり、既に悪化していた英中関係はさらにこじれそうだ。
香港警察は先週末、デモ参加者が立てこもった香港理工大学を包囲し、学生たちと激しい攻防戦を繰り広げた。警察は催涙弾とゴム弾を使用、学生たちは火炎瓶で対抗したが、ほとんどの学生が逃げるか逮捕された。だが今なお構内に100人程度が残っていると見られる。
香港警察が中文大学や理工大学に突入したことや、高校生の服を脱がせて身体検査を行ったことで、市民の警察に対する反感は高まる一方だ。怒りと恐怖が渦巻く現状では、香港企業がいつ平常なビジネスを再開できるか見通しが立たないが、11月24日に予定されている区議会議員選挙で、香港市民が意思表示できる可能性はある。だが中国政府が選挙に介入すれば、いま以上に手の付けられない状態になるだろう。
<参考記事>香港の若者が一歩も退かない本当の理由
<参考記事>香港デモ隊と警察がもう暴力を止められない理由
米上院は19日、「香港人権・民主主義」法案を全会一致で可決。下院も20日に圧倒的多数で可決した。米政府は「一国二制度」を前提に、香港を中国本土と区別し、関税やビザ発給などで優遇措置をとっている。この法案は、一国二制度が守られているかどうかを検証するよう国務省に求め、守られていなければ優遇措置を打ち切るなどの制裁を科す内容で、ドナルド・トランプ大統領にとっては、議会がこれを通したのは頭の痛い問題だ。トランプが法案に署名すれば、中国政府の猛反発は避けられず、米中貿易交渉が頓挫するおそれもあるが、上院が全会一致で承認したため拒否権を発動するわけにもいかない。
中国政府は既に一国二制度を踏みにじる姿勢を見せいている。香港高等法院(高裁)は18日、デモ参加者が顔を隠すことを禁じた「覆面禁止法」は、香港の憲法に当たる「香港基本法」に違反するという判決を下した。これに対し、中国の全国人民代表大会(全人代)常務委員会は19日、この判決の有効性は認められないとの声明を発表。中国政府が香港高裁の判決を覆せば、香港の司法の独立は事実上失われることになる。
中国はやはり香港人を拘束し拷問するのか──英領事館元職員の爆弾証言に怒りが再燃 Is China Detaining Hong Kong Protesters on the Mainland? 2019年11月21日(木)16時05分 ジェームズ・パーマー(フォーリン・ポリシー誌エディター)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930005580.pdf

中国本土に容疑者を引き渡せば「一国二制度」が崩壊する「香港はもう私たちの政府ではない」200万人デモ 木村正人在英国際ジャーナリスト 2019/6/11(火) 5:57
「香港、頑張れ」フェーズ1(6月〜9月)
香港の抗議活動は当初、「逃亡犯条例」改正案に対する反対運動として始まった。タムさんは「6月9日に100万人以上が集まったデモは、とても平和的でした」と振り返る。抗議活動に参加する人たちは「平和的」な抵抗と、「力」で対抗する2つのグループがある。メディアでは力で抵抗する方が取り上げられやすい。だが、8月18日にも平和的なデモが行われ、12月8日も平和的なデモが計画されているという。
「平和的なデモをやっていく中で、警官隊の武力による実力行使が始まり、徐々に過剰になっていきました」。
「香港、抵抗」フェーズ2(10月)
スローガンが変わったのは10月。政府はデモ参加者が、マスクなどで顔を覆い隠すことを禁止する覆面禁止令を5日、導入したのだ。議会での審議を経ずに、香港返還後、初めてとなる緊急条例を適用したことも反発を強めた。
「マスク禁止令が出た日にデモ隊の黒いマスクではなく、反対を示すために、普通の白いマスクをした抗議活動も起こりました。この日が分かれ目の日となりました」とタムさん。
この時期から武力介入も頻繁化していったという。平和的なデモで歩いていると1時間後には警察が介入してくる。武力介入してくると、一部のデモ隊が反撃。レンガや水の瓶、火炎瓶で対抗。警察はそれに応じるように、適切なレベルではない武力を行使してくる。放水車や催涙ガスの多用。最初はゴム弾だったが、実弾を発砲するなど、どんどんエスカレートしていく。
「香港、復讐」フェーズ3(11月〜現在)
11月初め。デモの現場で22歳の大学生が亡くなった。「彼の死を境に、スローガンが復讐へと変わりました」。
11月中旬は、香港理工大学などで学生たちがキャンパスを占拠。警官隊は大学の封鎖を決行し、緊迫した事態となった。多くの学生が逮捕され、29日に理工大の封鎖は解除された。
アムネスティ香港は警察の過剰な暴力を批判
アムネスティでは6ヶ月の間に、どのような人権侵害が起きているか、警察の過剰な武力、暴力の調査を行なっている。
「6月22日、集めたビデオを分析して警察の武力行使の実態を明らかにしたレポートを作成し、メディアや国連に提出しました」
過剰な武力の一つに催涙ガスの過剰使用がある。「催涙ガスを使うこと自体は、治安維持に必要であれば認められます。違法ではありません。しかし、過剰に使われていることが問題です」という。
催涙ガスは主に人を解散させるために使用される。だが、香港警察は報復のために使っている。3時間に1000発の催涙弾が使われたこともあり、明らかに過剰だという。
催涙ガスの問題は対象を絞れないこともある。参加者以外の人にも影響を与える。高齢者や子どもが被害にあう自体も起きている。「使えば使うほどエスカレートしています。逆効果です。鎮圧になっていない」
6月から8月にかけて、アムネスは二つ目の報告書作成。警察に逮捕・拘束された30人ほどへ聞き取りを行い、証言をまとめた。
「どんな目にあったかが明らかになってきました。警官が報復のような形で殴る、拷問することがあったこと。逮捕者の中には、医療へのアクセスが拒まれたり、弁護士連絡とらせてもらえなかったりしたこと。警察の暴力は個々の問題ではなく、組織的で構造的な問題だと考え、明らかにしようとさらに、分析を進めています」
独立した調査機関を設置し、状況を分析を
アムネスティでは香港政府に、警察の過度な暴力に対する調査と、平和的な集会の自由、表現の自由を尊重することを求めている。
「警察によって香港の人々の表現の自由、集会の自由が踏みにじられているのです」
香港は「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」に基づき、平和的な集会の自由権がある。警官の暴力行為はこれに違反するものである。
タムさんは「香港政府が自ら、国内で適正な調査を行なって対応する。それが、関係を修復することにもつながります。政府が信頼できる政党な権力であると信頼を取り戻すためにも、自ら行うべきです」と見解を述べた。
選挙で平和的に変えることができる
11月24日にあった区議会選挙で、民主派が議席の85%を獲得し圧勝した。過半数をしめていた親中派は、292議席から59議席に減った。
「香港市民は投票で結果を出せることを学びました。2020年には次の選挙(立法会議員選挙)があります。平和的に物事を変えるため行動していくことができます」
選挙を受け、キャリー・ラム行政長官は市民の意見に耳を傾けるとも述べている。このまま、武力で市民を押さえつける対応を続けるのか。別の手段を考えるか。タムさんは「可能性はあります」と信念を伝えた。
アムネスティ日本の活動
「香港頑張れ」アムネスティが3つのスローガンを解説
https://www.city.kawasaki.jp/980/cmsfiles/contents/0000107/107111/311121soumu1-11.pdf
4 デモ参加者側の5つの要求 逃亡犯条例改正案に対する抗議が発端となって発生したデモは、次の5つの要求を達成 することを目的としている。
① 逃亡犯条例改正案の完全撤回
② 市民活動を暴動とする見解の撤回
③ デモ参加者の逮捕・起訴を中止
④ 警察の暴力的制圧の責任追及と外部調査の実施
⑤ 林鄭月娥(キャリー・ラム)行政長官の辞任と民主的選挙の実施
陳情第19号 日本政府に香港の「自由」と「民主主義」を 守る行動を求めることに関する陳情

旧統一教会側と自民党、改憲案が「一致」 緊急事態条項、家族条項…濃厚な関係が影響? 2022年8月2日 06時00分東京新聞

旧統一教会側と自民党、改憲案が「一致」 緊急事態条項、家族条項…濃厚な関係が影響? 2022年8月2日 06時00分東京新聞
安倍晋三元首相銃撃事件を契機に、自民党との深い関係が露呈した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)。その旧統一教会の政治部門とされる国際勝共連合(勝共連合)の改憲案と、自民党の改憲草案が、「緊急事態条項」や「家族条項」などで一致していることが、注目を集めている。被害者弁護団から「反社会的勢力」とも指摘される旧統一教会側の主張が、関係の濃い自民党の改憲草案にも反映されていたのか。(特別報道部・山田祐一郎、中山岳)
◆中国の覇権的行動、北の核・ミサイル、大地震や原発事故の対応が最優先
改憲案を説明する国際勝共連合の動画=同連合のホームページから
国際勝共連合の関連サイトでは、安全保障や憲法、家族政策などについての同団体の考えが動画で紹介されている。その一つに、「憲法改正」がある。2017年4月に公開された長さ約17分の動画で、渡辺芳雄副会長が同団体独自の改憲案を解説している。
渡辺氏は「個人においても組織、国家においても変化に対応できなければ存続できない。滅びるのであります」と改憲の必要性をこう訴えかける。
日本を取り巻く状況の変化について、「中国の覇権的行動」「北朝鮮の核・ミサイル開発や挑発的行動」「大規模地震や原発事故」などを指摘した渡辺氏。改憲の優先順位として「緊急事態条項の新設」を真っ先に挙げた。
災害時を想定して「政府の権限を強化して、所有権を一時的に制限したり、食料や燃料の価格などをしっかり規制したりして命を守る」とした上で、こう述べる。「早く憲法で明記して憲法を守りながら国民の生命と財産を守る状況を作らないといけない」
自民党は、12年にまとめた改憲草案の中で、外部からの武力攻撃や大規模災害時に、首相が緊急事態の宣言を行い、緊急政令を制定できるなど首相や内閣の権限を強化、国会議員の任期を延長できるなどと定めた。その後の議論を踏まえ、18年に公表した「たたき台素案」では、大規模災害時の対応として同様の緊急事態対応を規定。対象に「外部からの武力攻撃や大規模テロ・内乱」を含めるかについては、「対象にすべきだとの意見がある」と付け加えた。
◆旧統一教会との関係は改憲にもマイナスに働く?
岸田文雄首相は今年5月、改憲派の集会に寄せたビデオメッセージで、改めて緊急事態条項の必要性を訴えた。新型コロナウイルスへの対応やロシアによるウクライナ侵略を挙げて「有事における迅速な対応を確保するため、こうしたことを憲法にどのように位置づけるかは極めて重要な課題」と強調。大規模災害以外の有事にも対象を拡大する印象を与えた。
「18年の素案で、緊急事態の対象が限定されたような印象を与えたが、現状は12年の草案の考え方に逆戻りしている」と話すのは、愛媛大の井口秀作教授(憲法学)。「一番の懸念は、国会を通すことなく政令によって国民の権利が制限される可能性があるということ。必要な根拠も、新型コロナやウクライナ侵攻など後付けで増えている」と緊急事態条項の問題点を指摘する。
安倍氏の死去を受け、岸田氏は「思いを受け継ぐ」と改憲への意欲を見せたがその後、霊感商法などで多くの被害者が出ている旧統一教会と自民との関係が次々と明らかになった。勝共連合が緊急事態条項の創設を唱えることに、井口氏は「反共を掲げる団体の素直な主張なのだろうが、自民草案との間に因果関係があるのかは分からない」としつつ、「旧統一教会との関係は改憲派からも反発を呼び、改憲にマイナスに働くのでは。自民が緊急事態条項など改憲の主要項目を戦略的に変更することもあり得る」と話す。
◆「教団側に都合の良い自民の改憲草案」
改憲を巡る自民草案と旧統一教会側との「一致」は、まだある。
渡辺氏は先の動画で、憲法に「家族保護の文言追加」を主張。「家庭という基本的単位が、最も社会国家に必要。だから保護しなきゃいけないという文言を、何としても憲法にいれなくてはならない」と強調する。これに対し、自民草案で新設された24条条文には「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される」とある。双方の「家族重視」は、よく似通っている。
旧統一教会は2015年の改称で家庭連合と名乗っている通り、関連団体を含めて「家庭」「家族」はキーワードだ。創始者の故・文鮮明氏を「真のお父さま」と呼び、「神様の下に人類が一つの家族である世界」を理想に掲げる。
こうした教団の「家族観」について、北海道大の桜井義秀教授(宗教社会学)は「目指しているのは文氏を中心にした『真の』家族。自由恋愛や婚前交渉は論外で、信者には合同結婚式で相手が選ばれる」と解説する。
こうした教義に基づく家族観は、自民草案のうたう家族とは似て非なるものだ。ただ、桜井氏は、勝共連合が教義に基づく家族観を前面に出さず自民草案に同調していると指摘。その思惑について「教義を真正面から説くだけでは、多くの人々は受け入れず信者も増えない。だから教団側に都合の良い自民の改憲草案に乗っかり、利用しようとしている。実際に関連団体は『家庭づくり国民運動』などの講座を開き、旧統一教会の名を出さずに布教につなげてきた」と述べる。
今年6月に開かれた衆院憲法審査会=国会で
◆類似するのは「個人の尊重を退け、父権主義的家族の中に埋没させる危うさ」
自民草案は、現憲法20条にある「いかなる宗教団体も政治上の権力を行使してはならない」の文言を削除。さらに、国とその機関の宗教活動を禁じた点も変え、「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない」とする。政教分離の原則を緩めるとの批判はかねてあったが、旧統一教会と自民党との関係が問われている今、これを許していいのか。
恵泉女学園大の斉藤小百合教授(憲法学)は「自民草案にはもともと、政治家による靖国神社参拝の違憲性を払拭ふっしょくし、国家神道を復権させるもくろみがあるとみていた。さらに旧統一教会との関係も浮き彫りになり、政教分離のハードルを下げる方向で改憲が進むならば、憂慮すべき事態だ」と警鐘を鳴らす。
斉藤氏は、自民草案と旧統一教会の考えに類似するのは「個人の尊重を退け、父権主義的家族の中に埋没させる危うさ」とみる。「立憲主義の柱となる個人の尊重をないがしろにするかのような改憲に、自民と旧統一教会が足並みをそろえているように見える」と問題視する。
ただ、自民草案への影響が取り沙汰される主張を展開してきたのは、旧統一教会・勝共連合に限らない。宗教団体の言説に詳しい評論家の古谷経衡氏は「日本会議や神社本庁などの『宗教右派団体』は、自民草案に一定の影響を与えてきた。旧統一教会とも共通するのは、復古的な家族観、夫婦別姓反対などだ。そうした『雑念』が自民草案には入っているといえる」と説く。
古谷氏は「旧統一教会については、かつて霊感商法で多く被害者を生み、今も宗教二世たちは苦しんでいる。そうした団体のエッセンスが含まれる自民草案に沿う改憲は政治倫理上、許されないだろう」と述べ、こう強調する。「このまま改憲の議論が進み国会で発議され、国民投票にかけられるならば一部の宗教団体を利する面がある。国民は一度、立ち止まって考える必要があるのではないか」
◆デスクメモ
安倍氏が2006年に上梓し、改憲を訴えたのは「美しい国へ」。その2年前、勝共連合初代会長久保木修己氏の遺稿集として出た本が「美しい国 日本の使命」。偶然か、思想の一致か。今となっては2人とも故人だから確かめられないが、こんな縁が感じられる改憲は不気味だ。(歩)
【関連記事】旧統一教会と岸一族と北朝鮮 この奇妙な三角関係をどう考えるべきか
旧統一教会側と自民党、改憲案が「一致」 緊急事態条項、家族条項…濃厚な関係が影響?
2022年8月2日 06時00分

入管、同性愛迫害理由に難民認定 国に勝訴のウガンダ30代女性 2023年4月19日 10時16分 (共同通信)東京新聞
同性愛者への迫害を理由にした難民認定を国に命じる判決が大阪地裁で確定したウガンダ国籍の30代女性が19日、大阪出入国在留管理局から難民認定を受けた。
女性は同性愛を理由に現地の警察に暴行を受けたとして、2020年に来日し、難民認定申請したが認められず退去強制命令を受けた。女性は処分取り消しを求めて提訴。今年3月の地裁判決は、帰国すればウガンダの刑法で処罰される恐れがあると判断し、強制送還は違法で難民と認定するよう国に命じた。国は控訴せず判決は確定した。
出入国在留管理庁は同月、同性愛など性的マイノリティーを理由とする迫害も難民に該当し得るとの判断基準を公表した。
入管、同性愛迫害理由に難民認定 国に勝訴のウガンダ30代女性 2023年4月19日 10時16分 (共同通信)東京新聞

入管難民法改正案、実質審議入り「監理措置制度」巡り論戦 2023年4月19日 10時12分

入管法改正案、山積みの課題とは? 難民申請3回以上は送還可能に...申請者「命の心配をせずに暮らしたいだけ」 2021年5月12日 06時00分
外国人の収容や強制送還ルールを見直す衆院法務委員会で審議中の入管難民法改正案に対し、外国人収容者の人権を侵害する懸念が広がっている。3月には名古屋の入管施設でスリランカ人女性が死亡、施設内で過去20年に24人が亡くなるなど法務省出入国在留管理庁(入管)の対応が批判が集まる中、改正案の問題点を探った。(望月衣塑子)
【続報】ロシアのウクライナ侵攻から逃れた人々を「準難民」に指定検討 真の狙いは送還停止なくすこと?
◆入管局長通知「不安を与える外国人を大幅に縮減」
「五輪の年までに安全・安心な社会の実現を図る」「社会に不安を与える外国人を大幅に縮減する」
2016年、当時の入管局長の通知以降、半年超の長期収容者が倍近くに増加。抗議のハンガーストライキが全国で拡大し、19年6月、茨城県牛久市の入管施設でナイジェリア人男性がハンスト中に餓死した。
これを機に法務省は長期収容を見直すための専門部会を設置。部会の提言を受けた改正案は日本社会で生活を認める仕組みを作る一方、国連人権理事会や国連難民高等弁務官事務所が懸念を示してきた収容期間の上限設定や司法審査の導入を盛り込まなかった。立憲民主党の枝野幸男代表は10日の衆院予算委で「法案には国際基準に反する重大な問題がある」と批判した。
◆送還停止は難民申請2回まで、送還拒否で罰則も
改正案で支援者らから批判が強いのが、現行法では何度でも申請を繰り返すことが可能な難民申請を、3回以上には原則、送還停止を認めず拒否すれば送還忌避罪などの罰を科す点だ。
20年末時点で、送還忌避者3103人のうち難民認定申請中は1938人で、3回目以降の申請者は504人。改正案が成立すれば、504人は「相当な理由」を示さない限り、送還忌避罪が適用される。
上川陽子法相は「過去に3回目の申請で難民認定された人はいない」と説明するが、イラン出身の男性は3回目の申請中に「宗教を理由とする難民に該当する」との判決が出て昨年、難民認定された。
◆外国人を支援する「監理人」にも罰則規定
長期収容の解決策として改正案に盛り込まれた「監理措置制度」にも批判が集まる。同制度は収容者の弁護士や支援団体を入管が「監理人」に指定。入管が認めれば就労も可能になるが、監理人は収容者の生活などを監督・報告義務を負い、違反すれば10万円以下の過料も科す。
制度について、NPO法人「なんみんフォーラム」が支援に関わる弁護士や支援団体から意見を聴取した結果、「監理人を引き受けたいか」の質問に90%が「なれない・なりたくない」と回答、「罰則が規定されているから」との理由が多くなり手不足は必至だ。
◆在留特別許可も条件厳しく...
改正案では、在留特別許可申請で運用のガイドラインになかった「1年を超える懲役・禁錮の実刑前科等の場合、原則許可しない」という趣旨の文言も盛り込む。これまで3年以上の懲役刑を受けた人でも、日本で育ったなどの事情を考慮して在特が認められたケースもあったが、今後は原則認められなくなる。
丸山由紀弁護士は「現場の運用は改正にそった厳しいものになる」と指摘、日本弁護士連合会も意見書で「刑罰前科を原則的な不許可事由とすべきでない」とし、「『家族の統合と子どもの最善の利益を積極的に考慮すべき事情として』を明記すべきだ」と批判する。
◆日本の難民認定率は0.4%と極端に低い
長期収容の原因の一つが低い日本の難民認定率だ。19年は10375人の申請者のうち、認定は44人で認定率は0.4%。ドイツの25.9%、米国の29.6%、カナダの55.7%と比べても極端に低い。
ミャンマーのカチン族のラパイさん(仮名)は現在3回目の難民申請中だ。彼女は「私たちは人間。命の心配をしないで暮らしたいだけ」と訴えた=4月7日、都内で(弁護士提供)
19年のUNHCR統計によると、難民の出身国別で、ミャンマーは世界で5番目に多い110万人。国軍のクーデター以前から政情は不安定で政治迫害を受ける恐れがある難民が多いが、ミャンマー出身者の昨年の難民申請者は602人だったが、認定者はゼロだった。
父親がミャンマー反政府武装組織の将校で、家族も迫害を受け14年前に来日したカチン族のラパイさん(仮名)は、2度の申請が却下され3度目の申請中。「命が危ないから申請している。私たちは人間。命の心配をせずに暮らしたいだけ」と訴える。
クルド人の男子大学生ハルさん(仮名)も4回目の難民申請中。「日本の大学で学び日本で働き。日本社会と世界のために貢献したい」と訴える=4月22日、都内で(移住連提供)
クルド人の男子大学生ハルさん(仮名)も10歳の時に母と来日、現在4回目の難民申請中だ。「高校入学後、入管職員から『あなたは日本で学校行っても就職できない。時間と金の無駄だから帰って』。良い成績を入管に見せると『頑張っても意味ない』と言われ、ショック受けた」と話す。
「入管の規定ではクルド人は他県に移動したり働くのも駄目で、人権が保障されていない。日本の大学で学び日本で働きたい。日本社会と世界のために貢献したい」と訴えた。
◆「人権保護の観点で国際的な基準に満たず」 国連批判にも向き合わず
国連人権理事会の特別報告者は3月末、法案について「人権保護の観点から国際的な基準を複数の点で満たしてない」と批判したが上川陽子法相は「一方的に見解を公表されたことに抗議せざるを得ない」と反論、国際的な批判に向き合う気配はない。
日本が加盟する難民条約では「保護求めた国へ不法入国したことや不法にいることを理由に罰してはいけない」と定めるが、改正案は難民条約にも矛盾する。
19年末で日本にいる外国人は293万人。安倍前政権は、労働力を求める財界の要望を背景に入管難民法を改正し、5年で最大34万人の外国人労働者の受け入れを認め、実質的な「移民政策」が進む。一方、死者が出ても入管の収容状況は改善されず、国際社会に批判されても難民認定制度を見直す動きは皆無だ。
【関連記事】「外国人収容、改善どころか悪化」「難民保護中心の法案を」 研究者ら が入管法改正案の再検討求める
入管法改正案、山積みの課題とは? 難民申請3回以上は送還可能に...申請者「命の心配をせずに暮らしたいだけ」 2021年5月12日 06時00分

「外国人収容、改善どころか悪化」「難民保護中心の法案を」 研究者らが入管法改正案の再検討求める 2021年5月12日 06時00分東京新聞
入管難民法改正案の衆院法務委員会審議を巡り、国際法や憲法などの研究者ら124人が11日、日本政府の外国人収容に対し「司法審査を経ず、出入国在留管理庁の判断で身体を無期限拘束しており、人権条約に照らして問題がある」とした声明を発表し、政府に廃案を含めた改正案の再検討を求めた。
声明によると、改正案を「外国人収容のあり方を改善するどころか悪化させる」と、国際人権機関が懸念していると指摘。国際人権法に適合しているかどうか検討する必要があると主張している。
同日、東京・霞が関の厚生労働省で会見した北村泰三中央大教授は「(政府は他国に)人権条約の批准を呼び掛けながら、法改正で逆行することをし、長期収容や難民認定率の問題に向き合っていない」と批判した。同席した上村英明恵泉女学園大教授は「国際社会は日本をみている。難民保護を中心に据えた改正案にするべきだ」と訴えた。(望月衣塑子)
【関連記事】入管法改正案、山積みの課題とは? 難民申請3回以上は送還可能に...申請者「命の心配をせずに暮らしたいだけ」
「外国人収容、改善どころか悪化」「難民保護中心の法案を」 研究者らが入管法改正案の再検討求める 2021年5月12日 06時00分東京新聞
麻生太郎副総理は、9月23日、栃木市内での講演において、朝鮮半島から大量の難民が日本に押し寄せる可能性に触れ、「武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない*1」、10月8日、新潟県聖籠町の集会では「難民は武器を持っていて、テロを起こすかもしれない*2」と発言しました。
大量の難民が日本に逃れてきた事態を想定すべきという麻生氏の問題提起は理解するものの、本来は命の保護をすべき対象である「難民」を上記のように捉えることに、難民支援協会(JAR)は憂慮します。難民と武装の関係や、北朝鮮有事に際し、逃れてきた難民を保護するための備えについてなど、JARは以下のように考えます。
北朝鮮難民(いわゆる「脱北者」)の実態
国外に逃れる北朝鮮人の大半は、人道・人権の危機的状況から、命を守るために逃げ出している人たちです。2017年4月の国連報告書 によると、国民の40%が低栄養の状況であり、慢性的な食糧不足と栄養失調の問題が蔓延している*3とされています 。北朝鮮から逃れた人が国へ戻された場合には、「難民」となるために不法に国を出国したこと自体が処罰対象となり、拘禁、投獄、強制労働、拷問などを受けるおそれに晒される*4ことを忘れてはいけません。
北朝鮮難民の大多数は中国経由で韓国に逃れます。韓国統一省によると、今年1月から8月にかけて780人が韓国に逃れました。1953年の朝鮮戦争終結以来、3万人以上を韓国が受け入れています*5。
日本へもこれまで約200人が逃れてきている*6と言われています 。中国などを経由して来日した、帰還事業で北朝鮮に渡った元在日朝鮮人や日本人配偶者とその家族など日本に縁がある人が大半です。今回の「麻生発言」で想定されているように、船で逃れてくる事例は非常に稀です。北朝鮮の厳しい海岸警備と日本海の荒波という大きなリスクがある上に、燃料の不足から日本まで航行できる船舶は決して多くはないという事情からだろうと考えられます。たとえば、2007年6月2日、青森県深浦町に漂着した男女4人の家族は、屋根もない小さな木造船で逃れてきました。所持品はソーセージなど食料の入った麻袋2個と3〜4メートルの木製オールや羅針盤でした。事情聴取に対して、「北朝鮮から⾃由を求めて、1週間ぐらいかかってやって来た」などと話したということです*7。その後、2011年9月13日に石川県能登半島沖に9人、2016年7月16日に山口県長門市に1人などが到着しています。いずれも日本政府により一時的に保護され、収容施設で数日から数週間過ごした後に韓国へと受け入れられています。
ただし、現行の北朝鮮体制が崩壊し、まとまった人数の難民が船で逃れてくる可能性を100%否定はできません。その万が一の事態に日本が対応するためには、起こりうる事態を適切に想定し、備えることが重要です。
想定される難民の「武装」とは
難民が逃れる過程で武装することは、現実的には非常に考えにくいでしょう。一般的には、最低限の食糧、薬、着替え、身分証明書、携帯電話や充電器、現金など、最小限の荷物を持って逃れます。それを踏まえた上で、難民支援の現場における難民の「武装」とは以下のパターンが想定できます。
1. 元兵士(当面武器持っている可能性がある)
2. 戦闘員(現役で戦っている人が難民に紛れ込む)
3. 非戦闘員(財産として武器を持っている難民。武装解除になれば現金化できる、逃れる際には家畜より扱いやすい、逃避行中の自己防衛のためになるという理由で、難民が武器を携帯することは、アフリカ等の紛争地域では散見される現象)
難民と、武装した人が混在して流入してきた場合、まずやるべきことは、戦闘員と非戦闘員を見極めること、見極めるにあたり一定期間留めおくための収容施設を準備することの二点です。
難民が武器を携帯していた場合、安全な国に到着すれば武器は不要になるため、武装解除に応じるのが当然の流れとなります。逆に武装解除に応じる意思がなく、戦闘の意思を有する場合には「難民」ではなく戦闘員としての対応となります。保護を求めるのが難民であり、戦闘の意思を有している人を難民と呼ぶことは適切ではありません。
難民条約には戦争状態や緊急事態に対処するために、緊急時には暫定的な措置で対応すること(第9条:暫定措置)としています。つまり、暫定的に収容等を行うことは禁止されていません。しかし、締約国として難民を人種や出身国で差別しないこと(第3条:無差別)、出身国に送り返さないこと(第32条:送還の禁止)などを守る必要があります。
北朝鮮有事を想定した日本政府の受け入れ態勢-北朝鮮人権法
北朝鮮有事に備え、難民をどのように保護するかという議論は、以前より政府の中で行われてきました。報道*8によると、1996年には当時の橋本首相が「極東有事」の際の大量難⺠などの対策検討を関係省庁に指示、2003年には政府で検討し、上陸する難⺠を「10万〜15万人」と推計しています。
2006年6月には、「脱北者の保護及び支援に関し、施策を講ずるよう努めるものとする(第6条2)」と記された「北朝鮮人権法」が施行されました。当時自⺠党幹事⻑代理だった安倍氏は、自⺠党が同法の法制化に着手した2005年、「脱北者を支援することで(北朝鮮の)現政権の変化を助⻑する。レジーム・チェンジ (体制転覆)も念頭に法律をつくらなければならない」と発言しています。
国会での議論においては、前原大臣(当時)が「避難民を発見した際の身柄の保護、応急物資の支給、身体検査の実施、上陸手続、入管、税関、検疫、収容施設の設置及び運営、我が国が庇護すべき者等に当たるかどうかについてのスクリーニング、こういった手順というのは設けまして、備えは万全に整っている*9」、安倍首相が「我が国に避難民が流入するような場合の対応については、避難民の保護に続いて、上陸手続、収容施設の設置及び運営、我が国が庇護すべき者に当たるか否かのスクリーニングといった一連の対応を想定しています。これらの対応を適切に行うべく、引き続き、関係機関による緊密な連携を図ってまいります*10」 と語っています。歴代の総理、大臣は一貫して身柄を保護した上で検査をし、日本での受け入れについて検討する旨を述べています。避難民の保護についての議論がなされており「射殺」という選択肢は一切入っていません。
国際的な行動規範-ルワンダ難民対応からの教訓
現在、人道支援・難民支援に携わる関係者においては、国際的に支援に関する行動規範*11が確立しています。
行動規範が作られたきっかけは1994年のルワンダ危機への対応です。短期間に約200万人が隣国へ逃れた危機に対して、難民の大量流出における支援の経験が少ない人道・難民支援機関は効果的に対応ができませんでした。多くの人が虐殺を逃れた先の難民キャンプで十分な支援物資を得ることができず、劣悪な衛生環境のために命を落としたと言われています。虐殺を指導した立場の人々や、武装した過激派組織のメンバーが難民キャンプに紛れて入り込んでいたために、難民キャンプへの支援の正当性が問われることとなりました。そのため、人道支援の現場で活動する赤十字社やNGOの主要メンバーが中心となり、この行動規範を作成し、その後スフィア・プロジェクトなど多くの人道支援に関する実施レベルの行動指針が確立されてきました。
北朝鮮から大量に難民が流出する大規模な人道危機が発生した際、国際社会はこうした過去の教訓に基づき、各種規範に従って行動することになります。日本も当然それを踏まえた対応をすることが国際的には求められるでしょう。
最後に
今回の「麻生発言」は、想定される状況を適切に認識していないばかりか、これまでの難民保護の議論を否定し、今後逃れてくるかもしれない保護されるべき人へ疑いの目を向けてしまうという意味でも非常に問題があると考えます。圧政から命をかけて逃れている人たちをあたかも危険な存在であるかのように表現し、不必要に不安をあおることは、決して建設的な議論を生み出さないでしょう。難民の過半数は女性、子どもです。粗末な船で海上を少なくとも数日間漂流し、飢餓や病気に瀕しているかもしれない人たちに対してどう救命措置をとるか、保護するか、議論を深め、備えを整える必要があります。難民の命を保護するという基本的な原則に立ち戻り、北朝鮮からの避難民が万が一日本へ来た場合の人道的で現実的な対応を官民で連携し考えることができる契機とできればと考えています。
*1 朝日新聞『麻生副総理「警察か防衛出動か射殺か」武装難民対策』2017年9月24日
*2 産経新聞『麻生太郎副総理「北朝鮮には危なそうな人がいる」』2017年10月8日
*3 AFPBB News 2017年3月24日<https://goo.gl/QdLdjn>2017年10月10日アクセス
*4 アムネスティ日本「朝鮮民主主義人民共和国」<http://www.amnesty.or.jp/human-rights/region/asia/north_korea/>2017年10月13日アクセス
*5 BBC NEWS JAPAN「韓国への脱北者、人数約13%減」2017年9月18日<http://www.bbc.com/japanese/41302779>2017年10月13日アクセス
*6 宮塚寿美子「日本における北朝鮮難民(脱北者)の実態」『難民研究ジャーナル5号』2015年12月、80頁
*7 朝日新聞『「自由を求めて来た」 小舟、日本海900キロ余り 青森「脱北者」』2017年6月3日付朝刊
*8 朝日新聞「(時時刻々)日本直行、どう対応 脱北者4人青森に」2007年6月3日付朝刊
*9 2012年11月25日、衆議院予算委員会における前原大臣の答弁より
*10 2017年4月17日、衆議院決算行政監視委員会における安倍首相の答弁より
*11 災害救援における国際赤十字・赤 新月運 動および非政府組織(NGOs)のための行動規範
http://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/code-of-conduct/code-japanese.pdf
※ 現在、上記注釈11にある行動規範の日本語版は、同サイトには掲載されていません。英語版、もしくはスフィア・ハンドブックに掲載されている日本語版(p.385)を参照ください。(2022年1月追記)
麻生氏による「武装難民」発言の何が問題か?
2017.10.19
https://www.ifrc.org/sites/default/files/2021-07/code-of-conduct-movement-ngos-english.pdf
https://www.spherestandards.org/wp-content/uploads/Sphere-Handbook-2018-Japanese.pdf
以前にも「難民が大挙して押し寄せてきてテロを起こす危険性」について述べられたそうですが、その発言に信ぴょう性はあるのでしょうか?
以前に書いたブログ「朝鮮半島有事で日本に大量に『難民』が流入するの?」と「『武装難民』は射殺してもいいの?」と重なる部分もありますが、発言の真偽について再確認しておきましょう。
1)大量の難民が日本に来るの?
以前のブログにも書いた通り、朝鮮有事の際に大量の難民は日本には来ません。北朝鮮の人々にとって最も魅力的な避難先は、言語的・文化的・歴史的背景や親族関係も近い韓国です。
北朝鮮出身者は、韓国に逃れたら原則的に韓国籍を与えられることになっていますし、既に韓国政府は非常に手厚い支援パッケージを脱北者に提供しています。非武装地帯(いわゆる38度線)を越えられない場合でも、北朝鮮と地続きの中国やロシア経由で韓国入りを目指すでしょう。
恐らく唯一、命がけでも舟で日本に渡りたい方々は、日本人拉致被害者の方々、「北朝鮮帰還事業」で北朝鮮に渡った方々、その子孫の方々でしょう。
その方々は(元)日本人ですので、就籍を支援する、あるいは「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格を付与するのが筋ですし、日本国全体として帰還を温かく迎えるのが当然でしょう。万が一自衛のために武器を携行していたとしても、誤っても「射殺」などしてはいけません。
今年1月に韓国の軍事専門家が、北朝鮮人民の階級や所得、居住地域、船の所有の可能性などの細かいデータを分析した結果、朝鮮有事の際にわざわざ海を渡って北朝鮮から日本を目指す人は、3600人程度に留まるだろうとの見込みを発表しています。
3600人を「大量」と呼ぶのが相応しいか分かりませんが、その程度であれば、万が一全員を一時的に「収容する」必要が出たとしても、既存の入管施設で対応できる範囲内です。
2)難民を「収容」しないといけないの?
難民には(庇護申請中も含めて)基本的に「移動の自由」が認められています(難民条約第26条)。命からがら逃れて来た人を十把一絡げに「強制収容」するのは、そのような国際法上の原則や憲法第34条から見ても、明らかに違法です。
少なくとも金正恩体制が続いている限りは「迫害のおそれ」がありますので、身元確認が終わり次第、一時庇護上陸(入管法第18条2)を許可して、速やかに「宿泊施設」に移送すべきです。
実際、日本には1970年代後半から1990年代にかけて計13000人を超えるボートピープルが辿り着きましたが、いわゆる「収容」ではなく、移動の自由が確保されている「宿泊施設」が提供されていました。日本政府にも民間団体にも、その時に得た豊富な知見がありますので、それを生かせばよいのです。
ただし実際問題として、しばらく収容しなければならない「庇護申請者」(「難民であること」を確認中の人)や不法入国者も出てくるでしょう。人数的には極めて少数のはずですが、北朝鮮からの流入民の中に金正日体制の幹部やいわゆる「工作員」と呼ばれる人が混ざっている可能性も、仮想上は全くゼロではありません。
そのような人々の中に、「平和に対する犯罪」「戦争犯罪」「人道に対する犯罪」あるいは「国連の目的や原則に反する行為」などを行った人がいれば、そもそも「難民」の定義に当てはまりません(難民条約第1条F)。
また「工作員」などで、日本の安全にとって危険人物であることが判明した場合には、(有事の間は物理的に難しいと思いますが、「拷問のおそれ」がなくなれば北朝鮮に)追放・送還して良いことになっています(難民条約第33条2項と拷問禁止条約第3条)。
一部の方々からは批判されるかもしれませんが、特に北朝鮮という国の特殊な事情に鑑みて、人定事項や入国目的の確認が非常に困難なケースの場合は、収容期間が例外的に長くなってしまうケースが出てくることはやむを得ない、と私は思います。
いずれにせよ上記のような北朝鮮幹部や工作員などは(少なくとも金正恩体制が続く限りは)「迫害のおそれ」が無いので、そもそも「難民ではない」ことは強調しておきたいと思います。
3)「不法難民」とは誰のこと?
麻生副総理がどういう人達のことをさして「不法難民」と言ったのか定かではありませんが、もしパスポートやビザを持たずに不法に入国してきた難民のことを指しているのであれば、国内法的にも国際法的にも完全に間違いです。
「不法に入国してきた難民を処罰してはならない」という原則(難民条約第31条)が、既に1951年から国際的に確立していますし、日本も1982年からその原則が国内法として施行されています。
ちなみに9月の副総理の「射殺」発言の直後、「武装難民」という概念の「ある」「なし」が一部で議論されました。
一般に「武装難民」という言葉は、ことに90年代からルワンダ危機などで顕在化した「難民の武装化」(armed refugees、refugee warriorsまたはmilitarisation of refugees)という現象で、主に周辺国に難民として逃れた後、難民キャンプ内やその周辺で武器が流通し、キャンプ内で軍事訓練や母国に向けた攻撃準備が行われる問題をさしています。
漂着時に武器を携行している人をどう対処すべきかという議論とは、文脈が全く異なる概念です。
またそもそも、そのような概念の有無が問題なのではなく、実際に武器を携行している漂着民が来たらどう対処するのが「正しいのか」を考えるのが重要なことでしょう。
4)「武器の携帯」の可能性?
詳細は以前のブログを参照頂きたいですが、「武器を携帯している」だけでその人が難民でないとは言えません。自衛のために武器をもって辿り着く人や、北朝鮮軍部による強制徴兵制度を逃れてきた(元)軍人かもしれないからです。
もし安保法制に基づいて日本も「紛争当事国」となった場合には、国際人道法が適用し始めますが、ジュネーヴ条約第一追加議定書第50条によると「武器を携行していること」だけをもって直ちにその人を「戦闘員」(軍人)と見なすことはできません。
「直接的な攻撃行為に参加していない人は、文民として保護しなければならない」というのが国際人道法の原則であり、国際赤十字社が最近出した指針です。
そもそも今の北朝鮮の状況で何かの武器をもって舟で出国できる人は非常に限られると思いますが、仮に北朝鮮の軍人(あるいは民兵や便衣兵)と疑われる人が武器を携帯している状態で日本の領海に入域したら、まず武器放棄を命じて、どうしても必要であれば威嚇攻撃の上、拘束し収容する、というのが順当な手続きでしょう。
また上の2)で書いた通り、体制幹部や工作員などは、武器は一切持たずに市民や戦争被災民を装って入国を試みると思いますので、そちらの方が質的には審査がずっと難しくなると思います。
5)難民はテロリスト?
世界にはテロリストの定義がありませんので網羅的な統計資料はないのですが、欧州諸国で起こっている「テロ事件」は、いわゆる「ホーム・グロウン・テロリスト」すなわち自国民あるいは移民の2世・3世などによるものが殆どです。
その国の社会経済政策に極端な不満を持っている者、またはひどい外国人差別などの被害者が、自暴自棄になって起こしたものです。テロの原因は「彼らが外国人だから」ではなく、「その国の社会経済政策や移民の統合政策が失敗しているから」です。
そもそも、日本には既に223万人以上の定住外国人がいますし、難民や庇護申請者も近年1万人以上、日本に来ています。彼らによる「テロ事件」というのは聞いたことがありますか?
少なくとも戦後に日本国内で起きた「テロ事件」は全て日本人によるものです。複数の市民が犠牲になった日本における大規模殺傷事件(例えばオウム事件、佐世保の乱射事件、「津久井やまゆり園」の事件)も、犯人は外国人ではありません。
少なくとも過去の事実に基づくのであれば、日本人によるテロ対策に力を入れるべきでしょう。これはおそらく「外国人はテロリスト」という幻想を広めたい人にとっては「不都合な真実」だと思いますが、幻想ではなく真実を直視したいものです。
ちなみに国際法上、万が一庇護を求めてきた人がテロを画策していることが判明したら、その時点でその人は「難民」の定義から外れますし、もし一旦「難民」として認定されても、日本の安全にとって危険人物であることが判明した場合には、一定の条件下で母国に追放・送還して良いことになっています(難民条約第1条Fと33条2項)。
もちろん、副総理自身が上で書いたような国際難民法や国内入管法の詳細を最初から知っている必要はないかもしれません。
でも、もし本当に難民危機が訪れると思っているのに、私のブログで書いてきたようなベーシックなことさえブリーフできる人材がいない政権、あるいはブレインはいるのにその人が言うアドバイスや事実に基づかない言説を繰り返す副総理がいる政権で、本当に大丈夫なのでしょうか?
選挙中なのであえて明記しておきますが、私は個人的に「反自民」ではありません。自民党内にも、知性と良心を持った素晴らしい政治家が(特に宏池会系を中心に)沢山いらしたと理解しています。けれども現政権が北朝鮮難民に「きちんと対応できる政府」なのかどうか、麻生副総理の発言を聞く限り、残念ながら疑問を持たざるをえません。
現政権は、北朝鮮難民に「きちんと対応できる政府」?
以前のブログにも書いた通り、朝鮮有事の際に大量の難民は日本には来ません。
橋本直子
ロンドン大学高等研究院難民法イニシアチブ リサーチ・アフィリエイト
2017年10月17日 10時28分 JST
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/pdfs/giteisho_01.pdf
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/k_jindo/pdfs/giteisho_02.pdf
9月23日に日本の副総理が、朝鮮半島から大量の難民が日本に押し寄せる可能性に触れ、
武装難民かもしれない。警察で対応するのか。自衛隊、防衛出動か。射殺ですか。真剣に考えなければならない。
と発言したことが物議を醸しだしました。
この発言の表面上の乱暴さについてひとまず置いておくとして、北朝鮮難民がボートで漂着した際にどのような対応をすべきか具体的かつ真剣に考えておく必要があるという点は、的を得た発言と言えます。
そこで、日本政府が批准している国際条約に則るとどのような対応が適切なのか、少し丁寧に考えてみましょう。なお、北朝鮮有事の際に本当に「大量の難民」が日本に押し寄せる可能性があるのかについては、既に過去のブログに書いていますのでここでは割愛します。
1.武装していても難民は難民
今回の副総理の発言を受けて、あたかも「武装している難民は保護しなくてよい」かのような誤解が散見されますが、武器を保持していようがいまいが難民は難民です。一旦日本の領域や領海内に入ったら、彼らを人道的に保護する法的義務が日本政府に発生します。
難民の定義については既に過去のブログで説明していますので詳しくは繰り返しませんが、基本的に母国(北朝鮮)での迫害を逃れて他国(日本)に保護を求める人です。「武器を持っていたら難民ではない」などという条文はどこにもありません。
実際、自衛のために武器を所持せざるを得ない難民は世界中で大勢います。残念ながら、(潜在的)難民が母国にいる間に外国政府からビザを発給してもらえることは非常にまれなので、彼等の大多数は非合法な方法で他国に入らなければなりません。
その非合法入国を目指す上で暗躍しているのが密航業者や人身売買業者で、密航途中にそのような業者やギャング達に暴行されたり殺害されるケースが実際に頻発しています。
難民達は文字通り命からがら逃れてくるのであって、そのような業者やギャングから自分の身を守るために必要な自衛の策を講じるのは、人間として当たり前のことでしょう。
因みに、北朝鮮からの漂流民は(日本人の拉致被害者や北朝鮮帰還事業で北朝鮮に渡った方の子孫以外)ほぼ100%不法入国になるはずですが、不法入国を理由として難民を処罰してはならない、というルールも既に確立しています(難民条約第31条)。
北朝鮮出身者が不法に日本の領海や領域に入ったとしても、難民なのであれば適切に保護する法的責任が日本政府にあります。
但し実際問題として、本当に日本に保護を求めてくる北朝鮮難民であれば、保護してほしい相手、つまり日本政府(海上保安庁、海上自衛隊、入管職員、警察など)を攻撃してくるというのは、矛盾する態度でしょう。
従って、それらの人々が日本の領海や領域内に入った段階で、朝鮮語で「こちらは日本政府である、武器を放棄せよ」と再三警告してもまだ攻撃してくるような態度を示した場合には、難民である可能性が低いかもしれない、と疑うことはできるかもしれません。
そのように、こちらが保護してあげる態度を明確に示したにも関わらず、いつまでも攻撃を仕掛けてくる漂着民については、一旦難民かどうかの判断を保留して、警察なり自衛隊なりが通常の手続き規則に則って武装解除して拘束すればよいのです。
軍事や公安専門家ではない私にでさえ、例えば威嚇攻撃や足元・手元の狙撃といった武装解除措置はすぐに思いつきます。日ごろから公務員としてきちんとした訓練や研修を受けている日本の自衛隊や治安当局の方々であれば、問題なく対応できるでしょう。
そのように粛々と武器を放棄させた上で、一定の宿泊所などに保護ないしは収容して、一人一人の身分事項を確認し、難民かどうか(つまり北朝鮮に送還したら迫害のおそれがあるかどうか)の判断を、時間をかけて落ち着いて行えばよいのです。その際、最初から丸腰で保護を求めたきた漂着民と、武装解除措置が必要だった漂着民を、念のため分けて保護するといったことも考えられるでしょう。
いずれにせよ、漂着民が武器を持って入域・入国したからといって、本当に難民なのかどうかの審査もせず「射殺する」などといった極端な措置をとる必要は一切ありません。そのような提案をすることは逆に、日本の領域・領海・国境を最前線で日々守って下さっている海上保安庁、自衛隊、入管職員、警察の方々のプロ意識と能力を過小評価し過ぎではないでしょうか。
また、難民かどうかの判断について難民条約(第1条F)は、母国で迫害のおそれがあっても国際法上「難民とは認められない人」も規定しています。簡単に言うと、(1)平和に対する罪、戦争犯罪、人道に反する罪を犯した人、(2)日本国外(主に母国)で重大な犯罪を犯した人(政治犯は除く)、(3)国連の目的や原則に反する行為を行った人です。
漂着した段階で、その北朝鮮出身者がこのような罪を犯した人である確固たる証拠を日本の公安側が持っている可能性がどれほどあるのか分かりませんが、例えば金正恩体制の幹部などは明らかに「難民」の定義にあてはまらないでしょう(その後の処遇については以前のブログを参照。)
更に難民条約は、戦争状態や緊急事態の場合には、最低限必要な期間のみ「暫定措置」を採ることを認めています(第9条)。具体的には、日本が戦争か緊急事態にあるため、丁寧に一人一人の漂着民が「難民かどうか」の審査をできない間だけ、拘束ないし収容するといった措置が想定されます。
但しその暫定措置は、難民性の判断ができない間、あるいはそのような暫定措置が必要かどうかを判断するために必要な期間だけに限られますし、措置は「暫定的」でないといけないので、「射殺」などといった最終的措置は含まれません。
2.難民の「射殺」は「人道に対する罪」または「戦争犯罪」
一言でいえば、難民を射殺することは殺人で犯罪です。特に殺人行為が、例えば副総理からの指示に基づいて国家の政策として組織的に執行された場合には、「人道に対する罪」という国際犯罪であることが、日本政府が2007年に加入した「国際刑事裁判所に関するローマ規程」の第7条(1項の(a))に定められています。
この場合、射殺された難民が「文民」であることが条件ですが、国際人道法上、単に武装しているだけでは「戦闘員とはみなされない」(つまり文民である)こと、そして文民かどうかわからない時には文民と見なすことが既に確立しています(ジュネーヴ条約第一追加議定書第50条)。
更に日本が北朝鮮と国際的武力紛争(つまり戦争)をしている間は、北朝鮮からの(文民である)難民を殺害することはもちろん、たとえその難民が漂着時に武装している「戦闘員」だったとしても、武器を放棄したにもかかわらず殺害したり負傷させることは、「戦争犯罪である」ことが、国際人道法と上記のローマ規程(第8条「戦争犯罪」2項(a)の(i) 、(b)の(i) と(vi))に定められています。
日本政府はこのローマ規程に加入した際に、その規定に沿った形で国内法を整備していますので、そのような「人道に対する罪」や「戦争犯罪」が犯された場合には国内法に則って犯罪者を起訴・処罰されることが期待されます。しかし、もし日本政府が捜査と起訴を真摯に行う意思や能力がないと判断される場合には、国際刑事裁判所の検察官が独自に捜査し起訴することも可能です(ローマ規程第13条・第17条)。
国際刑事裁判所は、第二次世界大戦後の極東国際軍事裁判とニュルンベルク裁判の反省に基づき、また1990年代に設立されたルワンダ国際戦犯法廷および旧ユーゴスラヴィア国際戦犯法廷の経験を踏まえて設立された常設の国際刑事法廷です。
日本外務省のウェブサイトによれば、我が国は、ICC規程の起草時より、重大な犯罪行為の撲滅と予防、法の支配の徹底のためICCを一貫して支持しているそうです。
日本の政治家が再度、国際犯罪の被告人として戦犯法廷に出るような不名誉な事態にならないよう、切に願いたいものです。
3.日本には既に多数の漂着民を保護した経験がある
実は日本は、主に1970年代後半から1990年代にかけて、1万3000人以上のインドシナ難民が自力で漂着ないしは海難救助されて日本に上陸した、という経験を有しています。その間、日本国内で2か所のレセプションと救援センターが設立・運営されていた時期もありました。
確かに、海難救助に始まり、一人一人の身元確認から、健康診断、日々の衣食住の手配などなど、少なくとも一定期間はそれら漂着民の全ての面倒を見なければならないのは大変なことです。
でもこれは世界中のどの国家も果たしている義務であり、残念ながら日本だけが逃れられる訳ではありません。
特に日本は、シリア難民を数百万人抱えている国々から、負担分担という意味でシリア難民を受け入れるという積極的な「痛み分け」をほとんどしてきていません(今のところ5年間で最大150人の留学生の受け入れ措置に留まっています)。
よって、「以前日本がうちの負担を分けてくれたから」、「今日本が大変なら昔のお礼として」といって日本にいる北朝鮮難民をわざわざ引き受けてくれる国はまず出てこないでしょう。これが国際政治の現実的「相互主義」というものです。
まとめると、武装している状態で漂着しても難民は難民ですし、そのような難民を文民か戦闘員かの判断をすることなく十把一絡げに射殺したら、「人道に対する罪」ないしは「戦争犯罪」として、場合によっては国際法廷で裁かれ処罰されます。
今すべきことはそのような犯罪を犯すかのような極端な発言をすることでなく、日本自身が持つ豊富な過去の経験を踏まえ、危機管理施策に基づく具体的なシミュレーションをしておくことではないでしょうか。
「武装難民」は射殺してもいいの?
条約から読み解く難民のこと
橋本直子
ロンドン大学高等研究院難民法イニシアチブ リサーチ・アフィリエイト
2017年09月26日 10時35分 JST|更新 2017年09月27日 JST
朝鮮半島での緊張が高まっています。北朝鮮が北東アジアの安全保障にとって不安定要素であることは新しいことではありませんが、昨今の動きを踏まえ、日本の安倍首相も朝鮮半島有事の際に予想される日本への避難民流入の対処策を検討していることを明らかにしました。
では、朝鮮半島有事の際に本当に日本に「大量の避難民が流入する」可能性があるのでしょうか? 結論から言うと、それほど大量の北朝鮮出身者を日本が保護しなくてはならなくなることは考えにくいですが、シナリオによっては「質」的に難しい判断を求められるケースが出てくるだろうと筆者は考えています。以下で少し詳しく検討してみたいと思います。
シナリオ1:北朝鮮が攻撃されたが、金正恩体制が維持される場合
軍事専門家によればその可能性は低いとされているようですが、何らかの形で(恐らく米国により)北朝鮮の国土が砲撃され、一般市民(国際法上では「文民」とか「非戦闘員」と呼びます)が住む地域にまで砲撃の被害が及んだ場合、彼らはまず北朝鮮国内で「国内避難民」となるでしょう。
また砲撃と戦争により北朝鮮当局の国境管理が緩慢になり、一般市民が北朝鮮国外に逃れることが現在よりも簡単になるかもしれません。その場合、圧倒的大多数はまず韓国(あるいは中国経由で韓国)に逃れるでしょう。物理的に陸続きですし、また韓国の憲法上、北朝鮮籍を有する者は韓国に入国できたら一定の身元確認作業を経た後で原則的に韓国の市民権を得られることになっています。言語や文化、歴史的背景また親族関係という意味でも、韓国に逃れることが大多数の北朝鮮市民にとって最も合理的な選択と言えるでしょう。
その一方で数は限られるでしょうが、北朝鮮から海を渡って日本に辿り着く人々が増える可能性もあります。そのうちの多くが上記の理由から最終的には韓国行きを希望するはずですが、もし日本への一時的避難あるいは定住を希望する場合、日本政府はどのような対応をすることが適切なのでしょうか?
まず、北朝鮮から辿り着いた人々の中に拉致被害者の方が混ざっていた場合、彼らはもともと日本国籍を有しますので、確実に日本政府に保護義務があります。今までも拉致被害者の方々で日本への帰国を果たされた方々はいらっしゃるので、その方々と同様の処遇となるでしょう。この点は大きな問題とはならないでしょう。
次に、北朝鮮から日本に辿り着いた方々の中にいわゆる「日本人妻」とその子孫が混ざっていたとします。「日本人妻」とは1959年から1984年まで続いた「北朝鮮への帰還事業」において北朝鮮に渡った日本国籍保持者のことで、実際に今何人くらいの方々が北朝鮮でご存命か定かではありません。
しかし、この方々もそもそも日本人ですし、また北朝鮮で日本人妻から生まれた子孫も母子関係を証明できれば日本国籍を「就籍」することが可能ですので日本人となり、日本政府が保護する責任がある対象となります。恐らく、中国残留邦人の方々への対応と同じような対応が適切となるでしょう。
では、北朝鮮から到着した人がそのような日本国籍も日本人との血縁関係も無い方の場合はどうなるでしょう?
まず、米国と北朝鮮との戦争が継続している間で、しかも米国との同盟関係やいわゆる「安保法制」に基づき日本も「紛争当事国」と見なされる程度に関与することになった場合、国際人道法(特に「戦時における文民の保護に関するジュネーヴ条約」と「国際的武力紛争の犠牲者の保護に関するジュネーヴ条約追加議定書」)が適用することになります。
日本も(ちなみに北朝鮮も)この2条約の締約国ですので、その内容を遵守する法的義務が生じます。この2条約は紛争下における文民の保護と処遇についてかなり詳しく定めていて、日本の管轄権内にいる北朝鮮出身の非戦闘員や文民についてはこの条約上の義務に基づいて人道的に取り扱う義務を日本政府が自ら負っています。
また戦争が終結した後でも、日本に辿り着いた北朝鮮出身者を北朝鮮に追い返すわけにはいきません。というのは、この「シナリオ1」では金正恩体制が継続する想定になっており、現在の体制下では、北朝鮮当局の正式な許可なく国外逃亡を企てた者は(北朝鮮に帰国後)投獄、強制労働、拷問、処刑などの「迫害」の対象となることが明らかになっています。
従って、北朝鮮当局の許可なく日本に逃れた北朝鮮出身者は難民条約上の「難民」となり、彼らを北朝鮮に送還することは難民条約に違反します。また政治的にも、そのような者を北朝鮮に送還することは「日本政府は金正恩体制を支持・信頼しています!」というメッセージになってしまうため、戦略的にも絶対に行うべきではありません。
もっともここで述べたことは必ずしも新しいことではありません。日本政府は「北朝鮮制裁措置」の文脈で、北朝鮮との間では原則的に人的往来を禁止していますが、日本の領域・領海内に辿り着いた脱北者については今までも少なくとも「上陸特別許可」を与え、身分事項や本人の意思を確認した上で、北朝鮮当局による人権侵害の被害者については「北朝鮮人権法」に基づいて保護と支援を施してきているものと筆者は理解しています。
従って、朝鮮半島有事によって数が一時的に増えたとしても、従来行ってきた通りの「脱北者」に対する保護・支援措置を粛々と進める、というのが基本的なスタンスとなるでしょう。
ただしここで注意すべきは、そのような北朝鮮出身者は北朝鮮が砲撃されている、あるいは戦争状態だから「難民」と認められるのではない、ということです。今までのブログでも繰り返し述べている通り、一般化された紛争や戦闘状態を逃れただけでは国際難民法上にいう「難民」とは認められません。「難民」とは「迫害のおそれ」を逃れたものであり、北朝鮮出身者が「難民」とみなされるのは、上で述べた通り、もし送還されたら「非合法的出国」に対する北朝鮮当局による懲罰措置が待っていて、その懲罰措置の内容が「迫害」に該当するからです。決して戦争状態だからではありません。この点は未だにかなり広く誤解が見られますので、繰り返し強調しておきたいと思います。
シナリオ2:北朝鮮が攻撃され、金正恩体制が崩壊する場合
このシナリオでも、上の「シナリオ1」で述べたことが、国際人道法に基づく保護の部分まではそっくりそのまま適用します。ただし、異なってくるのは北朝鮮出身者つまり脱北者を「難民」と認めるかどうかの点からです。
シナリオ1で、戦争終結後に北朝鮮出身者を送還することができなかったのは、金正恩体制が存続しているため帰国したら「迫害」を受ける可能性があるからでした。ところがシナリオ2では金正恩体制は崩壊しているので、厳重な国境管理・出国禁止措置がなくなり、より多くの脱北者が出てくると想定されると同時に、「非合法的出国」に対する懲罰的措置もなくなっている可能性があります。
もちろん、戦争継続中に北朝鮮に送還することはシナリオ1で触れた国際人道法に抵触しますが、戦争終結後かつ金正恩体制崩壊後に樹立される政権の中身によっては、今まで「迫害のおそれ」とされてきた懲罰措置がなくなり、脱北者をほぼ自動的に「難民」と認める法的根拠がなくなる可能性もあります。
また(あくまでも希望的観測に過ぎませんが)軍事独裁政権が崩壊し、自由民主主義を掲げる暫定政権が樹立する可能性も全くゼロではありません。更に言えば、南の韓国でどのような新政権が発足するかにもよりますが、本格的な「南北統一」に向けて朝鮮半島が動き出す可能性も、少なくとも「想像」することは可能です。そうなると、日本に一時避難していた北朝鮮出身者は朝鮮半島への帰還をより多くの者が希望するでしょう。
もっと言えば、在京韓国大使館(や総領事館等)におけるビザ・渡航文書発給手続き、あるいは暫定的国籍付与(確認)手続まで可能になれば、その方々は韓国から「新たな国籍」(あるいはそれに準ずる地位)を得る(あるいは確認される)ことになるので、日本政府が彼らを「難民」として保護する法的責任は無くなります。このことは難民条約第1条Cで「難民の地位の終止条項」として規定されています。
ただし、金正恩体制が崩壊した場合には、難民法に加えて「国際刑事法」の観点から一つ難しい問題が生じることになります。これは政変が生じた際に往々にして問題になるのですが、新体制・新政権が発足した後、その政変の生じ方によっては、前体制・前政権側と見なされる人々が逆に弾圧の対象となることがあります。要するに、金正恩体制「側」であった人、またそのように一般に見なされている人で、政権交代後に弾圧に遭うおそれがある人をどこまで保護するのか、ということです。
ここで特に難しくなるのは、「前体制・前政権側」と見なされる人々のうち特に金正恩氏の側近や政府高官であれば、拷問や迫害、超法規的殺害などに首謀的な立場で能動的に関わっていた可能性があります。そのような「平和に対する罪、戦争犯罪及び人道に対する罪」、または「国連の目的や原則に反する行為」を行っていた人々は、難民条約第1条Fで「難民」の定義から除外されることとなっていますので、日本政府ももちろん彼らを日本で保護する必要はありません。
ただし、北朝鮮のような全体主義的軍事独裁体制では、どこまでの人々を「前政権側」あるいは上記のような犯罪の「加害者」または「共謀者」・「加担者」と見なし、どこからを「一般市民」つまり「あくまでもいやいや金正恩体制に付き合っていた人」と見なすのかの判断は容易ではありません。
新政権樹立後の(北)朝鮮で「前体制・前政権側」と見なされ弾圧や迫害のおそれがある人については、日本政府は「難民」として保護する国際法上の義務がある一方で、深刻な国際犯罪を犯した「前体制・前政権側」の者を保護する必要は無いのです。むしろ国際刑事裁判所での訴追に向けた手続きを進めるべきでしょう。
従ってその両者の間の見極め、つまり「金正恩体制による国際犯罪の首謀的加害者」から「前体制・前政権支持者と見なされ迫害のおそれがある一般市民」までの間のどこで線を引くのかが、冒頭で述べた「質的に難しい判断を求められるケース」にあたります。国際難民法と国際刑事法の原則と潮流(つまり判例法)を重ね合わせた対応が求められることになるでしょう。
最後に、上記の二つのシナリオに加えて、シナリオ3として「韓国が北朝鮮によって攻撃され、韓国籍を有する人々が日本に保護を求める場合」、さらにシナリオ4として「北朝鮮によって日本が攻撃される場合」もあくまでも想定としては考えられます。これについては別の視点からの検討が必要になってきますので、別のブログに先送りしたいと思います。
朝鮮半島有事で日本に大量に「難民」が流入するの?
朝鮮半島有事の際に本当に日本に「大量の避難民が流入する」可能性があるのでしょうか?
橋本直子
ロンドン大学高等研究院難民法イニシアチブ リサーチ・アフィリエイト
2017年04月30日 23時13分 JST

選択的夫婦別姓になると、名字の異なる人が同じ地番に住むことになり、郵便屋さんに支障が出るという言説がありますが、誤りです。同じ住所に異なる姓の人が住む例は現在までも数多くあり、郵便局は郵便物に記された宛名にこれまでも届けていると説明しています。
検証対象
拡散したツイート
「選択的夫婦別姓制度が適用されると、家長がはっきりせず、バラバラの名字で同じ家に住む人が増えて郵便屋さんが困ると言っている」などという内容のツイートが拡散した。4月17日現在、610万件以上の表示があり、リツイート・引用リツイートは2500を超える。 この書き込みに対して「配達員はマジで困る!」というリプライもあったが、「我が家はそれぞれ世帯主で苗字が違いますが郵便屋さんが混乱したことはありません」「私の旧姓と家族の苗字を併記した郵便受けで10年以上ですが、郵便も宅配も混乱なく届けていただいてます」など否定する書き込みも多数あった。 「困る」かどうかは個々の配達員によって感じ方が異なる可能性がある。日本ファクトチェックセンター(JFC)は、実際に郵便配達に支障が出るのか検証した。
検証過程
そもそも、二世帯・三世帯住宅や旧姓で働く人など、同じ地番に異なる名字の人たちが住んでいる事例は現在でも多い。日本ファクトチェックセンター(JFC)は、日本郵便株式会社に問い合わせた。日本郵便の広報からは以下の回答があった。 「弊社では、同一住所に異なる姓の方がお住まいであっても、郵便物等に記載されたあて名へ配達しております。引き続き、正確な配達を行うよう努めてまいります」 これまでも同一住所に複数の名字の人が住んでいても、郵便物の宛名通りにそれぞれの人に届けているように、今後、選択的夫婦別姓が実現したとしても、対応は変わらないということだ。 また、選択的夫婦別姓制度について調査検討を進めてきた「内閣府男女共同参画局」に問い合わせたところ、これまで姓の異なる人が増えると郵便配達に支障が出るかに関して検討や調査を実施したことはないという。 この投稿をしていたアカウントに、問い合わせフォームを通して取材を申し入れたが、17日の午後5時までに返信はなかった。
判定
以上により「選択的夫婦別姓でバラバラの名字で同じ家に住む人が増えると郵便配達に支障が出る」というのは誤り。 あとがき 検証:宮本聖二 編集:古田大輔、藤森かもめ 検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。 「ファクトチェックが役に立った」という方は、シェアやいいねなどで拡散にご協力ください。誤った情報よりも、それを検証した情報がより広がるには、みなさんの力が必要です! noteやTwitter、Facebookなどのフォローもよろしくお願いします。今後はYouTubeなど動画発信にも取り組んでいく予定です。

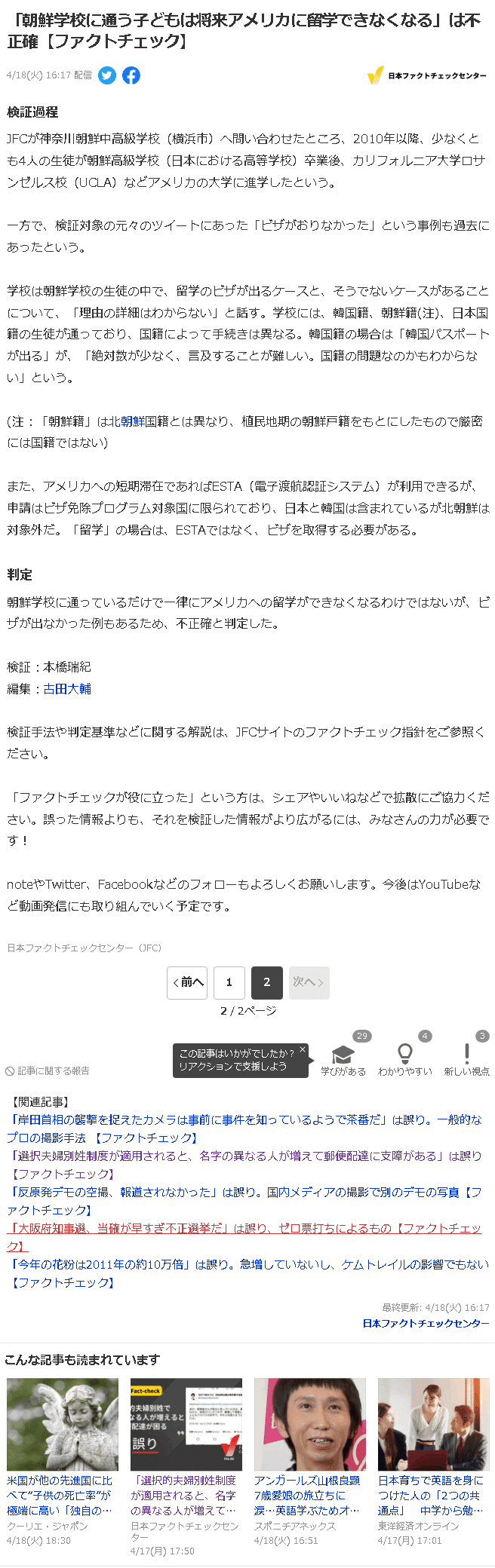
検証過程
JFCが神奈川朝鮮中高級学校(横浜市)へ問い合わせたところ、2010年以降、少なくとも4人の生徒が朝鮮高級学校(日本における高等学校)卒業後、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)などアメリカの大学に進学したという。 一方で、検証対象の元々のツイートにあった「ビザがおりなかった」という事例も過去にあったという。 学校は朝鮮学校の生徒の中で、留学のビザが出るケースと、そうでないケースがあることについて、「理由の詳細はわからない」と話す。学校には、韓国籍、朝鮮籍(注)、日本国籍の生徒が通っており、国籍によって手続きは異なる。韓国籍の場合は「韓国パスポートが出る」が、「絶対数が少なく、言及することが難しい。国籍の問題なのかもわからない」という。 (注:「朝鮮籍」は北朝鮮国籍とは異なり、植民地期の朝鮮戸籍をもとにしたもので厳密には国籍ではない) また、アメリカへの短期滞在であればESTA(電子渡航認証システム)が利用できるが、申請はビザ免除プログラム対象国に限られており、日本と韓国は含まれているが北朝鮮は対象外だ。「留学」の場合は、ESTAではなく、ビザを取得する必要がある。
判定
朝鮮学校に通っているだけで一律にアメリカへの留学ができなくなるわけではないが、ビザが出なかった例もあるため、不正確と判定した。 検証:本橋瑞紀 編集:古田大輔 検証手法や判定基準などに関する解説は、JFCサイトのファクトチェック指針をご参照ください。 「ファクトチェックが役に立った」という方は、シェアやいいねなどで拡散にご協力ください。誤った情報よりも、それを検証した情報がより広がるには、みなさんの力が必要です! noteやTwitter、Facebookなどのフォローもよろしくお願いします。今後はYouTubeなど動画発信にも取り組んでいく予定です。
日本ファクトチェックセンター(JFC)
入管法と関係ありの「朝鮮」籍を持つ人に対する日本の再入国許可制度が
「誓約書」強要で問題に。
この法的根拠のない「誓約書」強要問題が日本国籍の日本国民に対してもあったのですよ、コロナ禍でね。
元衆院議員の山尾志桜里さん(47)が2日、自身のツイッターを更新。先月31日にイタリアでの国際会議から帰国した際、新型コロナウイルス対策として提出を求められた「誓約書」について「法の根拠なく自粛を政府から事実上強制・誓約させられるいわれはない」などとして、一部を書き加えるなどして提出したと報告した。
山尾さんは自らが記した「誓約書」画像をアップ。本来は厚生労働大臣と法務大臣宛てに感染防止のために定められた事項を守ると誓約し、署名することが求められているが、山尾さんは「政府に対し誓約する義務はないと考えますので誓約いたしません。ただし、私は自らの意思でこれらの記載事項を守り、感染防止策を講じます」と署名欄外に記して提出した。
入国手続きには支障がなかったようで「なにひとつ質問されずに手続き終了。なんのための誓約書なんでしょうか?誓約しなくても提出すりゃいいってこと?」と山尾さん。「公共交通機関不使用にしろ14日間待機にしろ、本当に必要だと考えるなら法で根拠づけるべき」と問題提起した。
山尾さんは31日の衆院選には不出馬。「議員卒業」を宣言している。
新型コロナ水際対策の隔離誓約書「法的根拠ない」と山尾志桜里・元議員、事実上の入国素通りに問題提起
2021年11月2日 17時32分

海外渡航の「朝鮮」籍者に「誓約書」強要する入管当局――再入国許可の取り消し警告も 韓東賢日本映画大学教員(社会学) 2016/4/3(日) 22:30

「朝鮮・韓国籍」分離集計の狙いとは?――3月公表の2015年末在留外国人統計から 韓東賢日本映画大学教員(社会学) 2016/3/7(月) 21:39
朝鮮学校の金一族の社会主義独裁体制容認は嫌ですけど朝鮮学校無償化署名にせやなって感じで朝鮮学校無償化署名したことある。
1.今回の第5回政府報告書における在日韓国・朝鮮人に関する項目は、「偏見・差別をなくすための啓発活動」、「外国人登録証明書の携帯義務」、「朝鮮学校」のみにすぎず、「在日韓国・朝鮮人問題」は、ほとんど何も触れられていないに等しい。
2.主体について
-「在日韓国・朝鮮人」は「特別永住者」だけではない-
いわゆる「在日韓国・朝鮮人」と呼ばれる人たちは、日本の植民地支配に基づき、日本での居住を余儀なくされた者及びその子孫をさす。この点、政府報告書においては、「外国人登録証明書の携帯義務」の項目におけるように、「特別永住者」と一括して呼称されている。
しかし、再入国期間内に日本に戻れず、あるいは再入居区許可を得られないまま出国した者は、新規入国者扱いとなって、この「特別永住者」という在留資格を剥奪されている。また、他にも、「一般永住者」(通常の一般外国人として永住権を申請し許可された者)、「定住者」(一般外国人としての永住権申請をしていない者あるいは申請しても拒否された者)が存在している。
従って、そもそも、「在日韓国・朝鮮人」を法律要件を満たした者のみに与えられた「特別永住者」に置き換えることはできないのであり、こうした置き換えは、「在日韓国・朝鮮人」の歴史性を捨象するのみならず、法的地位の安定が全く顧みられない「在日韓国・朝鮮人」を生み出してしまうことになる。
3.「偏見・差別をなくすための啓発活動」について
-「啓発活動」のあり方-
政府報告書によると、「外国人の人権擁護のための活動の1つとして、在日韓国・朝鮮人に対する偏見・差別をなくすことを含めた啓発活動を行っている」としている。しかし、「在日韓国・朝鮮人」に対する偏見・差別の除去のために必要不可欠なのは、その歴史的背景を周知させることである。
また、政府報告書では、「拉致問題」に伴い発生した在日韓国・朝鮮人児童・生徒らに対する嫌がらせ等につき、パンフレット・チラシ等の配付を挙げ、さらに、「在日韓国・朝鮮人児童・生徒に対し、嫌がらせ等を受けたときには、法務省の人権擁護機関に相談するよう呼びかけを行った」とするが、こうした「相談」に基づき、法務省が「啓発」を行った前例は存在しない。むしろ、「拉致問題」以降、本名での営業活動中に顧客から「北のスパイだ」などと誹謗中傷を受けたとして損害賠償請求を求める民事裁判が提訴されているように、「在日韓国・朝鮮人」全体をめぐる状況は悪化しているといえる。
従って、現在、日本社会に求められているものは、啓発では不十分であり、こうした差別を禁止する立法措置であると言わざるを得ないが、2001年の委員会勧告39項で「非差別立法を強化することを強く勧告」されているにもかかわらず、全くその言及はなされていない。
4.「外国人登録証明書の携帯義務」について
-変わらない日常的な治安管理-
政府報告書によると、外国人登録証明書の携帯義務違反の罰則が行政罰に修正されたことを評価する一方で、「いわゆる不法入国者や不法残留者が多数存在する等の我が国の現状においては」、「外国人登録証明書の常時携帯を義務づける制度については、引き続き維持する考えである」としている。
まず、罰則が修正されたのは、「特別永住者」に関してにすぎず、その他の在留資格の場合は、やはり刑事罰が課せられる状況に変化はない。しかも、登録義務者となる16歳から適用されることになるのである。
5.「朝鮮学校」について
-日本の学校に通うこどもと民族学校に通うこども-
政府報告書では、「日本国籍を持たない外国人の子女であっても、我が国の公立学校において義務教育を受けることを希望する場合は、すべて無償で受け入れることとしている」とする。
しかし、日本の公立学校での義務教育は、「希望すれば受け入れる」という前提を崩しておらず、生徒の権利とはされていない。そのため、京都市の公立中学校の校長が、「外国籍の生徒には義務教育がないから退学にできる」という理由で、「在日韓国・朝鮮人」の生徒を退学扱いとしており、その違法性をめぐって現在、裁判で争われている。
また、政府報告書では、「大学入学資格検定の受験資格の拡大」や、「大学入学資格について弾力化を行った」として評価しているが、無条件に大学入学資格を認めた訳ではなく、現実に、未だに入学資格を認めない私立大学が存在している。のみならず、東京に続き大阪においても、行政が朝鮮学校の敷地につき裁判上の返還請求を行っており、「学ぶ場」そのものの存続すら不安定なものとなっている。
6.その他
-様々な「在日韓国・朝鮮人」をめぐる問題の棚上げ-
また、「特別永住者」以外の者の法的地位の安定化、再入国許可制度のあり方、公務就任権、社会保障システム、地方参政権、入居差別や就職差別、「嫌韓流」といった、在日に対する攻撃などの問題は、全く棚上げとなっている。
しかし、いわゆる少数者の人権保障は、少数者を取り巻く多数者の意識変革を促し、社会全体の人権が尊重されることにつながることからも、日本政府の差別解消に向けた積極的な施策が望まれるところである。
在日韓国・朝鮮人の現状から見た問題点
康由美
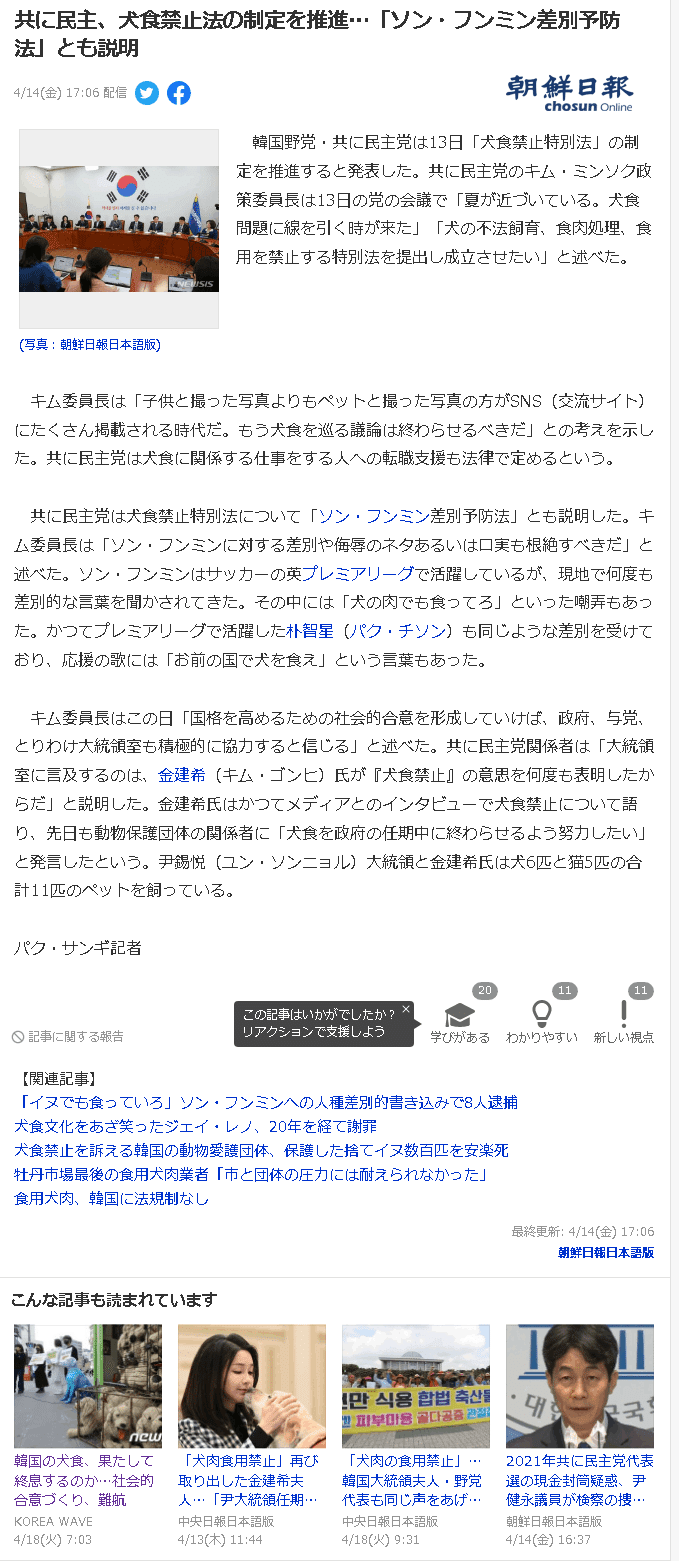

【04月18日 KOREA WAVE】韓国政府が犬食を終わらせるための議論を始めて数年が過ぎた。だが、依然として社会的合意案が導き出されていない。動物保護団体、大韓肉犬協会など利害関係者間の意見の相違が大きく、政府は関連ロードマップ作りに困難をきたしている。 農林畜産食品省によると、2021年12月に「犬食問題議論のための委員会」を発足させ、先月まで22回余り会議を開いたが、ロードマップの草案さえ用意されなかった。 犬食問題を議論するための委員会は、政府と動物保護団体、大韓育犬協会、専門家などで構成されている。メンバーは各界の意見をもとに、犬食問題の解決に向けた議論を進めているが、意見の隔たりが大きく、議論が遅々として進まない。 動物保護団体は、犬食文化が動物を虐待する「犬工場」を乱立させるなどの理由で早期に終息させるべきだと主張する一方、育犬協会など業界は零細商工人の生存権を訴えるとともに、動物虐待と食用犬の違いを強調している。 政府が犬食終息のための立法に着手するためには社会的合意案の準備が先行しなければならないが、この手続きが終わっていない。 1年4カ月余りの協議でも社会的合意案は出ていないが、政界では最近、犬食終息議論に火がついており注目される。 韓国のユン・ソンニョル(尹錫悦)大統領の妻キム・ゴニ(金建希)氏が最近、動物保護団体と会って、大統領の任期内に犬食を終息させるために努力するという立場を明らかにしたうえ、政界でも関連立法を推進しているためだ。 キム氏は「ある程度の経済規模の国の中で犬を食べるのは韓国と中国だけだ」とし、犬食終息への意志を明らかにした。 与党「国民の力」は14日、犬・猫を食用として使用・販売する行為を禁止する動物保護法改正案を発議した。犬・猫食用事業廃業申告をしたり業種を転換する場合、政府が支援金を支給できるようにする案も改正案に盛り込まれた。 野党「共に民主党」もやはり犬の不法飼育・食用を禁止し、従事している関係者の安定的な転職を支援する特別法を発議して通過させるという方針を打ち出した。

数年間繰り返されている「犬肉の食用禁止」論争に今度こそ終止符を打てるかどうか関心が集まっている。尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の金建希(キム・ゴンヒ)夫人はもちろん、169席を抱える巨大野党の政策委議長も「犬肉禁止」を公言しているためだ。 12日、金夫人は動物保護団体関係者と青瓦台(チョンワデ)常春斎(サンチュンジェ)で会って「犬食用を政府任期内に終息できるように努力したい」と明らかにした。金夫人は昨年6月、メディアインタビューでも「経済規模がある国のうち、犬を食べるのは韓国と中国だけ」としながら「犬の食用終息は政策で解決することができると考える」と話した。 金夫人の発言から2日後の14日、与党「国民の力」最高委員である太永浩(テ・ヨンホ)・趙修眞(チョ・スジン)議員はそれぞれ関連法案を発議した。太議員法案は犬や猫を食用で飼育したり販売するのを禁止した。趙議員も動物を殺す虐待行為に対する処罰程度を高める改正案を出した。 これに対して野党「共に民主党」では「金夫人の一言により与党議員が法を出す形」〔高ミン廷(コ・ミンジョン)最高委員〕という批判が出てきたが、事実「犬肉禁止」は李在明(イ・ジェミョン)民主党代表も強調してきた内容だ。李代表は大統領選挙予備選中だった2021年8月、京畿道高陽(キョンギド・コヤン)動物保護センター付近で動物福祉政策を発表しながら「犬食用販売禁止問題は容易ではないが進まなくてはならない道」と話した。李代表は城南(ソンナム)市長在職当時、牡丹(モラン)市場「犬販売場」撤去経験に言及して「5年間可能な方法を総動員してなくすことはしたが容易ではなかった」とも述べた。 金民錫(キム・ミンソク)民主党政策委議長も金夫人の発言翌日(13日)、政策調整会議で犬の食用禁止特別法を約束した。金議長は「伴侶動物時代、韓流時代で、孫興ミン(ソン・フンミン)選手に対する差別とヤジの素となった口実も根絶しなければならない」とし「特別法を発議すれば政府・与党、特に大統領室も積極的に協力するだろうと信じている」と話した。 「犬の食用禁止」は40年以上にも及ぶ議論の種だ。法令間で一致しない部分があるからだ。食品医薬品安全処所管である食品衛生法は牛・豚など食品原料として使える13品目から犬を除いた。反面、農林畜産食品部所管である畜産法は犬を家畜に含め、畜産物を「家畜として生産された肉など」に規定した。 特に畜産物加工処理法(現在の畜産物衛生管理法)施行規則が変わって混乱が大きくなった。一時施行規則に犬が鹿と共に屠殺が可能な獣畜のひとつに規定されたが、この条項が1978年改正時に消えた。農食品部関係者は「いかなる理由で変えたのかは記録が残っていない」と話した。 今も「補身湯(ポシンタン)」「四チョル湯(サチョルタン)」のような名称で犬肉飲食店が残っているのはこのような理由からだ。法理的な面だけから考えれば食品衛生法を根拠に営業停止や行政処分を下すことができるが、食品医薬品安全処は実際に取り締まらない。食中毒が発生した時に例外的に行政処分を下すだけだ。 国会はかなり以前から曖昧な法体系問題を知っていた。2011年国政監査で朱昇鎔(チュ・スンヨン)当時民主党議員は「屠殺段階までは農食品部が、屠殺以降は食品医薬品安全処が担当していて犬肉を囲んだ論争は続かざるを得ない」と話した。だが、10年以上経っても立法は遅々として進んでいない。肉犬協会は関連法が提出されるたびに生計対策準備を要求して反対デモを行った。国会関係者は「このように敏感な問題は全国選挙を控えているとうやむやになりやすい」とし「かえって総選挙直後が議論の『ゴールデンタイム』」と話した。
神真都Qさんの主張が陰謀論かは置いておいてコロナワクチンのmRNAワクチンDNAワクチンはトランプ共和党政権のワープスピードで生ワクチンや不活化ワクチンでさえ通常10年かけて検証されないといけないのに約1年で開発されたワクチンで副作用被害あるのは事実でmRNAワクチンはmRNAという遺伝子を構成する物質を使用してますしコロナワクチンであるmRNAワクチンDNAワクチンの特徴から人体の遺伝子組み換えに繋がると懸念されているのは事実ですから。

日本製鉄さん、ワクチン接種強制はあかんよ
— しまゆう (@p774tryb) December 5, 2022
国はこういうのを取り締まらなあかんのと違う?
こういう職場多いと思うよ
打て打てばかり言ってこういう切実な問題は野放しですか?#日本製鉄#厚生労働省#自民党#公明党 https://t.co/h5DGJDgJG6 pic.twitter.com/4Gi6LXjEVq


しまゆう
@p774tryb
日本製鉄さん、ワクチン接種強制はあかんよ
国はこういうのを取り締まらなあかんのと違う?
こういう職場多いと思うよ
打て打てばかり言ってこういう切実な問題は野放しですか?
#日本製鉄
#厚生労働省
#自民党
#公明党 https://t.co/h5DGJDgJG6
🚨本日のナチス日本DS紹介🙏
— 橋広バロン幸之助🇯🇵MJGA💫 (@hasibiro_maga) December 5, 2022
橋本 英二
日本製鉄代表取締役社長
日本経団連副会長
日本鉄鋼連盟会長
日本製鉄はワクチン4回強制
経団連はGITMO一択🙏
御愁傷様です🙏 https://t.co/R9ciBsfOA9 pic.twitter.com/Z8PoYycYKr


昨年3月、静岡県焼津市内の新型コロナワクチン接種会場に侵入したとして、建造物侵入罪に問われた、反ワクチン団体「 神真都やまと Q会」のメンバーで会社役員の被告の男(49)(掛川市)の初公判が17日、静岡地裁(国井恒志裁判長)であった。男は会場に入ったことを認め、弁護人は「『侵入』には当たらない」として無罪を主張した。
国内で新たに1万1901人コロナ感染…東京の1週間平均は5%増
静岡地裁
検察側の冒頭陳述によると、男は、昨年3月13日午後、ワクチン接種の中止を求める目的で、焼津市内の集団接種会場に侵入したとされる。
男の弁護人は「危険なワクチン接種の中止を求めることに違法性はない。無施錠の正面玄関から入っており、『侵入』ではなく、『訪問』だ」と主張した。
事件を巡っては、男を含む同会メンバー8人が昨年12月に建造物侵入容疑で逮捕され、静岡簡裁が罰金10万円の略式命令を出した。男はこれを不服とし、正式裁判を求めていた。
神真都Q会メンバーが接種会場へ、弁護人「侵入ではなく訪問だ」…初公判
2023/04/18 23:46
新型コロナ
第三章 国民の権利及び義務
〔国民たる要件〕
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
日本国憲法
