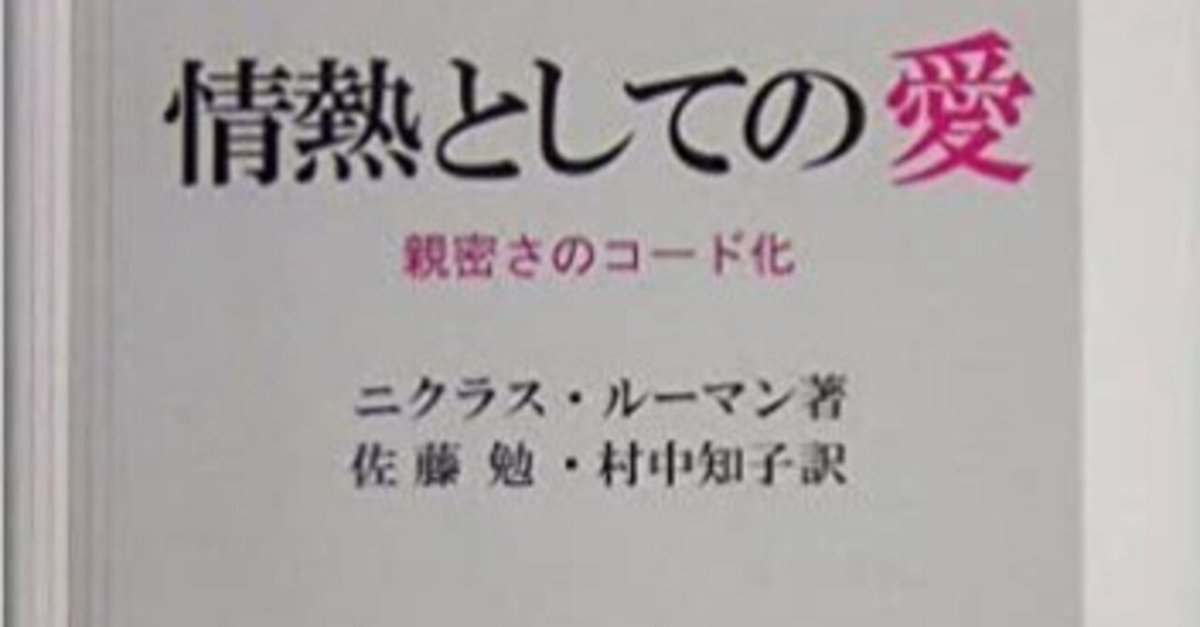
[読書の記録]ニクラス・ルーマン「情熱としての愛」(2013-08-01読了)
好きな人の条件を30個あげると結婚できるときいた。
「こいつとはずっと一緒にいたってもいい」
と思える、パートナーに求める条件をわりと厳しめに決めておくことで、満足できない相手と満足できない関係に陥るのを回避し、結婚までのコスト(時間的・精神的)を最小化しようという戦略らしい。
恋愛において「若さ」に対して異様なまでに大きな価値が置かれる日本では、若さが失われればずっと結婚できない可能性が高まる。そして若さは一度失われれば二度と取り戻すことはできない。したがって、特に出産適齢期との兼ね合いもある女性たちは結婚を急ぐ傾向にある。
私と同年代の女性たちも、このところ結婚適齢期を迎えている(※2013年に書いています)。結婚していく者もあれば、単身者は恋愛/結婚市場において現役プレイヤーとして活動できる残された時間を計算し、パートナー探しを焦りはじめている。
これから失敗できる回数に余裕がないアラサーにとって、効率よくパートナーを選定することは至上命題なのだ。
条件というのは例えば、
・よく笑う
・怒鳴らない
・煙草を吸わない
・年収1000万円以上
・長男ではない
といったヤツだ。
もちろん、こんなにありがちじゃなくてもいいけど。
で、こういう話になると必ず、言語哲学でいうところの確定記述の束と固有名に宿る剰余、あるいは社会学でいう機能主義と親密圏みたいな議論になってしまう。俗にいう商社マンでイケメンなら誰でもいいのか問題である。
だから、「恋愛は結局フィーリング♪パートナーに求める条件みたいな話は、飲み会でのネタ程度にしかならんじゃろ」という結論を、われわれは往々にしてだしがちだ。
ただ、30個というのは膨大なリストなので、すべての条件を満たす人を見つけることは簡単ではないし、すべてではないにせよ、条件に多く適合する人物を選んでいけば候補は必然的にかなり絞り込まれるため、近似的に「商社マンでイケメンだとしても、誰でもいいわけではナイ」を実現できる。
この30個という数の多さが、リスト化戦略の有効性の鍵であるといえそうだ。
もちろん、仮に30個の条件をすべて満たす人物が本当に現れたとしても、条件リストは、その人の個性を表現しきってはいないだろうし、世界のどこかには30個の条件を満たす人物が2人以上いたとしてもおかしくはない。
しかし例えば、30個の中でも重視する条件とそうでもない条件によって重みづけを変えて採点し、気になる異性について定量的にかつ多角的に評価する、というような使い方もできるかもしれない。
ここで提言したいのは、パートナーに求める条件のリスト化による逆説的な効果だ。
例えば、
・よく笑う
・怒鳴らない
・煙草を吸わない
・年収1000万円以上
・長男ではない
という要件を含めていたとしよう(わかりやすくここでは五箇条にしている)。
そんなあなたの目の前に、
・めったに笑わない
・怒鳴る
・ヘビースモーカー
・年収200万円
・長男
という男が現れたとする。
条件リストに合致していない項目があるので、本来ならパートナー候補から弾かれそうなものだが、それでも何らかの理由で、例えばわかりやすくそいつがハンパじゃない床上手だったとして、否応なく惹かれてしまったと仮定しよう。
そのときあなたは、自分で決めた条件を満たしていないにも関わらず、そのハンデを乗り越えてもなお、自分を惹きつけてくる彼に、より強く惹かれるのではないだろうか。
(あれ・・・こんなヤツ・・・一番きらいなタイプなのに・・・・・・でもなんで?気づくとあいつのことばかり考えてる・・・?!)
恐らくこうした、理性的に決めた自分ルールと、生殖という動物的な本能の間にはミスマッチがあって、管理しようとすれば管理しようとするだけ、本能は制御不能になるのではないかと考えられる。
男女ともに精神的ストレスもダイレクトにホルモン分泌などに影響を与えていることが知られている。「こうしなければならない」とか、「こうじゃないとヤダ」といった制約が増えれば増える ほど、ややこしいことになっていくのだ。
つまり30個条件を挙げるというようなリスト化思考は、理性に基づいて個人的なルールを設定することで、それを超えようとする本能のはたらきを強める効果があるのではないか。
ハードルが高いほど燃える!ということだ。
付き合う相手についての自分ルール。これを恋愛ハードルの第1形式と呼ぼう。
いっぽうで、ニューヨークの大停電の際、その停電中に恐怖を感じたカップルが性交渉をし、更に劇的に出生率が高くなった(明らかに停電中の性交渉で妊娠したと思われるベビーが後に一時期にまとまって生まれた)というから、本当に、ワイルドな動物的な本能を否定してはいけないと思う。
これはいわゆる吊り橋効果で、ふたりでストレスフルな状況を乗り越えるというハードルを共有することから、本能のはたらきが強まるパターンだ。
これを恋愛ハードルの第2形式と呼ぶ。
どこかセクシャルな分野というのは、野性的な要素に満ちていて、その欲求・要求から切り離せないので、それを考えたときに、ハードル設定の効果を侮るべきではない。
そして実は、個人的なルールを設定したり、吊り橋を一緒に渡ったりしなくても、世の中には恋愛関係になるうえで乗り越えるべきハードルが満ち満ちている。
ここでハードルがポジティブな役割を果たす、つまりハードルが存在することによって逆に恋する気持ちが強まる、と言うときに前提になっているのは、われわれの心の中で、理性(言語)によって記述可能な領域が、本能(言語化不可能な領域)を絶えず抑圧しているというフロイト派っぽい仮定である。
例えば親友の彼女に手を出してはいけないというのは理性からの語りかけであるが、それがテメエを繁殖に駆り立てるリビドーの働きを弱めることはない。
語りつくされていることだが、本能はDNAを残すために利己的な行動を促す。むしろ、不実を働いているときのほうが精液中の精子の数や運動量は増えるという医学的エビデンスすらある。
このような「裏切り」とか「不倫」のような、社会の規範や倫理に反するシチュエーションこそが恋愛を盛り上げる燃料となるケースは珍しくない。
理性に従えば、好きな女が親友の彼女である状況は、障害にほかならない。好きな女が親友と別れるのを待つか、あきらめて枕を濡らすかというのが理性に従った行動パターンである。
ところが理性の語りかけを振り払い、親友の彼女とヤル状況まで漕ぎ着ければ、それは有り体に言って非常に「エロい」し、正直、普通に彼氏がいない女とヤルより燃えるだろう。
自分が子孫を残す確率を増やしているだけでなく、他のオスが子孫を残す確率を減じているのだから当然である。
というわけで往々にして、ロマン主義的な恋愛を駆動するのはタブーであることが多い。
社会的に共有された規範や道徳観を、恋愛ハードルの第3形式と名付ける。
ここまで行った、何らかの形で設定される”ハードル”的なものの存在が親密な関係の構築に対して果たすポジティブな役割の類型化を再整理しておく↓
恋愛ハードルの第1形式:個人の理性が自らに課す障害(eg. 条件リスト)
恋愛ハードルの第2形式:男女(男女じゃなくても可)がふたりの間で共有している間主観的ストレス(ie. "吊り橋")
恋愛ハードルの第3形式:社会的に共有されたタブー
ドイツの理論社会学者ニクラス・ルーマンは、唯一といってもいいエピグラフ的著作『情熱としての愛』において、人間同士の親密な関係について私たちがあらかじめ共有している「コード」こそが、親密な関係を可能にする、と述べている。
つまり、例えばチェスのルールを知らないと遊べない(対戦者とコミュニケーションできない)のと同様、恋愛についても、恋愛がどういうものか、どういうコミュニケーションが期待されているか、前提を共有していなければ、恋愛することはできないということである。
コミュニケーションのコードとしての愛は、社会からの逸脱によって特徴づけられるとルーマンはいう。情熱としての愛のコードは道徳的な根拠を必要とせず、社会の秩序によってその持続が保証されるということもない。ルーマンもまた、社会的・道徳的規範からの逸脱に愛のエッセンスを見出す立場をとっているということだ。
愛の再帰性にとって不可欠なのは、こちらの感情と相手の感情が呼応することが双方の感情に基づいて肯定され探し求められるということ、言い換えれば私自身が愛する者としてまた愛される者として相手から愛され、相手も愛する者としてまた愛される者として私から愛されるということ、つまり自らの感情と相手の感情が呼応することなのである。愛は、私という人と同時にあなたという人にも向けられ、そうである限り私もあなたも愛の関係にあり、つまり私もあなたも互いにこうした関係を可能にしている──このように愛し合えるのは、私やあなたが善良であるとか、美しいとか、高貴であるとか、金持ちであるという理由からではない。
ロミオとジュリエットに典型的だが、文化表象において伝統的なタブーのひとつが、階級や人種を超えた恋愛だ。あるいは宗教上の理由や、親族同士の対立なども第3形式の恋愛ハードルとして機能する。
厳格なバプテスト派の家庭で育てられ、婚前の性的交渉など御法度中の御法度という環境でありながらも性的に奔放にふるまう少女たちが否応なくエロいソフィア・コッポラ監督の『ヴァージン・スーサイズ』はこの典型だ。ことハリウッド映画において、キリスト教的な倫理観は専ら破られるものとして消費されてきているのではないか。。
いっぽうで、世の中はガンガンリベラル化してきており、特にここ日本で民族や宗教上の価値観との齟齬が恋愛の障害になることはもはや考えづらい。
そこで昨今、わかりやすくタブーを超克する第3形式の恋愛ハードルとして代替的に消費されているのが
・NTR寝取られ
・同性愛
・年齢差
といった設定だと考えられる。
浮気や同性愛はまだまだ現代日本でもタブーとして共有されている。
あるいはAKB48なども、「恋愛禁止」というタテマエがありつつちょいちょいフライデーされている。これは、生殖能力がありながらも生殖してはいけないという少女(=処女)性を売り物にしているアイドルでありながら、その禁断が破られるところを見たいという逆説的な大衆の欲望を映し出している。
森山未来主演のドラマ/映画作品『モテキ』などからも見て取れる通り、最近では、身分/階級制度無き時代に疑似的に創出された身分差というものも、ハードルとして機能しているのではないかと考えられる。
すなわち、モテ層と非モテ層の間の差だ。
現在の日本で、金持ち、若い、イケメン、オシャレな趣味、夢、イケている友達がたくさん、高いコミュ力etc...といった恋愛資本を多く持つ者と、持たざる者の間では格差が絶えず再生産されている。ピエール・ブルデューを引くまでもなく。
リア充と非リア充の間の境界は、実質的に「恋愛してOKな層」と、「恋愛する資格がない層」の間の境界に近づいている。
映画版『モテキ』では、サブカルオタク、金なし、夢なし、学歴なし、友達もあんまいない、といった「恋愛する資格がない」層に属する幸生が、「恋愛してOK」な層に属するみゆきに恋をすることで物語が成立した。
これは極端に言ってしまえば奴隷から貴族への恋と本質的に差がない。現代の日本で非リアがリア充を好きになることはタブーなのだ。映画の序盤で、幸生はみゆきとの身分差を絶えず自分に問いかけ、葛藤する。
住む世界の違う女子に恋焦がれる平凡な男子という構図は、ビリー・ジョエルのヒット曲「アップタウン・ガール」や、わが国におけるヒュー・グラントの知名度を一気に高めた映画『ノッティングヒルの恋人』等でも描かれている。
しかしモテキでポイントとなるのは、幸生とみゆきは、一見すれば同じ世界に住んでいるように見える、ということだろう。
別に所得や職種や年齢や出身家庭環境に極端に大きな差があるわけではない。ただ、持っている恋愛資本に大きな差があり、その差を乗り越えることが社会的にはタブーと見なされているし、幸生当人もそれを自覚している。
恋愛資本の格差問題は、身分制度無き時代にロマン主義的恋愛を演出するタブーとしての機能を果たしていると述べたが、ここまでくると恋愛ハードルの第1形式、すなわち恋愛についての自分ルールとの区別があいまいになる。
リア充と非リアの差を意識するかどうかは、あくまで当事者の問題ともいえるからだ。
宗教や、法的に定められた階級制度といった厳然たる社会ルールがハードルとして機能しない時代、恋愛ハードルの形式の区分は質的に意味をなさないのかもしれない。
ただ、どのような形であれ私たちのエロスは言語、文明、理性、意識、自我・・・といった象徴界からの抑圧を受けており、そこからリビドーを解放しうるのは、プラトン的な愛でしかない。というのがハーバード・マルクーゼのメッセージだった。(『エロス的文明』)
では、さまざまな抑圧の形はどのように決定されるのか。
表象文化が与えるステレオタイプなイメージが恋愛に対して果たす役割については、スロベニアの思想家スラヴォイ・ジジェクが興味深い議論を展開している。
曰く、小説や映画に現れる「理想的な恋愛関係」は、私たちが実際に経験する恋愛関係の「消える媒介者」、すなわち精神分析理論における「原初的神話」の役割を果たす。平たく言えば、私たちの内面に、あらゆる恋愛関係のひな型となるようなファンタジーが存在するからこそ、私たちはリアルでも恋愛関係を取り結ぶことができるというのだ。そしてこのファンタジーは、小説や映画、ポルノグラフィーの消費を通じて形成されるという。
したがって、モテキや電車男のようなポピュラーカルチャーに表象されるということは、その時点で既にリア充-非リア充間の恋愛は多かれ少なかれ社会でタブーと見なされているということでもあるのではないか。
恋愛の絡んだ物語の創出には何らかのハードルが必要であることを長々と語ってきた。
唐突だが、『テラスハウス』の視聴率が低いのは、この辺りが理由じゃないかと思うのである。奴らには恋愛をするうえでなんの障害もない。
イケメンと美女が葉山のテラスハウスに一緒に住んでいる。普通に考えて恋愛する以外にやることないだろ!と思うところだが、意外とカップルはあんま成立してない。
逸脱すべきコードが無いから、逆に恋愛できないのかもしれない。よく比較されるあいのりには、恋愛するとドロップアウトしないといけないというルールがあったから、物語が生まれていたのでは。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
