
ジョルジュ・サドゥール『世界映画全史 7』(国書刊行会)
サイレント期の映画史
『世界映画全史 7』には、「無声映画芸術の開花 アメリカ映画の世界制覇 [1] 1911-1920」との副題がついている。この本じたいが1950年代の出版物であるせいか、全史の7巻でまだ1911年という仔細さに驚くが、本書は映画業界の覇権がフランスからアメリカへ移った時代を描いているのがポイントだ。この時代、全世界においてアメリカ映画の影響力が決定的となるのである。知らなかった事実も多く、興味ぶかい指摘も多数あり、映画ファンであればどなたでも楽しめるのではないか。価格が7260円である点はあまり気にせず、購入されるといいと思う。ちなみに宇多丸さんの家の本棚にも同書がありました(テレビ番組で紹介。写真の赤く囲った部分、何巻かは不明)。
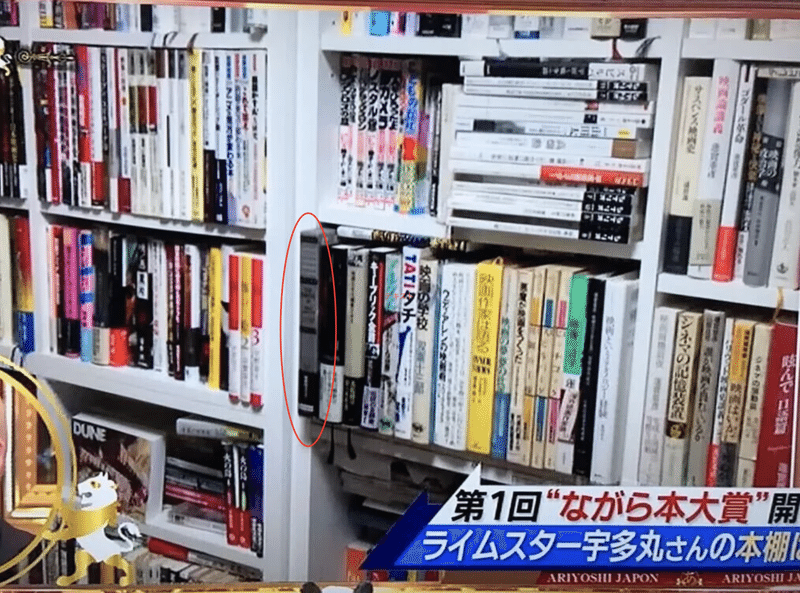
転機は1915年
映画が誕生した1895年から、その後20年間、1915年まではフランス映画が全世界を支配していた。フランスは映画が生まれた土地でもあり、映画を発明した国のアドバンテージを生かして世界の映画界をリードしてきたのだ。ところが1915年、ついにアメリカ映画に追いつかれてしまう。途方もない制作費をかけて大型作品を撮影し、大規模に公開して圧倒的な利益を上げるブロックバスターの仕組み、ハリウッド的な映画製作の原型が生まれたのである。そのきっかけとなった作品は、デイヴィッド・W・グリフィス『国民の創生』(1915)であった。本書はこう説明する。
アメリカ映画にとって状況は有利であった。ハリウッドの建設が開始可能になろうとしていた。ハリウッドは、単にアメリカ映画による国内市場の実質的な完全独占だけではなく、国際市場の征服と全世界におけるアメリカ映画への覇権の確立をも意味した。『国民の創生』の成功は、石油と大手銀行によるロックフェラー・トラストに支援され、融資されて、すべての国のスクリーンを征服することを狙ったトライアングル社への道を開いた。アメリカの帝国主義は『国民の創生』の勝利の直後に、信じられないような膨張とともに映画の領域に素顔を現した。
覇権はアメリカへ
『国民の創生』は非常に問題の多いフィルムであり、KKK 賛美というテーマは到底許容できないが、同作の倫理性についてはひとまず措く。『国民の創生』は映画史的に、作品のブロックバスター化、映画市場におけるアメリカ映画への覇権移行という意味合いにおいて重要である。フランス、イギリスといった国の映画産業では、どうすればアメリカ映画に勝てるのか、アメリカ映画に特別な関税(報復関税)を課して輸入を食い止められないかといったことを真剣に相談している。こうした経緯の紹介は実にユニークな視点であり、映画史の読み解きとしていままでに見たことのない指摘だった。アメリカ映画を模倣して人気を取るべきのか、それとも自国らしさ(イギリスらしさ、フランスらしさ)をより強調して対抗するのか。フランス映画界は、上流階級の人びとを描く作品を撮ることでアメリカ映画との差異化をはかり、惨敗したそうである。
ラマート氏──アメリカ映画のわが国への流入を拒否する報復措置を、アメリカに対して取ることができますか。いや、政府以外には、誰もそれをすることができません。いかなる商業勢力も、そのような行動をとれるだけの力を持ちあわせていません。
会長──アメリカ映画への課税は少額である。課税額を三分の一ペニーに上げるべきである。
書記──生フィルムに三分の一ペニーですか。ポジ・フィルムは一フィートにつき一ペニー、現像済みネガ・フィルムは一フィートにつき五ペンスにすべきだと思います。

当時の欧州映画界は、それぞれにアメリカ映画の脅威に備えていたのだが、あえなく陥落してしまった。それ以降についてはみなが知る通りである。トーキーの登場(1927)までは時間があるが、サイレント映画期の映画産業について認識が深まった点が実によかった。また、『国民の創生』で世界を制したかに見えたグリフィスが、続く大型作品『イントレランス』(1916)で興行的に大惨敗し、頂点から一気に転落してしまう様子も非常に克明で、読んでいてハラハラしてしまった。また、スウェーデンのサイレント映画史に関する記述が興味ぶかく、知らない作品名が多々飛び出してくるのも得る部分が大きかった。100年以上前に、映画人たちが生き残りのためいかに苦心していたかが伝わる、独特のリアリティがある本である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
