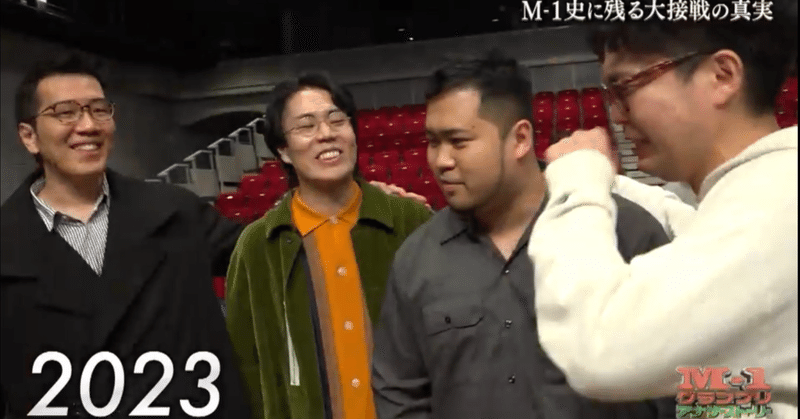
「M-1グランプリ アナザーストーリー」と、人を愛でる文化としてのお笑い
M-1に挑戦するドキュメンタリー
毎年楽しみにしている「M-1グランプリ アナザーストーリー」が、今年も放送された。ウエストランド井口さんが「ウザい! 泣きながらお母さんに電話するな!」とネタ中に怒っていたでおなじみ、お笑い芸人がM-1に挑戦する姿を記録したドキュメンタリーだ。井口さんには叱られそうだが、感動的な内容だった。誰が優勝するかわからない状態で撮っているとは思えない、膨大なアーカイブ映像に驚かされる。2018年、令和ロマン(当時は魔人無骨というコンビ名だった)が初出場したM-1舞台裏で他コンビのネタを眺めている様子や、ヤーレンズが2022年の準決勝で敗退して落ち込むくだりなど、なぜここでカメラが回っていたのだろうと不思議になるような場面が連続する。よく探してきたものだ。番組は、M-1に挑戦するお笑い芸人たちの人間模様が感動的に描かれており、胸を打たれた。しばらくはTVerで見られるし、そのうち別の配信プラットフォームにも置かれるようになるだろうから、気になる方はぜひご覧になってみてほしい。
今回のアナザーストーリーでクローズアップされたのは、優勝した令和ロマンと、2位のヤーレンズとの関係性である。2022年の準決勝で共に敗退した彼らが、毎月3本の新ネタを披露するツーマンライブをしようと決めて、2023年の1月から11月までライブを続けたことが語られる。毎月、新ネタのみで3本という縛りのなかで切磋琢磨した令和ロマンとヤーレンズが、M-1全体の1位と2位になったというのも信じられない展開だ。12月24日、すべてが終わり、楽屋に戻ったヤーレンズ楢原さんが、令和ロマンくるまさんと抱擁しあい「ありがとう。ほんま君らのおかげや」と声をかける場面は感動的だった。また、決勝に進むコンビが発表される日、自分たちは決勝に行けなかったオズワルド伊藤さんからお祝いの言葉をかけられたヤーレンズ出井さんが、「優しいな、お前」と涙を流すシーンも心に残った。決勝へ行けなかった芸人の涙は、自分が出られなかった悔しさなのか、仲間が先に進めたよろこびなのか、その両方であるような気がするが、彼らの姿はとても純粋に見えた。私はここまでなにかに打ち込んだ経験はないなと、自分を恥ずかしく思った。
お笑いと批評に関する気づき
さてここからが本題である。私はずっと、なぜお笑い芸人は批評を嫌がるのか、お笑いの批評が野暮に見えてしまうのか、よくわからずにいた。考えてみれば、これもまたウエストランド井口さん的なテーマである。過去には記事を書いたこともあったが、具体的な理由はわからずじまいだった。これまで私は、お笑いに批評は成立するのではないか(みんなもっと批評した方がいい)と思っていたのだった。しかし、今日「アナザーストーリー」を見ながらあらためて気づいたのは、お笑いはまずなにより「人を愛でる文化」ではないかという点だ。私はこの視点が抜けていたような気がする。以下は仮説なのであまり自信はないが、私なりに考えたことを書いてみた。異なる意見があればぜひ聞かせてほしいと思う。
【過去の記事】
お笑いにおける「人を愛でる文化」とはなにか。思うに、お笑いを好きになることは、芸人の存在そのものをまるごと好きになる状態、コンビの関係性や、2人で舞台に立っているその雰囲気や空気感をそのまま肯定し愛すること、すなわち「人を愛でる」ことに帰着するのではないか。人間として芸人を好きになること。個々のネタを点数やロジックで評価するのではなく、舞台に立つ人をそのまま愛し、受容すること。たとえば最近、オードリーのふたりがマクドナルドのコマーシャルに起用されていたが、あのコマーシャルなどまさに、ファンからその存在を「愛でられた」コンビならではのものだ。ふたりが並んで話しているだけで、なにげない会話をして笑い合うのを見るだけで、ファンは嬉しい。お笑いを通じて、ファンは芸人を人として愛でる。もしお笑い芸人に対して人間らしい愛情や尊敬の念を持っているのなら、「去年よりツッコミのテンポが遅くなった」だの「ネタの起伏がない」だのと傲慢な指摘ができるはずがない、というのは理解できる。ファンは批評するためにではなく、演者を愛でるためにお笑いを見ているのだ。

作家と作品を切り分けること
私はもともと小説や映画が好きだったので、そこまで「人を愛でる」文化に親しみがなかった。たとえばキューブリックの映画は最高だが、キューブリック本人は病的なまでに執着心が強く、パワハラの傾向があるので、彼を人として好きかと言われても全然好きじゃない。評伝を読んだとき、この人ヤバいなと思った。生き返ったキューブリックと話してよい、と言われても、怖いからやめておきたい。ヒッチコックは単なるセクハラ男で、現代の倫理基準ならとても映画監督を続けられない。フィッツジェラルドは最高クラスの小説家だが、アル中で問題行動も多かった。とはいえ作品そのものは突出してすぐれているため、作家の人間性と作品の質を切り分けて評価はできるが、監督や作家を人として愛でる発想はまったくない。また映画や文学は批評がジャンルとして成立しているので、私はその発想をお笑いに持ち込む傾向があった。そんな感覚を持つ私のような文化系が、「漫才だって、映画や絵画と同じ『作品』だ。ならば批評が成立しなければおかしい」などと主張しても、それはお笑いを好きな人たちが大事にしている価値観とはズレてしまう。私は「漫才やコントは『作品』だ」と考えすぎていたのかもしれないと、「アナザーストーリー」を見ながら気づいた。
では、漫才やコントは「作品」ではないのか。思うに、ある芸人と、その芸人が作った漫才を切り分けて評価することはむずかしい。ファンは、漫才を楽しみつつ、同時に、舞台上に立つ芸人そのものを愛でているのだ。この場合、作品は個々のネタではなく芸人の存在そのものであって、芸人自身をまるごと作品として受容するというのがお笑いファンにとって一般的な態度であるような気がする。そして芸人も、自分自身の存在と、漫才やコントの出来不出来を切り分けて評価されたいとは思っていないように感じる。舞台の上に立つ人間をまるごと肯定する文化としてのお笑い。その「切り分けられなさ」こそが、日本のお笑い文化の特徴であり、人気の秘訣なのかもしれないと思う。そう考えてみると、漫才やコントのネタをすべて投票で点数化したラインキングサイト「ロッテンお笑いトマト」や、あらゆる芸人のプロフィールやネタをデータ化した「IODb」(インターネットお笑いデータベース)のようなサイトが、今後の日本で作られることはないと思う。お笑い好きな人たちが大切にしている、芸人を愛でるという価値観にようやく気づいた、今回の「アナザーストーリー」であった。
【私の作ったスキンケア本です。スキンケア批評的な側面もあります】
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
