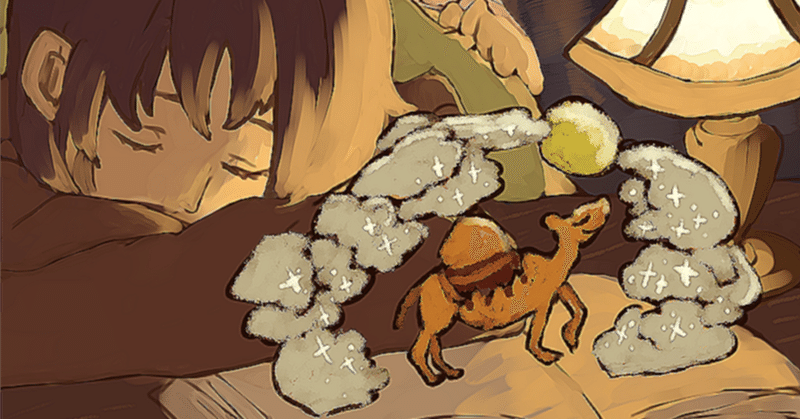
【掌編小説】ストッキング
彼女は帰ってくるなり、ストッキングを脱ぐと、それを丸めて僕の顔に向かって投げつける。まるで異教徒に石を投げつけるみたいに。それからソファにぼすんと体を投げ出し、脚を伸ばしながら、ほら、舐めなさいよ、と言う。僕は磨いていたフォークを置くと、彼女の前に跪いて、足を取る。蒸れた匂い。くらくらする。埃を払って、足の甲に口づける。汚い犬ね、と彼女が言う。それから指を口に含む。一本一本丁寧に。「野良犬以下ね」
右足を綺麗にして、左足を取ろうとすると、彼女は足の裏で僕の顔を踏みつける。ほら、もっと舐めなさいよ、と言う。「舌を出して」言われた通り、舌を出して足の裏を舐めると、彼女はくすぐったがる。やめて、放して。でも、僕は彼女の足を離さない。滑らかな足の裏に顔を押し当て、匂いを胸の奥まで吸い込みながら、心ゆくまで舌を這わせる。
「ねえ、ユウ君、いつからああいうのが好きになったの?」とマミさんが訊く。
僕らはマカロニを食べている。ミートソース。フォークはぴかぴかに輝いている。ミートソースはしっかりコクが出ている。いつもより長めに煮込んでおいたのだ。僕は今日、早めに仕事を切り上げてきた。食事を作ってマミさんの帰りを待つために。マミさんは出版の仕事をしていて、大体帰りが遅い。僕はたまにこうしてマミさんの家で食事を作って、マミさんの帰りを待つ。マミさんの匂いと、少し疲れた顔と、蒸れた足のことを考えながら。それはとても幸せな時間だ。
「いつからかな。社会人になってからだと思う」と僕は応える。
「何かきっかけでもあったの?」
「うーん。前の彼女が好きだったんだよ。ああいう、男をかしずかせる、みたいなのが」
「それであなたもはまっちゃったっていうわけね」
「そうだね」
「私は、前の彼女の真似をさせられてるわけ?」
「いや、そうじゃないんだよ」と僕は慌てて言う。「マミさんだからやりたいと言うか。マミさんにしてもらいたい、と言うか。決して、前の彼女がどうこうというんじゃなく」
「いいわよ。どうせ、私なんて前の彼女の代わりなんでしょ」
彼女はふくれて言う。断じてそうじゃない、と僕は言う。だって、僕はマミさんのことを本気で愛しているのだから。
マミさんと出逢ったのは、街のワインバーだった。僕はようやく前の彼女の呪縛から抜け出そうとしていた。前の彼女はさんざん僕に尽くさせた挙句、他の男を作って僕を捨てた。僕は一ヶ月で四キロも痩せた。職場の仲間達が心配するほどにやつれた。実際僕は絶望していた。あんなに好きになる人にはもう二度と出逢えないだろうと思った。半年経って、前の彼女を夢に見る回数が毎日から二日か三日に一度になった頃、僕はマミさんに出逢った。同僚達と飲みに行った店で、セルフサービスのワインの栓が抜けないで困っているのを助けてあげたのだ。ありがとう、と彼女は言った。その笑顔には何か特別なところがあった。僕にしかわからない特別な何かが。それで僕は自然と、一緒に飲みませんか、と彼女を誘った。彼女は女友達と三人で来ていた。こちらも男三人だったのでちょうどよかった。僕らは広いテーブルに移り、三対三で飲んだ。彼女はやっぱり特別だった。話し方も、食事の仕方も、仕草も、笑顔も、ワインの飲み方も。別れ際に僕は彼女の連絡先を訊いて、彼女は少し迷った後、教えてくれた。
次に会ったのは、翌週の週末で、僕は彼女に告白した。
「じゃあ、今度は私の言うこと、なんでも聞いてくれる?」と彼女は僕を上目遣いで見つめながら言う。
「うん、なんでも聞くよ」
「本当に?」
「本当に」
彼女は俯いて、フォークを止めた。何かを言い出しかねているようだった。胸がどきどきしてきた。彼女は目を伏せたまま、小さな声で言った。
「実はね…」
僕はその日もマミさんの家で彼女の帰りを待っていた。真っ暗な部屋の中で。窓辺で月明かりを浴びながら、僕は心の中で呪文を唱えた。俺はあの月から落ちてきた情欲に満ちた獣だと。冷蔵庫からワインを出して、コップ一杯を一気にあおった。それで少し気分が落ち着いた。体は熱く、頭は冷静だった。二十二時。僕は待った。もう一杯ワインを飲む。目を閉じる。瞼の裏側で、緑色の線と黄色の線が交わり合っている。二十二時十五分。かちゃかちゃと玄関の鍵が開く音がした。獣は息を潜めた。
玄関の扉が開く。靴を脱ぐ音がする。彼女は廊下の明かりをつけて、こちらに歩いてくる。僕はカーテンの陰に隠れていた。彼女の呼吸が聞こえる。彼女はバッグをソファに投げ出すと、ストッキングを脱ぎにかかった。そこで僕は後ろから彼女に襲いかかった。素早く塞いだ口の奥で、彼女は悲鳴を上げた。僕は彼女の耳元で凶暴な声音で囁くように、かつはっきりと頭に響くように言った。「騒ぐな。騒いだら、殺す」
なんて陳腐な言葉だろうと思ったが、これ以外の科白は思いつかない。口を塞いだまま、僕は彼女の体を後ろから思いきり抱きしめ、ベッドルームに引きずり込んだ。それからベッドに彼女を投げ出した。僕は目元と口だけ空いたマスクをしていた。彼女の上に馬乗りになって、シャツを引きちぎった。ボタンがクローゼットまで弾け飛ぶ。彼女が悲鳴を上げそうになったので、すかさず片手で口を塞ぐ。殺されたいのか、と押し殺した声で言って、片頬を思いきり引っぱたいた。それで彼女は茫然自失となった。僕は引き裂いたシャツの下のブラジャーを上にずらして彼女の乳房を露わにした。スカートをたくしあげ、ストッキングを破り、下着をむしりとる。彼女が泣きながら小さい声で、やめて、と言った。僕はもう一度彼女の頬を思いきりはたいた。あらかじめベッド脇に用意しておいたガムテープで、彼女の両手をぐるぐる巻きに縛る。そして両脚を開かせ、彼女の体の中に自分自身を思いきり突き立てた。
その後、発作を起こして泣きやまないマミさんをなだめるのに、僕は三年分くらい謝らなければならなかった。彼女はいまだに恐怖が抜けきらず、ぶるぶると震えていた。僕はマミさんの頭を抱きしめながら、ごめんね、ごめんねと言い続けた。元々、彼女に頼まれたこととは言え、やりすぎだった。加減を知らないのは、僕の昔からの悪い癖だ。一時間くらいして彼女はようやく落ち着いてきて、本当に怖かったんだから、と言った。
「まさかあんなに本気で殴られるとは思わなかった」
「レイプされたい願望があるって言うから、こっちも本気でやらなくちゃって思って…」
「加減があるでしょ!」
それで僕はもう一度謝った。
「もう二度と、足を舐めさせてあげないから」と彼女はまだ涙の消えない瞳で僕を睨みながら言った。
「そんな…」
「だめ。罰よ」
「許してよ。なんでもするから」
「なんでもするのね」彼女は横目で僕を睨みながら言った。
「ああ、なんでもする」
それで僕は、マミさんが次はどんな命令するのか、どきどきしながら待った。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
