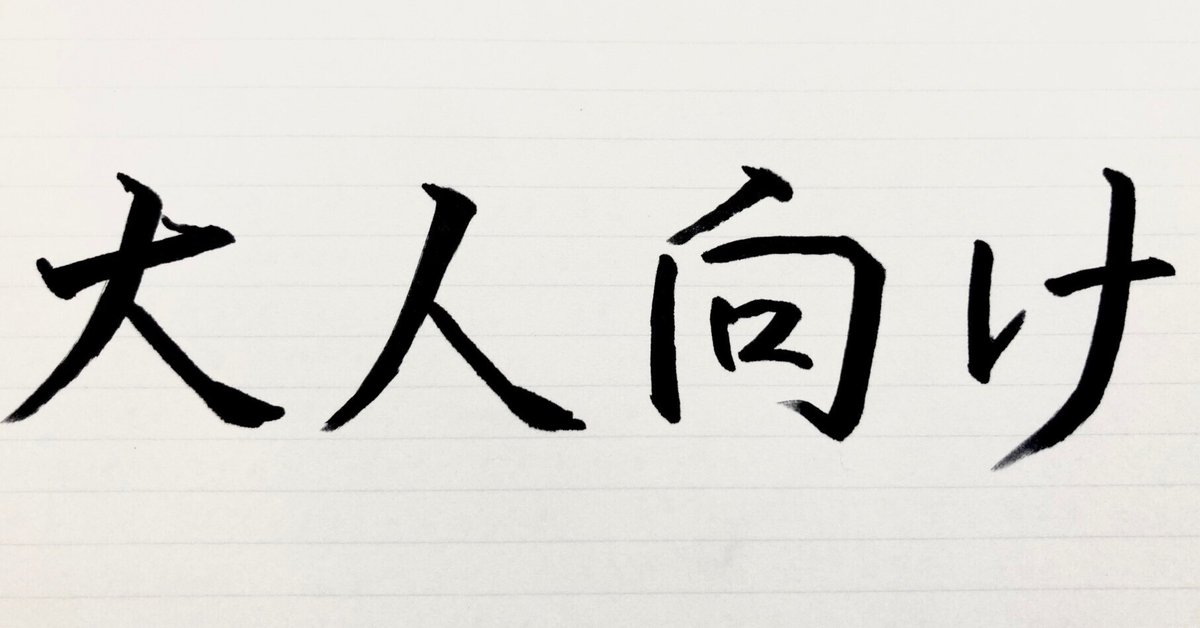
言語とはなにか(part1③) (クイズ答え)
note執筆、10日目。
さて、徐々によんでくださる人の数が増えてきました。
今のところ、日に5~10人ペースで増えてますね、ありがとうございます。
つい最近、わたしの肩の力を抜かせてくださった恩人がいるのですが、自分自身が緊張状態に入ってることに気づいてませんでした。
基本的に最悪な想定から逆算する人なのですが、
ダメですね。笑 わたしもまだまだです。
生きることを、もう少し、
わたし自身も諦めずにやってみよう。
マスター様、ありがとうございました。
私の情報が少しでも皆さまの手助けになることを祈って。
--
さて、今までのおさらいと
前回の答え合わせです。
『文字』とは
『事象』を『観測』する事を、わかりやすく『記号』で表したものです。
『語学学習』には3ステップがあり、
そのうちの1ステップ目、
①『書く・読める』(目) の例題を、前回出しています。
漢字検定一級の問題です。
①『杳渺』の読み方と、意味を答えなさい。
②何故、この漢字の『カタチ』にしたのか
予想してみてください。
では答え合わせです。もうすでに答えを書いていただいてましたが
①(読み)ようびょう
(意味)はるか遠くに霞んでいるさま
です。
さて、何故この文字の形を選んだのかの
推測を始めましょう。
『杳 語源』で調べると、
日が木の下、即ち日が西に沈めば暗くなる。 故に杳の本義を、くらしとする。とありますね。
杳は日が落ちて暗くなってきたよ。という意味です。
更に、『杳 類語』で調べると、
◦ぼうっと
◦薄々
ってのが出てくるので、陽の光が薄いよって意味も『杳』という字には込められていそうですね。
木に陽の光が遮られるところまで日が傾いてるということは、夜になる寸前の時間帯ということですね。
ひとまず、『杳』という字には、
①日が沈みかけてるくらい辺りが暗くて、モノの形がぼんやりとしか見えないよ。
②お日様の位置自体が、自分から遠い位置にあるよ。
という意味あたりが込められていそうですね。
次が『渺』ですが、こっちの方が難しいですね。
1.泪(なみだ)が少ない、で分割するか、
2.沙(砂)を目で見ていると捉えるか、
1だと、陽の光が少なくて、目に刺激がない分、泪が出にくいよ(少ないよ)と捉えることで、意味が通じそうです。
これも何となく、早朝や夕方や、夜に近いイメージですね。
2はどうでしょうか。
沙の意味を調べる必要がありそうですね。
沙とは、水が少ないと書きますが、
海辺や川辺の水が少なくなるとこでは、
沙(=すな、砂)が発生してるよ。
みたいなイメージで使われる字です。
海辺の砂などは、水に削られて、大きさが小さくなることなどから、
『とにかく小さいモノ』というイメージも『沙』という字には込められていそうですね。
調べたところ、
沙=10-8(1億分の1)であることを示す、数の単位であるという解説もあるので
概ね間違った解釈ではないでしょう。
『渺』という文字を、『沙』を見る『目』と捉えた時、
とにかく『小さいモノ』を目で見ていると状況を解釈することもできますね。
さて、『渺』という文字そのものの意味を調べると、
渺(びょう)は、10-11(1000億分の1)であることを示す漢字文化圏における数の単位である。埃の1/10、漠の10倍に当たる。
とのことなので
泪が少なくなるくらい、外が暗い環境で、
沙(すな)を目で見ているため、
ますます大きさが捉えづらい という意味で、
沙よりも小さい数の単位扱いになっているのかもしれませんね。この辺りは調べても出てこなかったので、ただのわたしの予想です。
後は、
渺渺(びょうびょう)という字は、「水面などが限りなく広がっている様」という意味を持つ。
とも書いてあったのですが、
これは、砂浜や海を眺めている人間の様子と解釈することができそうですね。
おっきい砂浜(=沙)があるとこには、おっきい海もあるよ。
ということで、『渺』という字には『水辺』のイメージが込められていそうです。
これとは対照的なのが『杳』の字。
これは、山や、森のイメージが込められていそうです。
何せ、木の下に、お日様が沈んでる訳ですからね。少なくとも『水辺』のイメージではないでしょう。
つまりです。
『杳渺』という意味は
①日が落ちかけてる環境で(=夜に近い時間帯で)
②山や森などの『木』がある場所
③沙(=すな)がある、『水辺』がある場所など
④はるか遠くまで見渡しても
⑤モノの形が薄ぼんやりして見えづらいよ
これを一言でまとめると、
(意味)はるか遠くに霞んでいるさま
ということになる訳ですね。
流石に漢字検定1級までなると、
言葉の意味一つ一つを調べるのに時間がかかると思うので、
純粋に暗記した方が早いとは思うのですが、
理屈で覚えていくと、
こんな覚え方もできます。
『文字』とは
『事象』を『観測』する事を、わかりやすく『記号』で表したものです。
と書きましたが、
上で書いた『杳渺』の5つの意味(=事象の観測)を全部説明してたら時間がものすごくかかってしまうので、
5つの意味を『杳渺』って一言にまとめたのが、
『漢字』という『文字』なんですね。
基本的に、『英語』でも『数字』でも理屈は同じです。
目、耳、鼻、口、手足、などの『五感』(狭義)で
感じた出来事を、
誰にでもわかりやすく、
より伝わりやすく置き換えたものが
『文字』というものです。
さて、今日はここまでにしましょうか。
明日は、
①例題を増やすか
②漢字の『読みの覚え方』か
③語学学習の第2ステップ(読む、聞くの学習方法)
のどちらかをしますが、決めていません。笑
気分に合わせて書きます。
今日はここまで。
筆を置いて。
今日も来てくれてありがとう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
