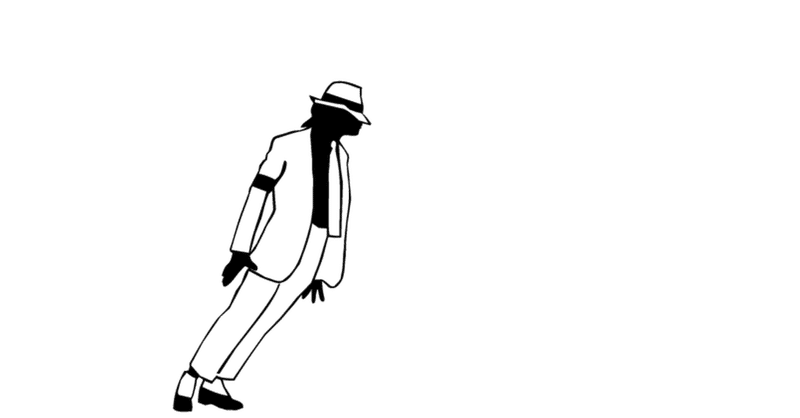
不文律の世界と、鬼滅の刃
不文律。
それが、いまのコロナの世の中における不都合の正体だ。
でも、その不都合が簡単に解消できるのだとすれば、世の中はどうなってしまうだろう。その答えが「鬼滅の刃」の中に、赤裸々に描かれていると思った。
_____
不文律とは、暗黙の了解とか、しきたりとか、そういうこと。
今のことでいえば、マスクをするべきシチュエーションと、しなくてもいいシチュエーションというのは、ほぼ世間に了解済みだと思うけれど、必要もないのになんとなくマスクをしていたり、必要と思われるけれどなんとなくマスクのしずらい空気を感じるときには、その人は世間の不文律に従おうとしているというわけだ。その一度だけならなんとか切り抜けられる不文律の空気も、一日に何度もさらされるとなると段々にストレスがたまっていくというのが、いまの状況である。
「さっきは良くて、いまはダメ」とか「この人はよくて、あの人はだめ」という暗黙のルールは、社会の中で、そのルールがある程度の犠牲と引き換えであることを皆が承知するという手続きの上で成立するものだけれど、その犠牲を潔しとしないのであれば、いつまでもその社会は争いが絶えない。
不文律は、例えばお店の中とか、学校のあるクラスとか、商店街の組合とか、そのくらいの小さな社会が抱えている分には、その中で生活するためにある程度は必要なことだけれど、国全体とか、いまみたいに世界全体でシェアしようとするととんでもないことになる。
そのような不文律を、より広い社会に応用しようとする動きはコロナ以前からずっとあって、それを潔しとしない人たちとの争いが、大きな世界では絶えずあった。
犠牲を伴ってまで、なぜ不文律が重宝されるのかといえば、それは、それぞれの場面において物事の解決が必要だからであって、その解決によって物やお金の受け渡しが滞りなく行われるのが健全な社会という意識が一方に強くあるからではないだろうか。
そのとおりだとすれば、皮肉なことに、健全な社会には犠牲がつきものだ。不文律ははっきりそれとは見えないことが前提なので、その犠牲を不当な割合で受けてしまう人がいたとしても、その人は助けを求めることがなかなか出来ない。だから、犠牲が一か所に集中しないように、つまり出来るだけ多くの人間に犠牲を小さく分散させるために、目に見えるルールを制定する必要がある。少し不便になるけれど、犠牲者が出てからでは遅いのだ。
そのルールの制定においての議論は、皆が犠牲を分け合うために建設的に行われるべきところが、不文律の解消が短時間で終わることはほとんどないのでつい解決を急いでしまうことがある。そのために、ルールなどは不要だといって不文律そのものを消し去ろうとする動きも段々に出てくる。そうなると、今度はそれを止めようとする動きが台頭して、そのあとは潰しあいの争いになる。それがエスカレートすると、もともと不文律が果たしていた大事な役割までもが忘れられて、世の中は混乱の極に達してしまう。その究極が戦争なのだ。だから3月の騒動は、本当に恐怖だった。
今年に入って、「鬼滅の刃」が尋常でないセンセーションを巻き起こしているのは、「あの人はよくて、あの人はだめ」という暗黙のルール=不文律を、世界規模で押し通そうとしている向きと、その不文律を解消したいという切実な願いが争いを起こそうとしている、今の世の中に対する警鐘ではないかと感じている。
「鬼滅の刃」の中では、すべての物事が解決する。それは本来危険なことであって、実際に物語の中で表現されている犠牲たるや、とんでもないレベルなのだけど、そこでは物事の解決がすべてにおいて優先されている。こんなことはあってはいけないとか、人はこうしたものを大切にすべきだとか、不文律の解消がものすごい勢いで進んで行って、鬼たちの成仏とともに正当化されていくのを見ていると、読んでいるこちらは圧倒されてしまって… つまり、ものすごく面白い。残酷な描写だといっても、フィクションだし、キングスマンだって流行ったらしいし、その種類の心配はいまさらしても遅いのだという気持ちのほうが、いまは強い。
ともあれ、「鬼滅の刃」は傑作であるとともに、問題作であることは間違いがないと思う。鬼史上最悪と思われる上弦の弐の鬼にしても、最後に「とっととくたばれ糞野郎」と言われて、一見ざまあみろと思われるような場面においてさえ、その実、彼にとっては現世でどうしても得ることのできなかった人間らしい情念の獲得を宣言しているのであって、その見方においては人生の見事な解決・成仏となっているのである。最悪の存在である上弦の弐が、あのように救済・解決される一方で、そのための犠牲が顧みられない「鬼滅の刃」の世界観は、自分には異常としか思われない。でも、異常だから余計に興味を持って読みすすめてしまうのだとしたら、…いや、理性を殺されない限り、面白いと思う以上やっぱり最後まで読むし、殺されたら自分の理性はその程度だという事なのだ。
あの中で描かれている特攻精神のようなものも、例えばスポーツや将棋など、プロでない範囲の娯楽の世界では、その愉悦達成の目的のために受け入れても差し支えない不文律解消の手段だ。でも、例えば国レベルであれをやってはいけないのは、誰にでもわかることだ。
新型コロナウィルスは、まず中国で、次いでヨーロッパで、あってはいけないレベルの不文律解消として成立してしまった。2月からの流れを思い返すと、あの戦争のような大混乱は致し方のないことだったと思わざるを得ないだけに、いま世間に漂っている敗北感は尋常ではない。そして、いまはコロナ以降の新たな不文律が世の中を支配している。そんななか「鬼滅の刃」が癒しのアルゴリズムとして組み込まれようとしているのも、それこそ致し方のないことなのだろうと思う。おそらくは「鬼滅の刃」を受け入れたことに対しても、いずれ世の中は敗北感を味わうことになるかもしれないと、少しは覚悟をしておかなければいけないとも思っているのだけれど。
しかし、不文律の解消が先送りにされて、終わりのない忍耐を促される場面が一つだけある。
「人を襲わないという保証がない。証明ができない。ただ、人を襲うということもまた証明ができない。」
という、カリスマ性抜群のセリフと鱗滝の手紙をもってしても柱達を説得することが出来ない中、不死川の血を見てもそれに食いつかなかったということで禰豆子の裁判はひとまず終了したのだけれど、「それでもまだ禰豆子のことを快く思わない者もいるだろう。証明しなければならない。これから…」と産屋敷が炭治郎に言いきかせる場面がそれだ。あそこでもし決着がついていれば、物語を進めることは出来ても、その軸は完全にブレてしまったに違いない。もし、どちらの証明も出来ないというだけで、いま現実にある不文律が簡単に解消・決着となれば、それだけで新型コロナウィルスの問題はほぼ消滅してしまう。でも、そうなれば消滅するのはコロナウィルスの問題だけではないことも想像が出来るので、世の中はまだそちらに動くことはできない。その話も少ししておきたい。
不文律を解消するのに、一番手っ取り早いのは、忘却である。
例えば、新型コロナウィルスをどのような脅威として世界が受け取ったかという今年3月の記憶を一瞬にして消し去ることが出来れば、いまの不文律は解消できる。人の記憶の消去には電気系のショックを用いるのがいいのか、もしくは狡猾さを駆使するのがいいのか。記憶消去のための電気ショック装置、もしくは究極の狡猾さが世界規模で活用可能となれば、消される記憶は新型コロナにとどまらないであろうことは、いくら人間の本性を楽天的に観察するのだとしても容易に想像がつく。それはもう、同じ方法でいろいろな消去活動が同時発生するに決まっている。
だから、新型コロナの記憶を一瞬でそのまま消し去るというわけにはいかないし、そんな技術が開発されてしまうのも困るのである。
しかしながら、生活に関わってくる不都合な不文律の緩和・解消は急務なので、ピンポイントに新型コロナの部分だけを消し去る方法を探る動きは絶えない。でも、それが出来るなら1月か2月の時点ですでに出来ていたはずで、それから半年で人類が進化したわけでもないのだから、すぐに効果のあらわれるわけはなく、どうしても徒労と不和だけが際立ってしまう。
「鬼滅の刃」にしても「TENET」にしても、不文律の一方的な解消が殺戮しか生まない悲惨な状況の描写がこれだけの熱狂を生んでいるのは、記憶の消去において、電気と狡猾さ以外のなにか別の方法の出現を人々が待ち望んでいる証拠ではないかと思うのは、楽天的に過ぎるだろうか。
忘却のためのもう一つの方法、それは時間という以外にはない。時間の概念自体、不文律のゆるやかな解消のため、必要に迫られて生まれたのではないかとさえ思われるのだから。
問題作「鬼滅の刃」はあと最終巻をのこすのみ。解決最優先の世界観を最後まで押し通してこの熱狂を正当化するのか、それとも問題を将来に持ち越す可能性を残したまま物語だけが終結して、時間が来るのを待つようにと大きな口を開きはじめるのか、大注目である。
これまでには、読める人だけが読めばいいという記号として存在していたものが、だんだんに人に知られ、深く語られるところとなっていく。それは、やはり時間と忘却によって可能になる。
戦後は本当に終わってしまった。「鬼滅の刃」の登場で、その感はこれまでになく強いものになったと感じている。
「果たして自分が本当に存在しているのかさえわからない。でも、存在している。人々もそれに気づき始めている」(JOKER)
それが果たしてどのような世の中なのか。まだこれからのことなのだ。
_______
(20.12.5 追記)
「鬼滅の刃」の最終巻を読み終えた。
ベッドに横たわる主人公の左肩には、ある不滅の想いを象徴する、乾ききった手がだらりとぶら下がっている。戦いの末に体が消滅してしまったものの想いを、全て引き継いで生きてゆく決心をした主人公が、その乾いた左手をもまた受け入れたということが、この物語の終結であった。
引き継がれるのは記憶ではなく、想いである。
鉄雄がAKIRAに連れていかれたように、全ての闇は日の光が連れ去った。しかし、金田と乾いた左手は、現世に連れもどされた。そこに写しとられた物語を、再び日が照らしつける。そこに東京が現れた。
一度見出された青い彼岸花が全て枯れたことと、母が電話越しにあやまる姿は、ある物語がすでにはじまっていることを示唆してもいたけれど、その始りを鳴らす鐘は読み手の手の中にある。
失われた闇の記憶。自分の体の中で唯一その感覚を保っている器官である目、日の光を見続けることの出来ないこの目、閉じては開けることを繰り返す目。
単行本には、連載のラストに加えて、書き足された部分があった。
そこでははじめに「4時間叱られる」という部分があり、それをどのように捉えるかが、全ての読み手の目に委ねられていた。作者の意図は果たして無邪気なものかもしれず、しかし、この世から不安が取り除かれたということの意味を見続ける目を多くの人々に与えた、この作品の大きさについては疑問を挟む余地がない。
・・・・・
ようやく昨日の出来事となった「鬼滅の刃」が、この後どうなるかはわからない。聖書からトルストイへ、光の中を歩く物語は語られ、これからも読まれ続けるのだとしか、今はわからない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
