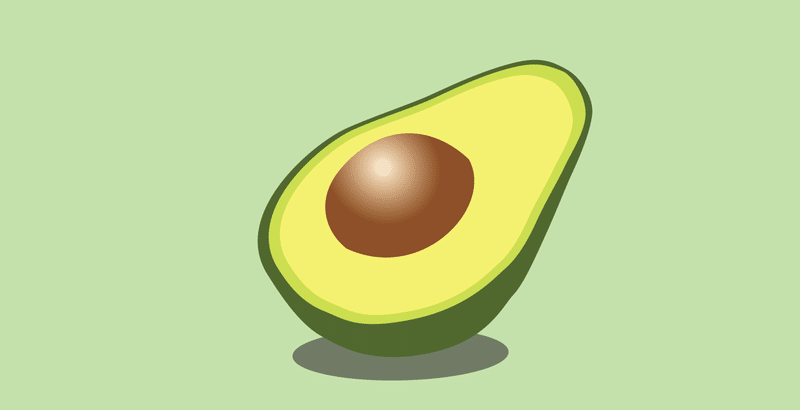
32 20年後の先生、自分、世界
成毛さんの本を読みました。(『2040年の未来予測』)学校の先生は「こういうことをしている場合じゃないぞ」という気になりました。実学だけが学校の役割じゃないけど、これから大人になる子たちといっしょに考えないといけないことをやっているのか。アメリカでは教育にかけるお金がかなり増えているらしい。そうしないと仕事にもつけない。教育ローンは当たり前。借金をして自分のキャリアを得、お金のために働く。これが幸せなのかな、と。
2040年の世界で誰かの役に立った対価としてお金を得、自分で生活していくためには目の付け所、アイディア、行動力、先見性、自分だけ得しない、いろんな力が必要だとつくづく感じました。あくまで成毛さんの限りなくリアル路線のイマジネーションの世界でしたが、「学校、大丈夫なの?」という。大学ももっと減っていくでしょう。第一、子どもが減っていますから。親は子どもに、大人は子どもたちに何を求めるでしょう。求めちゃいかんな、どういう大人になってほしいと願うでしょうか。どんな力をつけたら生き抜けるか。世話になる、というのん気な大人になっていてはいけない。そう強く思います。
学校の先生、徹底したジョブ型でいいとやはり思いました。子どもといっしょにいて、勉強を教えてくれる人、いっしょに好きな芸術やスポーツをしてくれる人、話を聴いてくれる人。事務仕事や日程調整や行事の計画のエキスパートもいる。学校は学力をつけるのが一番の仕事だと思いますが、子どもたちが体験する「家以外の場」です。そこで得た知見で社会に出ていきます。もっと多様でいい。お金のことや人間関係のこと、国際社会のこと、文化的なこと。アイディアや可能性を発見できる場として機能するためには大胆に授業を減らし、生徒たちが何もしない時間を作ることだと思います。合法的に。
「学校はしんどい場所だった」という決まり文句から始まる物語や映画は、あまたあります。家がしんどい子もいるけど、総じて家以外の場はしんどいのです。それをどう乗り越えるか、自分が社会の中で役に立てる存在であり、必要であると実感できる。それこそが学校の本来的な意味、そして将来的にも最も求められる機能だと思います。必要があれば勝手に子どもは調べるし、賢くなれる。最低限の読み書きや刺激があればいい。大学に行って働く。その道を外したら終わり、なはずがありません。僕も例外じゃありません。学校はそれを教えられないかもしれませんが、少なくとも「世界はこうなっていったら、あなたはどうする??」とフランクに話しあえる、そういう場があればいいなと思いました。
仮説を基に、みんなで考える。それにはウッテツケの本でした。見た目は立派なのに開いたら腐っていたアボカド。においはするけど食べてみたら案外おいしい納豆。みんな大好きなものでなくても、食卓は彩られます。いやあ、これは忙しくなりますね。話を聴くのは好きだから、ジョブ型になったらそれだけでどこかで雇ってもらえるかなあ。2040年。僕は60歳。まだ働きたいな。
スギモト
