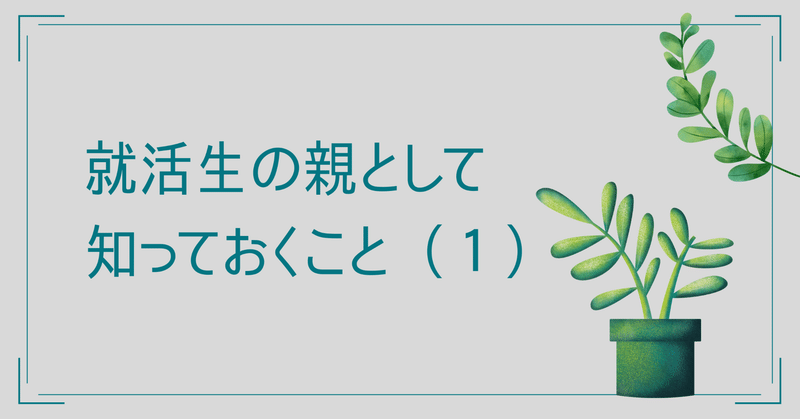
就活生の親として知っておくこと(1)
就活生の親として知っておいて損はないことをお伝えします。
1.親が出来ること
就活は子ども本人が行っていくものであるということは間違いありません。親の立ち場で出来ることは周辺の環境を整えること、大人として知っている情報を与えること、孤独にならないよう精神面での支えになることでしょうか。
この中でも情報というのが本当に今は移り変わりが早いです。IT技術の進歩により学生が使えるサービスがどんどん開発されています。親としてはなかなかついていくのは大変です。
以下に代表的な就活に関するインターネットサービスを見ていきます。基本無料です。
2.みん就とLINEオープンチャット
今もありますが、以前はみん就と呼ばれる今は楽天が運営するみんなの就活日記という無料の掲示板サービスが重宝されていました。各企業毎に掲示板が立てられており、登録した学生が就活の様子をリアルタイムに投稿、今日面接があった、どんな面接だった、面接官が●●だったなどの情報を交換しています。
ここ数年で加わってきたのがLINEのオープンチャットです。ビジネスの現場でもLINEを使用して連絡のやり取り行っている親世代の方も多いと思います。数年前にはなかったLINEのオープンチャットでの情報交換や交流が積極的に行われています。
どちらも匿名の掲示板のため、親世代であっても登録することは可能です。但し、最近は大学のメールアドレスや写真付きの学生証の提示を登録の際に求められることもあり登録しづらくはなってきています。
情報の精度といった面では匿名掲示板ということもあり、また競合する学生同士のやり取りとなるため、確実ということは言えないと感じます、但し、大枠での面接のリアルタイムの流れを掴むには有意義であると思います。
3.リクナビとマイナビ
企業との出会いの場としては、リクナビ、マイナビがあります。当初はリクナビが本家のような形で登録企業が一番多かったのですが、マイナビも同じかそれ以上の企業が登録されています。
こちらのサービスは、共に学生を採用したい企業が何百万円というお金を支払って企業情報を掲載し、学生はそれを見て自分が行きたいを考える企業にエントリーを行います。通常のやり取りとしてはメールが使用されます。
企業からの説明会の案内も掲載されており、学生はこの会社説明会に参加することで、会社の単なる情報だけでなく実際に働く社員から直接話しを聞くことが出来たり、グループワークを通じて会社の仕事を実体験したり、人事部の方に直接質問をして理解を深めることが出来ます。
これらのサービスは会社側の資金負担で成り立っているため、いわば会社にとって見せたい情報が掲載されていることになります。
4.ワンキャリアとユニスタイル
企業からは少し距離を置いていると言えるかもしれないのはワンキャリアとユニスタイルです。
ワンキャリアには現役学生のエントリーシートや就職体験を買い取る仕組みがあり、過去10年近くの学生の生の体験が書かれた記事を読むことが出来ます。
業種別、企業別に整然と企業情報が掲載されており、面接の内容やどんな雰囲気であったのか、どんな学生が受けていて、どこの学校の学生が受かっているのかなどの情報が掲載されています。
選考フローとともに編集部が推奨するエントリーシートの対策等も掲載されており、学生の就活、面接対策としては非常に役に立つサイトです。
ユニスタイルはエントリーシートを中心に企業情報が構成されています。実際に各面接を通過した学生のエントリーシートを読むことが出来ます。また本選考やインターンシップ別に学生の体験した内容をレポートの形で読むことが出来ます。
これを見ると分かるのは各企業の就活のやり方は数年のスパンではそれほど大きく変わっていないということです。面接で聞かれる質問や求める社員像、面接の回数や筆記試験の種類等、これらのサイトを見ることによってほぼ正確に情報を得ることが出来ます。
このため、これらのサイトを知っていない、もしくは知っていても十分に活用していない学生と、中身を徹底的に読み込んで素直に対策を講じている学生では全く企業が受ける印象は違うと思います。
5.WEBテスト
企業の筆記試験で一次試験ではほとんどの企業がWEBテストを使用しています。WEBテストには、SPI、玉手箱、CAB、GABといった複数の種類がありますが企業それぞれで異なります。インターネット上の情報を検索すれば、大企業に関しては、ほとんどの企業についてどのテストを実施しているかを知ることが出来ます。
自分が受けたい企業のテストの種類がわかれば、試験対策問題集がアマゾンに売っていますので購入して繰り返し繰り返し問題を解くことで対策を打つことが出来ます。ネットでは練習問題や正解かどうかは置いておいて回答まで知ることが出来ます。
また、同じWEBテストを使用している志望度の低い企業に大量にエントリーして本命企業のための練習をするということも出来ます。
これらを活用することで、制限時間があり、単純な計算の問題では済まないWEBテスト独特の出題に慣れることが出来ます。
WEBテストについてはどなたもおっしゃっていることですが、事前の対策をやらなければ絶対に良い点を取ることは出来ません。それほど慣れを必要とするテストです。問題出方や回答の仕方、独特の手順等、本来の試験内容と違うところでも差が出てしまうのです。
WEBテストは、いわゆるスクリーニング、募集をしてきた学生全てに対応することが難しい場合、ある一定の基準のふるい落としに使われることが多いため、エントリーした直後に、エントリーシートの提出と同時か、エントリーシートが通過した後に課されることが多いです。
企業はお金をかけてWEBテストを実施しますのでその結果は当然利用します。これは採用面接ではないと言われているインターンシップや職場体験でも同様です。
つまり、エントリーシートとWEBテストで良い成績を出さなければ、選考課程から脱落し、リアルの面接に進むことが出来ないということになります。
6.対策をやるかやらないか
インターネットが当たり前の時代に誰でも情報を得ることができる環境が整っているからこそ、努力する学生としない学生、情報を理解し自分なりに解釈してその対策を練ることが出来る学生とそうでない学生では大きな差がつくと思われます。
このことは一見すると、偏差値の高い上位校に有利に思えるかもしれません。しかしWEBテストに見られるように、どんなに上位校であったり勉学が優秀な学生であっても、これらの情報を活用して就活専用の努力を、限られた時間の中で、タイミングを誤らず対策をとっていなければ、その能力を企業に伝えることが出来ません。
その逆に、情報を活用し、早め早めの対応を行い、不得意なWEBテストの勉強も繰り返し行うことで慣れ、理解することで、上位校でない学生であっても十分に良い成績を上げることが出来るのです。
次に続きます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
