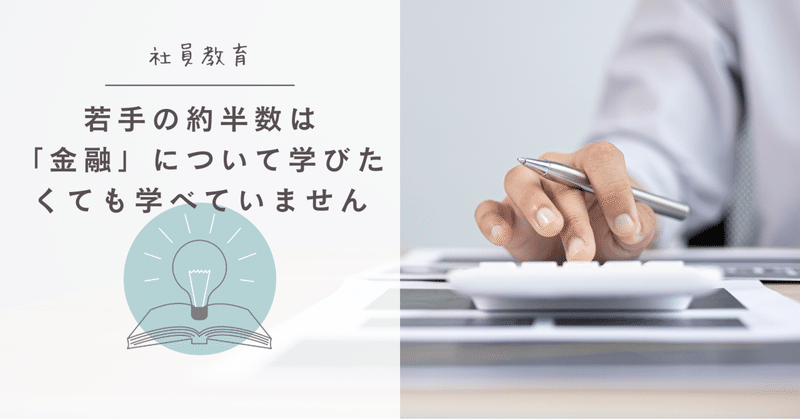
若手の約半数は「金融」について学びたくても学べていません
金融庁は、幅広い世代への金融教育を国家戦略として進めるため、新たな認可法人「金融経済教育推進機構」を来年中に設置する方針を固めました。
金融庁は、岸田政権が掲げる「資産所得倍増プラン」に沿って来年から個人投資家を対象にした優遇税制「NISA」を拡充しますが、投資や資産形成に関する知識を幅広い世代に身につけてもらうことが課題となっています。
また2022年4月からは、高校で金融に関する知識を身につけることを目的とした『金融教育』が必修化となり、注目が高まってきています。
中学生、高校生向けに学校で学ぶようになる金融教育、自社の従業員の投資や資産形成に関する知識は充分でしょうか?
LINEリサーチが以下のような調査結果を発表しました。
調査結果によると、
金融について勉強したいと思う人は約半数
男女とも20、30代が高い傾向
とのこと。
知識の源泉の多くはインターネット上の情報となっているようで、その情報の多さに、自身にとっての最適な投資や資産形成の手段に迷っている若手社員の方々も多いのではないでしょうか。
自身で実際の行動に移すのは、なかなかハードルが高いこともあると思います。
この機会に、従業員向けの金融知識の研修を実施するのも良いのではないでしょうか。
ES向上とともに自身のライフプランを明確にし、日々の業務に取り組みに当たってのキャリアプランに生かせる良い機会になると思います。
会社主導で金融教育を行う際に重要なことは
特定の利害関係に依存しない中立的な立場の専門家によるレクチャーであること
特定のサービスを強く勧めるような内容でないこと
です。
従業員が自らの将来のファイナンシャルプランを考えるようになることは、経営者にとって従業員とその家族を守る、育てることに他なりません。
また、対外的なアピールとして人材採用にも有利に働くことになりますので、この時流に合わせてご検討いただくことをおすすめします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
