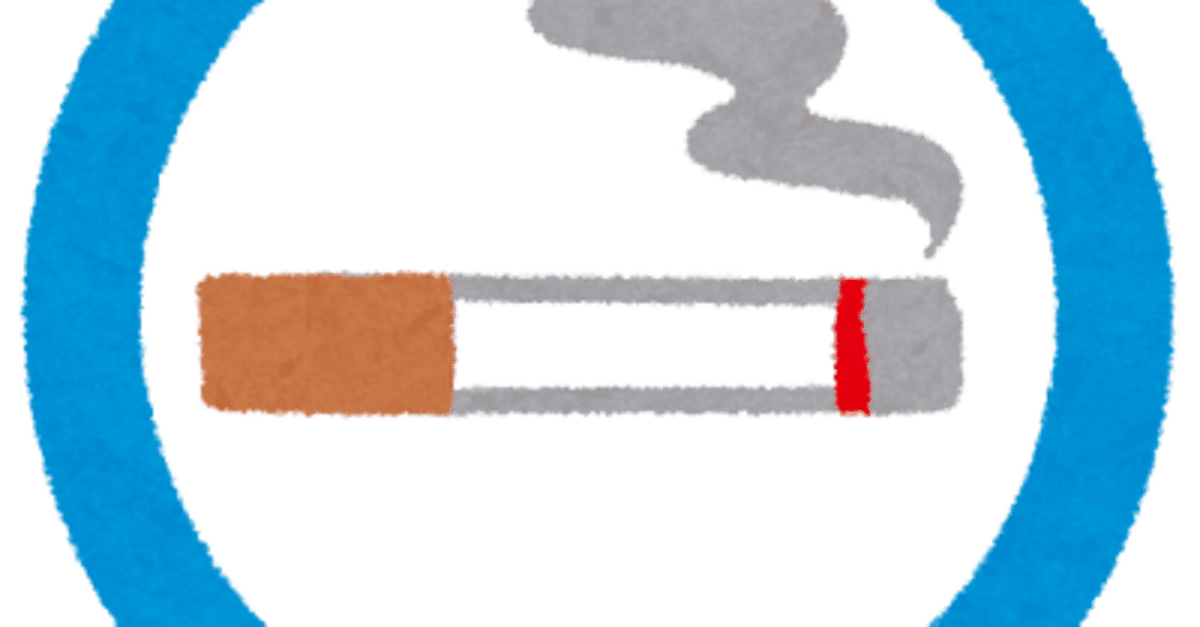
煙草の味を知らなかった
お題「シガーキス」
悪い予感の的中率ってどうしてこんなに高いんだろう。虫の知らせの最悪バージョン、毎回「これから悪いことが起こるよ」って通知の方がが来る人生。きっと最期も楽には死ねずに無の恐怖にじわじわ蝕まれながら死んでいくんだろう。
「ごめんね、退屈で」
ぽつりと呟いた彼の声色が焼き付いて消えない。その消え入りそうな声の寂しさに背筋が凍る思いだった。だけどそれを確認したら今まで積み上げてきたものがぜんぶ壊れてしまう気がして、え、何か言った?と聞こえないふりをした。彼はハッとしたようにな顔をして、いや、なんでもないよと笑った。
この時点ですべてが手遅れだった。
なんでもない顔をしてカフェオレを飲む私の前には、気分が悪そうに俯いてコーヒーが冷めるのを待っている彼。頭髪は湿気で少しぽわぽわしていてやわらかく見える。その不安げな頭を撫でて大丈夫だよと囁いてあげられたらどんなに良いだろうか。だけど私たちの物理的な距離は遠く、だいすきな長い前髪も、角度のせいで私からの視線を遮るカーテンになっている。合格発表を待っている時より強い絶望感を味わっているのは私の方だというのに、彼はなんて真摯なんだろう。
「それで、お話って何かな?」
平静を装う。いつものことだった。神様に祈るみたいにしていたかったけど、私はいつからこんな生き方になっちゃったんだろう。
「……別れて、ください」
消え入りそうな声で、彼は言った。
わかっていたことだった。覚悟もしてきたつもりだった。それでもこの状況が悪い夢であってほしいと願うくらい、心の準備ができていなかった。
「……どうして?私が何か悪いことをした?」
「麻乃は悪くないよ!」
彼はバッと顔を上げた。憔悴しているのか、目の下のクマとやつれた表情が痛々しく見えて私の胸を刺した。
「僕が……僕じゃダメだったんだ。ずっときみに気を遣わせて、隣にいる僕だけが幸せで……。それはきっときみの幸せじゃない。その事実がやっと分かったんだ。自分勝手で……ごめん」
彼は絞り出すように言葉を続けていく。違うよ、私のために気を回してくれたのはいつだってきみだった。私はきみに甘えていただけなんだ。受け身で消極的で、それを隠すために振る舞ってきた傲慢な私を。
「私は好きだよ。君のことが。……大好き」
声が震えるのを必死で抑えようとして、こんな時にも平静を装うことを止められない自分を殺してやりたくなった。
「そう……そうなんだ。今だって君に気を遣わせて……。僕は本当に、ダメだ」
私の偽りのない言葉もいまさら彼に届くはずがなかった。
彼は肩を落として「ごめん。これ以上は……」と言い目尻を拭った。
決して卑屈ではない、腰の低い男だった。私はそんな彼を手放すのが嫌で、つねに冷静でいた。嫌われたくないから、近づかない。引かれたくないから、はしゃがない。それが彼の自尊心を着実に傷つけていた。
お互いに好きなのに、どうして好きだけじゃいけないんだろう。
「……わかった。君がそう言うなら」
ドラマみたいに泣いて縋れば彼を引き止められるだろうか。「この鈍感男!」と激昂すれば彼の心を動かせるだろうか。私は…私自身は、床に寝転がって「嫌だ!」とこどもみたいに泣き喚きたい。別れるなんて、絶対に、したくない。
彼が本心を打ち明けてくれたのに、こんなときまで「彼に嫌われたくない」だけが私の行動原理になっている。心象の海上でマストに縛り付けられて身動きができない。世界の終わりのような大雨が痛いほど肌に突き刺さり、荒波が舟を攫う。やがて大風が吹きつけて転覆してもなお、私は彼に嫌われたくなかった。海の藻屑となって、そこでようやく後悔が立つ。
「私が君を好きなのは本当だよ。だから、これからも友達でいてくれる?」
彼は頷いた。そして立ち上がりながら「僕なんかと付き合ってくれて、ありがとう」と言い、千円札を二枚テーブルに置いた。
「また明日、大学で」
誰にも聞こえないような小さな声で彼の背中に声をかけてみた。当然、返事はなかった。
なんだ、今のは。私の最後の言葉があれなのか。まだ希望に縋ろうとしているみたいで、ダサすぎる。
二千円が手切れ金みたいに見えて今すぐにビリビリに破いてやりたかった。だけど少しでも動いたら「堰を切る」みたいで、微動だにできなかった。もはやどうしようもないのに、醜聞を気にして涙を堪える自分がもはや哀れに思った。
「本当に、ダサい……」
涙の代わりにそんな言葉が溢れた。
〜
「てんちょ〜。あの人ずっといますよね?」
「うん……。もう閉めるし声かけてきてよ」
静まり返った店内ではそんな囁くような会話も筒抜けだった。だけど、どうでもよかった。音も光もなにもかもが自分を通り抜けていく。
「あの〜。そろそろお店閉めるんでぇ」
金髪の女性店員が声をかけてきた。四六時中男を意識しているような甘い声。遊び慣れてそうな容姿。何より、可愛らしい顔をしていた。私は全部のエネルギーが怒りに変換されたような気がした。
「ほっとけよ!!」
私は猛然と立ち上がり金髪女の胸ぐらに掴みかかった。座席で数時間座り続けていた女が襲ってくるのは予想していなかったのか、彼女は大きな瞳を丸くして呆然としていた。勢いのまま艶の良い肌に平手を撃ち込みそうになったが、彼女の口元できらきらと光る紅がどうしようもなく美味しそうに見えて、私は唇を付けた。
「きも!!何すんだよ!!」
彼女の拳が私の鼻頭を捉えた。私はそのまま座席に吹き飛ばされ、呻いた。
「うっ……たばこくさい!」
「くさくねえよ!」
人の口内がこんな気持ち悪いなんて思わなかった。
暴力で引き剥がされたことと、あまりに想像の埒外すぎる煙草臭に私はかつてない恐怖に襲われていた。いつもはじわじわと蝕んでくる悪い予感が、今回ばかりは一気に全身を駆け巡った。悲しみではない本能的な涙がにじんでくるのが分かる。
怒声に気付いた店長が携帯片手にばたばたと駆けてきた。
「野口さん大丈夫!?警察……」
「呼ばなくていースよ。こんなビビってたらもう何もできないでしょ」
彼女が席に入り込んできて私を壁際まで追いやり、寸前まで顔を近づけてきた。チューベローズの香水が漂ってくる。ほんとうに整った顔立ちなのに、その口内に地獄みたいな煙草臭が居座ってるなんて信じられなかった。
私は怯え切って、がたがた震えながら彼女を見上げて泣いていた。いつの間にか彼女の瞳には嗜虐的な色が浮かんでいた。獲物を見下ろす肉食獣のような目で私を見つめている。私はもはや恐怖の涙を止められないでいた。
「ごめんなさい!ごめんなざいぃ!すぐかえります!だから、だから……近寄らないで……むう゛ぅ゛っ!?」
唇が押し上げられ、彼女の舌が入り込んでくる。女同士で唇を重ねているという嫌悪感よりも、強烈な煙草の臭いが全身を貫いた。あまりの臭さに鳥肌が止まらない。彼女の舌は口内で暴れ回り、まるで私の喉の奥から吐瀉物を引き出そうとしているかのようだった。逃れようと必死でもがいたが、私の頭をおさえつける彼女の細腕は力強く、唇は柔らかく、何もかもが闘志を奪う。
そう。彼女の唇は彼よりも柔らかかった。
初めてのキスの感想は、「人の唇は想像よりもずっと柔らかい」だった。我ながら気持ち悪いなぁと笑える思い出なので、大事にしていた。少しだけ震える唇。緊張してぎゅっと閉じられた目。私より身長の高い彼がそんな表情するのがあまりにも愛おしくて、ずっと守ってあげたいと心から思った。
そんな思い出が業火に包まれて燃え上がっていく。第三者の煙草の不審火による火災。焚き付けたのは私だった。上昇気流が彼との思い出を天高く攫って、キャラメル味の甘い炎が飲み込んでいく。
私はそれを取り戻そうと必死で手を伸ばした。だけど彼女の左手がそれを制し、指を絡めてくる。
抗うことができないと悟った瞬間、全身の力が抜けていくのが分かった。幸福も不幸も全部混じり合ったような感覚に支配され、私はただ身を任せていた。
店内の蛍の光を止める者はいなかった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
