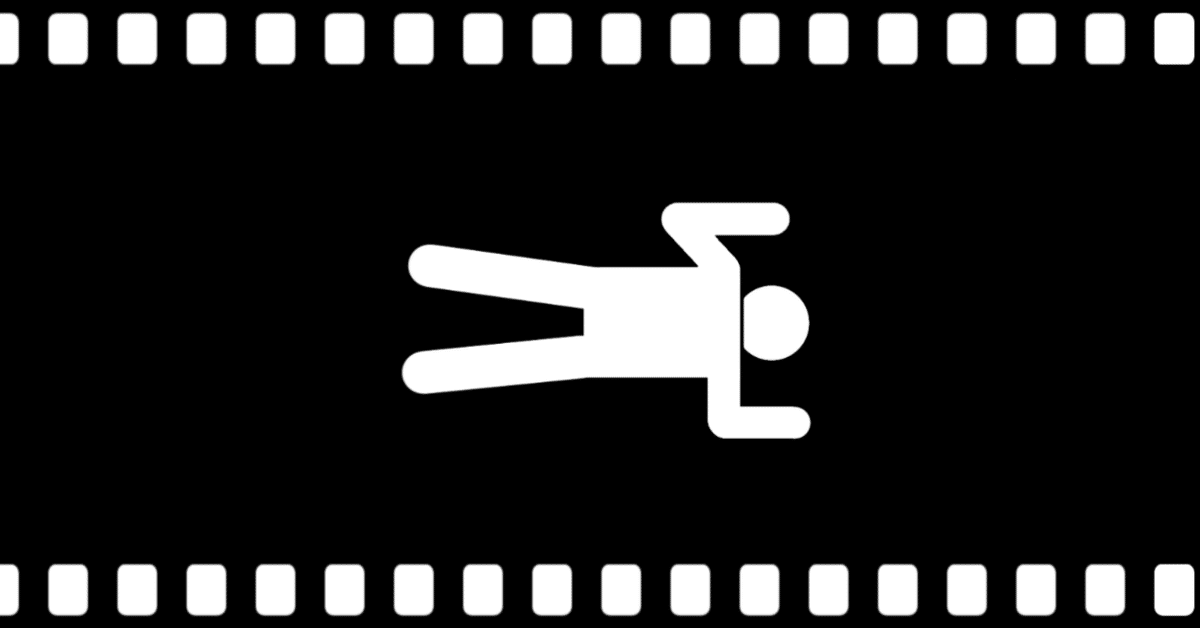
シリーズ“ある男”⑩ 殺人事件を殺した男
天気は西から下り坂とのことだった……
激しい雨が降り始め、張り込みを中断した私は、マツモトが待機する車に戻った。
刑事には雨男が多い。事件が泣いているのだ。
私は万年警部補だ。涙も枯れた。
乗ろうとしてドアを開けると助手席には子育ての本があった。
「あ、すいません、係長」
運転席の若いマツモトが慌ててそれを後部座席に放った。彼は巡査部長だ。
乗り込んでトレンチコートの雨粒を払う。大粒の雨が車のルーフを打つ。悲鳴のようなワイパーの音。それでも、映画セブンの初日の雨よりはやや小降りか。
「今日は何曜日だ?」私は気になって確かめた。
「日曜の次が月曜だとすれば月曜ですね」
刑事は曜日さえ疑ってかかる。
「月曜日か……」
「出しますか?」
「署に戻ろう」
車が走り出してしばらくは何も話さなかった。夕方の激しい渋滞。鳴り止まないどこかのサイレン。マツモトは信号で止まるたびにハンドルを指で叩いた。
「実はカミさんが妊娠したんです」
「それは、おめでとう」
「ずっとオレに内緒にしてたらしくて……。もう何ヶ月も経ってて……」
「君なら立派な父親になれるよ」
彼はいつも職務に忠実だった。彼は大きく左にハンドルを切った。
「係長の娘さん、もう高校生ですよね。早いですね、この前までランドセル背負ってたのに」
「早いもんだな」
私にも妻がいた。でももういない。妻が生きてたらきっと私よりも上手な弁当を娘に持たせていただろう。
妻がいなくなってしばらくして、大雨の日に娘が子猫を拾ってきた。
“ママの名前つけていい?”
── だから今は娘と猫と暮らしている。
「オレに子育てなんてできますかね……」マツモトのため息は大きかった。
「大丈夫さ」
「こんな東京で……子供を育てるなんて……」
信号が変わっていて、後ろから鳴らされた。マツモトはこのところ重たい事件の連続で少しノイローゼ気味だった。
私は彼の肩を軽く叩いた。車が動いた。
「とにかく一人でも多くホシを挙げよう」
我々が東京のためにできることなんてそれくらいしかない。
マツモトは何も答えなかった。前だけ見て運転していた。だから余計にワイパーの音が悲鳴に聞こえた。
*
署に着く。雨は少し落ち着いた。鞄を傘にしてアプローチ階段を駆け上がる。
玄関口。制服で木刀を休めて構える立番の警察官に答礼する。声がかかる。
「日曜も捜査ご苦労様です」
日曜日?月曜のはずでは??
マツモトと顔を合わせる。
なぜだか一気に7日間が通り過ぎた気がした。
一階フロアにはいつも通り、警察署にあるものだけがあった。床はとても滑りやすかった。
その雰囲気からは日曜にも思えた。
我々が大きな額に入った“安全祈願の絵”の横を通り過ぎようとしたとき、後ろから声がした。例の立番の警察官の「ちょっと待て」という声のあと……、
「ボクを捕まえてくれ」
つぶやくような声から始まり、それは最後大声になった。
刑事の勘がすぐに私を振り向かせた。
裸足の男がこちらを向いて両手をあげて立っていた。警察署には年がら年中変わったやつが来るが、そのどのタイプでもなかった。
「ボクが殺しました」
表情ひとつ変えずに続けてそう言った。男の白いTシャツに血はついていない。
──自首⁈
その異様な雰囲気にすぐに周りの職員が反応した。物々しい足音がすぐに男を囲む。
一般の方もいたのでそこに悲鳴が混ざる。
マツモトも駆けていき真っ先に男を取り押さえた。
私もハッとしてすぐ駆け寄る。拳銃を手で確かめる。抜いたことはあっても撃ったことのない刑事は沢山いる。
珍しくマツモトが声を荒げている。
「このやろう!ジョン・ドウ気取りか!」
警察学校だったら0点の逮捕術だ。
抵抗していない相手にマツモトはさらに感情的になった。東京を何とかしたくて、それでそうなったのかもしれない。
「もうやめとけ」
凶器の類も所持してないようだ。
私は男からマツモトを離して、床にうつ伏せになっていたのを起き上がらせた。
「猫飼ってますね」男がそのとき私にそう言った。
うっすら笑みを浮かべて。
何も答えずにズボンについた汚れを払ってやった。彼はまだ被疑者ではない。
当番刑事が降りてきて、「話を聞くから」と連れて行った。彼はまだ私に何か言いたげだった。
その時点では私がその男に業務上関わることはないと思った。私は他にいくつも事件を抱えていた。
もし仮に殺しなら特捜本部が立つ。
壁を向いて立っていたマツモトに声をかけ、エレベーターで刑事課の階へ上がった。マツモトは感情的になったことを後悔しているようだった。
*
翌日、本庁から捜査一課の刑事たちが来た。特捜本部が立ったのだ。
あの男はやはり殺しを自供したようだ。
いくつかの犯行現場を一課長が見分することになった。まずは一課長が現場を見分することから全ての特捜本部の動きは始まる。
管理官の指示で私もそれに同行することになった。ドラマとは違って所轄と本庁とはそれなりにうまくやってる。
すでにマスコミにも知れていて、社会的影響への考慮から地検とも連携が図られる。
事前の情報だと男は犯行現場のこと以外はないにも話さなかったらしい。特捜が立つということは、犯人しか知り得ない何かがあったということなのか。
都内各所の現場を回った。
その全てで一課長は首を捻った。
どの現場にも殺しの形跡がないことは明らかだった。鑑識が暇そうにあくびをしていた。私の長年の経験から言っても、ここでは何も起きてない可能性のほうが高いように見えた。
ただ、── 事件性だけがこびりつくようにしてあった。
そんな現場は初めてだった。
事件性だけが単独で存在しているのだ。
それが一課長と私の見解の差だった。
立ち入り禁止と書かれた規制線がどこか虚しい……。
「男は凶器として東京を使ったと言ったそうだ」
頭をかきながら一課長が言った。何度もしゃがんだり立ち上がったりしていた。
東京を……?
男が大きな何かを隠しているような気がした。
その翌日からは特捜本部が異例とも言えるキャンセルとなった。
“事件はない”という一課長の判断だった。
ほんの少しの捜査資料を入れた段ボールを抱えて本庁捜査員たちは帰っていた。
一方の男は継続して拘留されていた。彼は相変わらず一貫して“殺した”という供述のみを繰り返していた。
凶器は東京……、動悸は不明……、遺体なし。
「地獄より光に至る道は長く険しい、ということか……」私がデスクで椅子ごと回転しながらぼやくと、
「東京は世界一交通網が整備された地獄ってわけですね」とマツモトが半畳を打った。
*
捜査規模が縮小されたため、署員だけで、狂言の可能性も含めた裏付け捜査を継続することになった。
男の拘留期間延長を署長に進言した。少なくとも男はこの東京で起こった何かを知っている。
「あんたが刑事じゃなかったらとっくにクビだな」
いつも私の勘に泣かされる署長はそう言いながらもハンコを押してくれた。
一部のマスコミは怪事件だと報じたが、誰も理解できるものはいなかった。
弁護士が男の弁護を辞退した。理由不明。
私が男を取り調べすることはなかった。取り調べは取り調べのプロがやることになってる。私はどちらかというと地取り屋だ。
それから毎日、虚しいだけの聞き込みを続けながら何度もマツモトと現場へ足を運んだ。
ほとんどの刑事の常識として、事件は発生からの時間が経てば経つほど解決が難しくなる。
ところがこの事件は逆の動き方をした。
時間だけが解決してくれる気さえした。
その度に首を振って、捜査に没頭した。
雨が続いていて、気持ちも塞いでいたある日、いつものようにマツモトと車で移動中に、珍しく私から娘の話をした。思うように進まない捜査がそうさせたのかもしれない。
「このまえ、娘がうちに彼氏を連れてきたんだ」
「ほう、身辺調査がいりますね」マツモトは笑っている。オフのままの無線機を取って口に当て、「彼氏を連れてきた」と冗談で言ったりしている。
「これがとんでもない野郎でね。大学を中退したフリーターらしいんだが、研究を続けてるらしくて、なんたら理論とか夢物語なチンプンカンプンなことばかり言いやがって、挙句に“娘さんをそれで幸せにします”ときたからキレちまったのさ」
「係長をキレさせるなんて、素質ありですね」
「冗談よしてくれよ。まったく、こんな東京で父親なんてできるかってんだ」
窓の外では繁華街を若いカップルたちが手を繋いでデートしている。
「娘さんだって勇気がいったと思いますよ」マツモトは大きく右にハンドルを切る。
本当を言うと、あの場で何か違う言い方ができたのでは、と今も思っている。
とにかく、
現場は100回でも1000回でも行けるが、彼氏は一回で十分だ。
*
事態が動いたのはそれから数日後だった。
男が突然、自供を覆したのだ。
「ボクは誰も殺していない」と。
男の犯行を裏付けるものは現時点で何もなかった。
そして否認。
もはや嫌疑不十分で釈放せざるを得ない状況だ。
そして、私が現場を見た時の勘が正しければ、そのまま真実は永遠に闇の中だ。
彼は何かを殺している。
“どんな手がかりも煙のようなものだ”というサマセットのセリフ。
今は、どんな煙でも手がかりとして欲しかった……。
ただ時間だけが過ぎた。
それは拘留期限最終日のことだった。天気予報が外れて雨が降り出した。
副署長が私を呼んだ。彼は私とは逆年次だ。
「奴が君と話したいと言っているそうだ」
「私と⁇」
私はもう次の事件の書類に取り掛かっていた。
副署長は目に力を込めて頷いた。
「留置場管理課と署長の許可は取ってあるから」
私は取り調べ室で男と話すことになった。
可視化が進んでいるため、すべてが録音録画される。
取り調べは普段やらないせいか少し不安だった。
なぜだかセブンの似たようなシーンを思い出した。
だから扉を開けて入る前に副署長に冗談で言ってみた。
「もしも奴に殺されそうになったら助けてくださいよ」
すると副署長は手を広げて答えた。
「なーに、奴は手錠をはめてる。それに奴が君を殺せるなら、とっくに事件が見つかってるはずだ」
それもそうだ。
部屋に入る。
ノートパソコンもプリンターもないテーブル。
そこに手錠のかかった手を乗せて男が座っていた。
「やあ」と私に向かって少しその手を上げる男。
最初に男を見た時もそうだったが年齢が不詳だ。本名がまだないせいもあるかもしれない。若く見えるし老けても見える。
私も頷いてから対座する。
「あなたを尊敬しています」
「私を?」
機先を制すかのように言われて、私は少し動揺した。
取り調べマニュアルを前もって読み込んできていた。
マニュアルでは常に、まず刑事が話してから、相手が答えた。
「あなたは東京の全警察官の中で最も殺人事件を遠ざけている」
「私が⁇」
「ああ、データに出てる。だからあなたを指名したんだ」
そんなデータがあったなんて知らなかった。
「私から質問させてくれないか?」
男のペースがなぜだか居心地が悪かった。
「ああ、もちろん。これは取り調べだろ?」
男は手錠のまま、最大限、手を広げた。
「本当は何を殺した」
「……」
「質問を変えよう。何を殺さなかった?」
「何をかって?」
「ああ、そうだ」
「いったい東京がこうして生きてるのが誰のおかげだと思ってるんだい?」
「お前のおかげだと言いたいのか?」
少し沈黙があった。
「神の行いは神秘だ」
男が明らかにジョン・ドウのそのセリフを言ったとき、なぜだか突然、娘のことが気になって、中座してすぐ外で電話した。
まもなく娘の無事の声を聞き安堵する。
「パパがかけてくるなんて珍しいね」
「ああ、無事ならいいんだ」
「お弁当美味しかったよ。ありがとう」
「あのな、この前はすまなかった。謝るよ」
「ああ、彼氏のこと?べつに父親ってそういうものでしょ」
「……」
「ママが言ってたわ。“男は夢のためだけに生きていけるから美しい”って……アタシは彼の夢を応援したいの」
電話を切ってからしばらく妻の顔が浮かんだ。妻と出会った日も雨だった。
副署長が心配そうに近づいてきた。
大丈夫だと合図を送ってから再び取り調べ室へ入った。
私が座ると同時に男は言った。
「安心できましたか?」
「関係ないことだ」
「推理小説は読まれます?」
「いや読まない」
私は刑事にしては小説を読むほうだが、推理小説は読まないようにしている。推理小説を読みすぎると自分の考えを追うようになってしまいそうだからだ。
刑事は真実だけを追えばいい。
「殺人事件を殺したんです……ボク」
そのあとの私の長い沈黙もきっちり録音されているはずだ。
“ここの刑事はみんな死体が死んでると思ってやがる”とミルズにドヤされたかのように我に帰る。
私はなんとかマニュアルを思い出して聞いた。
殺人事件を殺した男に聞ける言葉はそれほどなかった。
「事件のあった日……、つまり事件のなかった日のことを話してくれないか」
「猫、飼ってますよね」
「ああ」
「猫ってすごく空気読むんですよねー」
男は窓もないのに外を見るように顔を向けた。
「何かもっと重要なことを言いたいのでは?」
「いいえ、ボクは猫以外の話はするつもりないですよ」
「聞こうじゃないか」
殺人事件を殺す話より猫の話の方が楽だ。
「雨の日でした……。その捨て猫を拾ったのは。だからアメと名付けたんです。不思議な巡り合わせでした。知ってます?ひとに捨てられた猫は横顔を見せたがるんですよ……」
男はゆっくりとした口調で話した。猫の話をすると心が和らぐように見えた。子供の頃、自分の母親が雨の日に出て行ったことと、煙雨の中に消えるまで見送ったことも、遠い目でその話にはさんだ。
そして続けた。
「よく猫が顔を洗うような仕草をするのは雨の降る前兆って言うでしょう?で、うちのアメのこともずっと観察してたんですよ……。そしたらどうやらその説は、うちの猫の場合は当てはまらないらしいことがわかって、それでしかも全然違う前兆だったんです」
男は自分の話に興奮したように少し前のめりになった。
私はなだめるような仕草で落ち着かせた。
「事件と関係が?」
「ええ、もちろん。事件の前兆だったんですから」
再び私の長い沈黙が記録された。
「まさか」
「ボクも最初はそう思いましたよ。でも一致したんです。すべて。ずっと記録をとって調べてみたら殺人事件の発生と一致したんです。それも方角まで。アメはいつも事件の方向を向いて顔を洗っていました。きっと清めてあげていたのでしょう。猫ってとても感じやすいから……」
「それで君は猫に代わって英雄になろうと思った」
「英雄だなんてやめてくださいよ」
「だから自首したんだろ?自首しなきゃ誰も君を英雄視できない」
「殺人事件が起こると分かっていたらきっと誰でも殺すと思いますよ。刑事以外は」
私は何も言えなかった。
「しばらく留守にするからと言って大家さんにその猫を預けてあるんです。早く会いたいなー、アメに」
おそらくこの男はほんとうに殺人事件を殺したんだろうと私は思った。
刑事の勘ではなくて刑事の執念がそう思わせた。
だからといってこの取り調べの記録を基に送検しても、不起訴だろう。
殺人事件を殺した人間を裁く法律がどこに?
……そして、約束の時間が来た。
良い意味でも悪い意味でも、我々は負けたのだ。
男は取り調べ室を出る時、無邪気に振り向いて言った。
「東京をなんとかしたかったんだ。夢があっていいでしょう」
終
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
