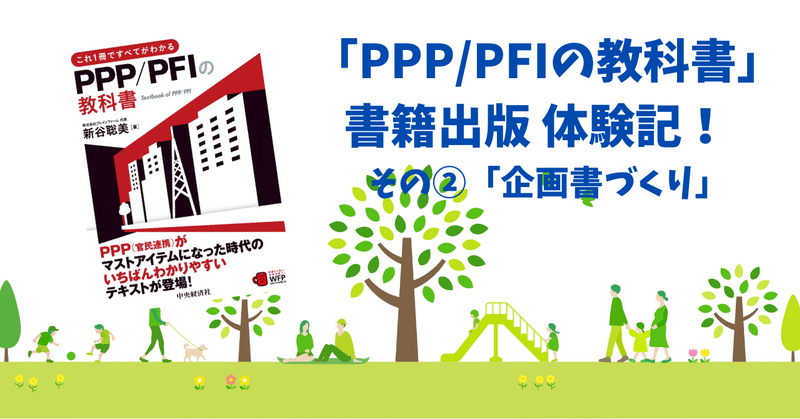
「PPP/PFIの教科書」書籍出版の体験記その②「企画書づくり」
2024年の2月に「これ一冊ですべてわかる PPP/PFIの教科書」という解説書を中央経済社より出版しました。出版前から「書籍ができたら、それまでの取り巻くストーリーを伝えると、誰かの役に立つかもしれないよ」とアドバイスいただいていたので、何回かに分けて綴っていこうと思います。
第二回は「企画書づくり」です。
「書籍出版には興味があるが、PPP/PFI(官民連携)って、何じゃそりゃ?」という方も、専門知識なしでもイメージいただけるようお伝えしますので、ぜひお付き合いください。
【1】書籍出版のキモは、マーケティングと悟る
書籍出版の体験記その①では、『「本を書く」「本を出す」を、どういう経緯で自分ゴト化したか』をお伝えしましたが、「よし、書くぞ」とある程度ハラをくくったら、次にするべきことは、出版社の編集長に認めてもらえるような出版企画書を作成することでした。
本を書くように強く勧めてくれたブランディング・コンサルタントの知人が、いくつかの出版社に知り合いがいるので聞いてあげる・・・と言ってくれたのですが、たとえネットワークがあるとしても、どんな本を書くのかが相手に伝わらないと話になりません。
そこで、その知人が、「出版企画書のフォーマット」なるものを送ってくれて、そこに書き込んでいくことになりました。
(ちなみに、もらった時は「こんな貴重なものを、サクッと分けてもらっていいのか・・?」と悩んだのですが、いまGoogleで「出版企画書 フォーム」で検索すると、どんどん出てきます。同じフォームかどうかわかりませんが、企画書を作るということは一般的なようです。)
中核となるのは、何を書こうと思っているかの「目次案」のはずなのですが、他にも、アピールの羅列が求められていました。
⇒いまこのテーマがなぜ重要なのかを説明して「このテーマの市場性」をアピールしたり・・・。
⇒類似テーマの他のいくつか書籍との違いを2軸のグラフ(マトリクス図)に図示して「この書籍の市場性」をアピールしたり・・・。
⇒著者(つまり、ワタシ)のプロフィールを詳しく記載して、いかにこの分野の専門家なのか「この著者の市場性」をアピールしたり・・・。
⇒はたまた、図書の帯やアマゾンで推薦コメントを出してくれる有名人をリストアップさせられたり・・・。
有名人には知り合いがいないし(結局推薦コメントのリスト欄は白紙で出しました)、自分も全く丸っきり有名ではないし、そもそも「売ろう」と思って本を書くことにしたわけではないので、「おやおや、ビックリ」の連続だったのですが、読み込むうちに、ふと気づいたのです。
書き手は、世の中に伝えたいことがあって、本を書こうとする。
でも、売り手は、売れるものじゃないと、流通に載せることができない。
最初から頭ごなしに『売れるかどうか、どう売るかを考えろ!』と言われていたら「PPP/PFIの基本がわからない方に解説書を出したい」という「世の中に役立ちたい『想い』」で動いていたため、気持ちはポキッと折れていたかもしれません。
でも、「企画書」というフォームの形で”マーケティングの重要性”を知る機会が訪れたので、客観的に理解することができました。
そうした当たり前の仕組みをストンと腑に落とすことができたのは、本当にラッキーだったと思います。
【2】結局「想い」が差別化要素として機能発揮
出版企画書を書くという仕事は、マーケティング発想をもって資料をまとめるのが仕事の一環となっているコンサルタントにとっては、そこそこ取り組みやすいものでした。
最初は、「これなら売れるかも」というマーケティング発想から書籍出版を企画したわけではなく、「これを書きたい」という想いから取り組もうとしていたので、マーケット分析なんて難しいかも…と思ったのですが、結局は「これが必要だと思うから、書きたい」というのは、市場ニーズに応えているはず、なんですよね。
私のように、有名人でもなければ、SNSもロクロクやっていないのでフォロワーなども全然いない・・というフツーの人には、自分がずっと携わってきた専門分野で、経験からくる「これが必要だろうという想い」=「潜在的な顧客(市場)ニーズ」という方程式が成り立ちやすいので、出版企画書作成も比較的取組みやすいのかもしれません。
ただ、潜在的な市場(マーケット)ニーズをつかんでいる自信はあったのですが、いかんせん、PPP/PFIという分野はそのマーケットが小さい。
(ほら、星座占いの本だと、日本人全員に当てはまるじゃないですか!PPP/PFIも、知らなくても日本に暮らすほとんど全員がその仕組みが活用された街に暮らしているのだけど、一般の認知度は極めて低く…。)
もしも目に留まらなければ、全然売れず、在庫の山となって出版社に迷惑をかけてしまいます。
小さいマーケットなりに目に留まるよう、本当ならばプロモーションをガンガン頑張らないといけないのでしょうが、有名人でもなく、SNSもやっておらず、おカネもない小規模企業には、ない袖は振れません。
そのため、編集長と相談して、出版日には相当こだわりました。
結果的には、効果があがったのですが、予想外のことが起きてしまい…。
そのお話はまた、もう少し先にお伝えしたいと思います。
さて、今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
第三回は、「スケジュール通りには進まない」をお送りします。
どうぞ、お楽しみに。応援よろしくお願いします!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
