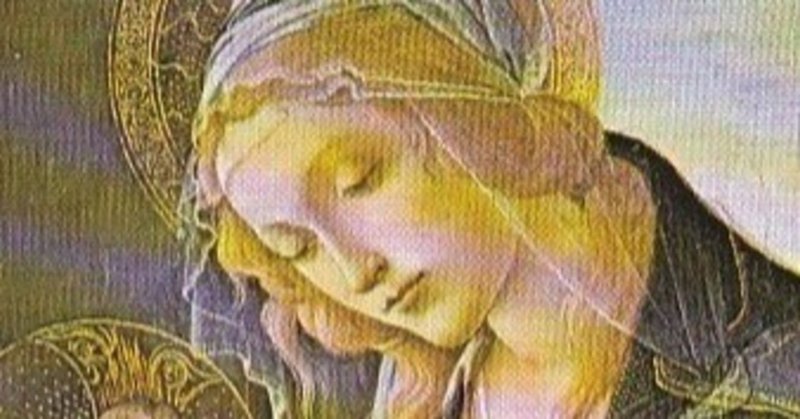
霧の宴 ミラノ Ⅲー7 クレリア夫人
*アンドレア、新しいシーズンのコンサートのプログラムをマリアムと検討する。
**********************************
どんよりと湿った空気がミラノを重苦しく覆っていた数日後、烈しい風を伴った豪雨の夜になり、一夜明けたその十月の朝、久方ぶりの太陽の光がヴェネツィアーを通して寝室に差し込んでいた。
広いテラスの鉢植えの低樹木の葉や花たちが、夜間の風と雨にレンガの床に叩きつけられ見るも無残に飛び散っている光景を、マリアムはただ茫然とパジャマのままで眺めていた。
表門のベルが鳴る。
「市役所のものだが、、、」
?、、、こんな早朝に市役所から何の用事か、と不審に思いながら、急いで部屋着を羽織ってドアに近づく間もなく内ベルが鳴る。マリアムは苛立ち、少しとがった声を上げた。
「何の御用か知りませんが、お静かに願えませんか?」スパイホールを覗き見るのも忘れてドアを開ける。
そこにアンドレアが立っていた。悪戯っ子の様にクスクス笑いをしている。
「まあ!何ということでしょう!!」と呆れていると
「十一時のフライトでローマに行く、学会に出なければならないのさ。暫く君に会う機会がなかったし、しなければならない話が沢山ある。電話より直接会った方が良いと思ったのだよ。それに君も僕も時間の調整をするのがとても難しい。厚かましいとは思ったが、君の家が空港に近いことを勝手に利用させてもらうことにしたのだ」
「それにしても、お電話くださればよいのに、、、」
「迷惑だろうとは思ったのだが、君を驚かせたい気持ちの方が勝ってしまった」と笑った。
「迷惑ではないけれど、わたしを驚かせるのには成功したわ。カッフェにしましょうか?それとも貴方は、朝食は紅茶ですか?」
いささか散らかし気味の居間で、二人は軽い朝食を取りながら、話題はやはり、ジュリア―ノ公爵邸でのコンサートに集中した。
「君がクレリア夫人を紹介してくれたので、今シーズンはとても充実したものになりそうだよ。あの方は、浮世離れした名家の深窓出身でいらっしゃるのに、現実的なオルガニゼイションの手腕をお持ちなのには驚いた。それがとても僕やエリアの後押しをして下さっている。
山のジョルジョや薬剤師のシモーネも積極的に協力してくれているし、今年は本当に素晴らしいシーズンになりそうなので、僕はとても幸せだ」
「この間、音楽美学のマンデッリ先生にお電話したら、先生も公演なさるんですって?」
「うむ、モンテヴェルディの夕べに解説をお願いしてあるのさ。君がモンテヴェルディを歌ってくれないから、僕は本当に残念だ」
「ジュリア―ノ公爵のために、M.ラヴェルの<博物誌>を選んだのですもの、、、、それに、あのジャンルを歌う専門家がいるじゃありませんか」
「いや、あのジャンルの専門歌手ではなく、演劇人の君だったらどんな風にモンテヴェルディの世界を表現するのか、とても興味があるのだよ」
「マクベス夫人の狂乱の場面を演じろと言われたら、貴方をびっくりさせるくらいの演じ方をして見せる自信はあるけれど、歌となると、、、わたしは専門家ではないし、、、、勿論M.ラヴェルにしてもそうなのだけれど、でも文学作品としてJ.ルナールに親しんだのは少女の頃からだし、M.ラヴェルはここ数年勉強はしていますからね、それなりの形にはなると思うの。
それに、公爵様のためにと云っているけれど、本当は私が大好きな作品なのです」
「クレリア夫人は君にA.ヴィヴァルディの何かを歌ってほしいとおっしゃっているけれどねぇ」
「さあ、、、、ヴィヴァルディは、勉強だけはかなりしたけれど、わたしには無理でしょう、声の純度が完璧でないとイタリアのバロック音楽は美しくないし」
「公爵のためにラヴェルを歌うのだから、君の大ファンのクレリア夫人のためにも何か歌って差し上げなければ、、、、僕のためにもね」
「まあ、貴方までも私の下手なヴィヴァルディを聴きたいなんて、よく言えますね!私を笑い者にするつもり?」
「いや、僕は真面目に言っているのだよ、何時か君がJ.S.バッハの<ホ単調ミサ曲>のコントラルトのアリアを歌ったのを聞いたけれど、あれは本当に素晴らしかった」
「いやですね、あれは曲が素晴らしいから、誰が歌っても素晴らしく聞こえるのよ。それに私の声の質がバッハに向いているのかも知れない。ヴィヴァルディは違うでしょ?もっと透明度がないと、、、」
「誰が何といっても君は、専門家でないと言って逃げようとするけれど、職業としていないということが専門家ではないとは言い切れないのでは、、と僕は思うよ。特に君の様な勉強の仕方をする人は、、、」
「貴方やクレリア夫人のような方々が、たいそう贔屓にして下さるのを、とても感謝していますが、それだけに皆さんのご期待を裏切ることはできません。私は未熟なアマチュアですし、音楽を心から愛し大切にしたいと思っていますから、わたしの未熟さで音楽の美しさを打ち壊したくないの。
<Coscienza artistica =芸術的意識>と、ルキーノ ヴィスコンティは言っていたけれど、ARTEに携わる者は、何時でも如何なる場合にも、芸術に対して謙虚な自覚を持たなければならいでしょう?
それに、ラヴェルとヴィヴァルディでは、あまりにもかけ離れていると思わない?」
「ラヴェルの夕べは、君の歌とリッツィのピアノで組めるから、もし君が受けてくれれば、別の日にヴィヴァルディだけの夕べにしたい。クレリア夫人の従兄弟さんたちの弦楽器のグループが引き受けてくれれば、<Salmo 26>
のようなものも良いかと思うけれど、、、、」
「ともかく、少し考える時間を下さいな、歌うのはわたしなのですから、、
芝居の方のスケジュールもあるし、、、来週中にはお返事できると思います」
ジュリア―ノ公爵のために選んだM.ラヴェルは、以前からマリアム自身が歌ってみたいと思っていた作品なのであった。<シャンソン ヘブライク>や<シェヘラザード>の様な、しなやかにしかも強靭に反り返る鋼の剣が描く官能的な美とは異なり、<博物誌>はM.ラヴェルの意外な一面を呈している思われる。アムプレッショニズ、サムボリズム、エスプレッショニズムの何れにも属さない独立した妖し気な光を放っているように感じらられるこの作品は、何処かA.ガウディが設計図に記すことが出来なかった、或いはV.ニジンスキーが舞踏譜に記すことが出来なかった、あの不思議な捉えることのできない、だが確実に存在している美の空間の暗示のようである。
<博物誌>は、J.ルナールの並外れた観察力から生まれる、人間の曖昧な情緒という感性には無関係な、実存的で簡素、素朴で繊細な美の世界である。P.ボナールの素描の入った<博物誌>を、マリアムは少女の頃読んだ記憶がある。無駄な装飾をそぎ落とした簡潔なフランス語の描写に浮彫される田園の自然の営みや、そこに生息している大小の生き物たちが、目の当たりに生き生きと動き回っている様子を見ているようで感嘆したのであった。
おそらく、それは夏の日々を田舎で過ごした或る年のことであった。
その後何年経っても、<博物誌>の頁をめくるたびに、物憂い静かな蒸しかえる真夏の午後の気怠さが、マリアムの肌に甦ってくる。
この楽譜に出会ったのは、まったくの偶然で、S.マラルメのシャンソンを探しにリコルディの楽譜売り場を覗きに行った折、間違えて引き出したのがこの<博物誌>であった。
J.ルナールとM.ラヴェルという一見奇妙に思える組み合わせが、マリアムの好奇心を刺激した。
譜面を観ただけでは、どのような音の展開が繰り広げられるのか、マリアムには見当がつかなかった。C.サンサーンスが動物を<謝肉祭>という形で作曲しているが、音楽的な匂いが全く感じられない<博物誌>を、どのようにしてM.ラヴェルは音の世界に創造するのであろうか、マリアムの好奇心は益々煽られていった。
J.ルナールの文章に触発されマリアムが想像した小宇宙は、M.ラヴェルによってどのように蘇生されるのであろうか?
楽譜を手に家にたどり着く間の時間が、たいそうもどかしかった。
つづく
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

