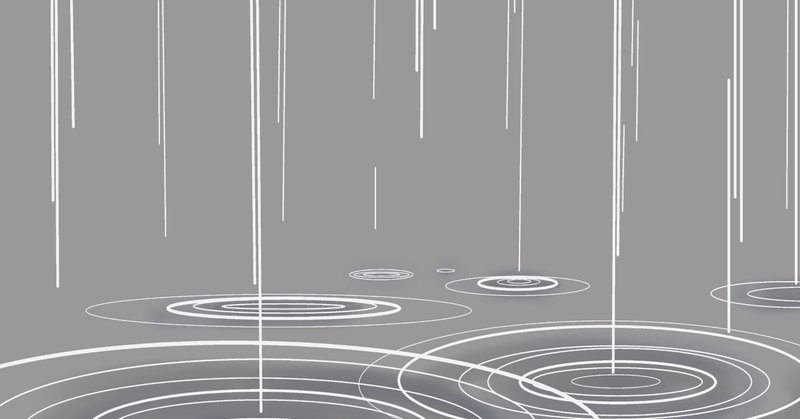
魔法のランプ
ディズニーでお馴染み、こすると魔神が出てくる魔法のランプ。あれがずっと不思議だった。
ランプ(灯り)って言うけど、急須に見える。
魔神を呼び出す以外には、どうやって使うものなのか。ランプと言うからには火を灯すのだと思うけれど、どこに?
液体を入れられそうな形状からして油壺付きの油皿なんだと思う。でも、灯芯はどこにさすのか。蓋を開けると灯芯を固定できるような構造があるのか、急須でいうと注ぎ口に当たる部分にさすのか。油をつぎ足すことを考えると、注ぎ口のほうかな?そういえば、あの上の蓋が開いてるところを見た事が無い。もしかして、開かない?実は嵌め殺し?
考えるほど謎が深まるので、実物を確認することにして、録画していた実写版のアラジンでランプをよく見てみた。
まさかの新たな問題発覚。
注ぎ口が下を向いている。
えー。
芯、挿せない。
油、も差せない。
どうやって使うの?
魔法のランプは特別仕様で形が違うとか?
分からないので、今度は辞書に聞いてみることにした。
ランプ。
①灯り
②立体交差の傾斜路
③牛のお尻の赤身肉
いやいやいやいや。そうじゃないんだ。
マイペディアさんにありました。
「……急須状の油皿をローマンランプなどという……」
ローマンランプ。ほお。
辞書にローマンランプの項目はなかったので、最終手段。ネット。
ジーニーのランプのおかげで金属製のイメージだったけど、テラコッタランプとも言うくらい、陶器製が多いらしい。遺跡からの発掘品ばかりなので実際に使っているところは見つけられなかったけれど、どうやら、元々は注ぎ口のようなところが上向きに作られて、そこに灯芯をさして油皿にするものであったよう。上の蓋は嵌め殺しどころか無いやつもあった。こちらが油の補充口。
となると、灯芯はかなり長いものを使わないと油壺の油を使い切る前に火が消えてしまう。そして、油皿が小さいので頻繁に芯を引き出す必要がある。
実写版アラジンのランプは油皿の部分が下を向いていたと書いたけれど、正確には、その開口部の先に舌のような板がついていた。この舌の上にちょっと長めに芯を引き出しておくと、保ちがいいということか。灯芯が短いと抜け落ちるかもしれないけれど、あのランプに使う灯芯がそもそも長いものであるなら、その心配は無い。
なるほどー。
だいたい世界中どこも、はじめは平皿に油を入れて、そこに植物などで作った芯を浸して火を点ける。その後、頻繁に油を足したり芯を引き出したりするのが面倒になってどうにか長持ちする方法を考える。日本だと、芯を螺旋状に巻いて蝋で固めて蝋燭を作ったけど、中東のあたりだと、液体の油をいかに補充し続けるかを考える方向だったということなのかな。砂漠は寒暖差が大きいから蝋燭は溶けちゃうのかも。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
