
尊氏の〝victory load〟を辿る ー浜石岳に登って
□ はじめに
室町時代の大河小説的な資料📖『太平記』の中に、薩埵山合戦の記述があります。
薩埵山とは、東海道の難所にして🗻富士山の絶景ポイントで知られるあの薩埵峠から、登って行き、浜石岳に向かう登山ルートにあります。

※薩埵峠展望台から冬の早朝に撮影してみました。
薩埵峠は安政の大地震が起こるまでは、国道11号線・東海道線・東名高速道路かある陸地はなく、直接、🌊波飛沫が海岸にあたる交通の難所でした。
北陸の親知らず子知らずの難所と同じような通行するには誠、不便な峠でした。
この薩埵峠では、二度の対戦があり、足利尊氏と実弟・忠義勢が激突した薩埵山合戦は、南北朝時代の観応2年12月(1351年)と、戦国時代に弱体化していた今川氏真+北条氏と武田信玄が永禄11年12月(1568年)に激突した薩埵峠合戦があります。
不思議と二度の大戦は年末12月の末から翌年の正月にかけて戦い、昔のお侍さんは、🎌正月返上で戦ったのですね😱

※最近では教科書にも載っていた有名な足利尊氏像が、
側近だった高師直だったとする説もあります。
薩埵山合戦に興味がある私は、歴史フィールドワークの一環として先日、静岡県内で唯一、1000mを切る低山で「岳」の名称を持つ浜石岳に登って来ました💦
□浜石岳を再び登る
静岡市内にお住まいの方なら、👣小学校の遠足で一度は登った記憶がある方も多いはず🤔
標高707m、JR東海道本線 🚉由比駅から登るのが一般的です。
おおよそ徒歩で120分ほど、頂上直下には駐車場もあります。
峰伝いに大きなパラボラアンテナ📡がありますので、晴れていれば🚃電車の車中からでも📡確認出来ます。
ここを敢えて、JR東海道本線 🚉興津駅から登るルートに挑戦してみました。
なぜなら、足利尊氏は、薩埵山合戦の際に東海道興津宿にある古刹・清見寺で足利軍を集結させ、南朝方と同盟を結んだ実弟・忠義勢との一戦に備えます。そして、本隊というべき足利尊氏は興津から薩埵峠から薩埵山、浜石岳を越えて富士宮に抜ける入山の手前、槍野《うつぎの》桜野地区で合戦に及んだとあります。
薩埵峠付近では陣を張れないため槍野・桜野地区まで出張ったものと思われますが、『太平記』の記述が曖昧で何とも地区が特定出来ません。
ですが、〝something New〟です。
先ずは実測です。
JR東海道線・興津駅を06:23分、
出発→薩埵峠 到着07:10分着 徒歩で3804歩 消費カロリー195kcal 3.2kmの行程

※この先に、展望台があります。
ここまではハイキングコースで多くの老若男女の方が訪れます。
□ 浜石岳登山ルート
ここから先、薩埵峠展望台を通過して左手の山沿いに延びる農道の途中から、薩埵山→浜石岳に向かう🥾登山ルートがあります。
普段は🚗で来ていましたから、この登山ルートは半信半疑でした。
急な農道を歩んでいくと、後ろからチャーミングなご婦人に声🗣をかけられました。
「浜石岳に向かわれるのですか?」👩🏻ショートカットのご婦人はトレイルランをなさっておられるようで、軽快に追い抜かれてしまい、着いていくこと能わず😅
登山口は⁉️と、思いましたがその👩🏻の後ろ姿が教えて下さいました。

※薩埵峠には何度も撮影に来ていましたが、こんな場所に登山口があったなんて知りませんでした。
行き慣れておられ、迷いはない様子。私も遅れながら、ついにこのコースに足を運びます。
このルートは、後醍醐天皇の建武の新政を否定して室町幕府を開いた足利尊氏が開幕後、実弟・忠義と天下を二分する大合戦となってしまった「観応の擾乱」の中での最後の大戦
「薩埵山合戦」で尊氏勢が決戦に向け登って行ったルートです。観応二年十二月二十七日 壬寅(新暦1352年1月14日 土曜日)の事です。
留守を守る尊氏が嫡男・義詮が南朝方と和睦し、駿河薩埵山に陣取った足利尊氏を恵源・忠義勢が包囲します。
この包囲軍を尊氏勢の宇都宮氏綱が薩埵山の後攻めに駆けつけて、尊氏勢が呼応し薩埵山を登って浜石岳を抜けて槍野(ウツギ)・桜野集落で勝敗を喫する薩埵山合戦となります。
📖『太平記』第三十巻 十
「宇都宮、すでに所々の合戦に打ち勝って、後攻めに廻る由、薩埵山の寄手の方へ聞こえければ、諸軍勢、皆一同に、
「あはれ、後攻めの勢の付かぬ前に、薩埵山を攻め落とされ候かし」と申しけれども、傾く運にや引かれけん、桃井も上杉も、かつて許容せざりければ、余りに身を揉うで、児玉党三千余騎、極めて険しき桜野より、薩埵山へぞ寄せたりける。
この坂をば、今川上総守、南部の一族、羽切遠江守、三百余騎にて堅めたりける‥‥」

この中に薩埵合戦の経緯を綴った第三十卷「薩埵合戦の事」が登載されています。
📖『太平記』も含めて詳細な記述はありませんが、尊氏勢は恐らくこのルートで登って行ったと思われます🤔
『太平記』では「由比山」とありますが、これが浜石岳のことを指しています。
薩埵峠展望台から妄想竹林の林を抜け標高406mポイントまでおおよそ95分ほど。ここまでは急な登りや階段があります。

現在は急勾配を地元の方のご尽力で階段を作ってくださっておりますので大変でも上がっていけますが当時、足利軍はこんな急坂を鎧や武具を着けながら、どうやって登っていったのでしょうか?
登り始めから急な坂を階段で登っていきますが、尊氏勢がここを通過して行ったとは、驚異的です。

おそらく、今川家二代目・範氏勢は承元寺を守っていたのでここらあたりで足利勢本隊と合流したものと思われます。
登り始めて20分ほどで、緩やかになりましたが最初の登りは結構ハードです。
この分岐点は、標高406mポイントを超えて、興津・承元寺で警固していた今川上総守が登って来たであろう承元寺ルートとの合流点です。

興津川東岸にある安国寺。今川家ともゆかりが深い古刹です。

※興津川東岸にある古刹・承元寺。
承元寺からも浜石岳に登っていく登山ルートがあるようです。
国土地理院の地図には登載されています。

武家の名門・足利家の家紋を将軍家から直々に拝領した家紋で、一門衆の印です。
今川氏・細川氏・斯波氏・吉良氏・一色氏・畠山氏などが一門衆として、この家紋を用いています。
【今川家の家紋・丸に二匹両】
□今川家は足利一門衆。
足利家の分家筋で、言わば身内、親戚。足利家の本所はご存知、栃木県足利市。足利市には、足利家の菩提寺・鑁阿寺(ばんなじ)があります。

足利庄を本願地としていた足利氏の菩提寺です。
【足利市にある足利家の菩提寺・鑁阿寺】
今川氏は、その足利家の家紋「丸に二匹両」を伝承されています。二匹両は、雌雄二匹の🐉龍を表し、雌雄の仲睦まじい様を描く、縁起のいい家紋です。

隣町が今川氏の本家である吉良氏の本願地・吉良町です。吉良はあの赤穂浪士四十七士の討ち入りで有名になってしまった吉良氏の発祥の地です。
【今川氏発祥の地、愛知県西尾市に立つ🪦石碑】
この近くに吉良町があり、吉良氏も今川氏と同様に足利一門衆です。正確には、吉良氏の分家が今川氏です。
今川上総守範氏。 初代・今川範国の嫡男・範氏は二代目ながら短命だったこともあり、余り有名ではありません。むしろ、同母実弟の了俊の方が和歌に秀でて、九州探題も務めたこともあり、名を馳せています。

今川家二代目・範氏の墓があります。
【今川範氏公の菩提寺・普照寺、藤枝市花倉地区】
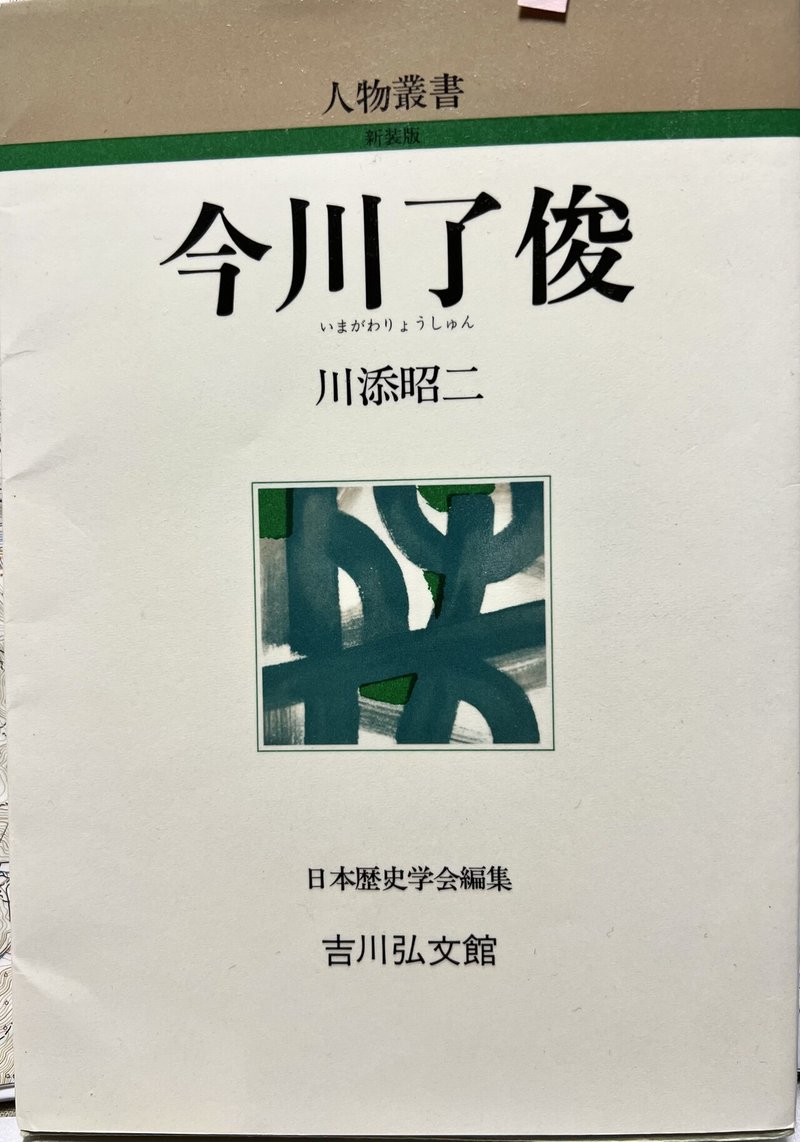
私は伊豆文学賞で応募して落選しましたが、範氏公の活躍を題材にした小説を執筆しました。
範氏公の活躍無くして、🏅尊氏の勝利は有りませんでした、と記しました。何故なら、今川家は最初から尊氏勢に手放しで加勢したのではなく、父・範国と実弟・了俊は恵源・忠義に心を寄せていたからです。
今川氏は忠義にも領国経営の際に、多大なる配慮していただき、恩義がありました。お人好しで気前が良く楽天家の尊氏から離反した武将が多かったのは、何故か🤔
尊氏を補佐する執事の高師直の存在です。
高師直は、実務にも長けていましたが、自らの才に溺れ、粗野で女癖も悪い。尊氏は良くても高師直の傲慢さに白む輩が多かったのです🤣
その今川家中を一つに纏めて尊氏勢に加勢したのは、二代目・範氏公の頑な忠義からでした。
尊氏勢はここで今川範氏らと合流。さらに浜石岳に向かう途中に、尾根伝いから8分を下がった所に、立花池があります。
静かな小さい池です。

立花池を下ると興津川沿いに広がるのが立花地区です。
この立花池には尊氏勢が寄ったことがあると伝承があります。標高422m、興津駅から歩行距離4942m。
立花池にて、一息ついたであろう尊氏に去来するものは、何だったのでしょう🤔
室町幕府を開いた際には尊氏と忠義は分業制で幕府の行政を執り行い、一歳違いの兄弟は仲が良かったのです。
家紋に表す仲の良い兄弟であったはずなのに、権力を握ると周囲を取り巻く家臣団に、それぞれの思惑と利害が衝突し始めてしまいました。
実弟と戦わなければならなくなってしまった、何処でボタンを掛け違えたか⁉️
敢えて〝load〟にしたのも、この戦いに勝ってもその犠牲や報いはきっと、ある。その負担のことを思えば、勝利には酔いしれることは出来ない、と🤔
人がよく気前のいい大雑把な足利尊氏にとって、かけがえのない実務に長けた実弟・忠義と袂を分つ。断腸の想いだったことでしょう。
実弟・忠義もその想いは一緒のようで、恵源と出家していた忠義は、薩埵山合戦の現場には参着していません。
やはり、兄との直接対決には、躊躇していたのでしょう😖

登山道整備の方々のご尽力に感謝です。
立花池からもおおよそ120分ほど登り続けます。途中77段の急な階段を登って浜石岳には11:02分に到着。

眼下には駿河湾も望めます。
興津駅🚉から、徒歩20018歩。距離8585m、消費カロリー2139kcal。
このルートは、頂上近くまで富士山を含めて眺望が楽しめないことですが逆も真なりで、大軍が移動するのには、高い木々に覆われて周囲からは目立たないことにつきます。

今は登山ルートとして、人が通れるルートになっていますが当時は修験道として、僧や甲州へ商いに向かう商人が通行していました。
それだけに、ハイキングコースには選ばれ難いのでしょう。
先ほど、私に声を掛けて下さった👩🏻ご婦人のトレイルランの方は、但沼分岐点前で再びお会いし、下山されて行かれました😱
その速さと驚異的な体力。あの細い身体の何処に、あのバイタリティがあるのでしょうか。
私は浜石岳山頂で、一度味わいたかった🍺を持参して看板しました。

250ml缶の小さいものにしました。
山頂でいただく🍺は美味しかった😋
尊氏勢は浜石岳を通過し、槍野(ウツギ)・桜野集落で決戦に及びます。これは📖『太平記』の記述でしっかり記録されています。児玉党とは恵源・直義方の軍勢で三千いたかどうかは解りません。
📖『太平記』の数字には誇張が多く、記述をそのまま信用できないからです。ただ、大軍であったことは事実。その直義方をわずかな手勢で打ち破った今川範氏は地元の利も活かしました。

※槍野地区で石碑やら痕跡は確認出来ませんでした。
ただやや広い農地が広がっています。
【槍野(ウツギ)集落】
この農道を左に曲がると浜石岳に向かいます。
範氏らが急坂を利用し罠を仕掛け、大木や巨石を落としたとされる場所は特定できませんでしたが、おそらくこんな感じであったろうとされる切り立った場所は撮影してきました。

※ご覧のように高低差があります。
【桜野集落の農道】
ルートは、YAMAPに登録して登りましたので全く迷うことなし。今の登山は、私が高校・大学の山岳部で登っていた頃より数段、進化しDXの時代。
⛰YAMAPで標高や消費カロリー、高低差、気圧に、到着予想時刻や通過時間までほんの数秒で確認出来ます。
⛰YAMAPに掲載した今回の山行データも添付しようとしましたが失敗。先週、YAMAPのアンケート回答にnoteとのリンクを希望しておきました。
未だ未だ未熟は公開報告でした🤣

※浜石岳山頂にある📡アンテナがはっきりと判ります。
下山し、振り返っての浜石岳。山頂直下のパラボラアンテナ📡の左手が山頂です。
ここまで来れば、JR東海道本線・由比駅までもう少しです。生しらすや桜エビを卸す商店が軒を連ね、由比旧市街というべき商店街の右端に由比駅があります。
□活動データ
縦走所要時間 7:41分
縦走距離 15.3km
標高差 1011m
総歩数 28832歩
消費カロリー 2122kcal
(終わり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
